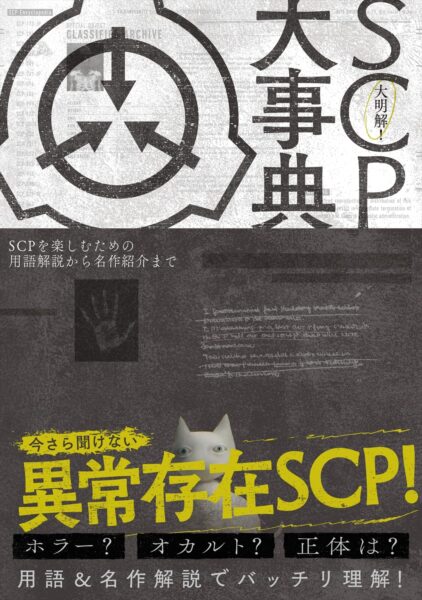国内メディアアートの文脈と“ゲーム”の結節点
──ここからは、森川さんの功績を踏まえ、あらためて三宅さんにご登場いただいている記事のテーマである「日本のゲームAI」について考えてみたいと思います。くり返しになる部分もありますが、森川さんが「AIを使ったゲーム」を作り続けた理由を訊ねさせてください。当時のゲーム作りの過程で、AIにどのような魅力を見たのでしょうか?
森川氏:
ひと言で言うと──「予定調和じゃないところ」ですね。
たぶん、普通のゲームの作りかたって“筋書きのあるプロレス”なんですよ。
フラグで管理したりしながら、プランナーが最初から最後まできっちり設計して作っている。それに対してAIを使ったゲームの作りかたって、セメントの格闘技みたいなものなんです。
そこには、「自分が作ったもののはずなのに自分の思いどおりにならない」という面白さがある。
──森川さん自身も予知できないことが起こると。
森川氏:
実際に作っていて、ふとした瞬間に「自律的な知性や感情」を感じてゾッとする瞬間があるんですよ。それは、言ってしまえば「命や魂みたいなもの」の感覚なんです。
もちろん、厳密に言えば知性でも感情でも何でもないんですけど──どうしてもそう感じてしまうんです。初めてそれを感じた瞬間は、全身に衝撃が走りましたね。そして「ああ、この感動をプレイヤーに届けたい」と思ったんです。
とくに『アストロノーカ』を作っているときは面白かったですね。
バブーがトラップを抜けるときには「そうきましたか」みたいな方法を使ってくるんですよ。実際に人間じゃ思いつかないことを彼らはやってくるので、もはや彼らが繰り出してくる発想の数々に、尊敬の念すら感じながら眺めているわけです(笑)。
 |
そんなふうに、自分が作りながら味わった面白さを、プレイヤーにそのままぶつけて心を揺さぶりたいと思ったんですよね。それを感じることで、初めて本当の意味でプレイヤーはAIに出会うことができると思うので。
──なんだか、お話を伺っていて思ったのですが……森川さんとその作品って、少し「メディアアート」っぽいですよね。
森川氏:
どういうことでしょう?
──まさに森川さんの先輩である石原さんこそが、もともとはメディアアートの世界でCGを手掛けていたけれどゲームの世界に来た方ですよね。森川さんも、彼のようなメディアアートからゲームに連なる系譜に位置付けられるんじゃないかと思ったんです。
三宅氏:
わかります。だからこそ森川さんのゲームには“作家性”があると思うんですよ。
ひとつひとつのゲームは商品というよりも、森川さんの「作品」に近い。僕は森川さんという人は、ゲームというよりもむしろ「AIを使った作家性のあるメディアアート」をやってきた人だと思うんです。
──そして、森川さんはテレビ番組にも関わられていますが、石原さんもまた、批評家の浅田彰さんと先進的なテレビ番組(『浅田彰の電視進化論』)を作ったりしたことで、メディアアート史にその名を刻んでいる方です。
そう思うと、日本のメディアアートの一部は、ある時期以降、テレビ番組やゲームに流れていった系譜があるんじゃないでしょうか。
森川氏:
確かに当時は、「これはCG、これはゲーム」などと自分の中ではあまり区別はしていませんでしたね。
成沢氏:
プレイすると、『アストロノーカ』や『くまうた』って、テレビ番組を観ている感じがありますし、自分が作品に関わって変化させることができるので、そこにもメディアアートらしい不思議さがありますね。
本城氏:
そういう意味では、森川さんって、いまでいうと落合陽一さんが近い存在かなと思いますね。テクノロジーも詳しく解り、アカデミズムでも活躍されながら、メディアアーティストとしての人格もあり……という形ですよね。そうした全然違うタイプの才能が奇妙に同居しているというか。
 |
三宅氏:
でも──いまなら解ると思うんです。こうしてAIが注目されることで、森川さんのこれまでの仕事がどういう文脈に乗っていたのかを照らしてくれると思うんですよ。当時は最先端すぎて解らなかっただけなので。
森川氏:
そうですね(笑)。
実際、ディープラーニングがブームになってくれたおかげで、こうして新しく会社を作ってお仕事をさせてもらっているわけですし。
でも正直に言うと、いま聞かれていることって、自分の中では20年前にインタビューで答えていた話に過ぎないから、いまさら聞かれるのが不思議な感じなんだよね(笑)。
日本のゲームAI史を、森川さんから始めたい
──ただ、森川さんの業績はだいぶ「属人性」が高いもののような気もしますね。それを日本の今後のゲーム業界にどう活かしていくのかは、かなり難しいことにも思えます。
三宅氏:
まさに最初の扉を叩くパイオニアって、そういう大局的な才能を持っている人ですよね。とくに森川さんはゲームデザイン、キャラクターデザイン、AIテクニカルデザイン、の3つの才能を併せ持っています。もし、このうちのひとつしかなければ、開発の立ち上げの時点で、ほかの開発者たちに思い描いていることを説明し、説得する必要があったはずで、とくにAIが関わると、これは当時とても難しかった。ところが森川さんはすべて持っていたので、そんな必要はなく、自分自身を軸にしてAIを使ったゲームを作り上げることができたわけです。
そうした森川さんの仕事は、ゲームの歴史のひとつの軸になるはずなので、その最初の出発点として明確にしておくだけでも必要なことだと思うんですよ。
実際、欧米の躍進なんてたかだか2000年以降の話なので、そう考えたらものすごく先駆的かつ歴史が長い軸になるはずなんです。
 |
ただその一方で、森川さんの後に続く人は天才じゃないので、仰るとおりどうやって巧く分業していくかが重要だと思います。僕にしたって、AIが解ってプログラムや分析はできますが、デザインはほかの人にやってもらうしかないわけです。
森川氏:
こういうことを言うのはちょっとおこがましいかもですが、これまでなら僕個人で終わっちゃうはずだった仕事が、AIの認知にともなって次に継承できるようになりつつあって、いまは単純にものすごく嬉しいんです。それをうまく継承するのが、自分の人生の最後の仕事だと思ってやっていますね。
──ただ、その継承や分業にあたって、AIの知識とそのゲームデザインへの応用のセンスって、そもそも切り離せそうにもなく。できるものなのでしょうか?
三宅氏:
この15年のゲームの歴史って、ゲームデザインやAIが渾然一体となっていたところから、独立した技術としてAIを切り出して扱えるようにしてきた歴史でもあるわけです。
キャラクターAI、メタAI、ナビゲーションAI、会話AI、感情AI……と、ゲームデザインからいろいろAIを取り出してきた。そしてAI開発者の尽力により、その取り出したものをUnreal Engineや Unityなどによって誰もが使える民主的なものにしてきたわけです。不可能ではないでしょう。
森川氏:
あとはまあ、ひとりの人間の中で統合するのはなかなか難しくても、有機的なチームを作ればいいかもしれませんよね。
本城氏:
専門学校などで、プランナーにAIの授業を真剣にやれば、状況もガラッと変わる気はします。
今日幾度となく話に出ていますが、ゲームデザインにおけるAIって、アカデミズムとは全然違う使いかたなんですよ。
キャラクターを動かしているスクリプトの定義を、別に用意した遺伝的アルゴリズムで最適化するというようなことをしていたり。これによってたとえば敵の攻撃パターンを読めなくさせたりできるわけです。そんな仕組みって、アルゴリズムの特性などを深く理解していないと、まずゲームに入れようとは思わないんですよね。それはやっぱり教育でどうにかするしかないと思いますね。
──それってもはや「いきなり畑は作れないから、土を耕し、肥料から地道に蒔くしかない」という話ですよね。
成沢氏:
でもそれがなければ始まりませんから。あと、ビジネストークで申し訳ないんですけど、志のある方は、モリカトロンにぜひ入社していただければ、いちばん近いところに大先生がいらっしゃるので……(笑)。
 |
一同:
確かに(笑)。
海外が作るのは考えるAI、日本が作るのは生命そのもの
──そこで最後に、最初の話に戻っていきたいと思うんです。森川さんの存在から、逆に日本のゲームAIの特徴というのが見えてこないだろうかと。
三宅氏:
欧米のAIというのはつねに「考えるAI」だと思っています。
ゲームで言えば、FPSにおける兵士のキャラクターであり、リアルタイムストラテジーにおける戦略家のイメージなんですよ。
それに比べて日本のAIというのは、まさに森川さんの仕事が象徴するように、「生命としてのAI」なんです。だから、ある意味では賢くなくても意図や感情を感じられればそれでいい。知能というものを極めて柔軟に捉えているのが日本のAIだと思います。
 |
海外の合理的なAIを見ていると、「そうした柔軟性などはちょっと欠けているな」という所感を抱きますね。日本って、むしろ非合理なものだったり、賢いのか賢くないのかちょっとよくわからないものを作るんですよね。
でも本来の生物だってそうじゃないですか。別にいちばん頭がいい生物が生き残るわけじゃなく、柔軟に環境に適応する能力があるほうが大事なわけですよ。
──確かに、凄く広い視野で知能を捉えてみると、そう言えるかもしれませんね。
三宅氏:
だから、さきほどの夢の島の話じゃないですが、そうした生物界の多様性をそのままゲームに持ち込むセンスを日本は持っていて、それはよく言われるゲームデザインの多様さにも現れていると思うんです。
そして、ゲームデザインが多様だということは、そのぶんじつはゲームAIの形も多様であるはずなんです。
いまのAIの捉えかたは、とにかくディープラーニング一辺倒になってますが、AIにはもっと多様な方向があるわけで、僕はその中に日本が取り出すべきAIがあると思っています。
森川さんの仕事は、その中のニューラルネットワークや遺伝的アルゴリズムでの開発をすでに実現してくれているわけで。
──言われてみれば、象徴的なのかもしれませんが、森川さんのゲームには動物や謎の生命体がたくさん出てきますよね。
森川氏:
ああ、確かに。最初から「AI=生き物」というのは、自分の中で完全に紐づけて考えていましたね。
そこに疑いの余地すらなかったのは、やっぱり日本人だからかもしれませんね。典型的なのは、日本って産業ロボットに名前を付けちゃうような国で、そこらへんの感覚が西洋人とはまったく違いますしね。
三宅氏:
そもそも西洋では人間以外に魂を認めることは、厳格に宗教的に言うとダメなはずなんですよ。
たとえば、『たまごっち』もそれで問題になったりした過去があります。日本人にはいろいろなものに生命を認める付喪神や八百万の神の感覚があり、だからこそキャラクタービジネスがこんなに花開いているのだとも思います。
 |
そうした日本人の生命観とAIは、まだ融合していないんですよ。じつはそこの可能性を探るだけで、西洋では絶対に作れないオリジナルなAIができると思うんです。そここそが日本のAIが海外に圧勝できる部分だし、とくにゲームというコンテンツとは激しくオーバーラップするわけです。
まずはゲームがそこに眠る可能性を掘り起こして世界に提示できれば、ゲーム産業以外のところでも生命ライクなものが生まれてくるんじゃないかと思っています。
──以前の三宅さんへのインタビューでは、海外でAIが異常に発展したのは、やっぱり人間中心主義への異常なこだわりがあったからという話がありましたね。
三宅氏:
そこで重要なのは、日本はゲームとしてのレベルデザインが優秀だったので、NPCなどキャラクターの知能が低くても成立するようなゲームを上手いこと作れてしまっていたわけですよ。
だからこそ、海外のFPSで「兵士は戦場でちゃんと自分で動いてくれ」というようなAIを作り始めていたときでさえ、日本はキャラクターに知能を負わせないように発展してしまったのかもしれません。
──高度に発達しすぎたレベルデザインによって、キャラクターにAIを加える発想が出てくるのが遅れてしまったということですね。
三宅氏:
本来はそこにAIも加えれば、むしろもっと幅広いゲームデザインができたはずなんですよね。
その部分で、日本は行き詰まっているんじゃないかと思うんです。
しばらく、大型ゲームはとくに海外のオープンワールドやFPSの流れから逃れられない部分もあると思いますが、我々のポテンシャルは西洋の歴史を追うだけでは全然足りないと信じています。
だからこそ、僕は日本のゲームAI史を引き続き掘り起こしていきたいと思うんです。
モリカトロンの今後
──さて、最後に森川さんの新会社、モリカトロンの話を伺って締めとさせていただければと思います。
成沢氏:
私がずっと森川さんと付き合ってきたのは、ひとえに、森川さん自体に予定調和な部分がないからですね。
ビジネス上、プロデューサーというのは予定調和を組まなきゃいけない立場なんですが、私自身は予定調和が好きではなくて(笑)。森川さんの作り出すものは予定調和のないものですが、作っている本人も当然、予定調和じゃないんですよ(笑)。
それから……偉そうな意味ではなく、これは私から森川さんへの恩返しでもあるんです。
森川さんには、ゲーム業界の大大大先輩として本当に緊張しながらお会いしたときから、「ゲームとは何か」ということを教わり続けてきたんです。
当時のエニックスのプロデューサーって、ゲームの知識がない人でも採用されたんですけど、中でも私は法学部出身でゲームは好きだったけど、専門知識としてはまったくゲームを知らなかった。
ではどうやって仕事を覚えるかというと、先輩のやっていることを見て覚える以外に方法はなかったんです。そんなとき齊藤さんと森川さんが『アストロノーカ』を作るという、いちばんいい時代の風景を見せていただき、育てていただいたわけなんです。
 |
ですからモリカトロンを設立する前に、森川さんがご自身の年齢のことを話されたことがあって。そこでは「僕の年になると、あと1回か2回しかできることがないんだ。僕が最後に賭けるのはAIだ」と仰っていた。だったら私はそんな森川さんの賭けに乗るしかないじゃないですか。
──思いの強さが伝わりますね。そんな経緯で立ち上がったモリカトロンがする仕事については……本城さんにお伺いしましょう。ゲームのAIの部分を専門で手掛けるというのは、具体的にはどういう業務になるのでしょう?
本城氏:
そもそも、「ゲームAIの組み込みを20年間ずっとやってきた人」って、日本ではあまりいないと思うんですよね。そうした森川さんの培ってきた技術を、「AIってこんなこともできるんだよ」と解りやすい切り口で現代的に提示して、いろいろな会社のゲームに組み込んでいくということをやっています。
というのも、ゼロからAIを学んでアルゴリズムを理解し、それをゲームに適用してちゃんとした結果が出るまで全体を設計して……というのはかなり骨が折れる仕事なんですよ。
森川さんはそのアルゴリズムを知っているだけじゃなく、いかに使いこなすかのノウハウをめちゃくちゃ持っているわけで、そこに関してはゲーム業界に非常にニーズがあるんですよ。
 |
具体的に言うと、いまは大きく分けてふたつの仕事の柱がありまして。
ひとつは「森川トーク」という自然言語処理系のエンジンです。これはアドベンチャーゲームのシナリオなどを、AIがキャラクターの自然な言葉のやり取りとして出力してくれるようなものですね。「チャットボットのようなもの」というより、本当に感情を持ったキャラクターのAIを作っている感じなんですよ。
もうひとつは、バランス調整を自動で行うエンジンです。ひたすらゲームのプレイをオートで進め、面白いポイントを抽出したりするものをイメージしてくださればと思います。
AIって何でもできるわけじゃなく、イメージとしては、デザイナーがPhotoshopを使うようなものなんです。描いた絵のトーンを下げたり色を変えるというときに、「手で描いたら大変なので、ボタンひとつでパッと変えちゃいましょう」というもの。
ゲームバランスだって、いままで全部手でやっていたものを「だいたいこんな感じ」みたいな感じで適当にやってくれる、便利なアシスタントみたいなソフトウェアのイメージだと思っていただければいいですね。
──丁寧な解説、ありがとうございます(笑)。
成沢氏:
こんな感じで、本城さんが経営の舵をちゃんと切ってくれていて、森川さんはそれに合わせて研究をしてくれているんです。
そこはもう安心してお任せしていて、私は本職がプロデューサーであるとおり、このおふたりがいちばんいい運転ができる場を作って、盛り立てていくというのが仕事ですね。
──伺っていると、とてもいいトリオのように感じます。そのトリオが最終的に目指していることはなんでしょう?
本城氏:
もともと「モリカトロン」というのは、森川さんの考える究極のAIモデルの名前なんです。
だから、いまはとにかくゲーム開発に役立つAIを作っているんですけど、いずれはそうした日本国内のAIの歴史の流れを汲んだ、ゲームデザインと結びついたゲームAIを作っていきたいんですよね。
森川氏:
そうそう。『がんばれ森川君2号』を作っていたとき、最初はニューラルネットワークがあまりにも大きすぎて入らなかった。それで、仕方がないからモリカトロンという自作のAIを作ろうとして。
それは、シグモイド関数【※】の代わりに別の関数をうまく入れ込んだ、もっと軽量化したAIだったんですが、そのときは結局うまくいかなかったんです。
だからそのときに作れなかった、自分たちのオリジナルなAIをいつか作りたいと思っています。
※シグモイド関数
ニューラルネットワークの概念を扱うときなどに用いられる、生物の神経細胞の仕組みをモデル化した関数。
──そんな森川さんが「最後の仕事」として賭けているオリジナルなAIに期待するとともに、この遺伝子をどう受け継いでいけばいいのかという大きな宿題を、今日はいただいた気がします。今日は長時間ありがとうございました!(了)
 |
AIを用いたゲームのパイオニアたる森川氏に、その先進性やゲームへの効果的な使いかたを伺おうと始めた取材だったが、AIはあくまで手段。森川氏の作るゲームは、すべてゲーム体験の楽しさをいちばんとする思想に貫かれていた。
ニューラルネットを使いながら、ときには“脳”そのものを入れ替えていた『がんばれ森川君2号』。
遺伝的アルゴリズムを用いながらも、「表面的に進化が感じ取れればいい」と、敵キャラの世代をスキップさせていた『アストロノーカ』。
そしてさらに、オントロジーを採用しながらも、テキストを歌詞にし、メロディに乗せることで違和感をなくしていった『くまうた』。
このように森川氏の手掛けたゲームは、つねにAIへの高い知見とゲームデザイナーとしての抜群なセンスが高度な次元で融合したものだった。
この融合が氏の個人的な能力に依存していると理解することは容易だが、その発端が1990年代後半の出来事であることは、にわかには信じがたい。
それがあまりに早すぎたがゆえに、氏の業績が現在もそこまで高く認知されていないことも事実だ。今回記事で取り上げたような功績が、現代の目線からあらためて広く正しく評価されることを願う。
三宅氏の言葉を借りれば、現在のFPSやRTSに登場するキャラクターたちは、つねに考える非常にロジカルな「西洋的なAI」だという。
これらに対して森川氏が手掛けてきた「ある意味では賢くなくても意図や感情を感じられればそれでいい」という、「知能」を極めて柔軟に捉えた「生命としてのAI」は、「東洋的なAI」と言えるだろう。
実際に森川氏もみずから手掛けたものでありながら、自律的な知性や感情、つまり「命や魂みたいなもの」をふとした瞬間に感じると語っている。
その感覚や感動を届けたくて氏はゲームAIを作り続けているのだ。
その感動をさらに拡げるべく、いま現役クリエイターとしての最後を時間を懸けるに値する仕事として、新しい会社モリカトロンを築き、それまで個人の内に培われていただけだったゲームAI構築のノウハウをもっともっと広げようとしているわけだ。
西洋的なAIと日本のゲームがいまだ完全に融合していない現在、東洋的なゲームAIのパイオニアたる森川氏が進んでいく先には、その融合点たり得るものが現れ、広がり、やがて一般的なものとなっていくことだろう。
そのときそこには、20年来変わらずゲームAIと戯れ、彼らの行動を神様のようにニコニコしながら見守ったり感動したりしている森川氏の姿があるのだ。
【あわせて読みたい】
21世紀に“洋ゲー”でゲームAIが遂げた驚異の進化史。その「敗戦」から日本のゲーム業界が再び立ち上がるには?【AI開発者・三宅陽一郎氏インタビュー】21世紀の世界のゲーム市場で日本が存在感を失った原因は「AI技術の軽視」にあった!?AI開発者・三宅陽一郎氏を迎え、21世紀に「海の向こう」で驚異の進化を遂げてきた、ゲームAIの歴史、そして同時に、日本のゲーム産業が3Dゲームの発展の中で、世界市場の「蚊帳の外」に追いやられていく十数年の歴史について伺った。