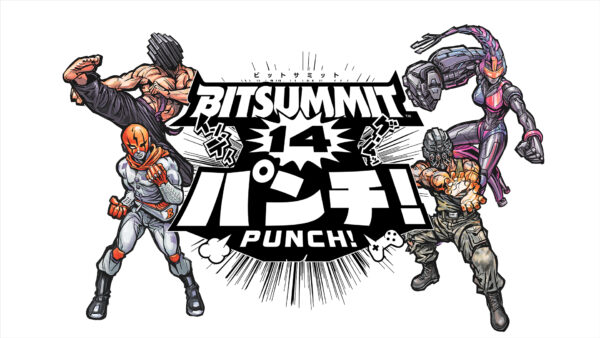「聖地巡礼」とは、日常空間にアニメという非現実が侵食してくる「体験」である
──いま土屋さんがおっしゃられたのは、時間や空間といったものを、プレイヤーとキャラクターが共有していると思える感覚のことですよね。
音楽業界でCDビジネスが成立しなくなった結果、ライブを中心にして収益を得るようになりました、という話があるじゃないですか。そういう話も含めて最近よく言われているのが「体験価値」。大量生産・大量消費の物質的な価値から、体験を中心した価値へと移り変わったことを考えると、一度きりのイベントとか、ライブ感とかがすごく重要で。みんな、なんとなくそのことをわかってはいるんだけども、じゃあそれをコンテンツに設計として盛り込めているかというと、そこはけっこう難しくて。
土屋氏:
それも私がいつも思っていることのひとつですね。いまは本当に体験ってスゴイじゃないですか。リアル脱出ゲームが流行っていますけど、無機質な日常の中で非日常感を体験として味わえる、そういったものをみんながすごく求めていることの表れだと思うんです。
先ほども申し上げましたが、私がやりたいことは、イヤな日常からひと時、別の世界に行けるという、本当にリアルな世界の構築。いい意味での逃げ道ですね。安心して非日常に浸かることのできる体験を、つねに新しい形で出していくというのがひとつの命題になっています。
──その「日常と地続きになっている非日常感」みたいなものが、ほかのコミュニケーションゲームとも違うし、ユニバース的な世界観のRPGとも決定的に違う、『サージュ・コンチェルト』ならではのところだと思うんです。そういう日常と地続き感のある作品というのは、土屋さんとしてはほかに思い当たりますか?
土屋氏:
どうでしょう、何かありますかね……。少しジャンルが違うかもしれないですけど、ちょっと前から「聖地巡礼」というのが流行っているじゃないですか。私はあれも、現実の中の非現実だと思っていて。
たとえばゲームやアニメの中で秋葉原が登場したりすると、多くの人が、普段は買い物や仕事で訪れるだけの場所に、ゲームやアニメの舞台という「非現実」が入り込んでくる。ゲームやアニメは嘘だとわかっているんですけど、でも本当にあったんだ、という感覚。これも「現実侵蝕」による非日常的な体験だと思うんですよ。
いままで、ただ無機的に気力なく歩いていた場所が、ゲームやアニメの聖地となることで、そこを歩くだけでも楽しい場所に変わる。そういうのも社会の潤いとして、すごく大事だと思っています。
 |
──なるほど、それはよくわかります。
土屋氏:
聖地巡礼みたいなことは、『シェルノサージュ』をやっていたときから思っていたのですが、『シェルノサージュ』の舞台は異世界なので、この現実の世界とは重ならないわけですよ。そこは弱点だなと思っていて。
実は『シェルノサージュ』や『アルノサージュ』の後に『拡張少女系トライナリー』を作ったのは、そういったものを表現したかったから、というのもあるんです。だから『拡張少女系トライナリー』は東京が舞台になっていて。
少し話がズレてしまうんですけど、『拡張少女系トライナリー』を作っているときに大事にしていたのは、「いまあなたが住んでいる世界の、この場所に彼女がいた」というのを明確に提示する、ということだったんです。“ここにはこういうものがあって、彼女がなぜここにいたかというと、ここにあるこれを使いたかったからだ”、というところまで全部、東京を使って表現したんですね。
『拡張少女系トライナリー』に出てくるヒロインたちはカフェが大好きで、それぞれ実在のカフェを自分のお気に入りにしていたんです。ヒロインのうちのひとりに神楽っていう子がいるんですが、その子がシャッツキステさんというカフェが大好きで。シャッツキステさんは『シェルノサージュ』でも懇意にしていただいていた経緯があって、『拡張少女系トライナリー』でもコラボすることができたのですが、その時にも現実代替的な事を色々やりました。お店のノートに彼女たちの落書きが追加されていったり、お店のメイドさんに彼女たちのことを話すと「実際に来ましたよ」と言ってくれたり。
 |
周りの人が「そうだ」と言えば、それが本当になってしまうんですよ。だから、シャッツキステさんにいるメイドさん全員が「神楽ちゃんなら昨日来ましたよ」と言えば、それはもう現実だと思うんです。そういうのがどんどん積み重なっていくことで、良くも悪くも、嘘だって本当になっちゃうわけですから。悪用すれば社会問題になってしまうジレンマがありますけど、一方ではそれをエンターテインメントとして、ユーザーさんに楽しんでいただくための嘘を徹底的につき続けて、ポジティブにいい意味で騙していければな、と。
そういう形の、“非現実なんだけど現実”という「現実侵蝕」ですね。それはこれからもガンガンやっていきたいと、自分の中ではそう思っています。
──ベストセラーになった『サピエンス全史』【※】という本があって、その本は「人類は嘘によって進化した」と言うんですよ。たとえばお金というものがあって、これが物と同等の価値があるというのは、言ってしまえばフィクションなんだけど、これを全員が信じることによって成立する経済システムがあって、そのおかげでみんなが幸せになるという。そんなふうに人間は、フィクションを活用して進化している。フィクションは人間にとって重要なものなんだと。ゲームをはじめとするエンタメも、その現代版というか。
※『サピエンス全史』
イスラエルの歴史学者ユヴァル・ノア・ハラリ氏による世界的ベストセラー書籍で、日本でも2016年に刊行されて話題となった。ホモ・サピエンスだけが持つ「虚構を信じる」という能力から全人類史を俯瞰し、これから人類が辿るであろう未来を予測している。
土屋氏:
本当にそうだと思います。ゲームやアニメといったコンテンツも、周りの人からすれば、その作品にファンが没頭する姿に驚いて「この人、すごい……」って思うのかもしれないけど、その人にとってはそれが癒しであって、それが明日への活力になるのだから、他人に迷惑さえかけなければそれでいいと思うんです。その世界に没頭することで明日への活力に出来るものが作れるなら、それは素敵なことじゃないですか。
──あるゲームクリエイターの方と、「人間にとってゲームとは何なのだろう」という話をしたことがあるんです。まず前提として、人間の富の価値はこれまで物質の総量で計算されてきたんだけど、いまは物質的な総量が頭打ちになってきたというのがあって。昔はお腹いっぱい食べられることが幸せだったけど、誰もがお腹いっぱいになっているのが前提の中で、何を価値とすればいいのかというのが、21世紀以降の人間社会の課題だと。
「そのときにゲームは、現実世界の価値の総量を増やすものなんじゃないか」と、そのクリエイターさんは言うんですね。本当は別に価値がないんだけど、敵を倒しまくることによってレベルが上がる。つまりそのゲーム空間の中では、現実世界とはまた違った価値が生まれている。
いまの子どもって、勉強でもスポーツでも一番になれるのは一握りで、どれだけ成功体験を持っているんだろうと。そんな中で『ポケモン』でモンスターを全部捕まえたといったことを、自分の武勇伝として語ったりするじゃないですか。それって要するに、勉強やスポーツで一番になるのとはまた違う軸の価値を、その人に体験価値として与えているわけで。ゲームとはそういった形で「人間の体験価値の総量を増やす」ものだと、そのクリエイターさんは言うんです。
たとえば位置情報ゲームなどでは、現実空間における土地の価値の上にもう一層、「ここはレアなキャラクターが出やすい」といった情報価値が重なって、世界の価値の総量が増えているわけですよね。
土屋氏:
究極的には位置情報ゲームも、聖地巡礼と同じコンセプトとも言えますよね。プレイしている方にとって価値のある場所が、未プレイの方の価値とは違っていて。そこに行くことによって全員が価値を共有できるわけではないんだけれど、自分にとってはまぎれもない価値が得られる。それを世界全土に普及させたのがスゴイところだと思います。
──本当だったら誰も集まらないはずの公園に、「ここにはレアなキャラクターが出る」ということで多くの人が集まるという、現実的な価値が生まれているんですよね。あの感覚は、これまでのコンピューターゲームという概念からは、かなり広がったものだと思うんです。そういう意味では、土屋さんの目指す地続き感だとか世界観といったものも、シンクロしていると思います。
土屋氏:
『拡張少女系トライナリー』でも、本当は敵のボスをこっちの世界に連れてきたかったんです。プレイヤーは向こう側の世界を平和にするために、彼女たちを支援しているんですけど、そうすると敵のボスとしてはもとを絶とうとするから、支援しているプレイヤーのほうに矛先を向けるはずだと。渋谷の109付近にボスが出現して、実際に現地へ行くとARでボスが現れるから、みんなでレイド戦をやろうとか。あとは現実の街中に散らばっている、クランっていうポケモンみたいなものを集めよう、といったアイデアも最初の構想にはあったんです。そういうところも含めて、タイトルに“拡張”という言葉を使っていたんですけど。そういうものをずっとやりたかったというのはありますね。
『シェルノサージュ』は、ファンとコンテンツが一体になったロールプレイで成り立っていた
──アイデアがあったとしても、ビジネス的にそれを実現できるかどうかはすごく重要だと思うんです。そういった中で、いま、『シェルノサージュDX』を発売する意図はどういったところにあるのですか。
土屋氏:
私としてはつねにいろんなアイデアを考えています。とくに『シェルノサージュ』に関しては、自分自身でいうのはなんですが、設計としては先駆性がかなり高かったと思っています。ただ、当時のガストとして実現できたこととのあいだに、多少乖離があり、ユーザー様にご迷惑をかけてしまったと感じています。
そういった反省もある中で、なぜいま、『シェルノサージュ DX』を発売するのか。はっきり言ってオフラインにしている時点で、我々が当時望んでいたコンセプトはかなりの部分、排除されてしまっているんですよね。
それでもなぜ、『シェルノサージュ DX』を出そうとしているのかというと、「メモリアル」ということなんです。
人生って二度同じことを経験はできないけど、アルバムで写真を見返すことはいつでもできるじゃないですか。そういうことって大事だと思っていて。
 |
──最近だとソーシャルゲームをサービス終了後にオフラインにして、シナリオだけでも残したいという発想に通じるものがありますよね。
土屋氏:
“そのときだけしかできない体験を得る”ということについては、スマートフォンアプリの得意分野だと思っています。けれども一方で、そのときのことを思い出としてだけでしか残せないというのは、あまりにも残酷だと思っているんです。そういう意味ではスマートフォンのタイトルは全部、アーカイブ化して追体験できるものが残せるといいな、と昔から切実に思っています。ただ、スマートフォンに関してはOSのアップデート等によってアプリが起動できなくなってしまうこともありますよね。
逆に言うとコンシューマーの強みは、ハードさえあれば10年前のソフトだって遊べる点にあるとは思うんです。でもそれだと少し手間がかかるから、『サージュ・コンチェルト DX』のようにリマスターすることによって、お客さんにとってもより便利になるし、以前よりも映像のクオリティが上がるしで、良いこと尽くめになるんじゃないかなと思ってます。
 |
かつての『サージュ・コンチェルト』で感じたのは、ハードをまたぐことの難しさなんです。『アルノサージュ』は最初、PS3で発売されたので、PS Vitaで『シェルノサージュ』を遊んだユーザーさんの中には遊べない方もいらっしゃったんです。『サージュ・コンチェルト』を地続きに楽しもうと思うと、PS VitaとPS3の両方を持っている必要がありました。もちろん『アルノサージュ』単品でも楽しめる作品になっていましたけど、『シェルノサージュ』があったからこそ楽しめる体験というのが、確実にあったわけですから。
あとになって『シェルノサージュ OFFLINE』と『アルノサージュ PLUS』という形で、同じPS Vita上のコンテンツとして発売しましたが、今回の『サージュ・コンチェルト DX』に関しては、最初からPS4、Switch、Steamという同一のプラットフォームで、地続きの体験ができるところも大きな魅力だと思います。
こうやって思い返してみると、やっぱり反省点の多いプロジェクトなんですよ。当時の我々としては高いところに目標を置いて、力を出し切ったタイトルではありますけど、実際にやってみるとうまくいかないところもありましたし。一方ではその結果として、様々な施策やコンテンツが生まれて、コアなユーザー様がついてくださったというのもあるんですが。
──当時のユーザーは、どういう年齢層だったのですか?
土屋氏:
だいたい20代後半から30代前半、30代前半がいちばんの山だったかなと思います。
──RPGというよりは、ノベルゲーに近いユーザー層なのかな、という印象を受けますね。
土屋氏:
まさにそんな感じだと思います。 我々としては、イオンをフックにしたコミュニケーションツールとしてコミュニティを維持したかったのですが、ユーザーさんはイオンに注目されることが多くて、我々が意図したユーザー間のコミュニケーションツールとしてではない楽しみ方をされる方が圧倒的に多くいらっしゃって、そのあたりも我々の想定と異なってしまったところですね。
最初はすごく盛り上がったんですけどね。バーコードでいろんな企業さんも掲示板に入ってきてくださったりして。これは盛り上がるかなと思ったら、そこで終わっちゃった。
本当はこのバーコードの仕組みを使って、いろんなものとコラボをしたかったんです。現実にあるお菓子の箱を背負っているシャールとか、そういうのがあったら、みんなバーコードを撮りたがるじゃないですか。そういうところでも常に現実とクロスしたかったんですね。現実にみんながよく知っているものがゲームの中にあることで、ユーザーさんにも盛り上がってほしかったというのがありました。その部分でも「現実侵蝕」をやりたかったんです。
──土屋さんが言われる「現実侵蝕」に関して、僕が思い出すのは、以前に遊園地でヒーローショーを見て、すごく衝撃を受けたことなんです。というのも、子どもたちがショーに出てくるヒーローを、ものすごく熱心に応援しているんですよ。子どもたちにとっては、目の前にいるヒーローは本物で、TVで見ているものとの違いなんてまったくないんです。あの感覚は改めてスゴイなと思いました。
土屋氏:
『シェルノサージュ』は、そういうロールプレイをゲームでやったコンテンツなんだと思うんです。先ほど言ったように、「ゲネロジックマシンという機械で7次元先から本が送られてきました」と言って、コミケの会場で本が売られていても、普通は「そんなわけないでしょ」とか「ただの本でしょ」などと思いますよね。でもロールプレイに参加してくれているファンの方にとっては、「イオンから届いた本」なんですよ。そういう意味では、本当の意味でのロールプレイ(役割を演じる)だと思います。それをあの当時ゲームでやったのは、かなり先鋭的だったかもしれません。
『シェルノサージュ』で初めて雑誌に掲載したティザー広告は、独自の言語で書かれた謎解きみたいな文章が載っている内容だったんです。じつはその広告に出ている文章を全部解読すると、ゲームの壮大なネタバレになるんですよ。ゲームがだいぶ進んだころに、その言語を解説するページを公開したんですが、早速それを手がかりに最初のティザー広告の文章をすべて訳している方がいらっしゃって。「こんなネタバレが書かれていたんだ!」と楽しまれていました。そういう意味でも『シェルノサージュ』は、最初の段階からすでに、ロールプレイが始まっていたんです。
先ほど、『シェルノサージュ』でVTuber的なことをやったという話をしましたが、じつは徳島のマチ★アソビでも、同じようなことをやろうとしたんです。私はそのとき現場にいなかったんですけど、映画館のスクリーンにイオンが登場して、声優の加隈亜衣さんが影ナレをするっていう。
ところが、ひとりのスタッフが、機材をつなごうとしたらHDMIの端子を折ってしまい、映像が出なくなってしまったそうで……。そのときは音響監督の納谷僚介【※】さんが司会だったんですけど、「7次元先のイオンにつながらないので、イオンちゃんとは会えません」とアドリブでフォローしてくださって。ユーザーさんも、あくまでロールプレイとして楽しんでくださっているので、「それなら仕方ないね」と納得していただけて……。あってはならないトラブルなのですが、そのときにこれがファンとコンテンツが一体化したロールプレイなんだなとも感じました。
 |
※納谷僚介
イオン役の加隈亜衣さんが所属する声優プロダクション・マウスプロモーションの前社長で、現在はアニメや洋画吹替の音響制作などを手がけるスタジオマウスの代表取締役社長を務めている。マチ★アソビでは、イベントの司会進行なども多数担当している。
──唯一無二のユニークさみたいなものが、チープな言い方ですけどデジタル社会におけるライブ感だとか、一回性の体験として重要なんだと思います。「この一回だけの体験」ということになると、たとえ同じことをしていても、価値がメチャクチャ高くなるという。
土屋氏:
それはすごくよくわかります。いまはデジタルが自分の生活の中でものすごくシェアを占めていて、スマホを持っていればだいたい、なんでもできちゃうじゃないですか。スマホって基本、サービスが続いているかぎりはやり直しが効くんですよね。何回でも同じものを見られるし、過去の記事も見られる。そんな中でみんなが求めるものは、スマホの外側にある「いましかできない体験」なんだろうなと。
いまはコロナ禍で、さらにデジタルに押し込められているじゃないですか。だからなおさら、そういう欲求がどんどん溜まっているのだろうと思います。私はグッズの企画もしていますが、普段だったらどこかに遊びに行って発散できていたのができにくいし、大きなイベントの開催もほとんどない。そういうなかでグッズを出すと、みなさんすごく関心を持ってくれるんです。そうした反響を見ていると、デジタルではない体験が求められているんだなと感じますね。
──ところで、話が急に飛んでしまうのですが、土屋さんはSFがお好きなんですか?
土屋氏:
SFのジャンルによりますね。宇宙モノや、『マトリックス』みたいな情報モノは好きです。20代のころはSFにまったく興味がなくて、ファンタジー映画しか観ていませんでした。
──それはおもしろいですね。ゲームの設定がけっこうSFっぽいので、お好きなのかと思ったのですが。
土屋氏:
それは結果的にSFになっちゃった、というのが正直なところです。『アルトネリコ』の1作目って、ガチガチのファンタジーなんですよ。表面上は、金属的だったり電子的だったりするものは出さない、という感じで。ただ、これは私の性(さが)なんですけど、ファンタジーには魔法が出てくるじゃないですか。そうすると私は「なんでファイアの呪文を唱えたら火が出るのか」という理屈や成り立ち、歴史を自分なりに作らないと気が済まないタイプなんです。
それはSFが好きだからじゃなくて、これまでの話の繰り返しですけど、本当にリアルな世界を作りたいからなんです。魔法だろうがなんだろうが、理屈を作らないと気が済まない。それが結果的にSFみたいに見えちゃうんだと思うんです。いわゆる一般的なSFって、そういう緻密な設定によって現実じゃないものを現実として見せている作品だと思うんですよね。「サイエンス・フィクション」というぐらいで。だからヘンな言い方ですけど、私が作る作品は“SFが好きだからそれっぽくなっている”のではなくて、“結果的にSFになっている”んだと思います。
 |
若かりしころの情熱を賭した『サージュ・コンチェルト』を、もう一度世に問いたい
──『シェルノサージュ』と『アルノサージュ』の2作品を新しいユーザーに、どのように遊んでもらいたいと思いますか?
土屋氏:
『サージュ・コンチェルト』の2タイトル、とくに『シェルノサージュ』は当時、良い意味でも悪い意味でも話題になったタイトルなので、名前を知っている方はけっこういらっしゃると思うんです。そういう方たちに、「あのときは敷居が高くて手が出せなかったけど、これだったら手が出せそうだな」みたいな気持ちで、気軽に手に取っていただきたいというのがあります。
あとは、今回の記事で伝わっているとうれしいのですが、「いままでよく知らなかったけれど、ほかのゲームとはこんなに違うものがあるんだ」という興味を持っていただければ。いろんなハードに移植する事によって、新たに多くの方に触れていただける機会が作れればと思っています。
──その当時の情熱がわかるエピソードとしては、具体的にどういったことがあったのですか?
土屋氏:
何が情熱だったかと聞かれたら、すべてですよね。もう、向かい風じゃなかった時がなかったので。ローンチの前から。すべてにおいて逆風の中で、とにかくもがき進んだような。
ローンチ後に不具合も出てしまい、改修するのに時間も要してしまいました。ですが多くのユーザー様にも遊んでいただいてそのユーザー様たちを裏切ることはできないので、「絶対に進める」と言い続けてやっていました。
途中で折衷案とか妥協案もが出てくるんですよ。「ここまでやったら止めにしないか」とか、「今年度で終わりにしよう」とか。「ダメです。絶対に最後までやります、やらせてください」というやり取りは、それこそ数え切れないぐらいやっています。
──発売から最後のDLCが出るまで、どれぐらいかかったんですか?
土屋氏:
2012年4月に発売し、2014年7月に最後のDLCを出したので、まる2年以上ですね。
『アルノサージュ』を2014年の3月に発売しているんですけど、じつはそれまでに『シェルノサージュ』のDLCは終わっているはずだったんです。時期はずれてしまいましたが、それでもきちんと完結したというのは開発チームとユーザー様の情熱がすべてだったかなと思います。
みんな、なんだかんだ言いつつも最後まで共に歩んでくれました。運営が始まってからはほぼ、運営チームのメンバーは替わっていないんです。メンバーのみんなにも本当に感謝しています。
──そのころ、土屋さんはおいくつぐらいだったんですか?
土屋氏:
30代後半ですね。38歳ぐらい。
──それはまだ血気盛んですね(笑)。
土屋氏:
たしかに、あのころはみんな若かったですね。『シェルノサージュ』チーム自体が若かったので、いろいろなことを勢いでやっていた面もありますね。
「ガスト・ガーラ」というガスト作品のステージイベントが、2012年の7月にあったんです。そのとき、『サージュ・コンチェルト』はまだ立ち上げたばかりで、お客さんも少なく、どちらかというとイベント内では『アトリエ』シリーズがメインという扱いだったんです。それに対して納谷さんは「おかしいでしょ」と怒ってくださって。『シェルノサージュ』のドラマCDを作ってくれたんですよね。ほかにも、電撃PlayStationで『シェルノサージュ』の担当編集の方もイベントの司会をしてくれたり。
『シェルノサージュ』は本当に、ファンの方はもちろん、周囲のそうしたたくさんの関係者の方の愛によっても支えられたコンテンツでした。
 |
『シェルノサージュ』を通して学んだIPビジネスが、いまのガストブランドのべースに
──コーエーテクモゲームスに入ってから、ガストの中では何か変わりましたか?
土屋氏:
大きく変わりましたね。ガストってもともと、同人気質なんですよ。ガストにもこれまで、当たる波が何度か来ていたんですが、良くも悪くもずっと同人気質で自分たちのやりたいものばかり作ってきたので、チャンスを活かしきれなかったんです。もちろん、だからこそクリエイター色の強いものを出せた部分もあるんですけど。
現在は、第三者評価機関など、さまざまな面で効率化が進んでいますし、クオリティも上がっていると思います。同人気質だったころのガストといまとでは、ぜんぜん作り方が違ってきているなと思いますね。
どっちが良い悪いはないと思います。時代の波もありますし。当時はコンシューマーだけがすべてでしたが、いまはスマートフォンとのせめぎ合いだったりとか、売り方も多種多様になっているので。
そういう意味では、昔はゲーム業界全体で同人っぽいところがありましたから。それに比べるといまはビジネスがすごく前に出ているというのはあって。ただ、それが良い悪い、というのは無いと思うんですね。
コーエーテクモゲームスとしては、取締役社長の鯉沼や代表取締役会長の襟川が、ガスト色というものをすごく重要視してくれています。細井がブランド長になっていますし、私はシニアマネージャーとして開発の中に入っています。さらにガストブランドの商品チームも私を中心に回っていますので、その点で言えば、ガストの色というものをすごく大事にしてもらっていますね。
作品性に関しては「ガストとしてこういうことをやりたい」ということについて、基本的には否定はされないので、すごくやりやすいと思っています。
マチ★アソビも、もともとはあんなに毎年行く予定はなかったんですよ。でも、ああいうイベントに参加し始めたのも『シェルノサージュ』からでしたね。ガストブランドとしてコミケに出展したのも、『サージュ・コンチェルト』が最初ですし。
最初のコミケ出展は「ななじげんや」という『サージュ・コンチェルト』専門のブースだったんですよね。
そういう意味ではいまのガストブランドとしてのベース、いまの商品ビジネスだとかIPへの考え方に影響を与えたのは『サージュ・コンチェルト』なんだろうなと細井も言っています。それは私も強く感じますね。
ゲームとIPビジネス、キャラクタービジネスって、いまはすごく近くなってきているじゃないですか。あのタイミングでそのことに気づけたのは、我々にとって大きな財産ですね。
先ほどのくり返しみたいになりますが、なぜいま『サージュ・コンチェルト DX』を発売するのかというと、その文脈の確認でもあるんです。我々が過去にやってきたことを、いまこのときにもう一回アプローチさせていただいて、その反応を見てみたいという。
『アトリエ』シリーズもそうなんですけど、我々はつねにユーザーさんの反応を見て、ユーザーさんがどういうものを求めているかを見て、そのうえでユーザーさんが思いも寄らないものを提案できるか、ということを考えています。『サージュ・コンチェルト DX』は、そのひとつの試金石なんです。
(了)
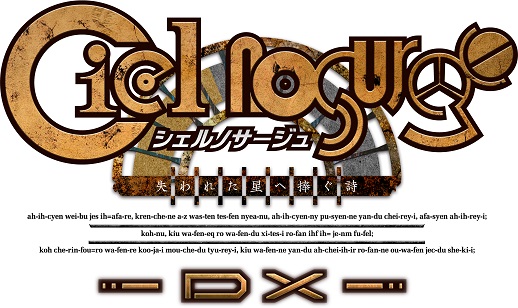 |
 |
2012年にPS Vitaで『シェルノサージュ』が発売された当時、正直言って筆者は、なぜこのソフトは「オンライン専用」でなければいけないのか、理解できていなかった。ある意味、今回の取材によって初めて、このソフトの持つ真価を理解できたと言えるだろう。
プレイ情報をサーバーに集積してゲーム外のイベントに活用すること。ゲームを通じたコミュニティの形成。そしてキャラクターの実在を「体験」として実感させるためのさまざまな仕掛け……。こうした要素は、オンラインに常時接続するスマホをほとんどの人が持ち、家庭用ゲーム機のオンライン接続が当たり前となった2020年現在では、どれも普通に行われていることだ。それを2012年の段階で企画し、さまざまな困難に直面しながらも実現させていった土屋氏の発想と行動力には、改めて感服する。
そして、そうした施策への理解が進んだいまこそ、そうした仕掛けの部分を超えた『サージュ・コンチェルト』というゲームシリーズの持つ本来の魅力が、改めて見えてくるのではないだろうか。当時を知る人だけでなく、まったく白紙の状態で新たに触れる人まで、現在のゲームファンが『サージュ・コンチェルト』にどんな反応を見せるのか、筆者としても楽しみだ。
【この記事を面白い!と思った方へ】
電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。
頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応
※クレジットカードにのみ対応