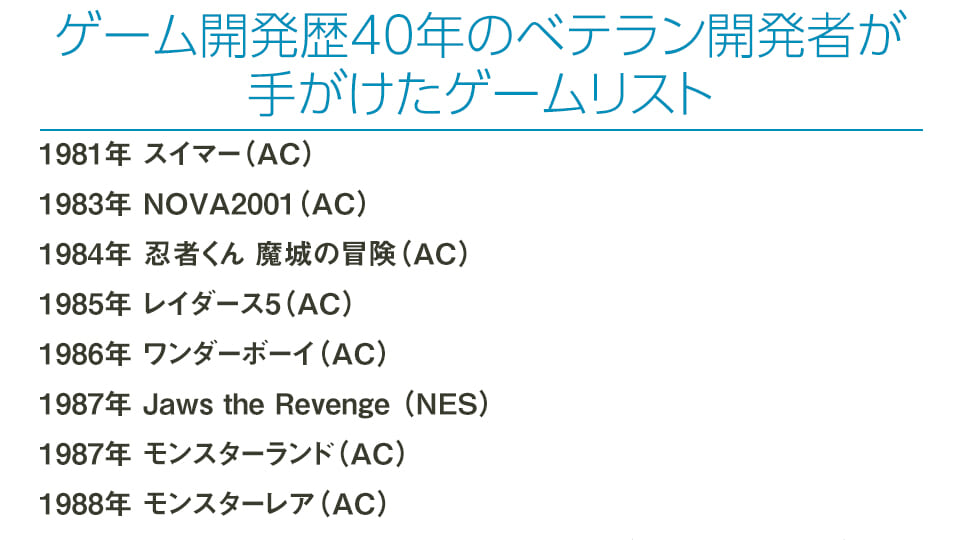「誰でもゲームを作れるわけではない」と、現場を離れて初めて気がついた
──石塚さんが辞められる時、つまりウエストンの中期には、社員は何人ぐらいいたのですか?
西澤氏:
30人ぐらいで、ラインは3〜4つぐらいありました。石塚さんと僕がそれぞれ1~2ラインぐらいを受け持って、坂本慎一さん【※】がもう1ラインを担当して。
※坂本慎一
16歳でテーカンに入社し、日本マイコン開発(NMK)で『アーガス』などの開発を手がけた後、ウエストンに入社。『ワンダーボーイ モンスターランド』をはじめとするウエストン作品のサウンドを担当し、同社の後期にはゲーム開発のディレクターも務めた。
──ということはゲーム開発の規模としては、1チームが10人いかないぐらいですか?
西澤氏:
そうですね。音楽など部分的にどんどんと外注にお願いするようになっていたので、コア部分だけのメンバーが社内にいた、という感じですね。
──ウエストン中期ぐらいの頃は、西澤さんとしてはゲームを作るのが楽しかったですか?
西澤氏:
僕が現場で作っていた頃は楽しかったですね。今でこそできないけど、予定の期間を超えてまで、本当に納得するまでずっと作っていたんですよ。そうやって作って評価も高くなって、開発予算をオーバーしたんだけどそれを売り上げで取り返す、みたいな形をずっと続けていたので、結果的にはそういうサイクルで作るのが当たり前になっちゃった。
だから、それがだんだん許されなくなってきてからは作るのが難しくなってきたし、つまらなくなってきちゃったんですよ。
 |
──それでゲーム市場全体の勢いが落ちていくと、売り上げで取り返すことが難しくなって……と、いろいろ重なってくるわけですね。
西澤氏:
そうですね。ワガママを言って「あと半年作らせてください」とお願いして追加予算をもらったり、自分たちの自腹で出したりして作り続けて、結果的に評価がすごく高くなったから、周りも納得できたんです。
でもそれができなくなってからはつまんなくなって、「どこで諦めて作るのを止めるのか」みたいな感じになっちゃったんですよね。
──社長としての西澤さんは、かつて自分がやらせてもらったように、若い人に任せてやらせてみる立場ですよね。その時に、ディレクターを任せた人が上手くいかないというのは、何か理由があるのですか?
西澤氏:
そこは僕も知りたいところなんです。じつは僕は最初「誰でもゲームを作れる」と思っていたんですけど、そうじゃないということに気づいたのがこの時期なんですよ。
僕が現場から離れたのは、「僕じゃなくてもゲームを作れるだろう」というのが根底にあったからなんです。でも実際に現場を離れると、「テコ入れしなきゃいけないからこっちのプロジェクトに半年入って」と、途中で僕が入って完成させないといけなくなるパターンが多くなって。
『時計じかけのアクワリオ』【※】も『ダークハーフ』【※2】もそうだったし。その時に「あれ? 誰でもゲームを作れるわけじゃないんだ」というのを初めて知ったというか、認めざるを得なくなったんです。

(画像は時計じかけのアクワリオより)

(画像はダークハーフ | SQUARE ENIXより)
──「途中からプロジェクトを立て直す」とは、具体的にはどういうことをされるのですか?
西澤氏:
『ダークハーフ』の時はシナリオを全部作り直して、シナリオに沿ってイベントや敵の調整を全部やり直しました。それでも、そんなに面白くはならなかったんです。
その時、「もっと大事なところを最初から僕が作んなきゃいけないんだな」と思いました。たしかにシナリオとかは良くなったんだけど、他のところで面白さが足りなくて、「これは良いゲームだね」というところまではいかない。途中から入ってテコ入れするような形だと、そんなに変わらないというのを、経験的に感じました。
──そのあたりは「面白いものを作れるのはどういう人なのか?」という問いになってくると思うんです。今だったらゲームエンジンが発達していて、それなりに動くものを誰でも作ることができるんだけど、面白いものを作れるかどうかはまた別の問題じゃないですか。
西澤さんがテコ入れに入ったゲームだって、きっと西澤さんが入る前でも工業製品というか、ソフトウェアとしては問題がなかったと思うんです。でもじゃあ、「動くんだけど面白くないもの」を立て直すというのは、いったい何をどうするんだろうと。
西澤氏:
その話を1時間ぐらいできれば、それは記事としてすごく面白いものになるとは思うんだけど、言葉にして語り合うには難しいですよね。感覚的なものがどうしても介入していて、それを複数の人で共有して理解するのがそもそも難しいので。
個別の方法論を語ることは可能かもしれないけど、「なぜそうしたのか」というところは語れないと思うんですよ。だって自分でも分からないところだもの、たぶん。
「自分はこっちのほうが面白いと思った。なぜだか分からないけど、実際そうしてみたら面白くなった。だからみんな見て。もしみんなが面白くないと思うんだったら、また作り直すけど」……って、そういう感じだと思うんですよね。
 |
「なんで面白いか」なんて本人も分からないまま、そこを突き進む時がある。オリジナルでゲームを作る人と、作らない人との違いというのは、「自分を信じて周りを巻き込んで、突き進めるか否か」じゃないのかな。
実現してみせないと、みんなも分からないし、自分も分からない。それでも実現する前に「そこに進もうと決める」ことができるのか、できないのか。説明できないけど、絶対にそれを入れたら面白いよ、という時があるんですよ。ちょっとそれをやらせて、っていう。
──ちなみに石塚さんには、その話は通じたんですか?
西澤氏:
こういう話をしたことはないと思います。彼はエンジニアであって、クリエイターではなかったから。
ただね、石塚さんはゲームを作れたんです。『ワンダーボーイV モンスターワールドIII』【※】は僕がまったくノータッチで、彼が作ったんですよ。その時に僕は最初から、彼がゲームを完成させられることを信じて疑わなかったんです。その頃はまだ、誰でもゲームを作れると思っていたというのもあるけど(笑)。
でも彼は実際に作り上げたわけですよ。だから同じことを他の人もできると思っていたけど、できない人もいた、という感じで。
ひょっとすると、石塚さんも僕もゲームを作れるけど、他の人が作れない理由は、他にあるのかもしれない。クリエイターという仕事に就かなくても、ゲームを作れるかどうかは別の次元にあるということですよね。プログラマーであっても面白いゲームを作れる才能を持っている人がいるわけだから。

(画像はゲーム紹介「ワンダーボーイV モンスターワールドIII」|SEGA AGES ONLINE セガエイジスオンライン- 公式Webサイトより)
──ちなみに石塚さんは、プログラマーとして何がどうスゴイ方だったんですか?
西澤氏:
すごく良い質問だと思います。その答えは、「分からない」です(笑)。技術的なことに関しては、彼は「お前、そんなコード書いてんじゃねぇよ、馬鹿野郎」という人だったので。
だから僕としては、相当にすごいプログラムを書いている人なんだろう、としか見たことがないんです。ただ他のプログラマーの人たちも「石塚さんの書くプログラムはスゴイっすよ」と言っていたから、きっとスゴイんだろうなと思っています。
 |
──ただ、ゲームのプログラマーの「スゴイ」って、世間一般のプログラマーの「スゴイ」とは、ちょっと違う感じだと思うんですよ。おそらく、純粋なプログラム技術がスゴイとか、知識量がスゴイとかいうことではなくて。僕もよく分かんないですけど。
西澤氏:
僕から見ると、優れたゲームプログラマーというのは、「ゲームの変更に強い」人なんです。仕様設計の変更に対して柔軟に対応できるプログラマーが、良いプログラマーだと思っていて。石塚さんはそういうプログラマーでした。
僕が仕様書を書いて「こういうふうにやってみたい」と言って、実際にそうしてみたら上手くいかないとか、面白くないといったことになるじゃないですか。
「なので、ここをこう変更してみたい」と言った時に、「そう言うと思って、それを変更できるようにしておいたよ」と言ってくれる。「じゃあこれをこの値にしてもう一回やってくれる?」と言ったら、「分かった」とすぐにフィードバックして目の前で見せてくれる。石塚さんはそういうことがパッとできる人だったんです。
たぶん彼の頭の中に「これよりもこうしたほうが面白いかもしれないな」という想像があって、そういう幅を残したプログラミングをしてくれるんだと思うんです。やっぱり、ゲームを面白くするというモチベーションがプログラマーにないと、そういうことってできないと思うんですよね。
──なるほど。
西澤氏:
あとは単純に、技術的にスゴイという面もあると思います。石塚さんの書くコードはとにかく速かったですから。
彼は「プログラムというのはいちばん速いコードを書けば、メンテナンス性も良くてバグもなくて、悪いことは一個もないんだよ」と、いつも言ってました。容量も少ないし。容量が少ないということは、他のデータをたくさん入れられるということで、製品の質も上がるし。
──正論すぎて反論の余地もないというか(笑)。石塚さんがいなくなった後で、社内での西澤さんの立ち位置とか、部下とのやり取りに変化はあったんですか?
西澤氏:
どうだろうなぁ。じつは石塚さんと一緒に仕事をしたことが、ほとんどなかったんですよ。ウエストンの初期はライン数が少ないから一緒のプロジェクトだったんですけど、人が増えてくると、僕と石塚さんは必ず別のプロジェクトだったんです。だからお互いに何をしているか分からない時間が多かった。
でもゲームのハードウェアが進化して、新しい技術をどんどんと覚えなきゃいけないところは、彼が全部面倒を見てくれていたんです。彼が新しい技術を吸収して、社内に共有してくれていた。それが当たり前のようにあったので、何も考えずに新しいハードウェアでゲームを作れていたんですよ。
PlayStationが出ました。セガサターンが出ました。3Dでポリゴンが動くみたいです……という時に、彼がまず最初にそれを使って、基本となるプログラムを作ってくれて、他の人に「こうやって作ればいいよ」と教えてくれる。
なので僕はいつも、プラットフォームを特に意識しないでゲームの企画をしていたんです。そこが石塚さんのスゴイところかな。
ゲーム作りの現場から逃げ出して、Webのシステム開発を行うことに
──ウエストンの後期、社名を「ウエストンビットエンタテインメント」に変更する前のあたりで、事業を縮小されていますよね。その時は、どれぐらいの規模になったのですか?
西澤氏:
30人ぐらいから10数人に減ったので、半分以下かな。本当はもっと縮小しなきゃいけなかったのに、あんまり縮小できなかったので困ったのを覚えています。
──ウエストン時代の後期は、自社で企画したゲームよりも、受託開発とかそういったお仕事が多くなっているのですか?
西澤氏:
そうです。自社でオリジナルを企画したり、パブリッシャーと協力して作るみたいなことは、ほとんどやらなくなりました。
──この時期の西澤さんの役回りとしては、社長業が中心ですか?
西澤氏:
そうですね。何本か開発にも携わってはいますけど、基本は坂本さんと栗原孝典さん【※】の2人がプロジェクトを進めていました。
 |
じつはその頃の僕は、ゲームを作るのを止めて、Webのシステム開発をやっていたんです。
※栗原孝典
ウエストンで『モンスターワールドII・ドラゴンの罠』などの『モンスターワールド』シリーズや、『時計じかけのアクワリオ』といった、数々のゲームでプログラムを担当。ウエストンが清算されるまで同社を支え続けた。
──それはいつ頃のお話なんですか?
西澤氏:
2001年ぐらいから10年ぐらいですね。Webのシステムが進化して、SNSっぽいものが出てきた、みんながインターネットを使い始めた頃です。あの頃に新しいビジネスがいろいろと出てきて、「僕も何か考えて一発当ててやろう」と考えた時期があったんですよ(笑)。
あとは、2000年ぐらいにデータベース系の技術について仕事で勉強する機会があって。サーバークライアント型のゲーム開発の仕組みを覚えたので、それを基礎にしていろんなWeb系のビジネスプランを考えたり、実際に作ったりしていたんです。
──西澤さんがWebのシステム開発をしている間、ウエストンのほうは?
西澤氏:
坂本さんと栗原さんの2人でずっとウエストンを運営していて、僕は他の会社とWebテクノロジーのほうをやっていました。この時期のウエストンは7〜8人しかいなかったので、他の会社と組んで一緒にゲームを作る、みたいな感じでやっていました。
──2003年12月に、西澤さんは「ビットエンジェル」という会社を興されていますが?
西澤氏:
ゲームではなくWeb系の仕事を引き受けるために作ったのがビットエンジェルです。
──ということは、ビットエンジェルというのはゲーム業界とはぜんぜん関係ない会社だったんですか?
西澤氏:
そうです。そこで覚えたのが、eコマースや動画配信サイトの仕組みだとか、Web上で複雑な処理を行う仕組みでした。ECサイトがどんどんできあがっていた頃だったので、その決裁だとか、クレジットカード決済のつなぎ込みの処理だとか。そういったところが発展途上の時期だったので、それを作って売る、みたいな仕事をしていました。
たださっきも言ったように、この時もウエストンはまだあって、そっちは坂本さんと栗原さんに任せっきりで、僕ひとりだけ違うことをやってるという構図だったんです。それがとても後ろめたかったんですよ。
だけど僕がゲームを作る現場に戻ると、上手くいかない気がして。僕は基本的にクリエイター気質だから、「良いものができるまで作るよ」みたいに予算をオーバーして作ったりしちゃうじゃないですか。そうなるぐらいなら僕はいないほうがいいと思って、ゲーム以外のことを一生懸命やっていたんです。
そういう意味では逃げていた。本来ゲームを作るべき人間が、ゲームを作る現場から逃げていたんですよ。
──では、ウエストン側でゲームを作る打ち合わせとかがあっても、それには行かなかった?
西澤氏:
会社にまったく行かなかったですね。他の会社の役員になったりもしていたので、他の会社に出勤していました。ウエストンのほうで何か問題があると、社長として相談されて、その時だけ会社に行く、みたいな感じ。
──その状態が10年ぐらい続いたんですか?
西澤氏:
そうなんですよ。しかもこの頃のウエストンはずっと黒字続きで、売上高は大きくありませんが利益率が上がってました。だから「僕がいないほうがいいんじゃないの」と思っていました。
 |
海外のファンからのラブコールが背中を押して、ゲーム作りの現場に復帰
──ゲームスタジオの社長でありながら、ゲームはまったく作らない生活を10年ぐらい続けていたわけですよね。それが変わっていくきっかけは、どういったものだったのですか?
西澤氏:
私生活で離婚して、再婚してということがあったのが、大きく影響していると思います。自分を変えなければいけない時期が来て「自分は今、何をやりたいの?」と改めて考えた時に、「やっぱりゲームを作りたい」という想いが強くなったんです。
でもその頃のゲームは規模が大きくなって、少人数ではとても作れなくなっている。「じゃあどうやって作るんだ?」というのも真剣に考えればできるんだけど、そこで面倒くさくなって、しばらく逃げていた。そこを面倒くさいと思わずにきちんと向き合って、もう一回ゲームを作ろうと思い始めたのが、2010年ぐらいのことです。
──そこでまた「ゲームを作りたい」と思ったのはなぜなんですか? Webシステムの仕事とはどこが違ったのでしょうか?
西澤氏:
Web開発の仕事はゲームと違って、「利益の確保がしやすい」んですよ。予定通りに仕事を進めれば、予定通りの対価を得られるという、そういう世界だった。だから、安定を求めるのならWeb開発のほうがいいな、というのがあったんです。
ゲームはどうしても安定しないじゃないですか。個人の生活も安定しないし、会社を安定させるのも難しい。でも自分にできることを考えると、やっぱりゲームを作ることがいちばん上手いんじゃないかと。
その時にやっていたWeb開発って、たしかに僕じゃなきゃ出てこないアイデアを入れて作ったりしているけれど、「でも僕じゃなくてもできるよな、やっぱりゲームのほうが作れる人は少ないよな」と考えるようになったんです。
あとはちょうどその頃に「『Wonder Boy III: The Dragon’s Trap』のリメイクをさせてほしい」という連絡があって。フランス人のオマールさん(Omar Cornut氏)から「僕が大好きなゲームなので、それをリメイクさせてほしい」と。
一方で同じ頃に、フランスのゲームアトリエ(Game Atelier)という会社の代表で、ファビアン(Fabian Demeulenaere氏)という人から「『モンスターワールド』と似たゲームを作っているから、クラウドファンディングの応援をしてほしい」と連絡が来たんです。 「だったらいっそ『モンスターワールド』のキャラクターを使って作ればいいよ」と言ったら、「そうする」と返事が来て。結局、クラウドファンディング自体は成功しなかったんですけど、そこにドイツのスポンサーがついて『Monster Boy』という大きなプロジェクトになって、「協力してくれ」と言われたので一緒に仕事をしたんです。

そんなふうに、「僕が昔作ったゲームが海外で高く評価されている」と、その頃になって初めて知ったんですよ。「僕が作ったゲームを海外でこんなに遊んでくれていて、こんなに好きだと言ってくれるんだ」というのがきっかけになって、またゲームを作ることを考えるようになったのはあるかもしれないですね。
──それにしても、『Monster Boy』の開発に7年もかかっているのはスゴイですね。
西澤氏:
そうなんです。彼らの『モンスターワールド』シリーズへの思い入れはものすごくて。
正式にライセンスアウト契約を経て『モンスターワールド』に近い新作を作っていい状態になったので、彼らとしては「人生を賭けて作る」みたいになっちゃったんですよ。こっちが逆に、「そんなにお金をかけて大丈夫なの?」って心配しちゃうぐらい(笑)。「そろそろリリースしてもいいんじゃない?」と提案しても、「まだここのキャラクターがおかしいから差し替えたい」とか言ってくるんですよ。
 |
完成した後、ドイツのケルンで実際に彼らと会って話をした時に、「こんなにお金をかけて作って、後悔していないのか?」って聞いたんですよ。
そうしたら「ぜんぜん後悔していない。良いものを作ることができて良かった。ありがとう」と感謝されて。こんなふうに情熱を持ってゲームを作る人たちがいるんだと、感銘を受けましたね。
──ゲームアトリエさんはどれぐらいの人数で開発していたのですか?
西澤氏:
10人ぐらいじゃないですか。今は規模が大きくなって、20人ぐらいいると思いますけど。
「そんなに何年も作っていて、チームは崩壊しなかったの?」とファビアンに聞いたら、「崩壊した」と(笑)。「家にも帰れなくなって離婚されかけたんだけど、なんとか今でも結婚生活を続けている」と言ってました。
──またゲームを作る気持ちになった背景には、そういう出来事があったんですね。
西澤氏:
平たく言うと、ゲームを作りたいけどやさぐれていた西澤さんに、フランス人が声をかけてくれて、ゲーム作りに対する情熱を思い出させてくれたと。それによって自分が変わったという部分は、たしかにあるかもしれないですね。
──ウエストンを畳むのは、その後ですか?
西澤氏:
そうです。
 |
フリーランスとして手がけたブラウザゲーム『ユバの徽(しるし)』
──ウエストンを畳んだ後、フリーランスで活動を始めたのはなぜですか? 新たなスタジオを作るといったことは考えなかったのでしょうか。
西澤氏:
そこは迷ったところですけど……。会社を経営することと、ゲームを作ることの両方をやるのはあんまり良くないなと経験的に感じたので、一緒にやらないほうがいいと考えたんです。
会社経営ができる人、ビジネスに強い人はいっぱいいるけど、ゲームを作れる人はそんなにいっぱいいるわけではない。だったら僕はゲームを作る仕事をやったほうがいいかなと、単純にそう考えているというのもあります。
──とはいえフリーランスだと、モノを作る上では難しいことも多いじゃないですか。そこはどう解決しているんですか?
西澤氏:
どう解決しているんでしょうね(笑)。ウエストンを畳むまで、栗原さんがずっと一生懸命やってくれていたんですけど、今は彼が僕をいろいろとマネジメントしてくれています。 西澤というタレントを使ってどうやってプロジェクトを立ち上げればいいか、彼が考えてくれているので。同じ事業体で彼と一緒に会社を作るという考え方もあるとは思いますけど、今はそうしない形でやっています。
──そうなると、お金を出してくれるところと、実際にゲームを作るスタジオを全部パッケージングしてくれるのは、その栗原さんなんですか?
西澤氏:
基本的にはそうですね。ただ作る現場については、僕が探してきています。今回の『アーシャ』も、以前に一緒に仕事をしたことのある大阪のモンキークラフトさんを紹介して、それでプロジェクトを組んでいます。僕自身も、今までにまったく仕事をしたことのない人たちといきなり一緒にゲームを作るのは、難しいので。
「この人がスタッフにいるのなら、ここまでは大丈夫だ」という信頼感のある人たちとやりたいですから。そういった面では、僕が紹介するというケースが多いかもしれないですね。
──西澤さんがフリーランスになられた後の2016年に、『ユバの徽(しるし)』というブラウザゲームを作られていますけど、これはご自身で企画をDMMに売り込まれたわけですか?
西澤氏:
そうです。会社を畳むのが決まった後に、一生懸命がんばって企画書を書いて、プレゼンして契約を取りつけたのが『ユバの徽(しるし)』です。この契約が決まったおかげで、僕は会社を畳んでも生活ができる態勢を作れましたから、協力してくれた方々にはとても感謝してます。
『ユバの徽』がリリースされた後で、プロデューサーに「なんでこの企画がオッケーになったの?」と聞いてみたんですよ。
そうしたら彼が言うには「西澤さんがいつになく真剣だった」と言われて(笑)。「僕、そんなに一生懸命に企画していたんだ」と思いました。
──DMMは一時期、いろんなブラウザゲームの企画を集めていたと思うんですけど、その中でも『ユバの徽』は特にユニークなゲームだったという印象があります。
西澤氏:
そうですね、僕自身も気に入っている作品です。特に世界観の構築にはかなり気合を入れましたから。ソーシャルゲームってサービスが終了すると、跡形もなくなっちゃうじゃないですか。それがもったいないなといつも思っていて。コンソールで『ユバの徽(しるし)』を作り直せないかなと、ちょっと考えています。
おかげさまで、Twitterとかを見るとファンの方がすごくついてくれていて、「いつ復活するんだ」と言ってくれてるので、そういう声に応えたいなという気持ちがありますね。
──『ユバの徽』の後、直接的にディレクションしているのは、この『ワンダーボーイ アーシャ・イン・モンスターワールド』ということになるのですか?
西澤氏:
そうです。『ユバの徽』を作っている時は東京に住んでいたんですけど、終わる前に京都に引っ越したんですよ。50年間ずっと東京に住んでいて、それから京都に移住して、今は6年目かな。
 |
──京都に引っ越したのは、何かゲームで働く上での理由があるのですか? それともプライベートな理由で?
西澤氏:
じつはちょうどその頃に僕の妻が、京都大学に合格したんですよ。大学院にいって学びたいことがあると京大を受けて合格したので、「これはもう京都に引っ越すしかないよね」と。学部編入で入学して、今は博士課程の1年目です。京都ライフを満喫してます。
──なるほど。
西澤氏:
僕はずっとセガ系の仕事ばかりしていたので、任天堂さんには行ったことがないんですよ。それでせっかく京都に引っ越したんだから「任天堂の仕事がしてみたい」と思って、任天堂のWebサイトを見たら、「『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』続編のレベルデザイナーを募集」って書いてあったんです。なので、それに応募してみました(笑)。

履歴書を書いて、ちゃんと職務経歴を書いて応募したんですよ。僕が任天堂の開発部内に入って、『ゼルダ』のレベルデザインをやったら、すごくいい思い出になるなと思って、ただそれだけで応募したんですけど、書類審査で落ちました(笑)。
──そのチャレンジングな感じが素晴らしいエピソードですね(笑)。