『Kanon』をきっかけに始まった折戸氏と中沢氏の交流
──I’ve内では、美少女ゲームの中にボーカル曲は「あって然るべきもの」という考え方だったんでしょうか?
中沢氏:
僕がI’veに入ったのは90年代末だったんですが、そのころは「楽曲に歌が入っていたらちょっと珍しい」という感覚でしたね。ちょうどCD-DA(CDに音楽を収録するための規格)が出てきたタイミングだったので技術的にもボーカルを入れることは可能だったんです。ただ、最初のころは商業のメジャースタジオではなく、ある程度インディペンデントなチームが歌を入れていたんですよね。90年代後半の技術進歩とちょうどクロスする時期だった気がします。
──ゲーム業界の話で言うと、家庭用に移植したときに主題歌が付いたり、サウンドにボーカルアレンジが追加されたりとか、そんな時期でしたよね。
中沢氏:
これは僕のイメージなんですけど、I’veに入るまでは「歌もので完パケ」というもののハードルが高かったような気がします。
折戸氏:
高かったですね。外のスタジオを借りて、エンジニアを呼んで、レコーディングからミックスまでスタジオ内で行わなければいけなかった。現在の宅録みたいに簡単にできる時代ではなかったですよね。
中沢氏:
ただ、高瀬さんは当時からすでに宅録のようなスタイルでやっていたんです。高瀬さんはいまで言うところのハードディスクレコーダーみたいなものを取り入れて、自分でスタジオを構築して完パケまで仕上げるところまで出来ていた。それがCD-DAなどの技術的な進化と噛み合って、I’veでは歌ものも載せることにチャレンジできたんです。
──それは1998年ぐらいのことだと思うのですが、折戸さんと中沢さんがお互いを意識するようになったのはいつごろだったのでしょうか?
折戸氏:
中沢さんとやり取りをし始めたのは『Kanon』のころですかね。そのころはどちらかというと高瀬さんとのやり取りがメインで、中沢さんとふたりで具体的に何かをやったりというのはなかったんですよ。
直接やり取りを行ったのは2005年あたりの、ヒーリング系ミュージックが流行っていた時期ですかね。うちもヒーリングアルバムを出そうとなったときに、自分が聴いていたヒーリングCDのレーベルと中沢さんが知り合いだったので、そこでお話をするようになったのが始まりだと思います。
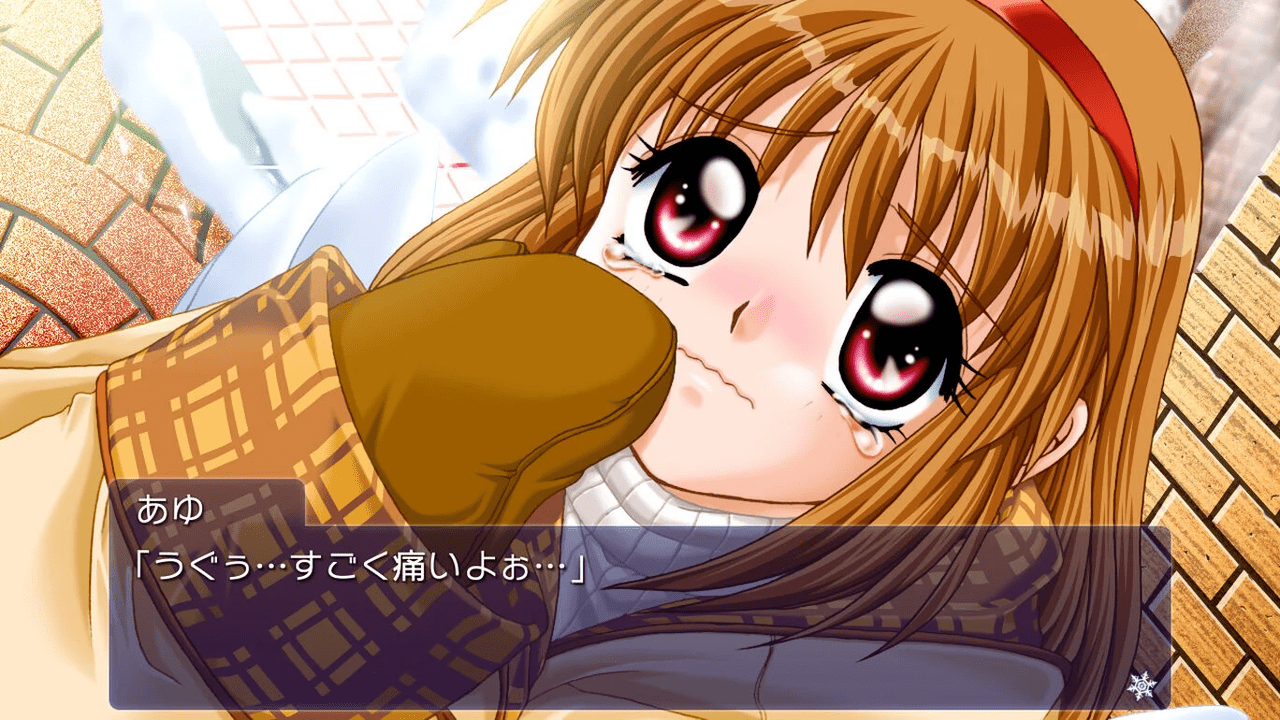
中沢氏:
僕は高瀬さんのアシスタントみたいな感じだったので、当時は折戸さんと高瀬さんのやり取りを「神々の所業だ……」と思いながら聞いていました(笑)。
折戸氏:
当時は高瀬さんが、事務所に電話をかけてもまずいないという事が多くて(笑)。そこで中沢さんに応対していただいて、どうやって高瀬さんに連絡を取ったらいいかを話し合ったりした事もありましたね(笑)
中沢氏:
折戸さんは覚えているかわからないですけど、コミケなどのイベントでもわりとごいっしょする機会がありましたよね。奥で品出しをしてる僕に折戸さんが「こうやったらすぐに小銭を出せますよ」と気さくにアドバイスしてくださったり(笑)。そういったイベントで交流できたのは、すごくありがたかったですね。
──当時ビジュアルアーツの方たちが集まる機会というのは、コミケ以外ではどんなものがあったんですか?
中沢氏:
ゲームを作っているときは年一で「ビジュアル総会」というものをやってましたね。
折戸氏:
やってましたねえ。当時はゲームシステムが大きく変わった時期で、その新しいゲームシステムの紹介をしなきゃいけなかったり。
中沢氏:
年1回、あの場に高瀬さんと行くのは結構楽しみだったんですよ。
──中沢さんは2000年前後からビジュアルアーツのさまざまなゲーム音楽を手掛けるようになりましたが、当時はどれくらいのペースで制作を行っていたのでしょうか?
中沢氏:
僕というより高瀬さんがすごかったですね。高瀬さんはあの当時数えられないくらいの量の仕事を受けていて、ものすごい量の曲を書いていました。僕がやっていたのはBGMの仕事などですね。
──少し調べさせてもらったんですが、2000年あたりの制作量はとくにすごいですよね。
中沢氏:
その時期はもう誰も追いつけないレベルで曲を作っていました。しかも全部完パケレベルで作っていたので、こんなにすごいクリエイターは高瀬さん以外いないんじゃないのかなと思うほどです。
──当時のI’veは、制作の過程で自社ブランドというのを意識されていたんでしょうか?
中沢氏:
「Lips~笑顔の行方~」の企画もそうですが、もともと高瀬さんは音楽を売るためにゲームを作るという考えでした。馬場社長からも「I’veが楽曲を提供したところには全部ロゴを貼り付けなはれ」と言ってもらっていたんです。そうすると「I’ve」というブランドが認知されて、のちのちの活動もしやすくなるでしょう、と。
いま思えば、ゲーム作りで失敗したのは逆に良かったのかもしれませんね(笑)。ゲームが作れないからこそ、音楽方面でいろいろなことができたと思います。
──ビジュアルアーツ作品の音楽という部分で勝負ができたと。
中沢氏:
当時はCDを売る流通も持っていなかったのですが、馬場社長がいろいろなところにかけあってくれたおかげで、『Kanon』を始め人気作の曲を自分たちで使えるようになったわけです。そうしたら「あの曲のフルバージョンが収録されている」ということで自社のCDを販売店に卸せるようになった。
ですので、ブランド的な部分で言えば、当初から会社の方向性はあまり変わっていないのかなと思いますね。音楽単体で切り出したからそういう風になった、うまくいった、ということなのかなと。
──馬場社長がブランディングをかなり先導してくれた印象がありますね。
中沢氏:
高瀬さんが企画したものに馬場社長が助言してくれて、それがうまくシンクロしていった結果なのかなと思います。
──当時I’veさんがやっていたことって、ゲーム流通や同人流通で音楽を売るというビジネスの先駆けですよね。
中沢氏:
それは本当に馬場社長の力ですね。最初に出した『regret』も、販売店の担当者さん全員に聞かせて、1曲ずつ解説していたらしいので。そういった協力があったからこそではありますね。ゲームにワンコーラスしか入っていない曲のフルバージョンをサントラに入れさせてもらったり、そういうありえない計らいもしてもらったので、ビジュアルアーツさんの横の繋がりには感謝しかありません。
作曲者がいま語る『鳥の詩』
──折戸さんはKeyでお仕事をされた際、シナリオや企画を手掛けられた麻枝准さんとどのようなやり取りをされたのでしょうか? 麻枝さんは音楽にも造詣が深いと思いますので、独特のやり取りがあったのかなと。
折戸氏:
麻枝さんの楽曲は結構アーティスティックで個性が強いので、自分の作風とはわりと対極の位置に存在すると思うんです。ですので、サウンドの方向性でバッティングすることはあまりなく、その点はゲーム内でうまく住み分けできたんじゃないかなと。
とくに『Kanon』の開発にあたっては、「ここは自分の曲で、ここは麻枝さんの曲で」という感じではなく、麻枝さんは自分のシナリオに対して自分の曲を書き、自分はそれ以外のところを請け負うという風に、ざっくりした感じで作っていました。
──分担作業のようなものですかね。
折戸氏:
そんなに綿密な打ち合わせはしていないですね。
──『Kanon』以降の仕事もそのような流れだったのですか?
折戸氏:
そうですね。麻枝さんは自分のシナリオは自分で曲を書くスタンスだったので、とくにやり取りはなかったんじゃないかなという気がします。
──制作した楽曲に対して麻枝さんからダメ出しがあったりは?
折戸氏:
麻枝さんはゲーム企画者でもあるので、シナリオに合っていないBGMですとリテイクは当然ありました。ただ、そんなにリテイクが発生したという記憶はないですね。基本書いたものはそのまま使って貰えたと思います。細かな部分の修正はあったかもしれないですけれど、「書き直し!」というリテイクは一切ありませんでした。
──折戸さんと言えば、『AIR』の『鳥の詩』を挙げる方も多いと思います。もちろんゲーム自体の評判も高いのですが、いい意味で曲自体が独り歩きしている印象も見受けられます。折戸さん自身は『鳥の詩』の人気に対してどう思われているのですか?
折戸氏:
当時は独り歩きしていることすら気付いていなかったんです。というのも、あの時代はいまでいうところのエゴサーチみたいなものがありませんでしたから。
評判をチェックすることをまったくしてこなかったので、『鳥の詩』がそんなに人気があることも知らなくて。人気があると気付いたのは、随分あとになってからのことでした。

──『鳥の詩』の人気も、始めのころは曲自体というよりも『AIR』のゲーム人気に引っ張られる形でしたよね。
折戸氏:
確かにそうですね。
──『鳥の詩』に関しては、制作時に何か意図された部分はあったんでしょうか?
折戸氏:
まったくないですね(笑)。
一同:
(笑)。
折戸氏:
そういえば意図したことがひとつだけありました。僕は『Kanon』のエンディングを担当したのが人生初となる歌曲の制作だったのですが、そのときに馬場社長から「サビがサビっぽくない」と言われたんですね。その助言を受けて、次の曲である『鳥の詩』はもうサビから始めようと考え、サビから書き始めることにしました。意図したのはそれくらいですかね。
中沢氏:
へえ、おもしろいですね。
──じつは今回の取材の打診をいただいた際、折戸さんのお名前を見て「あの『鳥の詩』の折戸さん!?」と編集部がざわつきまして(笑)。『鳥の詩』の知名度はずば抜けていると改めて感じたエピソードでした。
折戸氏:
過去にもいろいろな方々から楽曲の依頼を受けてきましたが、どういう曲調が良いかの話になった際に「『鳥の詩』のようなイメージ」と言われることが多かったかも(笑)。
──折戸さんご自身としても、『鳥の詩』は「これはいける」という手ごたえがあったのでしょうか? 再現性を分析されたことなどはあったのですか?
折戸氏:
当時はそういうことは考えずに作っていましたね。自分の中で歌曲への苦手意識がすごく強かったので、「何とか無事に書けた」という安堵感しかなかったと思います。手ごたえについては考えたこともなかったですね。
『鳥の詩』は曲単体だとあそこまで成功しなかったと思うんですよ。あくまで『AIR』という作品があったからこその話題性というか。
──ちなみに、曲を作るにあたり、ゲーム内容もご覧になられていたのでしょうか?
折戸氏:
いや、基本的にはゲーム開発と同時進行なので『AIR』がどういった作品になるのかはあまりわからないという状態で作曲していました。想像上で「恐らくこういう世界観なんだろう」と(笑)。
テストプレイの段階で初めて「ああ『AIR』ってこういう作品だったんだ」と知りました(笑)。
──(笑)。当時のPCゲームは、店頭で主題歌を使ったデモが流されていることが多かったですよね。『AIR』のオープニングが店頭で流れていたことをとてもよく覚えています。そういったプロモーション的な側面を意識されたことはありますか?
折戸氏:
曲を書くだけで精一杯だったのでデモ映えを意識することはできなかったのですが、経験を積んでいくうちに、デモ映えするようなアップテンポの曲を意識的に書いたことがあります。2000年前後は非常に多くのゲームが世に出ていたので、その中でお客さんの注目を引くためにどうすれば良いかという心構えはあったと思いますね。
──その時期の美少女ゲームメーカーには、音楽業界出身の方が多く在籍していた印象があるのですが、何か理由があるのでしょうか?
折戸氏:
多分、Leafさんやオーバードライブさんのように、会社のトップにいる方がもともと音楽をやっていたというのもあるのかもしれませんね。
一方で、音楽にお金を回せないブランドさんも多かったのではないかという気もします。当時のPCゲームは制作費も少なかったですから、絵描きさんや声優さんに払うお金だけでいっぱいいっぱいだった。その点うちは内部に音楽が作れる人間がいたので曲に力を入れることができたのですが、ほとんどのブランドさんは音楽一式を外注に依頼することが多かったんじゃないでしょうか。
──少ない予算の中で、音楽からゲームをヒットさせようとする狙いもあったのでは?
中沢氏:
それは会社のトップが音楽方面出身の方で、その方向に事業を持っていけたからじゃないですかね。音楽に限らず、みんなそれぞれ実現したいことがあり、美少女ゲームはそういったことを表現する場として機能していた。インターネットが普及していないあの時代ならではですよね。
──I’veの場合で考えると、かなり早い段階からボーカリストを前面に押し出していましたよね。歌姫と呼ばれていた歌い手さんがメジャーに出ていく流れもありましたし。
中沢氏:
そうはいっても、当時は制作に精一杯で、そこまで売り出し方を考えてなかったんじゃないかな(笑)。すべて結果論であって、当時からそこまで計算してやっていた人はいないと思います。
折戸氏:
目の前のものを一生懸命作るしかなかったですね。



































