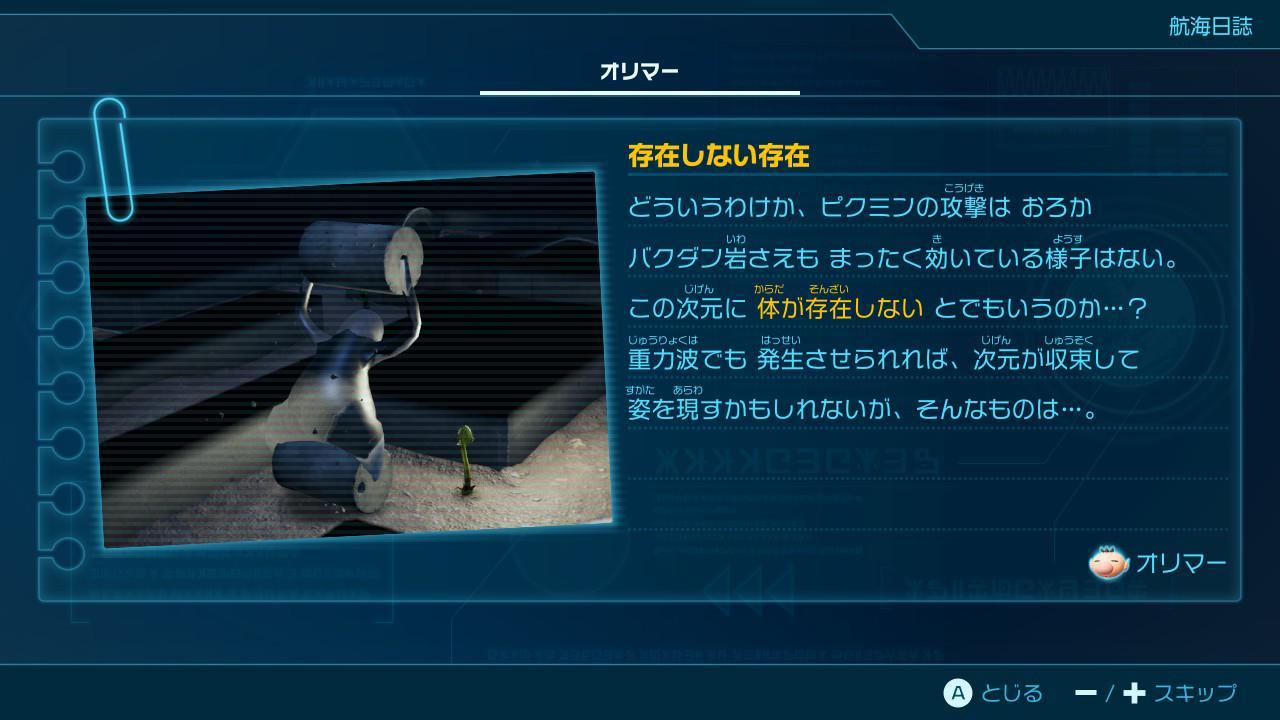『ピクミン』の面白さの本質とは、何か?
この問いに正確に答えるのは、意外と難しい。ピクミンを引っこ抜いて、増やして、連れ歩き、オタカラを集めたり、原生生物と戦ったりする。大まかな「ピクミンのゲーム内容」はある程度説明できるものの、いざその「面白さの本質」を端的に表そうとすると、これが意外に難しい。
そもそも、『ピクミン』はそのゲームジャンルすらも意外とハッキリ分類できなかったりする。
リアルタイムストラテジー?
アクション&シミュレーション?
一応、『ピクミン3』まで公式では「AIアクション」と名乗っていた。
正直、どれもしっくりこない。
『ピクミン』は、意外にもその本質を一言で表現するのが難しいタイトルなのだ。

ところが、最新作『ピクミン4』にて、その面白さを端的に表すワードが突如として生まれた。
それが、「ダンドリ(段取り)」。
作中のキーワード、または「ゲームの方針」そのものを表わすかのように使われる「ダンドリ」は、まさしく『ピクミン』の面白さ・楽しさをひとつに集約したワードと言える。ダンドリよくピクミンたちを動かし、ものを集める。ダンドリよく行動し、その1日を気持ちよく終える。
私は、まさにこの「ダンドリ」という単語に、「ピクミンの面白さ」を再定義されたかのような感覚があった。「そうか、ピクミンはダンドリを楽しむゲームなのか」と。ある種、「ダンドリ」というワードがゲーム全体を上手くまとめているような印象すらあった。
そんなこんなで、『ピクミン4』がとても面白かったので、任天堂の開発者にインタビューさせてもらった。今作の「チーフディレクター兼プログラミングディレクター」を務めた神門有史氏、「プランニングディレクター」を務めた平向雄高氏に、いろいろなお話をうかがっている。
そもそも、「ダンドリ」というワードはどこから出てきたのか?
『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』でゼルダの「アタリマエ」を見直したように、ピクミンの「アタリマエ」を見直したとはどういうことか?
オッチンの開発秘話、「氷ピクミン」や「ヒカリピクミン」などの新種のピクミンの作り方、任天堂ハードのオタカラに込められた意外な思い、そして今作の開発中「宮本茂氏から何度も説明を受けたこと」とは……?
『ピクミン4』の発売から少し時間が経ってのインタビューとなったが、その分、より今作のことを深く・濃くお聞きできたものとなっている。『ピクミン4』をプレイした方はもちろんのこと、プレイしたことがない方が読んでも、間違いなく楽しめる記事となっているはずだ。ぜひ、このまま最後まで読み進めてほしい。

※今回のインタビューは、任天堂の公式サイトにて掲載された『ピクミン4』の「開発者に訊きました」を前提としている部分があります。こちらの「開発者に訊きました」も合わせて読むと、より深く理解ができる内容となっています。ぜひ、ご一読を。
ピクミンの面白さを端的に表した「ダンドリ」って、どこから生まれた?
──本日はよろしくお願いします。まず最初に、「チーフディレクター兼プログラミングディレクター」を務めた神門さん、「プランニングディレクター」を務めた平向さんの今作における役割についてお聞きできればと思います。
神門有史氏(以下、神門氏):
まず「チーフディレクター」についてですが、おおむね普通のゲームにおける「ディレクター」の役割だと思っていただいて構いません。ゲームデザイン全般の提案と調整を行いました。とにかく「全般」を担当しましたので、大体のところは関わっています。
そして「プログラミングディレクター」としては、今作の下地となるシステムの設計、ピクミンのAI、操作周りの処理などを担当していました。私はこれまでの『ピクミン』シリーズにおいてもプログラミングを担当していましたので、『ピクミン4』でもプログラミング全般に関わったような形ですね。
──「ゲームデザイン全般の提案」というのは、「今作はオッチンが登場する」といった根本的なデザインの提案などを行っているということでしょうか?
神門氏:
そうですね。オッチンの性能を決めて『ピクミン4』の軸にすることを提案しました。具体的にはオッチンの「プレイヤー以外の操作キャラでありつつ、強力なピクミンとしての役割もある」という二面性のあるゲームデザインなどですね。
とはいえ、最初に「犬を出そう」と提案した時に、それがすぐに決まるわけではありません。新たな機能を登場させるにあたって、まず「検証」から入ります。その検証段階においても、「検証に必要な機能はこれです」といった仕様書を作ったりもしていましたね。
もう1つあげますと、「夜の探索」のゲームデザインも提案しました。まずヒカリピクミンがワープしてくる性能にして、それにあわせてオッチンと切り替えながら防衛していくようにまとめるのはどうかという提案です。
平向雄高氏(以下、平向氏):
私が担当した「プランニングディレクター」は、主に「レベルデザイン」に関わっています。原生生物の仕様や配置なども含めた「どういった遊びにするか」というゲーム全体のレベル(空間)を設計する仕事を主にしています。
地上と地下の両方のレベルデザインを担当しているのですが、特に地下の洞窟に関しては、大部分を設計しました。
そして、もうひとつ「スクリプトリード」という肩書もあります。具体的には、原生生物図鑑やオタカラ図鑑などの「ゲーム内のテキスト全般」の制作と監修を行っていました。そこに加え、ストーリーの制作やカットシーンの監修なども行っていましたね。
──「洞窟の設計を担当した」ということは、もしかしてあの「深海の城」【※1】も制作されたのでしょうか?
平向氏:
はい、担当しています。
ちなみに『ピクミン2』の「水中の城」も私が担当していました(笑)。
神門氏:
アメボウズの原案は私です(笑)。
──なんと! そうだったのですね(笑)。
※1「水中の城と深海の城」
『ピクミン2』に登場した「水中の城」。かなりの難易度と「アメボウズ」の存在によって、多くのプレイヤーに大きなインパクトを与えた。そして『ピクミン4』にはこの「水中の城」をオマージュ(?)した「深海の城」という洞窟が登場した。こちらもアメボウズの存在が印象的。
──さっそく本題に入っていきたいのですが、『ピクミン4』では「ダンドリ」というキーワードが新たに登場しました。「ピクミン」というタイトルの面白さを4文字で端的に表している素敵なワードだと思うのですが、そもそもなぜ「ダンドリ」というワードを推していくことになったのでしょうか?
神門氏:
そもそものワードが出てきた経緯としては、まず『ピクミン3』の開発をしていた頃に遡ります。実は『ピクミン3』にも「ダンドリ」という言葉はありましたが、開発のスローガンにはなっていませんでした。
開発が進んでいくにつれ、「ミッションモード」……つまり現在の「ダンドリチャレンジ」の原型となったモードにて、「ピクミンを采配する楽しさ」「時間を短縮する面白さ」などを「段取り(ダンドリ)」というワードに集約できることに気がつきました。
それが、『ピクミン4』における「ダンドリ」の元々の始まりです。
ただ、実際の『ピクミン4』の制作初期において「“ダンドリ”という要素を全面に推し出すかどうか」は割と悩みました。そこからの試行錯誤の結果として、ゲーム全体のプレイ感として「ダンドリ」を推し出すのではなく、あくまで「遊びの本質」としての「ダンドリ」を今作では推し出すことに決めました。
そこの方針が決まってから、過去作にあった「ビンゴバトル」「ミッションモード」などの要素も「ダンドリバトル」と「ダンドリミッション」 に統一していきました。ゲーム全体をよりシンプルかつわかりやすい方向に「衣替え」していったと言いますか……「ダンドリ」というワードを中心に統一感を出していったのが『ピクミン3』から『ピクミン4』にかけて大きく変わった部分ですね。
──やはり根本的なゲーム作りの段階から、「ダンドリ」を意識されていたのですね。
平向氏:
そうですね。今作も含めると「ピクミン」シリーズは4作出ているのですが、それでも「パッと見でどんなゲームなのかよくわからない」と言われることがありました。たしかにビジュアルは印象的なのですが、明確に「ピクミンのゲーム性を表わす言葉」がこれまでは見つかっていなかったんです。
そして、その「一言でピクミンのゲーム性を表わす言葉」としての「ダンドリ」を全世界共通で推していこうと宮本(茂)【※2】とも相談し、今作からはゲームの核を言語化した「ダンドリ」という言葉を広げていこうとしています。
※2「宮本茂氏」
任天堂の代表取締役フェロー。『マリオ』シリーズや『ゼルダの伝説』シリーズなど、多くの任天堂タイトルを手がけている。『ピクミン』シリーズにも初代から携わり続けている。
「ピクミンの面白さを表わす言葉」って、実はなかった?
──「ピクミンのゲーム性を表わす言葉がなかった」とのことですが、『ピクミン4』以前のシリーズでは開発チーム内の間でも「ピクミンの面白さ」などを明確に言語化できていなかったのでしょうか?
神門氏:
「なかった」とまで言ってしまうとよくないかもしれないのですが……確かに「言語化できていなかった」という側面はあったと思います。もちろん開発チームの各々が考える「ピクミンの面白さ」として、「投げる」「運ぶ」といったアクションの楽しさなどは共通認識としてはありました。
ですが、「その面白さの本質とは何か」という部分を『ピクミン4』まで核として掴めていなかったのだと思います。
平向氏:
「ダンドリ」というキーワードが生まれる以前は、「ピクミンをマネージメントする面白さ」といった表現を使っていました。ただ、正直「マネージメント」というワードにもイマイチピンと来ていなかった部分はありましたよね……。
神門氏:
「ピクミン」というゲーム自体はリアルタイムシミュレーションやストラテジーといったジャンルに分類されることがあるのですが、開発側としてはあまりそんなつもりはなくて……。なんとなく「ピクミンというキャラクターを使い、マネージメントしていくゲーム」という認識でした。
──勝手な想像になってしまうのですが、なんとなく任天堂さんはゲーム制作の際も「面白さの言語化」などが完璧にされているのではないか、というイメージがありました。それこそ初代『ピクミン』の時は、「ピクミンの面白さ」を掴むのが難しかったのではないでしょうか?
神門氏:
いや、昔はそうでもなかったですね……(笑)。
純粋に「面白いものを作ろう」という感じで作っていました。
初代『ピクミン』に関しては「開発者に訊きました」でも少し語った部分ではあるのですが、やはり開発当時は結構迷走していました。中々キャラも決まらず、ゲームの内容もブレて……なんとかようやく「マネージメントする」というひとつの遊び方のスタイルが決まったような感じでしたね。
平向氏:
それこそ初代では「ピクミンを回収して、増やして……」というゲームサイクルが完成して、初めて『ピクミン』というゲームになったんです。

──今作で「ダンドリ」というワードが登場したことによって、「あぁ、そうか。このゲームは“段取りよく遊べばいい”のか」とゲーム全体の行動指針がハッキリしたような印象がありました。
そこから生まれる「その1日をダンドリよく攻略することができた」という達成感が今作の大きな魅力となっていると思うのですが、あの「ダンドリよく行動できた達成感」はゲーム的にどのように生み出しているのでしょうか?
神門氏:
「ダンドリチャレンジ」のように明確な時間設定と目標がある場合、ゲームの達成感は「クリア」や「報酬」などで味わうことができますよね。ただ、探索となってくるとその1日における明確な目標などはゲーム側では指定していないため、「個人的な達成感」を味わってもらうことが重要になってきます。
たとえば、最初に訪れた時は行けなかった箇所を突破できたり、「今日はあそこの黄色オニヨンを取ろう」と決めて上手くゲットできたり、原生生物を倒して新たな拠点を確保したり……。
こちら側が提示した目標というより、プレイヤー個人が感じる「今日は上手くいった」という達成感を1日のサイクルの中で刺激できているのではないかと思います。
平向氏:
実は「ダンドリの気持ち良さ」というものは、ゲームとは関係なく普段の生活からあるものだと思います。「自分で計画を立てて、それが上手くいった」という達成感自体は、割と普遍的なテーマなのではないでしょうか。
そして今作の場合は、「ゲーム自体が1本道ではなくなった」ことで個々の達成感をより刺激できているのではないかと思います。まず、今作はひとつのステージの中でも、自由にいろいろなところに行くことができます。ピクミンに出会う順番も自由ですし、どの洞窟からでも攻略することが可能です。
極論ではありますが、「ダンドリよくやってもいいし、ダンドリ悪くやってもいい」というゲームデザインになっています。この「プレイの幅」を持たせた部分が大きいのだと思います。
神門氏:
「いや、ひょっとしたら黄ピクミンと先に合流してゲートを壊せばよかったんじゃないか……?」と、別の解き方や進め方を思いついたときに、いつでも時間を巻き戻せるようにもなりました。おかげで、今作はこれまでと比較しても、プレイヤーごとに全く違う攻略方法が生まれていると思うんです。
この「プレイの幅」を生み出すことができたのが、今作の「ダンドリの達成感」に最も繋がっている部分なのかもしれません。
平向氏:
「原生生物にピクミンがたくさん倒されてしまい、時間を巻き戻す」といったような失敗の部分まで含めて、上手く「ダンドリ」という遊びにできたような手応えがありましたね。
──確かに、『ピクミン4』はこれまでのシリーズと比較しても「自分で攻略している感」が強かった気がします。その「プレイの幅を持たせる」ことは開発初期段階から意識されていたことなのでしょうか?
神門氏:
それは割と最初から決めていました。これまでのシリーズでも「自由度の幅」はいろいろ持たせていたのですが、「ピクミンが仲間になる順番」は決まっていました。大体まずは赤ピクミンを仲間にして、次は黄ピクミンで、青ピクミンはこの辺りで仲間になる……といった恒例の順番がありました。
ですが、『ピクミン4』の企画を作る時はまず最初に「ピクミンが仲間になる順番を取っ払いたい」と考えていました。つまり、「どの順番でどのピクミンを仲間にしても破綻しないようなゲームデザインにしたい」と考えたのが今作のスタートの部分にあったんです。
──今作はピクミンを仲間にする順番が固定されていないからこそ、「このピクミンが手に入ったから、あそこにも行ってみよう」と試してみたくなることが多かった気がします。これもある意味、「プレイの幅」ですよね。
平向氏:
初代『ピクミン』の時も順番こそ決まっていましたが、「このピクミンが手に入ったら、あとから戻ってこよう」と思えるような箇所をゲームサイクルに組み込んでいました。今作では、それと同じような体験を、 1本道ではなく、いろいろなプレイの幅がある中で実現することができました。
それにより、いろいろな遊び方を模索したり、「自分はこうしてみよう」と解き方を探したくなるようなゲームにできたのではないかと思います。
ピクミンの「アタリマエ」を見直す
──「ピクミン」全体のお話になってしまうのですが、やはり「ピクミン」は他のアクション性のある任天堂タイトルと比較すると、やや直感的ではないゲームになっていると思います。ただ、そんな中でも「ダンドリの面白さ」「戦略性の楽しさ」を、より直感的に寄せることに成功しているのが「ピクミン」のすごさだと感じています。
この相反してしまってもおかしくない「戦略的な面白さを、ダイレクトに・直感的に楽しませる」部分を、どのように実現しているのでしょうか?
神門氏:
先ほども少し触れましたが、やはり現実の家事などでも「ダンドリが上手くいったことの嬉しさ」は身近なところにありますよね。それはゲーマーじゃなくても、共通の認識としてあると思います。
その上で、「時間内にこなせたタスクの数」が集めたエネルギーやシザイとしてゲーム上の数値に表わされることで、直感的な嬉しさに繋がります。要は、「数字が増えて嬉しい」という根本的な喜びの部分ですよね。そして「数字が増える嬉しさ」も、現実でよく感じる嬉しさだと思います。
「ピクミン」はこの「ダンドリの嬉しさ」「数字が増える嬉しさ」という普遍的かつ直感的な喜びを表現しているので、そういった「ゲーム性が相反してしまう」部分などにあまり奇をてらわず作れているのかもしれません。
平向氏:
戦略的に指示を出すことを楽しむゲームとしての「ピクミン」の特徴を挙げるとすれば、「プレイヤーが中心にいて、その人がピクミンを投げる」という点だと思います。
特に戦略性を重視するシミュレーションやリアルタイムストラテジーなどのタイトルでは、いわゆる「神の視点」から指示を出して進行していく遊び方のものが多いと思います。ピクミンではそこにプレイヤー自身が介入したり、少しアクション性を持たせることによって、戦略的な面白さをダイレクトに楽しめることを目指しています。
──「戦略性と直感性」の両立において、やはりダンドリなどでも「これだけのタスク量を考えるのはOK」「これ以上タスクを増やしてはいけない」といったようなプレイヤーが遊ぶことを想定した線引きがあったりするのではないかと思うのですが、その辺りはいかがでしょうか?
神門氏:
いえ、明確なタスク量は決めていません。そこも、「それぞれの人ができる範囲でやってください」というデザインにしています。「最大効率でプレイできるのはどのくらいのタスク量なのか」という点もプレイヤー次第だと思います。
3つ~4つのタスクが最も効率よくプレイできる人もいれば、逆に5つの方が効率がいいと考える人もいますよね。その「自分にとって最も効率がいいタスク量」を探るところまで含めて、「ピクミン」の遊びなのではないかと。
──なるほど、その辺りをレベルデザインでコントロールしているということなのでしょうか。
神門氏:
今作はダンドリバトルなどで「開発側も本当の最適解がわからない」という状態がよく起きます。なにより、作っている側も最適解がわからない方が楽しいと思うんですよね。
「次はどうするか」という選択肢が常に3つ~4つほど提示されていて、さらにその先も選択肢が用意されています。ある程度こちらで「ここのルートは通ってくださいね」という道筋は提示しつつ、レベルデザインなどでメリハリはつけているのですが……それでも開発側にも本当の最適解はわかりません。
自分の中での最高スコアを出しても、マリオクラブ【※3】でのデバッグではもっとすごいスコアが出たりしていて……(笑)。開発側にすらいろいろな発見があるのは、ピクミンの面白いところだと思います。
※3「マリオクラブ」
マリオクラブ株式会社。任天堂の開発中のゲームソフトをプレイし、バグやセリフのチェック、モニターテストなどを行っている。
──なるほど。開発側の想定を超えて、「プレイの幅」が出るようになったのですね。
神門氏:
ダンドリバトルだけでなく、ゲーム全体を通して正解が決まっているわけではないので、「今度はこれを試してみよう」「先にこっちの洞窟を攻略したらどうなるんだろう」などの各々の楽しみ方にも幅を用意しています。
──ちょうど話題が出たのでお聞きしたかったのですが、『ピクミン4』はこれまでのタイトルと比較しても「繰り返し遊びたくなる」面が大きいと思います。
ただ、今作は過去作と比較しても時間や食糧のリミットがあるわけではなく、かなり自由にオタカラや探索などを楽しむことができます。ひとつのフィールドを探索して、また翌日同じフィールドを探索する。そのゲームサイクル自体はすごくシンプルでありながら、一方で何度プレイしても「飽きない」感覚がありました。あの飽きが来ずに遊び続けられる楽しさは、どのように生み出されたのでしょう?
神門氏:
やはり、これまで触れた「攻略ルートが1本道ではない」「最適解となるルートを決めていない」の2点が大きいのではないかと思います。
過去作で言うと、フィールドに電気ゲートを設置した場合は「黄ピクミンがいないとその先には進めない」状態になっていました。ですが、今作の場合は上から降りて電気ゲートを無視できたりするので、「攻略として許容している範囲」が広いんです。ただし、電気ゲートを無視した場合には「最速で運べる時間を考えたら、果たしてそのルートは正しいのか?」という課題が残ります。
つまり、「誰がどう遊んでも解けるようにはなっているけど、いざダンドリを突き詰めるとベストな選択は限られてくる」という試行錯誤の楽しさを残しつつも、一方で電気ゲートを無視することができるような緩さもあります。今作を飽きずにお楽しみいただけているのなら、そこが理由の1つかもしれません。
この幅を持たせたことにより、ゲームでよくある「時間をかけて目的に辿り着いたものの 、手持ちのアイテムがなくて戻らなければいけない」というストレスも『ピクミン4』ではある程度解消できたと思います。
平向氏:
これまでは「開発側が用意した遊びを、そのまま遊んでほしい」というコンセプトで作られているタイトルが多くありました。
ただ、「アタリマエ」を見直した『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』くらいから、「お客様が試してできてしまったことは、なるべく塞がないようにする」という考えで開発することが増えたかなと思っています。
『ピクミン4』でも「これをやってみたらどうだろう?」とプレイヤーの方が実践した結果、少しズルいことができてしまってもオッケーですし、それをこちらが想定した上で用意している箇所もあります。
たとえば、今作の体験版ではちゃんとダンドリを考えてプレイすると、実は体験版の時点で「ひだまりの庭」をコンプリートできるようになっているのですが、青オニヨンの回収方法は答えが1つではなかったりもします。
そして、「ひだまりの庭」だけでなくゲーム全体がその考えで作られているからこそ、飽きずに長く遊んでいただけているのではないかと思います。
「プレイヤーが自分で発見する面白さ」は、どうやって生み出すのか
──その「お客様が試して実際にできてしまったことは、塞がないようにする」という方針は、明確に開発チームの間で共有されているものだったのでしょうか?
神門氏:
最初から「自由な冒険」というコンセプトは決まっていたので、チーム全体の共通認識としてはありました。
ただ、やはりチーム制作ではあるので、あとから合流したスタッフに「これはちょっとピクミンでは御法度なんじゃないですか?」と言われることもありましたが、その都度「今回はこれで大丈夫です」と今作のコンセプトを説明していました。
「エンゴ射撃」【※4】も「自由な冒険」の要素だったりします。エンゴ射撃って……正直ものすごく強力じゃないですか(笑)。下手をするとゲームのバランスを壊しかねないシステムなのですが、それでも「2人で遊んでくださったのなら、1人用のスコアには残らないけどゲームの体験としてはアリにしよう」と決めました。
これまでは「ゲームのバランスが壊れてしまう」という声が上がったものはあまりゲームに入れていなかったのですが、コンセプトを一新した今作ではそういった要素をいくつか入れました。チーム内でもその都度「今作は自由な冒険がコンセプトです」ということを伝えていました。
※4「エンゴ射撃」
『ピクミン4』において、ふたりプレイで2Pが行える攻撃手段。小石を投げつける援護射撃で、ピクミン1匹分以上のダメージを与える。
──その「プレイヤーが自分で発見する面白さ」を作り出せているのが『ピクミン4』のすごいところだと思うのですが、やはり実際に実現するのはとても難しいことだと思います。直近の『ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム』なども自分で発見する面白さを実現できていた印象があります。
平向氏:
任天堂のタイトルというより、単に私個人の感覚になってしまうのですが、「自分で発見する面白さ」とは逆の作り込まれた1本道のタイトルももちろん好きですし、『ピクミン3』はその「作り込まれた1本道」にチャレンジしたタイトルだったと思います。『ピクミン4』のコンセプトは、それの反動のような部分もあるのかもしれません。
開発チーム内でも、はじめは『ピクミン3』のように「きっちりとしたレベルデザインにしないといけない」と思っていた人も多かったのですが、「いろいろな人が、いろいろな遊び方をしてもいいよね」といった雰囲気に変えていったりもしました。
もちろん、今後すべてのタイトルがそうあるべきというわけではありませんが、『ピクミン4』は多くの人に楽しんでいただけているようでよかったと思います。
神門氏:
私自身のモチベーションはもうちょっとシンプルで、「自分で作ったゲームを、ちゃんと自分で楽しく遊びたい」というのが大きいと思います。だから、1本道のゲームだとストーリーなども全部知ってしまっていて、自分でプレイするとあまり楽しめないのかもしれません。
加えて、1本道のタイトルだと難易度調整なども「単に簡単にして突破してもらう」ような方法になってしまいがちです。つまり、ゲームを進めはするけど「もっと上手くなったらチャレンジしよう」「自分のできる範囲で、まだやれることはあるはず」といったプレイヤー自身の意欲はあまり刺激できなくなるんです。
なんて言いながら……やはり私の場合は「自分も買って楽しみたい」というのが大きい気がしますね(笑)。
かわいさの裏にある、「死」の二面性。命の儚さを感じさせる「ピクミンの世界」はどう描く
──ここからは、今作のメイン要素でもある宇宙犬の「オッチン」についてお聞きできればと思います。オッチンのシステム的な成り立ちは「開発者に訊きました」でお話されていたので、今回はオッチンの「見た目」についてお聞きしたいです。オッチンのどこか不思議な愛嬌のあるビジュアルは、どのように作られていったのでしょうか?
神門氏:
オッチンのビジュアルに関しては、まず「ピクミンの世界の生き物」であることを重視しました。
「犬」とは言っていますが、オッチンはあくまで「ピクミンの世界の宇宙犬」という設定です。そのため、かわいらしさも必要ではあったんですが「ピクミンの世界にハマるかどうか」という点がデザインする上で難しかったです。
平向氏:
「かわいすぎずに愛着が持てる」ところはかなりの試行錯誤を重ねました。
──実際にゲームに登場したオッチンは初期案からは結構変わっていたりするのでしょうか?
神門氏:
耳の形ひとつ取っても、初期案からはかなり大きく変わっています。
本当に、いろいろな試行錯誤がありました……(笑)。
一同:
(笑)。
神門氏:
加えて、やはりピクミン自体がカラフルかつ大量に表示される生き物なので、「ピクミンと色が被ってはいけない」「地形に埋没する色ではいけない」といったオッチン自体の視認性を確保する必要がありました。こういったゲーム的な制約も加味しつつ、オッチンのビジュアルは作られていきましたね。
──実際にプレイをしていてもオッチンを見失うことはあまりなかったです。
遠くにいても発見しやすい「ちょうどいい黄色」と言いますか。
神門氏:
ただ、黄色すぎると、遠くから見た時に黄ピクミンとの見分けがつかなくなってしまいます。同じ色であっても見分けがつくようなカラーリングは重要視しました。そして、何より4作目であるがゆえに「使える色」も限られてしまうんですよね……。カラーリングも苦労した部分ではあります。
そして、オッチンは原生生物寄りのキャラクターではなく、「宇宙人(味方)寄りのキャラクター」としてデザインが起こされています。普段「ピクミン」シリーズで作っている生物とはまた違った方向性を出していく必要があったので、その辺りも落とし込みに時間がかかりましたね。
平向氏:
「味方っぽく見せる」必要がありましたので、普段の原生生物と同じラインでデザインしてしまうと、ちょっと「気持ち悪い」感触が出てきてしまうんですよね。とはいえ、「ピクミンの世界の生き物」として、かわいすぎてもいけません。この絶妙なラインを見極めつつ、作っていきました。
──「開発者に訊きました」でも、神門さんは「キャラクターがかわいいから、かわいいゲームにすればいいのに」ということに対して、「それは違う」とおっしゃられていましたよね。その「ピクミンの世界の生き物」として描くデザインのお話をもう少し詳しくお聞きしてみたいです。
神門氏:
それはやはり、「ピクミン」というゲーム自体に「子どもに媚びない」という方針があるのが大きいのではないかと思います。
平向氏:
初代『ピクミン』の頃から、開発チームに共有されていますね。
その上で大切にしているのは、「ピクミンも原生生物も、その世界の中ではひとつの生態系として存在している」ということです。オリマーなどの人間の視点から見ると「ピクミンが味方、原生生物が敵」といったように見えるかもしれないのですが、あくまでそれは彼らの都合にすぎません。
そのため、ピクミンや原生生物のどちらか一方をかわいらしく描きすぎてしまうと、ひとつの生態系というより「こっちが良いやつで、こっちが悪いやつです」と敵味方の区別がつくようになってしまいます。どちらか一方をかわいらしく描くのは意図的に避けていますね。
神門氏:
「ピクミン」というタイトルの明確な特徴として挙げられるのは、「食べられる」……要は「死がちゃんと描かれている」ということです。その「見た目はかわいいけど、実際は結構エグい」という二面性を持っているのが「ピクミン」ですよね。
その二面性こそが、他の任天堂タイトルとはちょっと違う立ち位置と言いますか……ある種「ピクミン」の独自の強みだったり、存在意義ではあります。
──やはりこのビジュアルに対して「死が描かれている」ことによる二面性は、「ピクミン」独自のものですよね。
神門氏:
大人にとっても子どもにとっても、「生き物が生まれてきて、生きて、死ぬ」ということは普遍的なテーマだと思います。それを直接描いているからこそ、多くの方に共感いただけるタイトルになっているのかもしれません。
ピクミンの見た目はかわいいので子ども向けっぽく見えるかもしれませんが、「生き物が生まれて、生きて、死ぬ」というゲームの根本は、年齢を問わず共通して理解できるものですよね。
その普遍的なテーマ性があるからこそ、大人も子どもも好きになれる……つまり「幅が広い」タイトルになる可能性があるんじゃないかと私は思っています。
「開発者に訊きました」でも宮本が「実はピクミンは任天堂で一番グローバルなキャラなんじゃないか」といったことを言っていましたが、まさに「ピクミン」は根っこの部分に誰もが理解できる普遍的なテーマがあるタイトルだと思います。人類共通の「生き物の儚さ」を感じられると言いますか。
そこを大切にしたいからこそ、「実は現実世界でもその辺にピクミンがいるかもしれない」と思えるようなリアリティを持たせたうえで描いています。
平向氏:
ゲーム内でも、「ピクミンは一見かわいらしく見えるけど、実はこんな生き物なんじゃないか」といったことをオリマーが考察していたりしますよね。その「生き物」としての描き方は、やはり「ひとつの世界としてリアリティを持たせたい」という方針に基づいているのではないかと思います。
──その「かわいさの裏にある普遍性、二面性」をシリーズ全体で維持することは、中々に難しいことだと思います。そして、まさにそれが「ピクミンの魅力」でもありますよね。
神門氏:
「ピクミンがかわいい」というお客様からの声はよく聞くのですが、実は原生生物も意外と人気があるんです。それこそ昆虫好きのお子さんとかに、原生生物のデザインが受け入れられているみたいで、そこはまさにこのタイトルにしかない特徴ですよね。
もちろん作り物ではあるのですが、プレイヤーの方に「割とその辺にいそうな、ヘンテコな生き物」として見てもらえていそうなのは嬉しいことですね。
平向氏:
原生生物に関しても、デザイナーが実際に作る時には「こういうデザインになると、かわいくなりすぎちゃうのでダメです」といったような線引きがあったりします。そこのラインをデザイナー同士で共有してもらいながら、それぞれの原生生物を作り上げています。
それこそオッチンも、一見かわいいようで実は原生生物に噛みつく時はしっかり歯が出ていたり、まぶたもリアルに作ってあったり……。そういった「かわいい」と「リアル」のバランスを取りながら、ひとつの「生き物」として作り上げています。