日本インディーの質は高い。だからこそ海外で認知を得られないのが悔しかった
──では、ここからは「iGi」や「創風」が実現した経緯についてお聞きしていきたいと思います。例えば、一條さんはこれらのプロジェクトの以前、インディーゲームの黎明期からさまざまな活動をされてきていますよね。その中で、こうした活動につながるようなきっかけを見つけたり、インディーゲーム業界自体の変化みたいなものを感じ取られていたんでしょうか。

一條氏:
私が自分でゲームを作り始めたのが2014年くらいで、2015年に『Back in 1995』というプロジェクトを発表しました。その時のトレーラームービーがウケて、海外メディアにも取り上げていただいたんですよね。でも、『Back in 1995』は売上的には超ヒットというレベルには到達できませんでした。
しかも今って、『Crow Country』や『Nightmare Kart』などの初代プレイステーション風のゲームがたくさんウケているじゃないですか。だから『Back in 1995』ではかなり先立ったことをやれていたし、一時は海外から注目も集められたのに、ゲーム自体の存在があまり知れ渡らなかったなという悔しさがありました。
で、「それはなんでだろう」と考えたとき、ゲームを作りながら、国内外のステークホルダー【※】に対して、インディーゲーム開発者としてしっかりと関係性を作っておくべきだったと思ったんです。これが2016年くらいの話ですね。
当時は、私の回りにも良いゲームを作っている国内の開発者さんはいっぱいいたんですが、なかなか世界的なヒットにつながるチャンスは難しいという状況でした。
その中で、もっぴんさんが開発した『Downwell』が、Devolver Digital【※】からリリースされるというのがエポックメイキングだったんです。同作のヒットで日本のインディーゲームへの関心が一気に高まったんですが、その背景にはもっぴんさん自身がアメリカ暮らしの経験があり英語ができて、海外開発者とのつながりが作れていた、という面もあったと考えています。

※ステークホルダー:利害関係者。ビジネスシーンでは株主、経営者、従業員、顧客など幅広い層を指すが、ここではパブリッシャーなどが中心。
※Devolver Digital:アメリカ・テキサス州に拠点を置く大手ゲームパブリッシャー・映画配給企業。
──個人開発者でありながら、英語圏のパブリッシャーとやり取りするだけの力をお持ちだったと。一條さんは、2021年には「インディーゲームサバイバルガイド」という書籍も手がけられていますよね。
一條氏:
はい。この本を出した理由は、日本のゲーム開発者さんがいま一番苦しんでいるのは「ゲームをたくさんの人に遊んでもらうためのまとまった知見がない」ことだと思っていたからなんです。
日本の開発者さんは、ゲームのクオリティ自体は他国に引けを取らないと思うんです。でも、それを「どうやってSteamやAppStoreを通じてたくさんの人に届けるのか」みたいな情報って、なかなか信頼できるものが得られない。
なので、本書はパブリッシャーのPLAYISMさんにもチェックしていただきつつ、そういう情報を書籍としてまとめる試みをしました。いち開発者として作品作りをする傍ら、自分をふくむ日本国内のインディーゲーム開発者がもっと海外で知ってもらえるよう、ずっともがき続けてきましたね。
──インディーゲーム開発者として活動を始められた当初から、海外の認知というところが主な課題だったんですか?
一條氏:
個人的にはそうです。理由としては本当に単純な話で、海外での認知を獲得すると、ゲームを買ってくれる人の数が圧倒的に増えるんですよね。
ここでいう海外の認知とは、海外メディアさんや会社コミュニティ、そして展示会を通じてゲームファンに作っている作品を知ってもらうということで、これがかなり大変なんです。
当時はIGF【※】などの海外アワードに単独でチャレンジするとか、台北ゲームショウなどの海外イベントにみんなで行くみたいな動きもあったんですけど……。結局のところ、海外コミュニティとの接点が上手く構築できなかったり、費用的な負担が重かったりで、なかなか難しいんですよね。
なので、開発者自身が海外での認知を得るための知見、情報の筋肉をつけるにはどうしたらいいのか、というのをずっと考えていました。
※IGF(Independent Games Festival):1998年より毎年開催されている、インディーゲームのアワード。「サンダンス映画祭のゲーム版」をコンセプトに、小規模でユニークなゲームを表彰している。
──確かに、少し前までの日本にはインディーゲームの市場というものがあまりなかったように思います。Steam市場の日本のシェアって、2%より少し多いくらいでしたよね?
一條氏:
そうですが、以前は1%程度だったのが近年急激に伸びたという印象です。それでも、ワールドワイドと比較すると小さい。となると、必然的に海外向けにも販売できていった方がいい。これは『Back in 1995』をリリースして分かったことですが、自分が愛している作風とかゲームの内容を、同じように理解してくれる人は世界中にたくさんいるんです。
たとえば初代PSが正規で売っていなかったような地域でも『Back in 1995』の売り上げがあったというのが面白くて。そういった体験を通じて、自分の身の回りでゲーム開発を頑張っている人たちの作品を、世界中のユーザーに見つけてもらいたいと思いました。
──他の国では都市単位でインディーゲーム開発者のコミュニティがあり、そういうローカルなコミュニティで横のつながりがあると良いという話を聞いたことがあります。それもまた、一條さんが意図する情報の筋肉というところになるのでしょうか?
一條氏:
その通りです。「Tokyo Indies」や「KYOTO PLAYROOM」といったローカルな開発者の集まりや、たとえばシューティングゲームを作っている人だけのDiscordサーバーみたいな、粒度が小さいコミュニティがたくさんあった方がいいと考えています。
というのも、そういったコミュニティがあるとお互いの機密情報を守った上でのぶっちゃけ話ができるんですよ。
とにかく、私としては技術的な情報はもちろん、契約周りの話や、ゲームの中で表現するものの法的な部分といった知見は、開発者さんにどんどん共有していかないといけないなと思っています。iGiではそれをメンタリングを通じて提供していて、創風でも同じことができると考えています。
──……これは素朴な疑問なんですが、自分のゲームを作るだけじゃなく、界隈全体のためにご自身のリソースを割いていくモチベーションというのは、どこにあるんでしょうか?
一條氏:
そうですねー……。単純に悔しいから、ですかね(笑)。
これは繰り返しになりますが、日本のインディーゲーム展示会で登場する作品を見ていると、ゲームのクオリティとか目指しているもの、こだわっているところの良さ、味の濃さっていうものは、世界規模でみても素晴らしいものだと思うんですね。
それなのに、クリエイター個人のせいではない「壁」に防がれて、全世界での露出が削がれているというのは単純に悔しいと思っていて。「この壁がなければ、この作家さんの作品は10倍も20倍もファンができるポテンシャルがあるんだよなぁ」という気持ちがあるんです。
その「壁」というのは、シンプルに言語の壁も含まれるんですけど。今後、機械翻訳が向上して言葉の壁がなくなっていくと仮定すると、その時に障壁になるのは堅い言葉で言うと “事業遂行能力” だなと。
ゲーム開発者さん自身で、作品のアピールの仕方やパートナー探しの方法、お金回りの知識といった知見をつけることが必要なんです。ですが、そういった情報を取りに行く術がなく、中間業者に絡めとられがちです。そこが非常に悔しいところなので、その術となれるよういろいろと時間を割いてきました。iGiも、本の執筆も、その一環ですね。
それにこういった活動をしていると、自分が作っているゲームの知見入手にもつながっていきますので、実を言うと、完全なる奉仕の心でやっているというわけではないんです(笑)。ですので、「自分も含めて」日本のインディーゲーム開発者の文化が盛り上がっていくための活動、と言っています。
国からの支援が少なかった日本。海外を巡る中で見えてきた課題から「iGi」は生まれた
──ここまで一篠さんの活動を振り返ってきましたが、そこからどういった点がiGiの立ち上げにつながったのでしょうか?
一條氏:
iGiの立ち上げの時は、私は佐藤さんからお声がけをいただきましたね。
佐藤氏:
元々、私の仕事は日本の作品を海外に届けるお手伝いと、海外の面白いゲームを日本にお伝えすることのふたつなんですね。
そういった中で、前職のメディアクリエイトという会社で「新興国ゲームビジネスレポート」というものを作るため、ラテン・アメリカ、中東、インド、アフリカと、世界各地に行って取材と調査をしていました。
そうして世界中で色々な開発者に会っていると、「どうも彼らは国の支援をゴリゴリ受けているらしい」というのが目に入ってくるんですよね。それに加えて、海外で色々な方に「日本って国からの支援が全然ないの!?」って、ずーっとツッコまれ続けていました。
やがて、仕事としてマレーシアで政策提言したり、サウジアラビアの政府機関のアテンドをしたりというところまでいきました。すると、今度は「海外の国のお手伝いはしているのに、日本のゲーム産業のお手伝いはできていないな」という思いがかなり出てくるようになったんです。
──なるほど。海外を回られて各地の状況を見てきたからこそ、日本ができていないことが見えてきたというわけですね。
佐藤氏:
そして2020年、私がルーディムス株式会社を起業した直後くらいに、マーベラスの担当者の方からお声がけがありまして。そこで「日本でもインキュベーションプログラムをやったらいいんじゃないか」とお話をさせていただき、「iGi」の元が生まれました。
私自身、海外方面に詳しい方ならばある程度知っているつもりではいたんですけど、この計画をしっかりと遂行するためには日本のインディーゲームにちゃんと詳しい人、そして長期間にわたってプログラムを見る意志を持っていらっしゃる方がいないと絶対に駄目だなと思ったんです。
それで色々な方とお話をして「これはもう一條さんで間違いないな」と思い、お声がけさせていただいた……という流れになります。
以前、電ファミさんに「インドのマーケットが、アフリカのマーケットがどうだ」みたいな記事を掲載させていただきましたように、私自身は「新興国の専門家」だったのですが、そうした思いが背景にあってお手伝いさせていただくことになったんです。
──ありがとうございます。ところで、知念さんはどういった形でiGiにご参加されたのでしょうか?
知念氏:
私は1期の途中からiGiに参加させていただいているんですが、マーベラス自体には10年以上在籍していまして。ブラウザゲームの企画を担当した後、在籍のほとんどの期間は人事で採用や教育関連のマネージャーをしていました。
その中で私個人が非常に歯がゆくおもっていたのが、「ゲームが作りたい」といって当社に入ってきてくださるのに、短期間で辞めてしまう方がいることです。ゲーム業界全体で見ると、30%くらいの人が入社して2~3年程度で辞めてしまうんですよね。
マーベラスがそこまで退職率が高いわけではなかったんですが、退職の理由を聞くと「思ったゲームを作れなかった」とか、「思ったところに携われなかった」という方が少なくなかったんです。
ゲームを作りたいという思いで入社をして、ゲームを作ること自体は実現できているにも関わらず、それが自分の思い描いていたものと違うから辞めてしまう。採用ってひとりあたりに結構な額がかかっていたりもするので、「ゲームを作りたくて入っていて、ゲーム作り自体はできているのに辞めちゃうんだ」というジレンマが、非常に心に引っかかっていました。
そこでクリエイターを育てていくiGiのプロジェクトの話を聞き、非常に興味をもってiGiに参加させていただきました。
というのも、私が培ってきた人事の経験も活かせそうだったのがひとつ。また、インディーゲームクリエイターの地位がもっと向上すれば、独立したクリエイターを目指しやすくなり、私が気になっていた「なぜゲームを作れるのに辞めてしまうのか」という問題の解決にもつながるんじゃないかと考えた面もあります。
一條氏:
実は知念さんがiGiに加わったとき、「元人事の方です」と紹介されて、「採用されてしまう!開発者が会社に取り込まれる!」と勘違いしてちょっと警戒してたんですけれども(笑)。
実際には今お話していただいたようにまったく逆で、インディーゲーム開発者に対する理解や解像度がとても高いうえ、開発者やチームの想いを見抜く力に助けられています。
大ヒットした『8番出口』も、実は協力者の多くがiGi関係者
──iGiを実際に立ち上げてみて、どういった苦労や反応がありましたか?
佐藤氏:
iGiは、ものすごくみっちりと色々なセッションが詰まったプログラムなので、参加する開発者さんたちは大変だと思いますね(笑)。
その上で、私たちもお手伝いをさせていただくためには色々なステークホルダーの方とお話しなければならないので、そういう面ではかなり工夫が必要でした。このあたりは、私も一條さんも知念さんも共通の認識じゃないかなと思います。
一方で「iGiをやってよかったな」と感じた瞬間も何度かありまして。
例えば、中国の一番大きなインディーゲームのイベント「WePlay」に参加したとき、中国のパブリッシャーさんに名刺をお渡ししたら、「ふーん、よく分からない人が来たな」みたいな反応をされたんですが……。そのあと「実はiGiの事務局長をやっておりまして」っていう話をしたら、3~4社くらいの方が「ああ、iGiね!」という風にすごく良い反応を返してくださったんですよ。
しかも、「『NeverAwake』のiGiね!」とか、「『34EVER LAST』のiGiね!」とか、挙げてくれたタイトルがそれぞれバラバラだったんです。この時、日本の開発者のタイトルを中国のパブリッシャーにも知っていただくお手伝いが、iGiを通じてできたのかなと感じて非常に嬉しかったですね。
それと、これは最近の話なんですが、インドネシアでゲーム販売店に行ったら、棚の中にiGi発の『NeverAwake』のパッケージがちゃんとした正規の形で売られていたんです。私が今までメインフィールドとしてきた東南アジアや中東にも、iGiの作品がちゃんと届いているという光景を目にすることができたのが嬉しかったですね。

一條氏:
海外のパブリッシャーさんって、日本国内のゲームに決して興味を持っていないわけではないんですよ。
「日本のゲームの作家さんと会いたい」という方はいらっしゃいますし、実際に東京ゲームショウやBitSummitなどにも多くの海外パブリッシャーさんが足を運ばれているんですけど、そこでなかなか後につながる出会いが生まれない、というのが日本のインディーゲームの障壁のひとつとしてあるんです。
日本の作家側としては、そもそも英語ベースでのコミュニケーションってハードルが高いし、海外に日本のインディーゲームを探している人がいるんだ、という認知そのものがあまりなかったりもするので。これはすごくもったいない状況だなと思っているんです。
そういった中でiGiを3期にわたってやってきて、すごく良かったなと思っていることがひとつありまして。それは、iGiのプログラムを受けた皆さんが、ゲームのジャンルとか完成度に関係なく、パブリッシャーに向けて「こういうゲームです」「こういう資金が必要です」「こういうスケジュールです」と話せる状態になっているということです。
iGiのクリエイターさんには、メンタリングで「パブリッシャーはこういうことを聞いてきます」というのをお伝えしているので、どういった準備をしておけば慌てずに済むのかが分かっていて、準備万端なんですよね。
であれば、海外のパブリッシャーやステークホルダーも、話しかけやすい。ちゃんと日本の作家さんと海外のステークホルダーとのやりとりが自然発生できるようになってきたというのが、iGiをやって一番良かったところかなと思っています。創風でも「成果発表会」が2回ありますが、これを通じてパブリッシャーに自分の作品を的確に伝えられるようサポートします。
──なるほど、開発者側でパブリッシャーとの対話の準備が整っているというのは確かに大事ですよね。
一條氏:
逆にiGiの一番つらいところは、1期間あたり5~6チームしか見られないということです。私たちのリソースもそうですが、ゲームと伴走するメンターさんの時間も取ることになるので。本当なら、もっともっとこういった活動をやっていきたいんですけど、それは難しい。
でも、iGiも3期まで続いてくると、メンタリングでクリエイターさんにお伝えしたことが良い意味で漏れだしていくんですね。『NeverAwake』の佐渡さんをはじめ、iGi卒業生の方が「こういうことを学んだよ」と周囲に伝えていくわけです。
もちろん、iGiのメンタリング内容の録画やスライド資料をポンと渡すのは禁止なんですけど、クリエイターコミュニティってそういう情報が自然と浸透していくものだと思っているので(笑)。そういったところからも、国内全体のインディーゲームの機会向上につながることができたんじゃないかなと思っています。
iGiは今、4期生のプログラムが開催されておりますが、今回申し込んでいただいたチームは「3期生に紹介されました」「1期生に様子を聞いてから来ました」という感じのところが多いです。卒業生の方から推薦を受けて応募してくださった方がかなりいたというのが印象的でした。
3年かけて、iGiというプログラムの立ち位置と、何をしているのかというところが開発者に対してやっと伝わってきたと実感しています。
佐藤氏:
そのお話を聞いて、iGiの立ち上げ当初に苦労したことをひとつ思い出したんですが、「インキュベーションって何?」っていうのが中々伝わらなかったんですよね(笑)。
ヨーロッパとかアメリカ、アフリカでは、「インキュベーション」とか「アクセラレーション」って言うと、ゲーム業界であれば特に説明もなしにどういうものか分かっていただけるんです。ですが、日本では中々伝わらなかった。その点については、みんな苦労したんじゃないかなと思います。
でも、一條さんが仰った通り、何年か続けていく中で、ようやくiGiがやりたいことが伝わっていったような感じがしますね。
一條氏:
iGiの立ち上げと同時期に講談社さんや集英社さんのゲームコンペティションが立ち上がったというのもあって、iGiも当初はゲームパブリッシャーのように勘違いされていたんです。
iGiが2021年に初めてピッチイベントを実施したときは、「パブリッシャーさんを多数招待し、契約したいゲームを探しにきてもらう」という主旨をパブリッシャーに伝えるのが難しかったんです。「これってパブリッシャーのマーベラス社さんのイベントなんですよね?」って言われてしまったりして、「いや、そうなんですけど、そうではなくてですね……」みたいな感じで(笑)。
そのころはまず、iGiの立ち位置を伝えるところから始めないといけなかった。でも、3期のデモデイには非常に多くのパブリッシャー様に参加していただき、そこから契約につながっていくということも起きるようになりました。
それと、iGi自体はパブリッシングをしない社会貢献事業ですので、デモデイが中立地帯のような空間になっているんですよね。関係者が一堂に会して情報交換ができる場に育っていったことは、iGiのユニークな部分だなと感じています。
──お話を聞いていると、「iGi」にはかなり手ごたえを感じていらっしゃるように見受けられます。単にプログラムを受講した方だけに留まらず、業界全体への影響の広がりを感じますね。
一條氏:
先ほど「iGiでクリエイターを育てる」と知念さんが仰っていましたが、仰る通り、iGiの目的は作品だけではなく、作家さん自身の成長サポートだと考えています。
実際にはゲーム作品の審査を経て、採択し、その作品を対象にメンタリングを行っていくわけですが、同時にいま作っているゲームだけでなく、その後の制作活動にも継続して役立つ情報の筋肉を提供することが非常に重要だと思っているんです。実際、『Ninja or Die』のNao Gamesさんや『NeverAwake』の佐渡さんは、iGiを卒業した後、次回作に着手していらっしゃいます。
特に印象的だったのは、3期で採択した『STRANGE SHADOW』のKOTAKE CREATEさんが、『STRANGE SHADOW』を製作しつつ、サブで作っていた『8番出口』で大ヒットを記録されたことですね。

一條氏:
『8番出口』については、iGiで直接メンタリングをしたわけではないのですが、『STRANGE SHADOW』を通じてKOTAKE CREATEさんにはさまざまな知見を提供しました。
面白いなと思うのは、『8番出口』のスタッフロールで流れるテストプレイなどの協力者の名前に、多くのiGi関係者が名前を連ねていることです(笑)。iGiの卒業生が、それぞれ同期みたいな形でお互いの活動を支援している動きがあるようでして。
iGiは『8番出口』そのものにはノータッチですが、そういう流れを見ていると、コミュニティの醸成であるとか、Steamやプラットフォームでゲームを出すための知識といった面でうまくサポートすることができたのかも、と実感しますね。
佐藤氏:
海外のインキュベーションプログラムだと、卒業生のみなさんが一緒に仲良く助けあう関係性に必ずしもなるとは限らないんですよ。
例えば、ヨーロッパのプログラムの中には、20チームを取った後、2か月後に5チームにプログラムから抜けてもらって、4か月後に更にもう何チームか抜けてもらう……みたいな、競争させる形のものも結構ありまして。
もちろん、競争を通じてすごく良いタイトルを生み出すっていうモデルも確かにあります。しかし、そこには協力関係とか、お互いにテストプレイをしあうような関係性が生まれづらいっていう側面もあるんですよね。
国民性的な側面もあると思うんですけど、日本でそういう競争をするとギスギスしがちじゃないですか。もちろん、色々な形があっていいと思うんですけれど、iGiはそういった卒業生の関係性という面でもユニークな、面白い形になってきているなと感じています。
──そういったiGiの活動が、晴れて今回の「創風」につながったわけですね。
一條氏:
そうですね、佐藤さんや知念さんと一緒に、理想を追い求めてiGiで頑張ってきました。すると、それがそのまま、インディーゲームを事業活動面で支援する国の事業という、本来私がやりたかったものに先祖返りするような形になりまして。今までiGiで培ってきた育成やサポートのノウハウを、そのまま国の事業にご提供する形になりました。
創風は「とにかく実践的」なプログラムに。
──さて、創風は記念すべき、「国からお金が出たインディーゲーム支援プログラム第一号」というわけですが、この先の課題みたいなものは何かあるのでしょうか?
佐藤氏:
国がゲーム産業を支援することになると、もし変な方向に動いてしまったりしたら、ゲーム産業全体にとってすごくもったいないことになるんじゃないか、という危惧はあります。これは私だけでなく、一條さんも他の皆さんも感じているところだと思うんですよね。
一條氏:
普段からインディーゲームのスタイルが肌感でわかっている方の知見がないと、現場の開発者に役立つものになりにくいんです。たとえば大手ゲーム会社のディレクターを連れてきてもあまりうまく行きません。私や佐藤さん、知念さんたちの働きかけがなければかなり違ったものになっていたかもしれませんね。
我々はこのプログラムを開発者に直接届く実地的、実践的なものにしようと考えていますので、メンターさんは実際にインディーゲームに携わっている方を選んでいます。「大スター開発者を連れてきてお金ありきの大規模ゲームについて講釈を垂れてもらう」というのはやっていないんですよね。
──確かに、メンターさんの顔ぶれを見ると「実力派」という感じがします。
一條氏:
iGiの方では『天穂のサクナヒメ』の「えーでるわいす」の開発者さんにはメンターとして参加していただいているんですが、他には実際にインディーゲーム開発者として活躍されている方、大中小さまざまなゲーム開発会社のマーケティング担当者をされていた方などを引っ張ってきました。創風もそうしたメンターを用意していきます。
なので、知念さんは「iGiはいぶし銀のプログラム」ってよく言っています(笑)。もちろんデモデイの開催みたいな派手な場面もありますが、多くは地味で地道な知見の提供ですね。
なので、開発者さんから「iGiって何をしてくるのかよく分からない」と言われてしまうこともありましたが……。それでも、iGiは今後もこのスタイルで続けていくつもりです。逆に言えば、こういった地味なことをコツコツやってきたからこそ、国が実施する事業の運営者としてフィットした面もあると思うので。
──ありがとうございます。最後に、今後の展望をお聞かせいただければと思います。
知念氏:
そうですね。先ほどお話したように、このプログラムでインディークリエイターとして独立したいと思っている方を支援できればと考えていますので、長く続けていくことが意義になるのかなと思っています。
また、日本のゲーム文化は世界から注目される財産であると思っていまして、昨今のゲーム市場の盛り上がりにもっと日本が追いついて、追い越して欲しいと感じています。
そのためには産学官連携の取り組みをもっと充実させることがひとつの重要な目標になってくると思うので、今回の経産省のプロジェクト「創風」が始まるというのは、かなり良い取っ掛かりになるんじゃないかなと思います。
今後については、国を巻き込んで何かしらの旋風を巻き起こす、日本全体でゲームシーンを盛り上げるような活動に寄与することができたらいいなと思います。
一條氏:
まずは、私が開発者を続けていく中で繰り返し言っていた、「日本はインディーゲーム開発者をサポートしてくれや」が実際に始まったこと、そこに自分の知見を投入して、プログラムがいいものになっていけそうだということが、大変喜ばしいです。
ただ、一番苦しいのは、私自身は中の人だからこれに申し込めないってことなんですよね(笑)。
──(笑)。
一條氏:
「創風」もそうですが、他の団体が別の観点からゲームの支援を始めるかもしれないし、他の省庁様が新たにプログラムを立ち上げられるかもしれない。そういったとき、そのプログラムが日本の開発者たちから見てズレた物にならないように頑張っていかなければ、という気持ちはやはりあります。
日本国内のゲーム開発者とのつながりが薄い方がそれをやろうとすると、すごくズレたこと……例えば、ゲームクリエイターとしてすでに有名人な方ばかりとか、海外方面にお金を出しちゃうことになりかねないな、という危惧はありますね。
少なくとも、iGiと創風については自分の知見を投入させていただくので、国内でコツコツとゲームを作っている開発者の方に向いた内容にしていきます。
また、このプロジェクトを通じて、日本のインディーゲームを好きになってくれる海外のゲームファンがもっと増えていくといいなと思います。日本の作家さんの個性がガンガン出た作品を世界中のユーザーに届け、好きになってもらいたい。
ゲームにはもちろん商品としての側面もありますが、私はやはりゲームとは作り手の個性が注ぎ込まれた「作品」だと思っているので。それらが今後よりいっそう、海外のゲームファンにつながりやすくなって欲しいですね。
佐藤氏:
知念さんが長く続けていくことが大事だというお話をされていましたが、海外の事例を見ていると、インキュベーションプログラムやアクセラレーションプログラムって、長く続けているところほど良い仕組みになっているんですよ。
長く続けていると、プログラムを卒業して成功した開発者さんがパブリッシャーや投資家になって帰ってきたりして。するとプログラム内での支援の仕方、仕組みがツーカーで分かっているから、更にドンドンとヒット作が生まれる。中には、2年に1回ペースで100万本以上売れる大ヒット作を出しているようなすごいプログラムもあったりするわけですね。
ぜひ、iGiもそういったものになって欲しい。どういう形になったとしても、クリエイターの成功率と生存率を高める存在であり続けて欲しいです。私は特に「クリエイターの生存率を高めるもの」であって欲しいなと思います。
あともうひとつは、ぜひとも海外のゲームファンに「日本のインディーゲームって、ここがすごいよな」みたいな、共通認識を持ってもらいたいなと思っていますね。
日本のインディーゲームを遊んでくださっている海外のファン自体はたくさんいらっしゃいますし、日本のインディーゲームにはたくさんの素晴らしい作品があります。
にも関わらず、海外ゲームファンの中で「日本のインディーと言えば、ココが素晴らしいよね」というブランディング的なものが固まっているとは言い難いと思うんですよね。そこを変えていければなと強く思います。
「日本のインディーゲームだから取り上げよう!」くらいに言ってもらえるような世界になって欲しいというのが、今の私の気持ちです。(了)
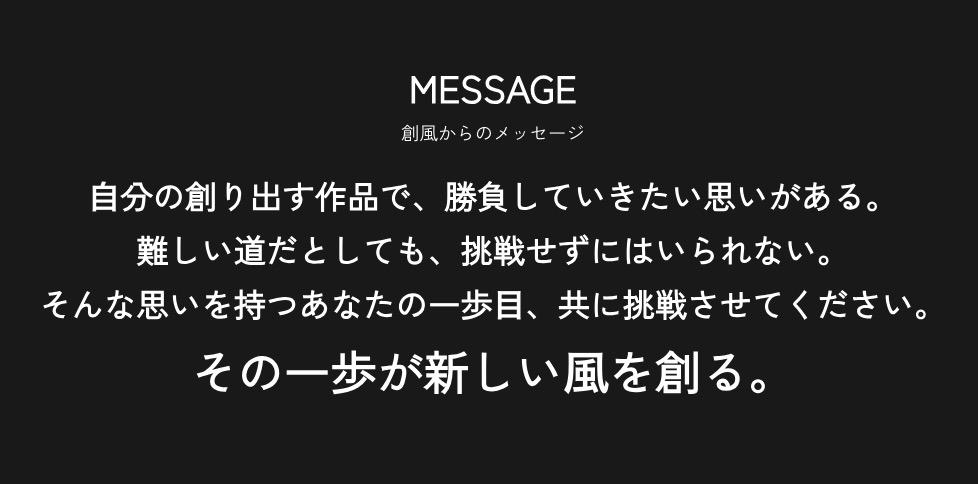
さて今回は、国がインディーゲームクリエイターを対象とした初の支援プログラムである「創風」成立の背景と、それまでのインディーゲーム開発者の苦労と実情に関して、その実行部隊であるiGiの皆さんにお話を伺った。
インディーゲーム、個人の開発者が海外で勝負をするためには様々な課題がある。その課題をクリアにするためには、開発面だけではない、事業を維持していくための知識の獲得が不可欠であり、その知識の共有を目指したiGiの活動が「創風」へ結びついていったことが読み取れるだろう。
とにもかくにも「国がインディゲームクリエイター支援に乗り出した」というのが、創風のもっともエポックメイキングな部分であることは間違いない。確かな実績を積み上げてきたiGiのノウハウを存分に活かし、多くのクリエイターの作品が世界で花開くことに期待したい。
なお、2024年6月13日には「創風」第一期の選出チームが発表された。全122件の応募があり、19件が採択されたという(うちゲーム部門が9件、映像部門が10件)。
採択されたタイトル・クリエイターは下記のとおり。7月より支援が開始されていくとのことなので、今後の動向にぜひ注目したい。
【ゲーム部門】
ァアアア”(アシ)
ウルトラクライムジェットガール桐生七・斉藤タカシ
Witch the ShowdownKei26
ロープくんアドベンチャー宍倉志信
子どもたちの庭志麻ひぬこ
み冬尽く日DON YASA CREW(佐川ドン・あだかとう)
リズデビ! : Rhythm of Deck Builder@_mathken(VR Game Media)
Blasted Stealth / 爆音ステルスモーノ
ヘルヘル – Hell Hell –るきみん。
RUKIMIN’s Disappointing Adventure All Stars【映像・映画部門】
伊藤瑞希
スクラッチ(仮)伊藤道史・江口智之・nyu・原野瑞希
「Morphing Dynamis / 起きた後のこと」(仮)北林佑基・松本佳樹・林真子
パッキン太郎笹谷周生
WISTナカダリオ・桝田康太
Nox橋本麦
Addition/Subtraction三谷怜司
ダンジョン&テレビジョンゆうか・あんな
ちいさな王さま(仮)ゆはらかずき・島尚比呂
First Virtual Suit吉岡一靖・木村響・ワタナベタスク・尾崎そよ
JAMES WEBB/PROJECT NOTCH


































