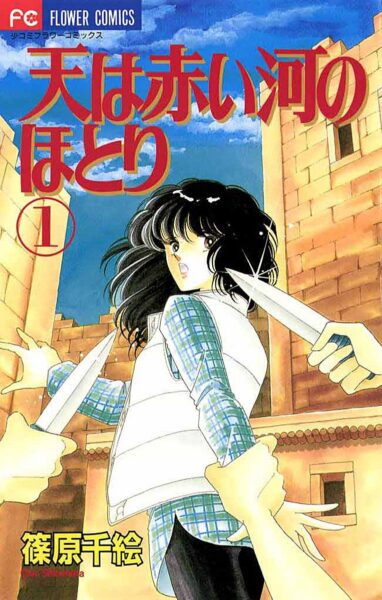2020年12月10日、『サイバーパンク2077』が発売された。一部コンソール版のローンチが崩壊し狂想曲がインターネット上を良くも悪くも騒がせる中、ジョニー・シルヴァーハンドとの物語に決着を着けると、作中のような「情報技術の発展」が現代社会にもたらしたのは何だったのかと、ふと頭に浮かんだ。
 |
現代では、飛行機で十数時間かかる世界の裏側で起こったことを、ほぼ同時に知ることができる。インターネット上のニュースは爆発的に増加したのに、悲しいことにサイバーウェアは流通していない。人間の脳の処理能力と、その周辺を駆け巡る情報量の差は、一気に広がり始めている。
場所も年齢も人種も選ばない情報の洪水の中、僕らはPCやスマートフォンといった個々人が持つ情報端末で、流れ込む情報を“剪定”しようとする。たとえ同じソースであっても、出どころも語り方も捉え方も異なるのだから。その中から自分にあったスタイルを選び、ほかの誰かに伝えたりもする。
だから同じニュース、同じゲーム、同じ政治、同じ文化の話を見る機会が増えたにも関わらず、誰かと同じ感情を共有することはいまだ難しい。年中無休で24時間動き続ける高度な情報社会によって、むしろその「同じ情報を共有しているはず」というボタンの掛け違いは増加し、SNS上は混沌とした様相を見せ続けている。
「同じものを見たら同じことを感じるはずだ」という牧歌的な倫理観は通用しない。それは良いとか悪いとかいう問題をとうに超え、そして近未来のフィクションなどではなく現実世界の事実として、そこに存在している。
 |
僕の世界は僕というバイアスがかかった「情報」が作り、あなたの世界はあなたというバイアスがかかった「情報」が作っている。『サイバーパンク2077』は現代社会と地続きのように、そういう類のインフォメーションで形成されている。
発表から8年を経て本作を完成させたCD Projekt REDは、もはや古臭く見えるレガシーなゲームデザインやシステムの革新ではなく、「情報」に新たなオープンワールドゲームの地平を見た。
オープンワールドゲームが求めてきた志向のひとつ「没入」
「私は誰で、いまどこにいて、何をしているのか」
 |
それはビデオゲームが「物語」を語るためのデバイスとして進化する過程で生まれた命題だ。ゲームという単なる娯楽は技術力の凄まじい進歩の中、ひとつの方向性としてその中に「世界」を生み出すことを志向した。
それはジャンルの括りを飛び越えて、その「世界」へとダイブしただひたすらに没入し得る空間を人為的に創り上げるという挑戦だった。その世界にどれだけリアリティがあるのか。プレイヤーに「私が誰で、いまどこにいて、何をしているのか」を、どれだけリアルに錯覚させるかという表現への飽くなきチャレンジである。
それは小説ではなければ、映画でもない。ビデオゲームならではのインタラクティブ性の追及とペアとなり、ときに大幅な、ときに細かい可能性を試行してきた。『Red Dead Redemption 2』などで顕著に示されたその「没入」への挑戦は、いまなお続いている。
なぜ『レッド・デッド・リデンプション2』は時代遅れで、それゆえに美しいのか。Rockstarが目指す狂気と理想の“世界”
CD Projekt REDも同様の挑戦に取り組んでおり、2015年にリリースした『ウィッチャー3 ワイルドハント』は、オープンワールドという形のひとつの完成形だった。
個性あふれる登場人物と魅力的なメインストーリー。どこまでも広がるワールドでは各国の情勢が描かれ、それに比肩するほど細かく作り込まれた膨大な量のサブクエストが、『ウィッチャー』の重厚な世界を確立させる。発売当時は多くのゲームプレイヤーたちの心を掴み、非常に高い評価を受けた。
 |
広くではなく“深く”創られた「ナイトシティ」の多重構造
それから五年の月日が経った。同社が満を持してリリースした『サイバーパンク2077』は、単純に作り込みという意味において、『ウィッチャー3』から正当かつ大幅にその表現を進化せしめることに成功した。
ただそれだけではなく、『ウィッチャー3』で実現した「旧来型のオープンワールドゲーム」という完成されつつあったスキームを転換させている。
それは単に三人称だった視点が一人称に、ファンタジー世界が近未来サイバーパンクに変わったという些末なことではない。それは一言で言えば、「情報」の扱い方の大きな方向転換だ。
 |
外部から来るものも、内部から来るものも含めて、『サイバーパンク2077』で表現される情報量は異常だ。それは過去のオープンワールドゲームにはけっしてなかったレベルに達しており、長きにわたる開発期間とコストを掛けて崩壊する寸前まで積み上げていった結果と見れるだろう。
舞台ナイトシティそのものに描かれた信じられないほどの広告の数々。プロモーション映像、ラジオ音声、テレビニュースは狂ったように声を荒げ続ける。
何か別のことをしていてもメッセージやコールが引っ切りなしに主人公Vを呼ぶ。街角を行く人々、その会話、喧騒、事件。裏道に入れば、世界観を補完するチップが至る所に落ちている。
 |
広さで見れば、『ウィッチャー3』が表現した広大な大地に対し、「ナイトシティ」は一都市に過ぎない。
しかし、そこに横たわるのは都市の沿革から技術革新の歴史、国家と企業の関係性、ギャングたちの息遣いまで感じさせるほどの仔細かつ膨大な情報がそこにはある。
 |
その外部からもたらされる情報群を見れば明確で、本作はオープンワールドで「広さ」を指向しているのではなく、「深さ」を指向している。
つまり本作はマップがいかに広大かで世界を感じさせるのではなく、マップ自体の作り込みと情報量による奥行きや密度を世界表現の軸と考えている。その情報の羅列は、まともに見聞きすればプレイヤーが立ち尽くしてしまうほどである。
 |
たしかに都市の形というものは、ビル群と垂れ流されるネオンテキストといまを伝える音声、雑踏や音楽の彩りが融合されて形成される、キメラのようなものだ。
『サイバーパンク2077』が目指したベクトルは、都市社会における膨大な情報というものが、人に対してどういった影響を与えるのかを非常によく考えた上で設定とされている。
それは「ゲーム中にある情報はすべて必須の部品で不要ではない」という、確信めいた信念すら感じさせるほど偏執的だ。
 |
『サイバーパンク2077』を構成するそれらの全てのパーツが高レベルで噛み合った瞬間、かつて誰も体験したことのなかった高密度がその世界には生まれる。それは単純に多彩で広大なワールドを作ったり、薄味のクエストや収集物を並べることでは実現しない世界だ。
うるさいからとラジオをオフにしたり、広告を横目で流したり、近場で起きた事件をスルーしたり、興味のないチップを読まずに積み続けたりと、多くのパーツはプレイヤーがまともに受け止めない情報となるかもしれない。
 |
しかし、その“存在する断片情報”は、人や店、通り、あるいは事件や任務といったクエストの輪郭をはっきりとさせていく。
それは旧来のアーカイブなどで見られた補完ではなく、もはや多重構造の情報レイヤーだ。そのときナイトシティという都市は、「そこに存在する」という強烈なリアリティをもって、プレイヤーをがんじがらめにしていく。
 |
「世界は場所ではなく情報で形成されている」というリアル
またこのゲームは、世界を構築しているものが外部からの「情報」だけではなく、その大部分が「内部」からの見え方によって形成されているという見識のもと表現されている。
特筆すべきは生体インプラントやUIなどによる「視覚表現」の多様さだろう。プレイヤーは自身の目を通して多くの情報を得る。
 |
それはたとえばハック対象のオブジェクト情報や街ゆく人物の名前や所属、指名手配度を含めたジェネラルな情報。知らない言語を翻訳ソフトを通して視界上にテキスト化をする演出もそうだ。
あるいは跳弾の起こる銃器を使う時の予測弾道、自分をハックしてくる敵の位置、グレネードの予測脅威範囲。ひとつひとつは自身の生体カスタマイズ、あるいはスキルのアンロック、ストーリー上の演出として違いがでるものであり、ゲーム性の拡張や効果という意味で存在している。
 |
もし目に赤いフィルターをかけて見れば、その人間の世界は赤くなり、青いフィルターがかかっていればその人にとって世界は青くもなる。ごく当たり前の話だが、同じ空間に存在している二者が見ている世界は別物である。
その「人によって見えるものが違う」というゲーム世界のルールが、本作の世界の在り方そのものに大きく影響していることをけっして無視してはいけない。当たり前の話だが、視界はその人間の見えている世界そのものだ。
『サイバーパンク2077』で非常に優れているのは、そんな当たり前の「情報のルール」を膨大な作り込みと多彩な見え方で確立させ、2077年という57年後の世界を見事に予測し現実と地続きにした点にもある。
 |
たとえば地球の裏側にいようとも自分の部屋にいようとも、個人の情報端末からのインフォメーションを頼りに生きていれば、その生活はつねにその人の世界だ。パーソナライズされた情報の海の中に沈みながら生活することが許されている現代では、もはや「場所」という概念は生きるためのメインの空間ではない。
そして近い将来、現実世界の技術革新は、その流れを急速に加速させていくだろう。人はいまよりもずっと、フルで接種してしまえば即座に発狂するレベルの膨大な量の情報を処理し、場所のみが持っている空気感や感触すらも味わえるようになる。
 |
わたしの見ている情報とあなたの見ている情報の違いは、彼我の世界に明確な区別をつける見えない大きな壁になり、人は群体でいながらにして個体化している。その世界では場所は、肉体がおいてある入れ物と大きく違わない。
そして自分自身の世界を創り上げ、ひとりひとりがその中で神に近い存在になる。その世界では情報の剪定の方法もその色も自分そのものがカスタマイズできる。そんな近未来の生活の中で世界を感じるためには多くの時間を「移動」に費やす必要などない。世界を感じるための情報があればそれで事足りる。
 |
オープンワールドゲームを“深化”させた『サイバーパンク2077』
『サイバーパンク2077』は、ゲーム内の情報の扱いを革新的に進化させ、「リアルにおいて世界のほぼ全ては情報で形成されている」という基本的過ぎて見逃しがちな事実をプレイヤーに感じさせている。
その事実が近い将来こうなるのではないかという“予感”によって、現代社会とナイトシティとの地平が繋がっていることを強く印象づけ、限りなく土地が繋がっているだけの冒険譚とは比べ物にならないほど、強烈なリアリティを生み出すことに成功した。
 |
ゆえにプレイヤーが『サイバーパンク2077』で遭遇するすべては、遠い未来あるいは中世や魔法世界のファンタジーの出来事ではなく、「未来の現実世界で起きかねない事実」と強く感じる。
それはゲーム内でどれだけバラエティに富んだ地形を用意し、どれだけの場所に行くことが可能かを、ひたすらに小さな問題として認識させてしまう。
 |
ビデオゲームの進化過程の中でその世界へと精神を仮想の場所にまるごと「ダイブ」させることがひとつの究極的な終着点であるのだとしよう。
ならば『サイバーパンク2077』は、いままであったビデオゲームデザインに「情報」という軸を、旧来よりも遥かに強く、概念としてゲーム自体の前面に大きく成立させている。完成系へと明確に歩を進めたと言っていいだろう。
ゲーム内で表現されうる情報という概念が根本から違う。補完ではなく、世界に何層ものレイヤーを重ねて立体感を出すというデザインはいままでにない。『サイバーパンク2077』は、文字どおりの意味でオープンワールドというジャンルを「深化」させた。
 |
完璧主義者のプレイヤーが見たら、それだけで目がくらむほど大量に追加されるサブクエストの物量。凄まじいバリエーションのセルフカスタマイズと、それに付随した攻略スタイル。誰ひとりとして同じではない街を行き交う人々。
ナイトシティに蜘蛛の巣のように張り巡らされた複雑な権力構造のマッピングと、自身の選択により様変わりする街の横顔。舞台のディティール全体にわたり細部まで狂気とも呼べる作り込み。
『サイバーパンク2077』を構成する全てのパーツが高レベルで噛み合った瞬間、かつて誰も経験したことのなかった高密度の「没入感」は生まれる。
物見遊山のつもりで飛び込んだ「ナイトシティ」の退廃的で狂気と暴力に満ちた魅力は、一度掴んだプレイヤーの心を簡単には逃がしてはくれない。
そこに赴くには、本気で全てを味わい尽くすか、脱兎のごとく逃げ出すかの判断をミスしない覚悟をするべきだ。
 |
そして覚悟が決まったら目が眩む量の情報の波に飲まれ、夜のネオンに飲まれ、暴力とドラッグと泥水に飲まれよう。
高密度の情報飽和にひとすら溺れ続けることによって体感できる世界とのシンクロはまさに異次元の領域だ。リアルの社会はもうこの領域に足を踏み入れつつある。
接種する全ての情報がわれわれの世界を規定せしめるものなら、本作が明確に指向した外部からの得られる情報の質と量、内部から視界を支配する情報による世界の見え方の角度、あらゆる情報を軸にした、「地形」というものに頼らない新しいゲームマッピングの形がどれだけの「没入感」をもたらすものなのか検証してみてほしい。
 |
「私は誰で、今どこにいて、何をしているのか」
それがビデオゲームが「物語」を語るためのデバイスとして進化する過程で生まれた命題だとすれば『サイバーパンク2077』の中に現状最優の答えはある。
「私はVで、ナイトシティーで裏稼業を請け負っている」
 |
【あわせて読みたい】
我々が見てきたものは氷山の一角だった──数十時間のプレイでも全体像が見えない『サイバーパンク2077』レビュー。オープンワールドRPGにひとつの区切りを付けた大傑作我々が見てきた『サイバーパンク2077』は、“氷山の一角”でしかなかった──。1週間前にレビュー用のコードを手に入れ、50時間を掛けて熱狂しながらメインストーリーを駆け抜けてなお、私の目の前にはまだ膨大なコンテンツが無限に広がっている。