太平洋の向こう、遠く離れたアメリカの大地、オハイオ州。日本からやって来た小学5年生の少年は、誰彼も知らない異国の地でひとり、人生に絶望していた。
日本の小学校では“コメディアンだった”と語るほどの自信を持っていた人気者が、言葉が通じない異国でひとりぼっちの隔絶された世界に叩き込まれる。まるで真っ白に輝いていた過去の自分が嘘だったかのように、少年の心は漆黒に塗りつぶされていった。
このインタビューで語られるのは、そんな人生最大の挫折を味わった少年が文字どおりゲームによって命を救われ、ある種の“呪い”を受けた話である。

彼は漫画『I”s<アイズ>』の高校生活に憧れて日本へと帰国し、信じられないほどの負けん気でゲーム開発業界に入り込んだ。そしていま、インディーゲームデベロッパー「ネストピ」を率いて、『アンクラウン』というリアルタイムのストラテジーゲームを配信・運営している。
「『アンクラウン』は操作は簡単ながら本物のにおいがする」とは、編集長TAITAIが先のレビューで評したとおりだ。
思いがけず、お手軽リアルタイム戦術ゲーム「アンクラウン」にハマった話
その少年──生田恭理氏の裏にある、「ゲームを作ってないと俺は死んじゃう」という、“呪詛”にも近い強迫観念は、いかに形成されていったのか。
彼が『アンクラウン』にまで至る道を追ってみた。

アメリカでゲームに命を救われたオタク、『I”s<アイズ>』に憧れ日本へ
──生田さんの経歴を伺いたいのですが、そもそもどのようにしてゲーム業界に入られたんでしょうか?
生田氏:
話せば長くなるんですが、そもそもゲーム業界に行きたいというのは、もう中学生とか高校生のころから考えていましたね。何も迷うことなく勉強もせず、ひたすらゲーム業界へと突っ走りました(笑)。
──そんな若いころからゲーム業界に行くと決めていたのは、何か理由があってですか?
生田氏:
そうですね。まず、僕は両親の都合でアメリカに住んでいた時期があって、小学5年生から高校1年生の夏まで、5年間ぐらいいたんですよ。
──留学していたわけですね。生まれは日本なんですよね?
生田氏:
はい。小学5年生ぐらいまで日本にいたときは……自分で言うのもなんなんですが、コミュニケーション能力は高いし、みんなと仲良くしていたと思います(笑)。
 |
──かなり根が明るい感じがしますね。
生田氏:
僕は父親が会社の経営をしていて、ファンキーな母親がすごく子どもを褒めるので、その影響を受けてか子どものころからすごい自信に満ちあふれていて、その上におちゃらけていたんですね。とにかく子どものころから自信を植え付けられていた(笑)。
でも、アメリカに行ってからは英語が話せなくて、会話もできず、根暗になったんです。1枚の紙を真っ黒に塗りつぶすみたいな、かなり精神的に病んでいる時期もあったんです。
根暗、というか、蓋をされてしまったみたいな感じでしょうか。
──学校の人気者がとつぜん孤独になってしまった。
生田氏:
学校のコメディアンというか、言葉で人を笑かしたりする少年だったんですが、それが取り上げられたわけで、かなりつらかったです。
たぶん、アメリカで心配して声を掛けてくれた人もたくさんいたと思うんですよ。でも言葉がわからないから、その人たちの笑顔がぜんぶ悪意にしか見えない。
こちらを見てクスクス笑ってるんじゃないか、指を差されてるんじゃないか。もうみんな敵だ、世界は全員が敵だみたいな状態になってしまった。
──精神的にかなり追い詰められていたようですね。
生田氏:
で、言葉も喋れないから打ち解け方もわからなくて困っていたときに、なんか現地の人から「日本のゲーム知ってるだろ?」と、突然もてはやされたんですよ。
──なるほど。
生田氏:
母親がゲーム大好きだったので、一番初めに『ロードランナー』を遊んだり、『MOTHER 2』が大好きだったりと、ゲームはずっと遊んでたんですね。だからそれをきっかけに……。
(画像はロードランナー | Wii U | 任天堂、MOTHER2 ギーグの逆襲 | Wii U | 任天堂より)
──それはどんなゲームだったんですか?
生田氏:
当時発売された『ポケットモンスター』ですね。もうすごかったんです。「このポケモンの育て方どうすればいいの恭理?」と聞かれているらしくて、その言葉は分からないけど、ゲームだから何となくやり取りはできる。

ほかにもニンテンドウ64の『大乱闘スマッシュブラザーズ』とか、『ゴールデンアイ 007』とかをプレイしていました。言葉が通じなくても、ゲームをプレイして笑ったり怒ったりするポイントは一緒なので、ゲームを介してコミュニケーションが取れていたんですよね。
(画像はVC ニンテンドウオールスター!大乱闘スマッシュブラザーズ | 任天堂、GoldenEye 007 (1997) – MobyGamesより。Screenshot via Mobygames)
──ゲームがアメリカでの孤独から救ってくれたわけですね。
生田氏:
人生を救われましたよね。
だから「ゲームからはもう離れられない」という考えが、そのころからもう根底に根付いちゃったんです。ゲームがないと僕は生きていけないくらいの(笑)。
──そこから日本に帰国されるわけですよね。それも親御さんの都合とかなんでしょうか。
生田氏:
ああ、それはもう単純に、「僕はきっとアメリカには馴染まないだろうな」と思いました。
ゲームで仲良くすることはできたんですけど、小学5年生から学び始めたので英語の発音もネイティブまでには近づけないですし、就労ビザを取るのも大変だし。
なので父親はアメリカで仕事を続けつつ、僕は日本に帰ろうという感じでしたね。
ただ、まあ、けっこう僕オタクなんですよ。アメリカでひたすら日本の漫画を読み続けていたわけです。
で、『I”s<アイズ>』【※】とかを読んでいて、「日本の高校ってなんて素敵なんだ!」と(笑)。
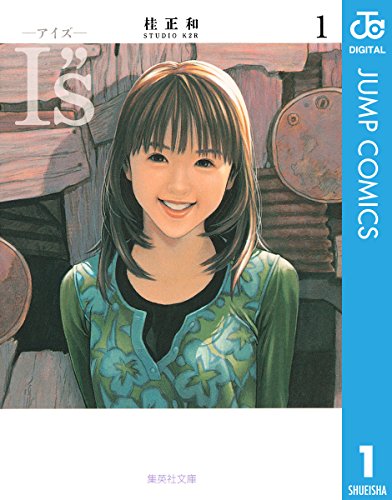
さまざまな環境や問題で思い通りにいかないふたりのストーリーを軸にしつつ、瀬戸一貴が葦月伊織や別の女性キャラクターと急接近し、エロティシズムにあふれたトラブルが巻き起こるという展開が散りばめられた。
(画像はI”s<アイズ> 1 (ジャンプコミックスDIGITAL) | 桂 正和 | Kindleストア | Amazonより)
一同:
(笑)
生田氏:
いや、それが幻想だってわからないんですよ(笑)。アメリカにいると日本の高校生活の情報なんて入ってこないから、漫画とかを通じて知ることになる。
それで、「俺もこんなスクールライフを過ごしてみたい!」という思いを抱いて、日本に帰った。
──ああ、こう、完全に海外オタクのパターンですね(笑)。
生田氏:
そうそう、まさにそれです。もう目を輝かせていましたね。
でも絶望するんです、漫画との違いに(笑)。
一同:
(笑)
生田氏:
もう青春できるだろうなと思って、日本の高校に行ってからバスケ部に入ったんですよ。バスケなんて知らないのに。
それが、なかなか強いバスケ部だったらしくて、しかも自分が日本語というか敬語を上手く喋れなくて、先輩から怒られまくったりと散々でしたね。
──夢見ていた日本の高校生活とはぜんぜん違った。
生田氏:
俺の青春はどこにいったと(笑)。
一同:
(爆笑)
 |
生田氏:
あと、当時アメリカではみんな「AOL Instant Messenger」【※】を使っていて、学校からスクールバスで帰るとすぐ散り散りになって、メッセージのやり取りをしながらオンラインゲームを始めるという感じでした。
※AOL Instant Messenger
アメリカの通信サービス会社であるAOLが配布していたインスタントメッセンジャー。通称AIM。現在のSNSやメッセージアプリが流行する以前、インターネットの黎明期である1997年からサービスが開始され、爆発的に普及した。2017年10月にサービスを終了している。
──アメリカではそれぞれの家が遠すぎて、日本よりも先にオンラインのチャットが流行したという説を聞いたことがありますね。だからXbox LIVEが広まったとか。
生田氏:
そうかもしれないですね。自分の周りでは流行っているというか、「使ってないといけない」というレベルでしたね。友だちとの連絡はもちろんです。
──それは日本でポケベルや携帯電話が若者たちの間で流行するという文脈のアメリカ版ですよね。
生田氏:
その代わり、モバイルでのコミュニケーションはアメリカではなかなか発展しなかった気がしますね。大陸が広大すぎて、基地局を全部すぐに作るわけにもいかない。
──はい、はい。
生田氏:
さっきの『I”s<アイズ>』じゃないですけど、「日本ではどうやら携帯電話でメールが打てるらしいぞ!」と聞きつけるんですよ。「なんだその未来は!?」って(笑)。
一同:
(笑)
生田氏:
まあそうやって、日本への憧れがどんどん高まっていったんですね。
 |
計算機を片手に「Blizzard青春時代」
──そういえば、『アンクラウン』のようなリアルタイムストラテジー系のゲームはプレイされてきたんですか?
生田氏:
やっぱり、アメリカに住んでいたころが僕の中のゲームの青春なので、Blizzard Entertainment【※】に育てられているんですよね。
※Blizzard Entertainment
1991年にアメリカ・カリフォルニア州に設立されたゲーム会社。
リアルタイムストラテジーゲーム『Warcraft』(1994)や『Starcraft』(1998)、ハック&スラッシュRPG『Diablo』(1997)などを世に送り出し、当時のPCゲームファンから圧倒的な支持を得た。その後はMMORPG『World of Warcraft』(2004)のほか、『Hearthstone』(2014)や『Overwatch』(2016)など現在も人気タイトルを輩出し続けている。
──ああ、なるほど。
生田氏:
一番最初にアメリカでハマったのが『Warcraft 2』でした。「Battle.net」【※】がリリースされたころですね。
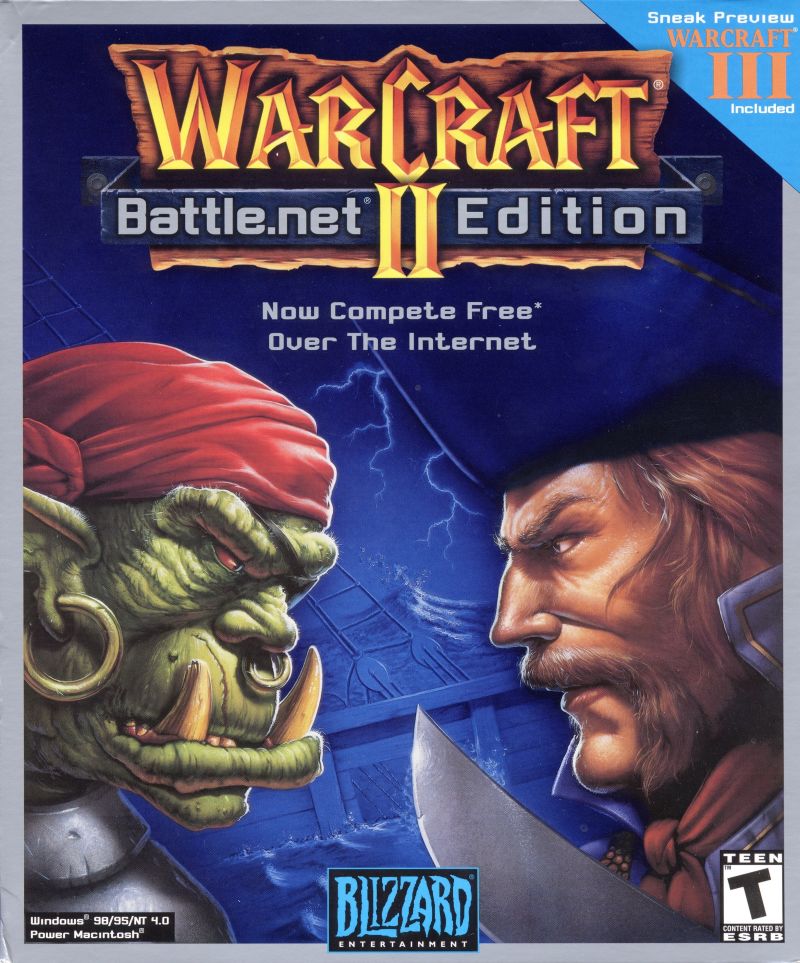
(画像はWarCraft II: Battle Chest for Windows (1999) – MobyGamesより。Screenshot via Mobygames)
「無料で対戦ゲームを遊べる世の中になった」という衝撃を、アメリカで一番初めに食らっちゃったんですね。向こうは電話回線がタダなんで、それもあいまってBattle.netは一気に普及したんですよ。
自分もその時期はゲームをひたすらやり込んでいて、なのでストラテジー系のゲームに関するオタク度はかなり高いですね。
──『Starcraft』とか『Warcraft』とか。
生田氏:
やりましたやりました、もちろんですよ、もうBlizzardファンですから(笑)。
そのあとに『Diablo 2』も遊びましたし、『Warcraft 3』と『Starcraft』、『Starcraft 2』とかも。
──ちなみに当時どれぐらいお強かったんでしょう?
生田氏:
めちゃくちゃ強かったですよ。『Warcraft 2』に関してはトップランカークラスだったと思います。
 |
──完全にBlizzardっ子ですね。そういったゲームは現地の方と遊んでいた?
生田氏:
そうです、はい。通っていた現地校にスクールカースト的なものがあって、いわゆるギーク層とかオタク層の中で遊んでいた感じですね。
──日本だと当時のBlizzard作品は、家庭用ゲームでもアーケードゲームでもない、超コアな層のものでしたよね。アメリカではどういう存在だったんですか?
生田氏:
わかりやすく言ってしまうなら『ドラゴンクエスト』みたいな感じでしたよ。
ゲーム遊んでいる人なら買ってるよね、遊んでるよねという感じでした。「Best Buy」みたいなアメリカの大型量販店に行くと、『Diablo』のパッケージだらけでした。
──親のパソコンを使って遊んだりしていた?
生田氏:
パソコンは数台ありましたね。アメリカだとそういう家庭は多かったと思うんですけど……。
そもそも、学校の宿題をやるためにも必要で、成果をフロッピーディスクで提出しろと言われるんですよね。持っていない人は図書館のパソコンを使ったりしていました。
あとパソコンではないですが、アメリカの授業では性能の高い計算機が配られるんです。僕らみたいなギーク連中は、方程式を入れたり、自分でプログラミングまでしたりしていましたね。
──それはおいくつぐらいのころに渡されるんですか?
生田氏:
たしか中学生だったと思います。中学生になるとアルジェブラ、要は方程式とか複雑な計算式が授業で出てくるんですね。
──代数学ですね。
生田氏:
それそれ、代数学ですね。基本的に計算はしなくてよくて、計算機に頼りなさいという文化なので(笑)。
その計算機が2万円ぐらいで買えるわけですが、みんなプログラミングで『インベーダー』とか『スネーク』みたいなささやかなゲームを作って、互いに遊ばせたりしていたんです。
 |
──アメリカでのゲームに救われた話ですとか、計算機で作ったゲームの話、あるいはBlizzardっ子だった過去が、原体験として生田さんに強く影響を与えているんでしょうね。
生田氏:
振り返ってみると、どこか自分の作ったゲームはアメリカの感性に近い要素やシステムが入っていることがあるんですよね。アメリカでの体験は、自分のゲーム作りと深く結びついてると思います。
負けん気にあふれた23歳の若きディレクター時代
──ゲーム業界を目指した理由は十二分にわかったのですが、そのあと具体的にどのような経緯で入られたんでしょうか?
生田氏:
アミューズメントメディア総合学院に通っていて、1年目の終わりにはもう就職が決まっていましたね。
自分が好きなゲームがさっきも言った『MOTHER 2』なんですが、面接練習に来ていた方がたまたま開発に関わっていた方で。ひたすら『MOTHER 2』のことを語っていたら、気に入ってくれたんだと思います。
──なるほど。ちなみに、どのような点が魅力だと語ったんですか?
生田氏:
一番覚えてるのは、ヒットポイントのドラムロールシステムですよね。
戦うと体力が減少して回るじゃないですか。
最初は「単なる演出かな?」としか思わないんですけど、徐々に徐々にヒットポイントが後半高くなっていくと、「ガンー!」という演出が入るあいだに回復すれば致死量のダメージを回避できるようになる。

(画像はMOTHER2 ギーグの逆襲 | Wii U | 任天堂より)
コマンドRPGなのに、いつのまにかアクションゲームみたいになっていて、味が変化していく料理というか。「ゲームだとこんなことができるんだ」と、えらく感銘を受けたんですね。
当時受けたあの衝撃も、ゲーム業界を志望した理由のひとつだと思います。ゲーム開発者としては、そこから一歩を歩みだした感じです。
──職種としてはプログラマーとかになるんですか?
生田氏:
基本的にはプランナーですね。ただ、僕がやってきたのは仕様書をまんべんなく書くとかいうよりも、バランス調整がメインでしたね。勝手に自分でバランスデザイナーとか呼んでいるんですけど。
あとは、この段階でアイテムが手に入って、こういうモンスターが出てくるので、こう倒すみたいな、いまで言うレベルデザインの仕事が多かったですね。
──当時は職種として名前がなかったのかもしれないですが、話だけ聞いていると完全にレベルデザイナーですね。
生田氏:
レベルデザイナー、それもRPGばかりやってきました(笑)。
いくつか会社を経て学びながら、次はディレクター職がやりたくて23歳か24歳のころにアソビモ【※】に入社したんです。
※アソビモ
2007年に設立された日本のオンラインゲーム開発・運営会社。
代表作は忍者をテーマにしたRPG『イザナギオンライン』や、近年ではスクウェア・エニックスと共同開発した『ファンタジーアース ジェネシス』など。「日本でナンバーワンのオンラインゲーム会社になる」を目標にモバイル向けのMMORPGを開発し続けている。
 |
──かなり若いですね。20代前半のディレクター。
生田氏:
自分が入社したころには60名くらいの規模に成長していて、会社としてはゲームを生産できる体制を求めたり、普及し始めたiPhoneを見て作り方を変えていくという感じでした。
──アソビモが本格的にゲーム開発に着手する前だったということですか?
生田氏:
開発はすでにがっつりやっていたんですが、仕様書で詰めずに開発を進めるようなモバイルゲームの黎明期というか、ワークフローとか関係なく感覚で作っていくような感じだったそうです。
入社した当初に開発中だった『セレスアルカ』(2010年)のチームに入ったんですけど、仕様書はまだ紙で、グリッド上にレベルデザインしていましたよね。

(画像は無料オンラインRPGセレスアルカ【Android/iOS対応】公式サイトより)
自分はさっき言った前職で仕様書の書き方とか、Excelの関数でシミュレーターを作るといったことを徹底的にやってきたので、そういう開発の仕方ができる人物として先陣を切っていたんじゃないかと思います。
──いやしかし、お若いですよね。アソビモ側は23歳の人がディレクターになりたいと言って受け入れてれたんですか?
生田氏:
それが、やらせてくれたんですよね。面接にいた代表の方がすごい器が大きかったんでしょうね(笑)。
──(笑)
生田氏:
いやあ、でも、もちろん若造が急に入ってきてディレクターって、上手くはいかないですよね。
当時は自分も負けん気が強くて生意気を言っていたので、かなり周りからバッシングを受けていました。
『イザナギオンライン』というタイトルのプレゼンテーションを、ほぼ変えずに僕は10回したんですね(笑)。

(画像はイザナギオンライン|iPhone対応スマートフォン向け忍者アクション×オンラインRPGより)
──ほぼ変えずに?
生田氏:
当時アソビモではリーダー会というのがあって、そこで半数以上がGOサインを出せば企画が通るというシステムでした。
リーダーは10人ぐらいいるんですけど、まあかなり嫌われていて、半数以上が手を挙げないどころか、「お前のことが嫌いだから手は挙げない」みたいなこと言われるんですよ。
──すさまじいアウェイですね。
生田氏:
「そっすかー」と言って、じゃあ「わかりました、いまいただいたご指摘を持ち帰ります」と返答するけど、次のリーダー会でほぼ同じ企画書を出す。
そんなことを2ヵ月ぐらいやっていました。「リーダーの時間もタダじゃないんだぞ」と言われたこともあります(笑)。
 |
──えっと、それは23歳とか24歳のときなんですよね。
生田氏:
はい。
──若いのにバチバチすぎませんか。
生田氏:
よく言われます。気が強すぎる。「俺が一番じゃー!」という気持ちですよね。
『イザナギオンライン』の開発が始まったあとも、順風満帆ではなくて、やっぱり24歳の若造が開発のディレクターやっているんで、炎上気味でしたよね。
周りは30歳のモデラーとか、40歳のエンジニアとかだったんですけど、それでも僕はガツガツ言っちゃうんで。
──そこまで気を吐きながら若い時期にディレクターを経験したのは貴重だと思います。
生田氏:
子どものころから自信家だったのもありますし、アメリカに住んでいた経験もあるかもしれないですね。アメリカは「お前の意見は違うのがわかっているから、聞かせろ」というディベートの文化なので。
日本だと「え、なんでそんなことを言うの」となって、話が終わっちゃう。
まあ当時のアソビモでは、言葉に出しすぎたこともあったので、いまでは反省している部分もありますね(笑)。
 |
「若い人にもディレクターを」から始まったネストピ
──いまのゲーム業界だと、なにか事件がない限りディレクターの席というのは空かないんですよね。会社が潰れそうになるとか、スタッフが離脱してしまうとか、そういう事件が起きて若い人がようやくディレクターとかプロデューサーになれる。
生田氏:
はい、まさにそうですね。
──でも、そこで受動的にじゃなくて、そういうディレクター職が受け入れられる場所に攻め入るという行動力は、年齢を考えるとすさまじいですよね。
生田氏:
もう次のフェーズも考えていて、それは「拡散させたい」というところなんですよね。
──拡散させたい?
生田氏:
要は僕がアソビモで体験したような、チャレンジできる場所をたくさん作るということですね。
いまはインディーデベロッパーの規模なんですが、将来的には10本ぐらいのラインを作って、それぞれにディレクターを置きたい。
ディレクターではなくて僕は監督と呼ぶ方が好きなんですけど、ともかくその人たちが有名になって羽ばたいていく場所として、「ネストピ」と名付けたんですね。
 |
──「ネストピ」というのはそういう意味が込められている?
生田氏:
ネスト(巣)とユートピア(理想郷)の造語ですね。
反対の意味合いを持つ言葉は「鳥かご」になると思うんですけど、イメージとしては羽ばたいて巣立っていける環境を作りたい。
ネストピは歩合制にしているのですが、チャレンジしてガンガン稼いでもらって、自分で起業して外に行ってもらいたい。
最終的な目標は、20年後とか30年後とかでいいので、ゲーム業界を見渡したときに「有名人の出身がみんなネストピだった」となってほしい(笑)。
──(笑)。
生田氏:
なんかあるじゃないですか。アニメ業界で庵野秀明さんが実はジブリ出身というような。
──トキワ荘みたいな感じですかね。
生田氏:
まさにそうですね。
ネストピがそういう思想のもとに設立されたのは、たぶん、ディレクターの席を取ることにかなり苦労した経験が原体験になってるんですね。
僕はコンソールでの開発を最初に経験したんですが、寿司職人じゃないですけど、ディレクターの席は20年は座れないぞと思ってしまったんです。
コンソール開発から新興のモバイル開発市場にあったアソビモへ行ったのも、それが理由のひとつなんですね。
 |
──アソビモから抜けてネストピを設立されたのは何歳くらいのときなんですか?
生田氏:
アソビモを抜けたあと、29歳くらいとのときにもう一度転職してるんですね。
そのころは『イザナギオンライン』の開発を3年、運営が2年目ぐらいに入っていたんですけど、ほかに経歴に書くようなタイトルの開発経験がなかったんですよ。1本目がそれなりにヒットしてくれて、それはよかったんですけど、2本目、3本目とさらに作っていきたいと思った。
そこで新しく設立されたばかりのGameBank【※】という会社があって、チャンスだと思って話を聞きに行ってみたんですね。

2017年9月に解散が発表され、同社の『強くてNEW GAME』の運営は、現在ネストピが引き継いでいる。
(画像は株式会社ネストピより)
──そこでもディレクター職を?
生田氏:
いえ、プロデューサー業でしたね。買い付けしたりとか、事業計画をちゃんと引いて株主を説得させるみたいなことをしたのは、そこが初めてでした。なんで、「あ、事業計画って書くんだ」みたいな(笑)。
いわゆるLTV(ライフタイムバリュー、顧客生涯価値)とか、そういう数字が見れるようになったのもそこでしたね。
──そこでプロデュース側に立ったのは?
生田氏:
実は自分の家系が起業家の家系でして、漠然と30歳ごろには起業したいと考えていたんですね。可能だったら、ゲーム開発が大好きだし、そのジャンルで起業したいと。
でも経歴がなくて名前も売れていない人間が、いきなり起業して上手くいくほどゲーム業界は甘くないと思っていたんですよね。
だからそこでディレクターは何歳までにやって、プロデューサーも経験して、ヒット作を何本か出したいという考えはずっとあったんです。
──若いころからそこまで考えているのはすごい。
生田氏:
いろいろと原体験があって、それをすぐに行動に移そうというのはあるかもしれないですね。
ほかにも、たとえば「クリエイターがクリエイターを評価すること」って、限界だと思っているんですよね。
 |
──ほうほう。
生田氏:
だからお客様から直接評価されるならわかる。
──いくつか大きな会社では人事評価が当たり前になっていますが、たしかにわかりますよね。たとえば部下が100人いて、いまから評価しますと言って、いったいなにがわかるのかという。
生田氏:
そうです、そうです。正直、好みや贔屓で評価しているパターンも多いですよ。
──あと、素行が良いことと、クリエイティブの能力が必ずしも直結していないことが多いですよね(笑)。クリエイティブな能力に振っている人ほど、会社で偉くなることは苦手だったりするわけですよ。
そうなると真面目に毎日通っているかどうかよりも、アウトプットがあるかどうかを重視した方がいいんじゃないかと。
生田氏:
そうなんですよ(笑)。なんか毎日遅刻してくるような奴のほうが、意外と面白いものを作ったりする。
みんな右向け右で同じ仕事をしていた時代から、個の力を発揮しないといけない時代が来ているって言われるじゃないですか。
そんな時代に、そういう評価制度は意味があるのかと。合ってないんじゃない、と違和感を常に抱いています。
だからネストピでは、歩合制を採用しているんですよね。それで業界に向けて「こういうやり方ってどう?」と問いかけているつもりです。
──歩合制ですか。
生田氏:
ネストピでは独身だと24万円、既婚だと30万円の給料を支払っていて、まず基本給だけで食べれる分を支給するようにしています。交通費とかも出して、社会保険完備です。
で、そこから先は歩合制になっていて、受託か自主制作かで変わるんですが、たとえば自主制作では10%の利益をチームに分配すると決めています。10人のチームだったら、ひとり1%の分配金を受け取る計算ですね。
月商1億円だとすると、毎月100万円が入る。
──ほかでは聞かないシステムですね。その割合は職種に関係なく均等なんですか?
生田氏:
いまのところは均等ですね。でも、プロデューサーやディレクターはちょっとだけ上乗せしようとかいう話はしています。
あとはやっぱり、独身者と既婚者では時間の使い方が違うせいか、独身の方がどうしても仕事時間が多くなる傾向にあって、労働時間で評価する軸も必要じゃないのかとか、いろいろ考えています。
 |
ゲーム開発で歩合制というのは、会社としてはまだまだ新しい試みだと思いますし、実際に誰にも教えてもらえていない。
自分たちで新しい試みに取り組んで、作り上げていっているところですね。
2軸で揺れる生田氏の根底にある「ゲームへの恩返し」
──生田さんとしては、自分のことはゲーム開発者と起業家のどちらだと思いますか?
生田氏:
あの、難しいんですけど、僕はもうゲームに本当に命を救われたと思っているという話をしましたよね。
──はい。
生田氏:。
なので、「ゲームを作ること」を取り上げられるのが、本当に嫌いなんですよ。2番目に働いていた会社はホワイトで、最初は残業するなと言われていたんですが、もう、怒っちゃって(笑)。
──(笑)
生田氏:
作らせろと(笑)。
一同:
(笑)
 |
生田氏:
だから、僕の中には軸が2つあるんですね。
起業家みたいに上手くいきたいなという自分と、クリエイターとして、作家性が高く、みんなじゃなくても誰かに「最高だね」と言ってもらえるような作品を作り上げたい。
この2つはいつもずっと、せめぎ合っているんです。
──それだと、開発側で良いゲームを作りつつ、ビジネス的にも大成功するようなビジョンが目標になるんですか?
生田氏:
実は開発者としては、万人に受けるタイトル、いわゆるもう世の中に社会現象で巻き起こすような規模のタイトルは意識していないんですね。それで莫大なキャッシュを得ようという目標もないんです。
ただただ、単純に自分が遊んで面白いと思えるものを作ってみたい。単純にゲームを遊んでいると、「こういう部分やだな」とかあるじゃないですか。
そういう部分をすべて自分用にカスタマイズしたゲームを作って、みんなに届けて「どう?面白いでしょ」と言うのが、開発者としての僕の夢です。
──逆にプロデューサーや起業家として成功したいという思いはある?
生田氏:
もちろんです。
でもゲーム会社のプロデューサーや社長として見ると、僕はみんなにチャンスを与えて、あとあと社長を辞めて開発に戻ると考えています。
 |
──それはみなさんにおっしゃっているんですか?社内で。
生田氏:
はい、言ってます言ってます(笑)。
──代表権を誰かに譲って自分はディレクターに回るってことですか?
生田氏:
そうですね。どうしようかなと悩んでいるんですけど、最終的なネストピの目標は、僕がクリエイターとして最高のものを作れる環境を構築するというのがミッションなんですよ。
そこまでいけば、気持ちよくゲームを作れるはずなので、開発側に回りたい。
もちろん、「お前いまさら開発に戻るのは邪魔だよ」と言われるかもしれないので、その場合は社外に出て新しく旗を立てるというのもありかもしれません。
──なんか、生田さんは自分ひとりでもなんとかしてやるんだという気概がありますよね。スタジオがもしなくなっても、自分で再建してやるとか。
生田氏:
ああ、まさにそのとおりですね。これは自分でもおかしいとわかってるんですが、どうしようもないほど前に突き進む性格なので(笑)。
──そんな生田さんが最終的に「ゲームの開発」に戻ってくるわけですね。
生田氏:
「作ってないと俺は死んじゃうんだ」ぐらいの感じなので。なんかたぶんもう呪われてますね、そこに関しては。
そこの情熱に関しては、「ゲームに救われた」という経験しかないという気がしますね。
けっきょく、ゲームに恩返ししないと、僕の人生は終わらない気がします。(了)
 |
生田氏の話を聞いて感じ入ったのは、まだゲーム業界人としては経験が浅いにも関わらず、ディレクターやプロデューサー、そしてゲーム会社の設立と、自身の次なるステップへ向けて次々に一歩を踏み出し続けている氏のすさまじい行動力、バイタリティの高さだ。
それは、すでに席が埋まり若者がトップに立ちにくい昨今のゲーム業界の窮屈さを跳ね除けるようで、ある種乱暴で荒々しい雰囲気さえまとっているようである。
しかし生田氏はただ乱暴にその道を進んでいるのではなく、ましてや単なる無知な自信家というわけでもない。
アメリカでゲームに命を救われた体験や、ディレクター時代に自身が問題だと感じた過去、それらの“原体験”を分析し、即座に「じゃあ自分ならどうするか?」と落とし込んでいくところに、他のリーダーとは異なる生田氏のパーソナリティを感じる。
『アンクラウン』を生み出した生田氏が次に向かうのは、ディレクターとして新たなゲームを作り出すのか、あるいはプロデューサーとしてさらにその巣たるネストピを拡大するのか。今後の活躍から目が離せそうにない。
【この記事を面白い!と思った方へ】
電ファミニコゲーマーでは独立に伴い、読者様からのご支援を募集しております。もしこの記事を気に入っていただき、「お金を払ってもいい」と思われましたら、ご支援いただけますと幸いです。ファンクラブ(世界征服大作戦)には興味がないけど、電ファミを応援したい(記事をもっと作ってほしい)と思っている方もぜひ。
頂いた支援金は電ファミの運営のために使用させていただきます。※クレジットカード / 銀行口座に対応
※クレジットカードにのみ対応
【あわせて読みたい】
思いがけず、お手軽リアルタイム戦術ゲーム「アンクラウン」にハマった話筆者は、いわゆるRTS(リアルタイムストラテジー)というジャンルのゲームを相当やり込んだ人間である。
最近、『アンクラウン』というスマートフォン向けのRTSをプレイしてみたところ、これが思いがけず、結構ハマってしまった。本作には、ライトでありながらも、確かな”本格派の味”がしたからである。
なので、せっかくならばと今回、簡単なレビューを書いてみたいと思った次第である。






































