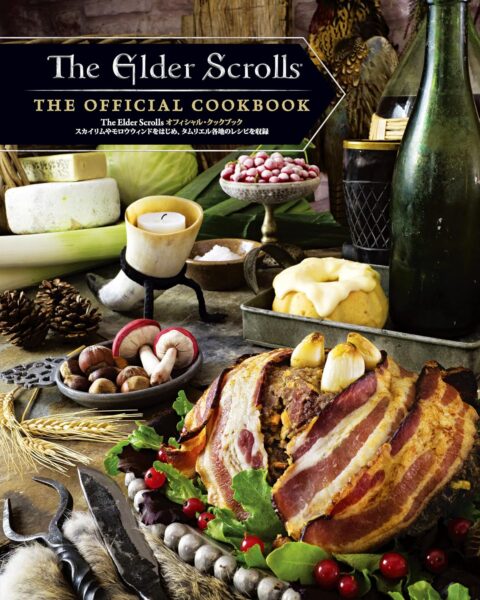手描きのアニメもCGアニメも、最終的に二次元の映像になるという意味では変わらない
──これまでのお仕事を伺っていると、みなさん最初から3DCGの世代ですよね。アニメ業界の外側から見ると、2Dの手描きのアニメが3DCGに切り替わっているようなイメージがあるんですけど、手描きのアニメーションの工程とぶつかるとか、違和感があるとか、そういう経験はあるのでしょうか?
柏倉氏:
「これから3Dに置き換わっていくぞ」と言われたりして、2Dの人がどんどん仕事がなくなっていくんじゃないか、みたいに思われて、お互いが少し気まずいみたいな空気は、一時期あった気はしますけど……でも結果、そうなってはいないですよね。
八木田氏:
なっていないですし、ならないです。日本のアニメの予算は低いので、手描きは絶対になくならないと思います。
田村氏:
3Dもなんだかんだで、1枚の絵でしっかり詰めないと、映像として映えないというのがあって。それを作ろうと思うと、手描きに近いことをやらなきゃいけないんです。
そういう意味では、やってることはあんまり変わらないですよ。
八木田氏:
だから最終的には手描きとあんまり変わらないかな。
柏倉氏:
もちろん道具はぜんぜん違うし、作る工程もぜんぜん違うんですけど、最終的にはどちらも二次元の絵なので。
その二次元の絵をどれだけ調整するかというと……どうだろう。僕は2Dのアニメーターでもアニメ演出家でもないから、なんとも言えないんですけど。
 |
──手描きのアニメーションで使われている誇張表現を3Dで再現する時に、パーツを専用で用意するみたいな話も含めて、2Dの技法を3Dに持ってくるという話がけっこうあったじゃないですか。でも最近は、それをあんまり聞かなくなった気がするんです。
柏倉氏:
たぶんそれは、誇張表現が決してアニメとイコールではないということに、みんな気づいたからじゃないかなと。
分かりやすい表現だとは思うんですよ、手前に来る手を大きくしてパースを調整したりとか。
でもそれは、映像のフィルム作りの本質ではないと思うんです。それで全部構成したからといって、すごく高級なフィルムが出来上がるかというと、イコールではないと思うので。
あとは、みんなやるようになったから言われなくなった、というのはあるのかなと。それ自体は別に、普通なことになりましたよね。
八木田氏:
そうですね。どこでもやってるなという感じはあるかなと。
田村氏:
あとは、モーションキャプチャーを多用するようになってきましたね。
昔は手つけが多くて、大規模にモーションキャプチャーを撮られてるのはポリゴン・ピクチュアズさんぐらいだったんですけど、最近はどこの会社さんもモーションキャプチャーをチャレンジされていて。そこがだいぶ違うなと思いました。
2Dのアニメーターの方に聞いたんですけど、キャプチャーで得られる情報量は「2Dアニメーターの側からするとうらやましい」と言われることがあって。新しい情報量の上げ方として、キャプチャーが使われ始めている印象はありますね。
──以前は、海外ではモーションキャプチャーで、日本は手つけで、みたいなイメージがありましたけど。
柏倉氏:
それはなんででしょうね。
八木田氏:
キャプチャーするお金がないか、知識がないかのどっちかだったんじゃないですか(笑)。ゲーム会社はモーションキャプチャーをけっこう使ってましたけど、アニメにはそういう文化がなかったような。
 |
──VTuberみたいなものも出てきて、キャプチャーのコスト自体が下がったんでしょうか。
八木田氏:
昔よりは安くなってますね。
柏倉氏:
モーションキャプチャーの手法が増えたというのもあると思います。安価な手法が増えたことで、それでいいという人はそれを使うようになったのかなと。
ちゃんと映像として残したいと思うものを作ろうとすると、それなりの精度が必要だとは思うんですけど。
──アニメーションの業界って、動きのコツといった基礎的な教養の部分は、カリキュラムがあるというよりは、先輩から教えてもらう文化の中でやっているのですか?
柏倉氏:
僕が知っている限りではそうですね。
八木田氏:
最初の研修で基本は教えてもらうんですけど、あとは現場に入って仕事で先輩に教えてもらうというのが、たぶんどこの会社でも変わらないんじゃないかという気がします。
柏倉氏:
ある程度マニュアル化しよう、というのがないわけではないんですけど。
 |
田村氏:
自分はマニュアルで覚えたクチなんですよ、じつは。
「アニメーション12の原則」という、ディズニーが提唱したアニメーションのノウハウがあるんですけど、ロマのフ比嘉さんからそちらを中心に教えていただいて。
最近だと若杉遼【※】さんっていう、海外でCGアニメーションをやられている方が、「海外ではこういう教え方をして、完全にマニュアル化できているんだ」というのを、日本にフィードバックしてくださっていて。
だから僕たちの世代のCGアニメーターだと、それを見ている人間がけっこう多いですね。

(画像はギャラリー | 映画『アングリーバード』 | オフィシャルサイト | ソニー・ピクチャーズより)
柏倉氏:
そういえば僕も、『楽園追放』が終わった後にその時のノウハウ集を作ったよね。「ここはシルエットがこうだから、表現がこういうふうに違うんだよ」みたいなのを。
八木田氏:
それがちゃんと後ろに共有されているかは怪しいんですよね。
柏倉氏:
されてないのかよ!(笑)
八木田氏:
グラフィニカの資料置き場には置いてあったのですが、新人さんの目に触れるかは謎ですね。大事なことが分かりやすく書かれてあるので、グラフィニカの新人さんにはぜひ、共有を!
柏倉氏:
けっこうがんばって作ったのに(笑)。
 |
──ゲーム業界でも、マニュアル化しようという話はたびたび出てくるんですけど、なかなか上手くいかないみたいですね。一方で、アジアをはじめとする海外のスタジオが台頭してくる際に、彼らはマニュアル化によって全体の水準を上げてくるんだけど、でもやっぱり最後のセンスオブワンダーが足りないよね、みたいな話しになって。
そこの部分のプラスアルファの差が、これからの5年、10年で埋まってしまうのか。それともなんらかの強みとして残るのかが、これからのポイントなのかなと思っているんです。
田村氏:
『スパイダーマン:スパイダーバース』【※】が出てきて、日本の手描きアニメーターは戦々恐々としているという話も聞きますけど。

(画像はスパイダーマン:スパイダーバース (吹替版) | Prime Videoより)
──『スパイダーバース』って、日本のアニメやゲームの業界人はみんな驚いたと思うんですよ。「これをやられたらオレたちって……」みたいな。でもそれって、まだあんまり大っぴらには語られていない気がするんですよね。
CGアニメもゲームも、制約の中でどう作るかを考える必要がある
──八木田さんと田村さんのお2人は2019年の秋に入社されたということは、VRだから大きく変わったというところに、まだそれほど直面しているわけではないのでしょうか?
八木田氏:
基本的にやってることは、アニメでもVRでも一緒なんですけど。
ただVRはフレームがなくて、従来のような画面レイアウトがないところで見るものになるので。普通のゲームと同じで360度どこから見ても大丈夫なものを用意して、あとは柏倉さんが最初に言っていた、視線をどう誘導するかを考えるという。
 |
柏倉氏:
僕らがつくるVRゲーム、例えば東京クロノスの制作には「演出」と呼ばれる工程があって、物語のシーンを実際に構築していくんですけど、そのシーンを作ることが、VRの意識誘導にはいちばん影響してくると思います。
今作っている『ALTDEUS』も、Oculus Quest【※】でプレイできるようにしているので、モバイル向けに調整するのが大変ですね。
従来の非VRゲームやPCでプレイできるVRのゲームよりもCGモデルなどの制約が大きいので。

(画像はOculus Quest: オールインワンVRヘッドセット | Oculusより)
八木田氏:
そうですね。スペックに対する処理負荷の調整は、けっこうハードルが高い気がしますね。
柏倉氏:
Oculus QuestはOclus Go【※】より性能がちょっとだけ良いんですけど、6DoFなど含めてやれることが増えたぶん、その性能をそっちに使っているので、ゲームに使える部分はOculus Goとそんなに変わらないと言われています。
制約的にはなかなかシンドイんですけど、でもOculusとしては、これでやっていきたいらしいので。Oculus Questでどう表現するかというのは、VRを作っている他の人たちもみんな、すごく頭を使うポイントだと思います。

(画像はOculus Go: スタンドアローンVRヘッドセット | Oculusより)
──『東京クロノス』は、性能的にスマホと大差ないOculus Goで、最大7人のキャラクターが一度に出てきて、かなりビックリしたんですけど。
柏倉氏:
あれは異常ですよね(笑)。
岸上氏:
『ALTDEUS』は『東京クロノス』よりも一度に出てくるキャラクターの数を絞っているぶん、もっと豪華にするという形にしています。
田村氏:
アニメを作っている時は制限がなかったので、なんでもやり放題という面があったんですけど、ゲームは制約の中でどういう表現をしていくかとか、プログラムの負担をかけずにやりたいことをどうやるのか、みたいなことがあって。
キャラクターがまばたきをする際に、CGアニメだと目が開く時に瞳孔がまぶたに押されてちょっと上がるっていう表現がよくされるんですけど、それをVRでプログラムをマジメに作ろうとすると、けっこう大変なんです。
 |
それで今は、目を閉じたモーフ(モーフィング)というモデルの状態の時点で、ちょっと目を下げている状態のものを仕込んだらいいんじゃないか、というのをやらせていただいていて。実際にどうなるのかは、通しの状態で見てみないと分からないんですけど、そういう工夫を考えたりするのは楽しいなと思います。
──谷口悟朗監督が『ID-0』【※】というCGアニメのTVシリーズを作られた時に、「CGアニメはモデルにいちばんコストがかかるので、登場するモデル=キャラクターの数と、舞台の数を決めてからストーリーを考えた」というお話をされていたんです。
それを聞いて、CGアニメは手描きのアニメとはまた違う制約の中で作られているんだな、と思ったのですが。

(画像はID-0 | Lantis web siteより)
田村氏:
CGアニメは基本、前提としてこれだけの人数を出せる、出せないと決めてから、脚本を練っていますね。
柏倉氏:
ノベルゲームの作り方っぽいですよね。ノベルゲームは背景の数、つまりシーンの数を出来るだけあらかじめ決めてしまって、基本的にはそこでできる範囲のシナリオを作っていますから。
 |
──ある意味、CGアニメはゲームの作り方に近いわけですか?
柏倉氏:
CGはやっぱりゲーム的な作り方というか、カッチリした計画的な作り方と相性がいいと思います。手描きのアニメがそうじゃない、というわけでも決してないとは思うんですけど。
──『HELLO WORLD』だと、CGモデルを作るまでもないモブキャラを手描きで追加したりといったこともあったようですが。
八木田氏:
そういうのもありましたけど、基本は汎用のモブキャラを作っておいて、それの色を変えたりとか、そういう形ですね。
田村氏:
『HELLO WORLD』のモブは、今までに見たCGアニメのモブの中で、ダントツに出来が良いなって思いましたよ。種類も動きも「これはモブにかけられる予算がどれだけあったんだろう?」って考えながら見てました。
八木田氏:
ホントっすか(笑)。
 |
柏倉氏:
芝居もすごく良かったから「このモデルってすごく良いんじゃないか」と、逆に勘違いするんですよね。
八木田氏:
モデルも、もちろんイイですよ。
柏倉氏:
これは持論ですが、アニメーションが良くないと、せっかく良いモデルでもクオリティが低く見えるんです。
逆にモデルが簡素でも、アニメーションが素晴らしいとモデルが良く見えたりもします。動かしやすい構造かどうかというのもありますが…。
『ルクソーJr.』【※】は、その点でとても尊敬しています。
※『ルクソーJr.』
1986年にピクサーが発表した、ジョン・ラセター監督による3DCG短編アニメ。大小2つの電気スタンドを親子に見立てて情感豊かに描き出し、当時のコンピュータ業界や映像業界を大いに驚かせた。ピクサー作品のロゴアニメーションは、この作品がモチーフになっている。
八木田氏:
そういう意味では、『HELLO WORLD』はバランスが良かったのかもしれないですね。
田村氏:
CGだと前提としてモデルがあるので、そこで仕上がりがある程度左右されちゃうのが、手描きのアニメとは違うと思いますね。
手描きだと作業者によって、出てくる絵がぜんぜん変わると思うんですけど。CGもかなり変わるんですけど、前提として作ったモデルに束縛される面が少なからずあるので。
もしくはめちゃくちゃ予算をかけて、モデルをたくさん作るとか。
八木田氏:
そうするとアニメーターが死んでしまうので(笑)。
 |
VRの演出では、受け手の視線ではなく「意識」を誘導する
──これまでの質問と被る部分もあるかと思いますが、VRのコンテンツを制作する際に、「これは今までのCGアニメではなかった」というのはどういうところだったんでしょうか。
柏倉氏:
今までになかったのは、やっぱり空間ですね。アニメーションの背景空間というのは、フレームの奥や手前や外とか、フレームありきのものになります。
それがVRだと、背景の中に自分が入っているという感覚ですから、それは今までにまったくなかったものなので。
個人的にVRで重要なのは、僕は背景だと思います。視野を占める範囲のほとんどは、キャラクターではなくて背景ですから。
「こんな世界ですよ」と提示するのはその背景空間なので。
岸上氏:
料理の味そのものは変わらないのに、すごくオシャレなレストランで食べると高いものを食べたような気になる、みたいな感じが、VRだと強いんですよね。
柏倉氏:
それはありますね。空間の雰囲気を比較的容易に持ってこれるというのは、VRの利点だと思います。そしてその雰囲気を持ってきた空間の中で、キャラクターが動き回ったり演技したりを、ユーザーは空間の中から体験できる。
 |
あと、これはVRだけじゃなくて、ARも含めたxRすべてに言えることかもしれませんが、視界の一部を編集することができる。つまり空間に自由に物を出したり消したり入れ替えたりできるんです。
場合によってはVRの中で、さらに何か拡張現実的なことをやったりもできますから。VRの中でVRをやるとか。そういうのも面白い。
──その「空間の概念」があることで、そこでの表現方法も、当然ながら変わってくると。
柏倉氏:
今まではフレームがあったので、フレームそのものを動かすことで観客の意識を誘導できたんです。たとえば飛んでいくハエをカメラが追いかけることで、意識を誘導できる。
でもVRの場合は、飛ぶハエを追って見せるためには、実際にプレイヤーを振り向かせなきゃいけない。そのためには、VRなりの「意識の誘導」が必要なんです。
さっきのハエの例で言うと、ハエがプーーンって自分の手前から横を通り過ぎて飛んでいったら、それにつられてプレイヤーが振り向くじゃないですか。そういうふうに、プレイヤーを振り向かせる道具としてハエを使うイメージです。
プレイヤーの真後ろにキャラクターを置いても気づいてもらえないので、ハエ自身もそうやって意識を誘導していった先に出すとか。
田村氏:
演出の手法でいちばん近いのは、ディズニーランドやUSJのアトラクションですね。あの演出は文法的に、VRとかなり近いと感じています。
アトラクションのノウハウと、アニメや映像のノウハウを組み合わせることができれば、また新しい体験が生まれるんじゃないかと思っています。
 |
柏倉氏:
VR演出って、なんだかマジックショーっぽいところがあると思います。プレイヤーの意識を一方に向けている間に、その反対側でギミックを仕込んでおいて、いざそっちを向くとビックリする、みたいに。
それもアトラクションの演出っぽいところですけど、発想としてはマジシャン的なものが求められるのかもしれないですね。
八木田氏:
自分がVRでいちばん驚いたのは、音でプレイヤーを誘導できるところですね。音響を立体的に作っているので、後ろで音がすると思わず振り向いちゃう。
普通の平面の映像だと、そういう演出はやりづらいので。
柏倉氏:
平面映像だと、音響効果で後ろから声が聞こえてはくるようにしても、しゃべっているのは画面の中にいる人物になってしまったり。
八木田氏:
カットが切り替わって、正面になっちゃうので。
柏倉氏:
それがVRだと、後ろを振り向いたら「いる!」になる。
今はまだ『レディ・プレイヤー1』【※】みたいに全身ボディスーツにはなっていないので(笑)、後ろから肩を叩かれるとか、そういうことはできないんですけど。でも後ろから声で呼んでもらえるという演出は、今でもできるので。

人々がVRオンラインゲームに熱狂する未来世界が舞台になっており、ガンダムやゴジラといった日本のキャラクターからATARIのゲームソフトまで、世界中のポップカルチャーが大量登場していることが話題となった。作中でのVRオンラインゲームは、HMDだけでなくボディスーツを装着して体感することも可能なフルダイブ形式になっている。
(画像は映画『レディ・プレイヤー1』PHOTO GALLERYより)
CGなら世界の大きさを自由に変えることも、視覚の一部を書き換えることもできる
──VRで作品を制作されるにあたっては、そのスタートというのは「何か新しいことをやらなきゃ」みたいな意識からだったのでしょうか。
柏倉氏:
新しいことをやらなきゃというか、そもそもVRで表現する時には何が効果的なのか、それを探るところからでしたね。まずそれが分からないので。
たとえば『東京クロノス』のオープニングムービーは、最初は平面の映像から始まるんです。大手のメーカーから出ているVRゲームでも、オープニングムービーは平面の映像になっているものが、けっこうあるんですよ。でも『東京クロノス』のオープニングでは、ムービーの途中でバンッ! と立体に変わるんです。
今まではフレームで仕切られた平面だったものが、目の前でフレームのない立体に変わる。その差を見せてあげることで、「平面と立体の境界線がなくなるとはこういうことです」ということを示そうとしたんです。これって一発芸なんですけどね。
何が効果的なのかは、なかなか難しいです。たとえば「ガチ恋距離」っていうのがあるんです。マジで恋するような距離感。
──パーソナルスペース(対人距離)と呼ばれる自分の至近距離に、他人が侵入してくることでドキドキするというヤツですね。
 |
柏倉氏:
そうです。あのキャラにここに来られちゃったら緊張する! という距離。
でも、それも使いすぎると慣れてしまって、「ガチ恋距離だった何か」になっちゃうんですよ。そんなふうに、何が効果的なのかをちょっとずつ検証したりして、考えていますね。
──そういったVRならではの表現は、『東京クロノス』で具体的に言うと、他にどんなものがありますか?
八木田氏:
モデルを大きくしていることですかね。
柏倉氏:
先ほどの、xRでは視界の一部を編集できるという話にもつながるんですけど。『東京クロノス』は世界がすべてCGで構成されているので、じつは世界の中にあるキャラクターや背景のサイズを、いくらでも自由にいじれるんです。
『東京クロノス』の場合は、世界もキャラクターも全部、プレイヤーに対して3.5倍の大きさにしてあります。それでキャラクターもちょっと望遠に見えるようにしたりとか。
なぜかというと、実はVR酔いの防止のためなんです。キャラクターも世界も大きくすることで、メッセージのテキストを遠くに置いて、文字を読む際に酔いにくくしています。
あとは、キャラクターが近くにいて立体感が続きすぎると、前後の動きで酔っちゃう人もいるので。
リアルな大きさにすれば、たしかにリアリティは増していくのかもしれないですけれども。でも一方で、世界の大きさを自由に変えたりできるというのはCGの魅力だし、VRにもその魅力を応用できると思うんです。
──ではVRではこういうことをやると通常のゲームや映像とは一段違うものになる、というのはありますか? VRならではのちょっとした工夫というか。
柏倉氏:
『東京クロノス』の時は、キャラクターがどこを見ているのかというのをかなり意識してやっていました。
 |
岸上氏:
キャラクターが全員、自分の目を見てくるというのを仕込んでいるじゃないですか。あれだけでもぜんぜん違いますよね。
柏倉氏:
他人から自分を見られるのって、すごくプレッシャーを感じるんですよ。
僕らは今、こうやって斜めになって話していますけど、これが急に真正面を向いて話したら、それだけで「おっ!」って思うじゃないですか。
Epic Gamesが作った『Robo Recall』っていうVRゲームの序盤で、ロボットが暴走して、周りのロボットたちが一斉にこっちを見るんです。僕はアレがすごく怖くて、最初は『Robo Recall』ができなかったんですけど(笑)。

あと、ユーザーが自分の頭を動かす動きは、それだけですごく刺激になるので、それを目線や音で上手く誘導して、リズミカルに頭を動かしてもらうことが、けっこう大事だと思います。
映画とかを見ていても、盛り上がっているシーンだと視聴者は前のめりになっていて、リラックスするシーンだと視聴者も後ろにもたれてゆったりしている。
それでまた盛り上がるシーンになると前のめりになるっていう、その繰り返しなんですね。極端な例ではありますが。これで身体のリズムを引き出して、体感として楽しんでもらう。
それがVRだと、視線を下から上に向かって動かすだけでもちょっと気持ちいいとか、視線を上から下に向けるだけで気持ちがちょっと落ち込むとか、そういうことも演出として使うことができると思います。