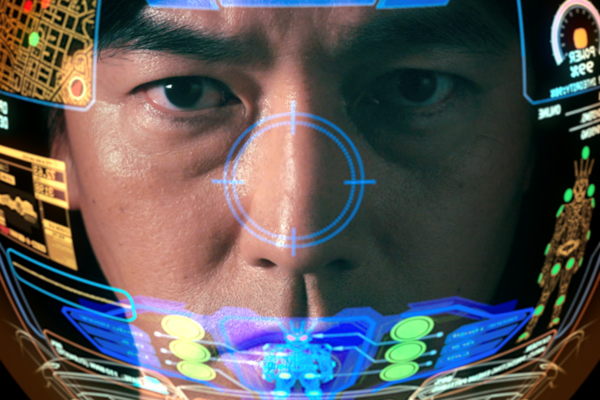このところ、ゲームセンターを取り巻く空気が重苦しいものとなっている。新宿西口の「GAME SPOT 21」をはじめ、全国各地の名だたるゲームセンターの閉店が相次ぐなか、セガ エンタテインメントの株式譲渡によって、セガグループがゲームセンターの直営事業からの撤退を発表。さらにバンダイナムコも、北米におけるアミューズメント施設事業からの撤退を発表した。ゲームを巡る環境の変化に加えて、長期に渡るコロナ禍がゲームセンターの経営を圧迫しており、既存のゲームセンターはどこも苦戦している状況だ。
そんななか、セガグループ設立60周年プロジェクトのひとつとして、2020年12月に「アストロシティミニ」が発売された。セガのゲームセンターに並んでいたアーケード筐体「アストロシティ」をミニチュア化したハードの中に、1980〜90年代のアーケードを彩った、セガの名作ゲーム37作品が収録されている。その中には、社会現象となる一大ブームを巻き起こした3D格闘ゲームシリーズ『バーチャファイター』(以下、『バーチャ』)の第1作も含まれている。

そこで今回は、「アストロシティミニ」に収録されたゲームが実際に稼働していた1980〜90年代のゲームセンターに、プレイヤーとして、あるいは開発者としてさまざまな思いを持つ3名のゲームクリエイターに集まっていただいて、“あのころ”のゲームセンターについて存分に語り合ってもらった。
バンダイナムコエンターテインメントの原田勝弘氏は、『バーチャファイター』と並ぶ3D対戦格闘ゲーム『鉄拳』シリーズのプロデューサーとして、ゲームセンターを大いに盛り上げてきた人物だ。

しかしそれだけでなく原田氏は、かつて西新宿にあった伝説のゲームセンター「プレイマックス」で、ナムコが送り込んだ刺客ならぬ名物店員として大活躍していた経歴の持ち主でもある。今回の企画の語り手として、最もふさわしい人物だと言えるだろう。
そして、アークシステムワークスで『BLAZBLUE』シリーズなどを手がける森利道氏。

ゲームクリエイターとしては2000年代以降のアーケードゲームを盛り上げてきた人物だが、一方で1990年代はプレイヤーとして、新宿や池袋のゲームセンターで時間を過ごしてきたという。今回は開発者としてだけでなく、当時のプレイヤーとしての実感にもとづくさまざまな話題を聞くことができた。
最後にもうひとり、今回の企画に欠かすことができない人物と言えば、『バーチャファイター』の生みの親である鈴木裕氏だ。

1990年代にはすでに第一線のゲームクリエイターだった鈴木氏は、どのような思いで当時のゲームセンターを見ていたのか。今回の鼎談では、鈴木氏の生み出した『バーチャファイター』シリーズが、さまざまな意味でゲームセンターという空間のあり方を変革した非常に大きな存在だったことが、改めて確認できるはずだ。
今回の顔ぶれから、話題は格闘ゲームが中心となっている。かつての“あのころ”を知っている世代の方はもちろんのこと、当時のことをよく知らない若い読者のみなさんにも、かつてのゲームセンターがどのような空間で、そこから今のゲームに至るどんなものが生み出されたのか、ぜひ知ってほしい。
 |
それまでゲーセンで見たことのない大人たちが『バーチャファイター』で対戦を始めた
──鈴木裕さんと森さんは、今日が初対面とのことですが?
 |
鈴木氏:
はじめましてですね。
森氏:
そうなんです。ゲームはさんざんやらせてもらいましたが。『鉄拳』も『バーチャ』も両方やってるんですけど、いちばん遊んでいたのは『バーチャファイター2』ですね。『バーチャ』が出たのは、ちょうど『鉄拳』が出たときと同じぐらいじゃないですか。なので友達と「どっちをやるか」みたいな感じで揉めてましたね。
原田氏:
セガとナムコがバチバチだったころですね。
──原田さんは以前、電ファミの記事で鈴木裕さんと対談されていまして、その時のお話だと、『バーチャファイター』が出た時にはすでに、ゲーム業界で働かれていたそうですね。
原田氏:
僕がちょうどナムコに入ったぐらいのときですね。
──そのころ、森さんは?
森氏:
僕は業界に入る2、3年前ですね。まだ19〜20歳ぐらいなので。
──これはいろんなところで語られているかもしれませんが、『バーチャファイター』が世に出たときの衝撃は、どういったものだったのでしょうか?

原田氏:
僕はプログラマーではないですけど、「この速さで動くんだ」という謎の感想を持った記憶があります(笑)。当時はポリゴンってなぜか、ゆっくり動くというイメージがあったので、それがあの速さで動くことに衝撃を受けました。それと同時に「これからはどんなゲームもポリゴンになる時代が来る」と感じましたね。全部これになるだろうと。
森氏:
『バーチャファイター』が出た時期って、SNKさんの格闘ゲームや『スーパーストリートファイター2』が流行っていたじゃないですか。そっちはコマンド入力式だったのに、『バーチャ』は→→PKとか、ボタン3つを押すタイミングや流れで技を出すので、ぶっちゃけ言うと最初はやりづらかったですよ。ずっとカプコンさんのゲームで慣れてきていたので。
ところが、ゲームは好きだけどゲームセンターで格闘ゲームをやらなかった友達が、何人も『バーチャ』にハマっていて。それと同じように、僕らがそれまでゲームセンターで見かけたことのない層の人たちを、すごく見るようになったんです。
原田氏:
それはすごくわかります。まったくゲームをやらないタイプの友達が、『バーチャ』だけを遊びにゲームセンターへ来るようになる様を見ていたので。ヘンな言い方ですけど、一般層を急に呼び込んだように見えましたよね。
森氏:
僕は当時19歳とか20歳ぐらいだったので、それまでは同じぐらいの歳の連中がゲームセンターに集まっていたところに、突然スーツを着た人たちがやってきて、『バーチャ』をやっているんですよ。
原田氏:
そうそう。それは『アウトラン』のときも同じなんですよね。『アウトラン』が出たころは僕も学生だったんですけど、そのときも僕が行っていたゲームセンターに、それまでは見たことのない大人たちが急にやってくるようになったんです。その様子を見ていたので、『バーチャ』のときも同じ雰囲気を感じましたね。

森氏:
その流れで、テレビでも取り上げられるようになったじゃないですか。『バーチャ2』とかになってからは。『トゥナイト2』【※】とかで大きく扱われて。
※トゥナイト2:
1994年から2002年までテレビ朝日系列局で深夜に放送されていた情報バラエティ番組。たまごっちやプレイステーション2の特集を組むなど、ゲーム情報をしっかりと取り扱うことで知られていた。
──鈴木裕さんとしては、そのあたりはしてやったりという感じだったんでしょうか?
鈴木氏:
そのころのゲームでは、カプコンさんが絵が上手なのに定評があって、『ストリートファイターII』みたいに素晴らしい描き込みのゲームが出ていて。それに対してこっちは、『バーチャ』のころはテクスチャもなくて、眉毛まで全部ポリゴンで描かなくちゃいけなかったんです。背景のほうはベタ絵で若干、絵は描けましたけど。だからいま見ると、パイの顔なんて相当ヒドいものでしたね(笑)。
原田氏:
いま思えば、「積み木」みたいな感じでしたよね(笑)。
鈴木氏:
過去は美化されるもので、「意外といいな」とか思っていたんですけど、つい最近、実物を見てビックリして(笑)。だから欠点もスゴイですよね。これはできない、あれもできないっていうマイナスポイントだらけで。できるのは唯一、頂点計算をして正確な位置に正確な3Dを表示することだけで。
みなさんの前に出す前に、社内でテストしたんです。セガ社内の廊下に、昼休みの2時間ほど筐体を出しておいて。開発だけで遊んでいても一般の人の反応がわからないから、総務の人とかに「遊んでみてくださいよ」って声をかけて、遊んでいる様子を後ろから見ていて。
森氏:
週刊少年マガジンで読みました。『バーチャファイターを創った男達』【※】で(笑)。
※バーチャファイターを創った男達:
『週刊少年マガジン』に不定期掲載された、ゲーム開発の現場を描いたドキュメント漫画『ゲームクリエイター列伝』に収録されている『バーチャファイター』編エピソードタイトル。のちに単行本化。
鈴木氏:
『巨人の星』の明子お姉さんみたいに柱の陰から見ていて(笑)。それで小形さん(※当時のセガAM営業本部長である小形武徳氏)に「これ、何台売ってくれるんですか?」と聞いたら、「2000台」って言われたのを、いまでも覚えてます。
原田氏:
当時の2000台ってメッチャ少ないですよね。あり得ない。採算がとれないですよ。
鈴木氏:
でも、遊んでくれる人が「イテッ!」って言ったんですよ。ゲームの中で自分のキャラクターが殴られたのを見て、思わず声が出たんです。それで「何かあるな」と思って、ロケテストに出してみたんです。ロケテストに出してみるまではいつも、受け入れられるかどうかはぜんぜんわからないですよね。だから『バーチャファイター』に関しても、「してやったり」という感じはなかったです。いつも陰のほうから見ていて、あとでこっそり感想を聞くんですよ。それでまぁ、なんとかなって良かったなという感じていました。
“バーチャル”のファイターだから、殴られると金属音がする
森氏:
『バーチャファイター』も『鉄拳』もそうですけど、音が印象的だったんですよね。『バーチャ』って殴ったときに「ゴンッ!」っていう音がするじゃないですか。
原田氏:
謎の金属音ね(笑)。『バーチャ』はそもそも、コイン投入時を入れるときの音【※】がキャッチーでしたから。あの音がゲーセン中に響いていて、本当に何年間も年中聞いていましたよ。
※コイン投入時の音:
アーケードゲームの特徴のひとつである、コイン投入と同時に流れるインサート音。これはアストロシティミニでも再現されている。どのような音が流れるのかは、動画1分23秒あたりを参考に。
鈴木氏:
1991年ぐらいに「バーチャル・リアリティ」というのが1回、流行ったんですよね。それでタイトルは『バーチャル・ファイター』でいいかなと。『ストリートファイター』が流行っていたので、こっちはバーチャルだから『バーチャル・ファイター』にしようと。ところがすでに登録商標を取られていて。それで「VIRTUAL」から「L」を取って「バーチャ」でいいや、って(笑)。バーチャルのファイターだから、人間じゃないから、効果音もちょっと金属的だったりするんです。
原田氏:
でも、あの音が逆に良かったですよ。腹に響く感じで。
森氏:
そうですね。「ゴン!」って。
鈴木氏:
だから個性はね、つけたくなくてもついちゃうんでしょうね。ポリゴンしか出ないものだから。
森氏:
これはぜひ聞きたかったんですが、『バーチャファイター』以前の格闘ゲームには、リングアウトという概念がなかったんですよ。そこに初めてリングアウトの概念を入れたのは、なぜなんですか? 僕はそれがすごく知りたくて。僕が逆の立場だったら絶対に入れないと思うんですけど、でもあれがひとつの面白さになったじゃないですか。
原田氏:
僕らナムコの中では、お客さんの回転を良くしてインカムを上げるために入れたんじゃないか、という噂になっていましたね。
鈴木氏:
僕は覚えてないですねぇ。壁にぶつかってキャラクターの体が潜るのがイヤだったのか、処理が重くなっちゃうのか……。
原田氏:
なるほど、そういったテクニカルな理由だったんでしょうか。
鈴木氏:
もちろんインカムを上げること自体は、当初から狙って作ってはいるんです。リングアウトがあると、プレイ時間に応じてリングがだんだん小さくなっていくとか、いろんなことができますので。
原田氏:
いまのバトルロイヤルゲームみたいな感じですね。
──プレイヤーとしては、自分の体力が減っていても相手をリングアウトさせれば勝てるという、一発逆転のドラマ性が生まれましたよね。

原田氏:
すごく勝ってるのに落とされて終わるっていう(笑)。
森氏:
ぶっちゃけリングアウトのせいで、ラウとカゲに対する殺意がどんどん上がっていきましたよ(笑)。
鈴木氏:
ロケテストに出した時の平均プレイ時間が、1分40秒ぐらいじゃなかったかな。
原田氏:
相当短いですね、それは。
鈴木氏:
ただそれでも、満足度があればなんとかなりますので。
原田氏:
『バーチャ』の稼働当初は、1プレイ200円の店も多かったですよね。キャビネット系の筐体では『バーチャ』が初めて、稼働当初は200円を取れるという不思議な価値を生み出したんですよ。
鈴木氏:
「(1プレイを)いくらにしますか?」と聞かれて、あまり何も考えないで「200円」と言った覚えがありますね(笑)。インカム狙いでいこうとは思っていましたから。
原田氏:
それでもサラリーマンがこぞって、200円を普通に出していましたから。大人が普通に遊んでいる、大学生と大人が並んでいる印象がすごくありましたね。
──『バーチャ』はアストロ筐体だけじゃなくて、大型のメガロ筐体にも入っていたじゃないですか。メガロ筐体だと2人が横に並んで対戦する形になるんですけど、その形はいまだと、たぶん入りづらいと思うんですよ。まったく知らない人の真横に座って対戦するわけですから。でも当時はみんな当たり前のように、コインを入れて「お願いします」と言って対戦を始めて。
本社受付前にスーパーメガロ筐体の『バーチャファイター』が置いてあった👊 pic.twitter.com/ZOMAfQykdC
— セガ公式アカウント🦔 (@SEGA_OFFICIAL) September 18, 2020
原田氏:
あれは大勢の人数が店内にいて、そこにたかっていたからできるんですよ。あんまり流行っていなくて、ひとりしかいないところに「いいですか?」は、さすがに行きにくいですけど、あのときはギャラリーも含めて店内に人がブワーッといたので。
恥ずかしいも何も、そうやって入らないと遊べないですから。それで自然と1P側の列と2P側の列みたいになっていて。だから注目度が高かったからこそ、やれていたみたいなところはあると思うんです。
鈴木氏:
珍しいというのもあったと思うんですよ。それまではああいうのがなかったわけですから。だからいま考えてみれば、パイもあれで良かったんでしょうね(笑)。
「不良のたまり場」という過去のゲーセンのイメージを変えたかった
──先ほど、『バーチャファイター』がきっかけになってサラリーマンがゲームセンターにやってくるようになったというお話がありましたが、『バーチャ』以前のゲームセンターはどんな場所でしたか?
鈴木氏:
自分が高校生のころだと、だいぶ古い話になっちゃうんですけど、テーブルタイプのゲームで、地下に店があって薄暗い感じで。それで店内では、学生がタバコを吸っていて……。だからお父さん、お母さんのゲームセンターに対する印象は良くなかったんです。不良のたまり場だし、お金も使っちゃうし。そのイメージがずっとついていたんですよ。
原田氏:
裕さんのころはたぶん「ゲームセンター」じゃなくて、「インベーダーハウス」みたいな呼ばれ方ですよね(笑)。
鈴木氏:
そう、喫茶店ですね。
原田氏:
僕はたまたま親戚が喫茶店をやっていて。ゲームと初めて出会ったのは、その喫茶店だったんです。喫茶店の中のテーブル筐体で『スペースインベーダー』や『ブロックくずし』が置いてあって。
鈴木氏:
『ヘッドオン』とか。
原田氏:
そうです、そうです。それでやっぱり店の中が暗くて、タバコの煙がもうもうとしている中に重低音だけが響く、みたいな。そういうところからのスタートですよね。
 |
鈴木氏:
モノクロのモニターに色のついたセロハンのテープを貼って「カラーだ」って言い張ったりして(笑)。
原田氏:
そこから時間が経って、シューティングゲームの『R-TYPE』が出たころでさえ、まだテーブル筐体なので。『グラディウス』の『II』とか『III』とかでもまだテーブルですよね。
森氏:
そうですね。
原田氏:
あのころのゲームセンターにいたのは、いつも決まって学校帰りに寄る学生なんだけど、ちょっと不良寄りの子か、ゲームを熱心にやるグループっていう不思議な取り合わせで。それとサラリーマンの常連ですよね。話したことはないんだけど「いつも○時に来ている人だ」とか、「今日はあの人が来てないな」とかわかるぐらいのコミュニティ。70年代後半から80年代いっぱいぐらいまでは、そういうイメージが強かったですね。
鈴木氏:
どうしても、薄暗くて不良のたまり場で……というイメージがありましたよね。僕はセガに入ってから『ハングオン』を作ったじゃないですか。あれって筐体が大きいから、地下には置けないわけで。そういうところでゲームセンターのアングラな雰囲気を変えたいな、という思いはありましたね。ちょうど『ハングオン』あたりから、自分がプレイしている様子を他の人に見せる、他の人から見られる、みたいな楽しみ方も出始めましたし。

──アップライト筐体が出てきたおかげで、テーブル筐体とは違ってモニターを立てることで照明の反射がなくなり、店内の照明を明るくすることができたんですよね。だから『バーチャ』が出てきたころに、そういう明るい店内のイメージが作られていく一方で、客層も変わっていったということですか。
原田氏:
その手前にまず、1985年に風営法の改正【※】があったんですよ。それによって、床から一定の高さでの照度がこれぐらいないといけない、という基準がでたんです。そのために店内が明るくなって、通路も広くなったんです。あとは24時間営業のゲームセンターがなくなって。昔のゲームセンターは夜中だろうと早朝だろうと、何時に行っても開いているイメージだったんですけどね。
※風営法の改正:
1985年2月に風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律(風営法)が改正され、ゲームセンターも施行対象となった。
──昔は地方の国道沿いとかに、カップラーメンの自販機と一緒にテーブル筐体が置かれている、24時間無人のゲームセンターなんかもありましたよね。
森氏:
新宿なんて基本的に24時間営業でしたから。
原田氏:
新宿はまたちょっと異世界でしたけどね。風営法の対象機種があるエリアだけシャッターを閉めると、それ以外の筐体はなぜか24時間稼働できるとか、不思議な営業形態になっていたので(笑)。
ただ、別の対談の時にも話が出ましたけど、裕さんの作るゲームはそもそも、ゲームを見てゲームを作っているわけじゃなくて、『アウトラン』だったら「カッコイイ車を運転したらカッコイイじゃん」とか、より一般的な価値観をゲームの中で体現するということをやっていたので。だからこそゲーマーだけじゃなくて、普通のサラリーマンだとか、ゲーセンの前を歩いている人たちが「何これ? カッコイイ!」「なんかスゴイ!」と興味を持つんです。
そういう意味で、裕さんの作る体感ゲームは層が広かったですよね。ずっとゲームセンターにいて「新作だ」と遊ぶ人だけじゃなくて、外を歩いていて「なんかスゲェのがある」と店内に入ってくる人がいる、振れ幅の広さがありましたから。
 |
──そういう意味では「ゲームが上手いことがカッコイイ」という価値観が、ゲームセンターの閉じたコミュニティの中にはもともとあったのかもしれないですけれど、そこに格闘ゲームが出てきたことで、よりオープンになっていったというか。「あのサラリーマン、すげぇ強い」みたいな。
原田氏:
それはやっぱり、『バーチャファイター』が初の現象ですよ。それまではゲームが上手くて褒められていたのは、高橋名人だけですから(笑)。
森氏:
毛利名人もいたじゃないですか(笑)。
原田氏:
橋本名人もね(笑)。日本に4〜5人しかいない「名人」とつく人たち以外は、誰も認められていなかったですから。
鈴木氏:
新宿ジャッキーが100人抜いた【※】とかね。
※新宿ジャッキーが100人抜いた
新宿ジャッキー氏本人のインタビューによると、実際には98連勝とのこと。
『バーチャ』の「鉄人」がTV番組で「カッコイイ」ともて囃されるように
森氏:
『バーチャ2』の時に、新宿ジャッキーさんやブンブン丸くんがTVの深夜番組にバンバン出ていたじゃないですか。『トゥナイト2』だとか。あれで僕は「『バーチャ』が強いとモテるんだ!」というイメージになったんですよ(笑)。
原田氏:
そうですよ。あの時代はまさに、『バーチャ』の強い人がモテて周りからひがみ・やっかみを受けた時代ですから。
森氏:
ちょっと羨ましかったですからね。
原田氏:
言ってみれば、いまのeスポーツ選手のもて囃され方の、いちばん最初の世代というか。このあいだもブンブン丸と話をしていたんですけど、「ちょっと時代とタイミングが違ったよね」と。あの時代はパイオニア過ぎて、ちょっと変わった人にしか見られなかったかもしれないけど、いまならもっと食えていたよねと。でも彼は当時、モテてましたよ。
森氏:
あれはモテるでしょう。『バーチャ2』が強い人はやたらとモテて、超羨ましかったですからね(笑)。
──彼らはいまでも「鉄人」と呼ばれているわけですから。
原田氏:
レジェンドになっちゃってますからね。
──『バーチャファイター2』のときに、上手いプレイヤーに対して公式に「鉄人」【※】という称号を与えたじゃないですか。
※「鉄人」
この称号を考えたのは、こちらの記事によると、当時のセガAM2研で広報を担当していた黒川文雄氏。また「鉄人」の称号が授与されたのは、こちらの記事によると、1995年に開催された『バーチャファイター2』全国大会マキシマムバトルの前夜祭でのこと。
原田氏:
あの取り組みは、じつはいろいろ画期的だったんですよ。日本の風営法とかいろんな法律で、ゲームの技術の対価として何かを得るとかいうことが、けっこう微妙になるんです。賞状ぐらいだったらいいんですけど、じゃあ交通費は出していいのか? 宿泊費は出していいのか? となると、いろいろなことがグレーでわからない。
でもセガさんは思いきって、全国津々浦々でそういうことを積極的にサポートし始めたんです。当時のナムコでは慎重論しかなくて。「でもセガはやってんじゃん!」って、僕はずっと言ってましたから(笑)。だからセガさんは、いろんな意味で殻を破っていましたよね。
──ゲームセンターは当時の最先端のカルチャーだったから、『トゥナイト』から『トゥナイト2』になったときに、とり上げるようになったという話を聞いたことがあります。
原田氏:
あの当時はテレビ関係者やマスコミの方にも、『バーチャ』好きが多かったんですよ。当時の新宿のゲーセンで、ホストの人がすごく『バーチャ』をやっていたり。だからもう、あらゆる業界で流行っていたんです。だから、何か新しいことをやろうというときに『バーチャ』というのは、すぐ思いつく状況ではあったと思うんですよ。逆にそうじゃなかったら、テレビであんな扱いは受けないはずで。番組を作っている側の人が好きだったというのは、大きかったと思います。
──テレビドラマの『GTO』にブンブン丸が出演して、放送されたら手の部分しか映ってなかった、というエピソードもありました(笑)。
森氏:
当時はテレビの特別さが、いまとは違いましたよね。
原田氏:
そうですね。あのころはテレビがいちばん強いメディアでしたから。「ゲームをやるだけでテレビに出られる」なんて、ホントに高橋名人以来の衝撃ですよ。
森氏:
しかも高橋名人や毛利名人って、なんだかんだ言ってもゲームメーカーの社員じゃないですか。ブンブン丸くんも新宿ジャッキーさんも、当時は本当に普通の人ですよ。
原田氏:
新宿のスポット21で、夕方の5時ぐらいに新宿ジャッキーとブンブン丸が対戦を始めたら、店の中に人が入れなかったからね。入口の看板の前まで行列ができちゃって。列が長すぎて、並んでいる人もこれが対戦列なのか観客列なのか、よく分わらないっていう(笑)。
もう芸能人が来たような状態なんですよ。みんなひと目見たいっていう。スゴかったですよ。ブンブン丸が50連勝ぐらいしていると、露骨にトイレに行きたそうで可哀想だった(笑)。
だからさっき言ったように、ゲームセンターには僕らからすればお客さんが見えるという良さがあったし、お客さんはお客さんで有名プレイヤーと直接会えるという、その良さがあったんですよ。いまは何でもネットなので。でもネットで見るのとリアルで対面するのとは、ぜんぜん違いますから。
森氏:
あの当時はブンブンくんなんて、『バーチャ』と関係ない番組にまで出演してましたからね。
 |
鈴木氏:
初めて聞く話ばかりですね(笑)。そういう話って、ぜんぜん聞いてないんですよ。
森氏:
そうなんですか!? 鈴木さんは『バーチャ』がブームになったときに、店舗を視察されたりしたんですか?
鈴木氏:
それはあんまりなかったですね。作り終わったらもう、違うゲームを作っていますから。なかなか外に出ないので。プロモーションで、たとえば全国大会をやりますよとか、プロモーションツアーに参加してほしいという場合にはもちろん出て行くわけですけど。自分が視察に行くのは、何かを作るために自分から情報を取りに行くためなので、出来上がったゲームに関しては、それはみなさんに遊んでいただければと。いったんリリースしたら、次のことを考えていますから。