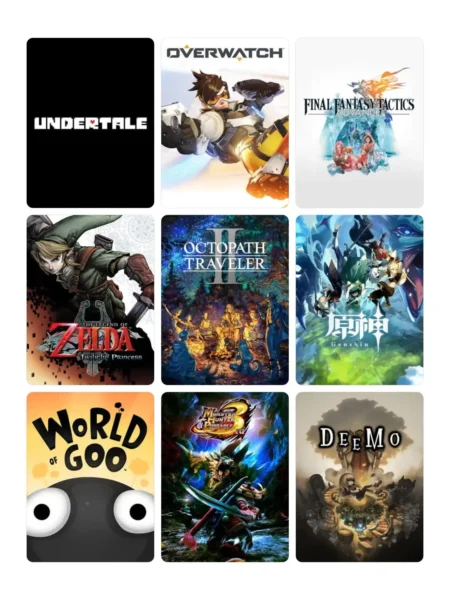『トライブナイン』は、小高さんの作品にまだ触れたことのない人への「入門編」にしたい
──それって、アカツキや山口さんの「当て勘」みたいなものだと思うんです。ちゃんと広げ方を考えているところに、プロデュース力を感じるんですよ。
その当て勘が今度の『トライブナイン』には、どのように活かされるんだろうか、というところをぜひお聞かせください。

山口氏:
『トライブナイン』に関しては、小高さんたちと僕らが一緒にやるという部分に対して、期待されることがあると思うんですね。ですので、有名な家庭用ゲームのクリエイターを招聘して「ただビジネスでやっている」というふうに、ユーザーさんに思われたくないというか。
──ただ「お金をかけて作りました」というものではないと。
山口氏:
はい、小高さんたちのクリエイティブを僕らがしっかりと理解して、一緒になって楽しんで作っているというところを伝えていきたいと思っています。
いまのYouTuberとか、クリエイター集団と言われる人たちって、ある種、社会のしがらみとかルールとか、そういったものに縛られない自由さみたいなものへの「憧れ」を体現していると思うんです。
──彼らの側でも、そういうふうに演出しているところもありますよね。
山口氏:
ファンもそういう人たちの仲間、つまりトライブのひとりという感覚になっていると思うんです。『トライブナイン』はそういう空気感をまとったタイトルにしたいですね。
なので、僕ら自身も、周りからは無駄だと言われるようなことでも大事だと信じてあえてやる。それはビジネスの常識に反しているように映るかもしれませんが、それこそがむしろ、いまの時代のゲーム制作には成功の種になるものだと思っているので。
シナリオにしても、「こんなに分量が多いと作るのが大変じゃないですか。効率が悪いですよね」って、普通はなると思うんです。でも、それをリスクだと考えてシナリオの文量を減らしたりした結果、ストーリー性が薄くて、キャラをとりあえずなぞったみたいなお話しかない作品になっちゃったら、そっちのほうがよっぽどリスクだと思うんです。
──言葉を選ばずに言いますけど、小高さんとかTooKyo Gamesとか、もっと言うと『ダンガンロンパ』でさえ、世間一般から見ればコアな存在だと思うんですよ。ゲームを好きな人のあいだではもちろん広く知られていますけど、それこそ「知る人ぞ知る」であって。
だから、先ほど山口さんが言われたような「マスに向けて小高さんが作りました」というのを打ち出しても、それでマスにウケるわけではないと思うんです。
そう考えたときに小高さんや小高さんに期待するファンの人たちを起点にして、どうやってマスにまで広げていくのだろうかと。
山口氏:
そういう意味では、スマートフォンゲームといえば、オートで遊ぶターンベースのRPGが多い中で、『トライブナイン』ではアクション性を取り入れるなど、やっぱりちょっと尖った挑戦をしています。
そういったチャレンジに対して、その精神性に共感してくれる人を巻き込んでいきたいと、そういうイメージです。なので、小高さんのファンのためにというよりは、小高さんの才能というかタレントを、より多くの人に知ってもらいたいと。
──「スマートフォンゲームにしてはちょっと変わっている」という違和感を前面に押し出して、それをやっているのが小高さんやTooKyo Games、タレントのあるクリエイターなんだよ、という順番ですか。
山口氏:
そうですね。たとえば『Fate』シリーズも、もともとはPCゲームだったのが、『Fate/Grand Order』でより多くの人に触れられるようになったことで、10代、20代の、もとのPCゲームを遊んでいない世代の人たちまでファンになった経緯があると思うんです。あれと同じような現象を起こしたい、というイメージですね。
──山口さんから見て、あの『Fate』の現象ってどういうものだと思います?『Fate』ってPCだけじゃなくてコンシューマでも、『Fate/Grand Order』が出るまでは『Fate/EXTRA』のように20万本前後のゲームだったんですよ。TVアニメも人気でしたけど、そこまでメジャーではなかった。だけど『FGO』というものが出てきた瞬間に、一気にメジャータイトルになっていったわけで。
山口氏:
そこはもともとポテンシャルがあったと思っているんですよね。『Fate』シリーズ自体の世界観であったり、サーヴァントが歴史上の偉人であるというところも、受け皿が非常に広い設定なので。
10代、20代の人たちの中二心をくすぐる本物の奥深さを有しているんだけど、じつはマスにも受け入れられやすい要素を持っていて。それがスマートフォンというプラットフォームによって爆発するきっかけを得た、と僕はイメージしています。
じつは、小高さんに対してもそういった感覚を持っているんです。小高さんは、ふだんからすごくいろんなことをインプットされていて。そうでありながら、自分の内なるアーティスト性みたいなものを発露していくのではなく、お客さんがどう思ってるのかな、ということも考えたうえでのモノ作りをされる。……こういった話を僕がしてしまうと、TooKyo Gamesさんのイメージ戦略に反してしまうかもしれないですが(笑)。
──(笑)。
山口氏:
なんていうんですかね。すごく一般の感覚を持ちながら、「あえてここをやっている」みたいな感性の持ち主だと思っていて。今回の『トライブナイン』も、もちろん小高さんらしい「尖り」だったりとか、「裏切り」だったりとか、そういったエッセンスは多分にあるんですけど。
でも一方では小高さん自身が「『ONE PIECE』をイメージして作った」って冗談で言ってましたが、実際、けっこう王道の話になっているんですよね(笑)。ただそこで「小高さんらしさ」がなくならないように、「エクストリームベースボール」という楔をちゃんと打ってある。『トライブナイン』はそういう作品なんですね。
だから僕は、いままでTooKyo Gamesや小高さんの作品に触れたことがない人たちにとって、『トライブナイン』がこれからTooKyo Gamesさんの作品に触れてもらえる入門編みたいなタイトルになるんじゃないかと思っていて。そのためにまずは作品の持つ魅力を知ってもらいたい。
フリー・トゥ・プレイの環境で、無料で体験して知ってもらえる。『トライブナイン』という世界に、お金を払わずに触れることができるというのは、ゲームのスタイルとしてすごく有効だと思っています。
 |
多様性を認め合う『トライブナイン』の世界と、ゲームの開発スタイルがリンクしている
──少し前の奈須きのこさんがそうであったように、小高さんも今よりもっとメジャーな存在になるのではないかと、山口さんが感じるポイントというのは、具体的にはどういったところなんですか?
山口氏:
評論家みたいな偉そうなことばかり言って恐縮なんですが、『ダンガンロンパ』も小高さんのたくさんある引き出しの1個だと思うんです。
小高さん自身が違うメディア、違うフィールドでモノ作りをすることになったなら、また別の引き出しを開けることができるはずで。TVアニメの『アクダマドライブ』も、ものすごい極上のアクションエンターテインメントに仕上がっていましたよね。

──引き出しのポテンシャルがかなりある方なんだろうな、というのは僕も感じますね。
山口氏:
小高さんは、ご自身の作ったものを「できるだけたくさんの人に触れてもらいたい」と思っているわけで、「わかる人だけがわかればいい」というスタイルでは決してなくて、実はプロデューサー的な感覚に近いものを内包されている方なんじゃないかな、と。
──そうですね。小高さんというと「尖った」とか「個性的な」とか「こだわりがある」みたいなイメージがある一方で、先日のインタビューでも出てきたように、意外と「譲る」部分も多い気がするんです。
独創的な面白さとはどうやって作られるものなのか?を聞いてみたら、いつもは飄々としてる小高和剛氏が、極めて真面目に答えてくれた。完全新規IP『トライブナイン』は何をしようとしている作品なのか?
山口氏:
そうなんですよ! それがすごく意外だったんですね。正直、このプロジェクトをやることになった当初は、僕はアカツキとTooKyo Gamesさんのあいだの調整役みたいなところに集中せざるを得ないんじゃないかと思っていたんです(笑)。
でも実際にはぜんぜんそんなことはなくて。むしろこちらからのアイデアを「もっと出してくれ」と言われるような感じで。
だから僕らもある種、クリエイターとして負けないように、いろいろなアイデアを出すんです。そういったマッシュアップで作られているのが、この『トライブナイン』というタイトルになっていて。じつはその作り方自体も、『トライブナイン』が持っている作品のテーマとリンクしている部分もあるんですけど。
──というと?
山口氏:
小高さんが明確に言ったわけではないんですけど、いまあるものや出来てきたものを総合して見てみると、『トライブナイン』という作品のテーマには、「多様性を認める」みたいなところが、すごく大きな部分としてあると思っているんです。
「区」がそれぞれ、いろんな特徴や個性を持っている。それぞれが自分のスタイルで生きている。それぞれがポリシーを持って集団を形成している。『トライブナイン』の各トライブって、ひとつの思想にみんなが染まるっていうことはないんですよ。いろいろあって仲間にはなるんですけど、でもそれぞれに一線は引いているというか。
お前たちはそういう考えだけど、オレたちはこういう考え方でやっている。でも「エクストリームベースボールが好きだ」って気持ちは同じだから手を取り合おう、と。だからといって、いつも一緒に過ごしたりはしない。そういう仲間のスタイルで、物語が展開するんです。
──なるほど。
山口氏:
『トライブナイン』という作品の作り方としても、ひとりのクリエイターが世界観とかストーリーとかキャラクター性とかを、全部きっちり統一して作られているわけじゃなくて。お話自体も複数のシナリオライターのアイデアがガシャガシャッと入っている、ごった煮みたいな作り方になっています。もちろん、最後は小高さんに細かく監修をしていただいておりますが。
ゲームのほうもいま、チームにいろんな才能が集まってきているところでして。コンシューマ業界の有名なタイトルに携わっていた方たちとかもいて。もちろん、アカツキでスマートフォンゲームを作っていたメンバーもいます。そんなふうにいろんなカルチャーの人間がこう、ゴチャッと集まっていて。この作り方自体が作品のテーマとも合っているんですね。
──『週刊少年ジャンプ』元編集長の鳥嶋和彦さんのお話で、「漫画家が“描きたいもの”と、その人が“描けるもの”は違う」というのがあるんです。それってモノ作りの本質、もっと言うと仕事の本質かもしれないと思っていて。
そもそも「編集者」って何なんだ!? 『ドラゴンボール』を手がけた伝説の編集者・鳥嶋和彦が語る、優秀な漫画編集者の条件とは。
たとえばいま、トリプルAのゲームが流行っているからトリプルAのゲーム作ろう、といきなり言ったところで、できるわけがないじゃないですか。やっぱり自分たちでできるものを作るしかない。そうなったときに、いまのアカツキさんのチーム構成だったり、社内の文化だったりというのと、『トライブナイン』という多様性のある作品が、うまく合致したと思うんです。
そうすると気になるのが、それがたまたま合致しただけなのか、それとも必然なのかというところで。
山口氏:
これは自分個人の想いですけど、「ゲーム業界ってこうあってほしいな」と思う世界観とも、合致しているような気がしていて。
僕らが子どもだったころのファミコンやスーファミには、本当にいろんなゲームがあったじゃないですか。ファミコンで野球のルールを知ったりとか、ゴルフや麻雀のルールを覚えたりとか。すごく多様なものにゲームを通して触れることができたところが、とても楽しかった。
でもゲームが大型化していく流れの中で、ゲームシステムがどんどん画一化されてきて、それに抗うこともなかなか難しい状況になっていて。
いまではインディーゲームのマーケットが、そういった個性を発露する場として機能していると思うんです。でもゲームって、やっぱり一定の規模がないと作れない。だから会社でゲームを作っている人間も、そういった気持ちは忘れないでいたいなと。あえて野球をやる、みたいなところで個性を貫くものがあってもいいのではないか、と思っているんです。
『原神』みたいな物量で来られると、全方位を真っ向から立ち向かうのは中々難しいと思っています。なので、全てを高次元にするというよりは、しっかりと高品質なものをベースとしては提供しつつ、あとは工夫や個性で対抗するといったバランスで考えています。
小高さんが筋の通った「串」を通すことで、ゲームとアニメを共通の体験にしていく
──『トライブナイン』で「オリジナルIPを作ります」とか、あるいは先ほど言われていた「普通じゃないことをあえてやる」いうのは、いったいなぜいま、アカツキさんがそういうことをやらなきゃいけないんでしょうか。
「新規IPを立ち上げてやっていくんです」って言うと、なんだかこうキラキラした感じがあるんですけど、僕はもうちょっと「切実な何か」があるんじゃないかと思っていて。だって人間は、「そうでもしなきゃチャレンジなんかやらないのでは」と思うんです。思い切った冒険をやらなくちゃいけないほど、切実な何かがあるんじゃないか。できればそこを聞きたいなと。
山口氏:
あぁ、そうですねぇ……自分でも考え込んでしまったんですけど。
 |
──たとえば、さっきの『原神』の話じゃないですけど、やっぱり普通にゲームだけを作っても勝ちきれんよなぁ、とは思うんです。
山口氏:
たしかにそういう黒船的な意味合いはありますね。海外製のゲームの進出が、これからさらに加速するでしょうし、彼らが作るものは日本のタイトルの研究がしっかりとされている。とくにキャラクターメイクとかそういったものはある種、データドリブンの極致だと、僕は捉えているんですけど。
──「いまウケるのはこうだよね」というところですね。
山口氏:
日本でヒットした、いろんなアニメのエッセンスを抽出して、それをパッケージ化しているっていう感じで、物量では真っ向勝負をするのは厳しい。かける予算とかも、もう桁違いになってきているので。
それに対して、日本のゲーム作りをどこでどう差別化していくのかというときに、作品自体の根幹のところを作る能力とか、そういったところで差別化していくしかないという。ある種の差し迫った脅威を感じているところはたしかにありますね。
既存のIPをゲーム化するにしても、僕らとしてはそのIPを同じ言語、母国語で深く理解したうえで、その作品のエッセンスをより細やかにゲームに反映させることができる、といったところを磨いていかなきゃいけない。
そういった「IPを理解する能力」を身につけるためにも、自分たち自身がIPを生み出す経験を積むことも、ひとつの説得力として必要になってくると思います。
とはいえ、そのへんも海外企業も早晩、追いついてくるでしょうね。だから僕としては、あまりのんびりしてはいられないなと思っていて。本当にこの2年、3年の勝負でしょうね。
そういった形で自分たちのポジションを確立できるタイトルを生み出さなきゃいけないと思っている中で、そのうちのひとつが『トライブナイン』。ほかに仕込んでいるタイトルもまだあるのですが、それぞれにそういった使命感を持って取り組んではいますね。
──昔の北米や欧州がそうだったんですけど、言語化できる部分ってキャッチアップされやすい部分なんですよね。簡単に言うと。
山口氏:
そうですね。
──言語化できる部分はどんどんキャッチアップされて、しかもより大きなサイズ、より大きな市場で展開されていくので、日本はなかなか勝ちづらくなっていく。そんな状況のいまだからこそ、言語化がまだされていない領域が、日本のクリエイティビティの「勝ち筋」のひとつだと思うんです。
それを持っているクリエイターが、たとえば小高さんだし、上田文人さんもそうだし、あとはフロム・ソフトウェアの宮崎英高さんとか、奈須きのこさんもそうですよね。言語化されていない領域を肌感でわかっているクリエイターが身につけているものを、ある程度の規模感を持ってどう再現していくのかというのを問われているというのが、いまの日本が置かれている状況なのかなって思うんです。
山口氏:
その意味で言うと、小高さんはゲームのストーリーテリングに関してもちろんプロフェッショナルなんですけど、それだけじゃなくてアニメにおけるストーリーテリングや、小説におけるストーリーテリングといった、さまざまなメディアでのご経験があるんですよね。
そこはすばらしい才能をお持ちだなと思います。だからこそメディアミックスを利用して、ゲームの盛り上げにうまく使っていくことが、ちゃんとできる方なんですよね。これは本当に業界では稀有な存在だと思っているんですよ。
──ただ、今回の『トライブナイン』に関して言えば、よくある「メディアミックスのプロジェクト」、「大型企画」といった見え方になってしまうと、もったいないなと思っていて。
逆に、既存のメディアミックスに魂がこもらないというか、なんとなくつまんないものになってしまうのは、なぜだと思います?
 |
山口氏:
メディアミックスでは、どのメディアでも同じ体験ができることが重要だと思うんですね。アニメで感じた体験と、ゲームで感じた体験が、しっかり同じものになっている。作品のコンセプトがしっかり立てられていて、それぞれの作品を作る人たちがそれをきちんと理解して、作品に反映されているってことが大事だと思っています。
一方で、よくあるメディアミックスで起こり得るのは「これじゃないんだよな」っていうもの。ゲームの魅力がアニメになったときにまったく反映されていないとか。
それはたとえばアニメの制作側で、そのメディアの中での最適解を出したのかもしれないんだけど、その結果、アニメとゲームにブリッジがかかっていない状態になってしまっている。それがメディアミックスの失敗する、いちばんの事例だと思うんですよね。
逆にそこがうまくいっていると、アニメを見ておもしろかった、じゃあゲームでもきっと同じ体験ができるだろうとゲームを触ったときに、「やっぱり同じ体験ができた」と感じていただける。
僕はアニメの『Fate/Zero』を見て、遅ればせながら『Fate』シリーズに入ったんですね。そこから『FGO』を遊んで、「あの『Fate/Zero』で得られた体験がゲームでも得られた」って思ったんです。そこがちゃんとできていると、メディアミックスはきちんと作用すると思っています。
──良くないメディアミックスって、プロモーション的な観点がすごく強いんですよ。でもそういう観点のメディアミックスは、多面展開以上の価値がなくて。成功している作品はやっぱり、それぞれのメディアの特性だったり、それぞれのお客さんの入り方をきちんとイメージして使い分けているんですよね。
山口氏:
その通りだと思います。そこで各メディアに対して一本筋の通った「串」を通せるのが、さっき言った小高さんみたいな人だと思うんです。
各メディアの特性を理解して、そのメディアに沿ったストーリーを作るんですけど、それをちゃんとセンターで統括できる。そういう人がいらっしゃるのは、スゴイことだと思っています。
──結局、誰かが本当にハンドルを握ってそれをやりきらないと、おもしろいものにはならないと思っていて。『Fate』だとそのポジションに奈須さんがいらっしゃるし。最近だと『ウマ娘』がそのあたりをすごくうまくやっているので、誰がどうやっているんだろうと興味があるんですけど(笑)。
そういった役目を担う人物として小高さんが立つ理由って、「オールマイティーさ」じゃないかと思うんです。「何でもあり感」みたいなところが、クリエイターとしての小高さんの魅力というか。
山口氏:
たしかにすごい魅力だと思います。一方で、そうしたメディアに串を通す部分に関しては、自分のほうでもサポートできるのではないかなとは思っています。
『八月のシンデレラナイン』という作品で、いろんなメディアミックスを作り手側、原作側で体験しているので。今回の『トライブナイン』のアニメに関しても、プロデューサーとして「ここは守りたい」というところが、やっぱりあるんですよね。

──それは具体的にはどういうところですか?
山口氏:
さっきも言った、アニメとゲームのあいだにどういう橋を渡すか、みたいなところですね。「これが成立していないとアニメの存在価値がない」といった部分に関しては、自分も制作の現場に入らさせていただいて、小高さんのやりたいことと、アニメの制作側でやりたいことの調整にあたるつもりです。
そのうえで「IPとしてやりたいこと」も、ちょっと忍ばせておくという(笑)
──『トライブナイン』のアニメは、ゲームとはまた違ったストーリーになるんですよね?
山口氏:
アニメは本当に入門編だと思っていて。無料で見られるものですし、オリジナルIPですから、まずはアニメで作品世界を知ってもらおうと。もちろん、アニメ自体がおもしろくなる、ということが大前提ではあるんですけど。
『トライブナイン』って、世界観がすごくわかりづらいんですよ(笑)。「アウトロー! ケンカ! バリバリ!」……みたいなものだとすごくわかりやすいんですけど、奥深くはなくなっていくというか。ですので、アニメではさじ加減としてわかりやすさみたいなものを保ちながら、『トライブナイン』の本質もちゃんと残すようにしています。
とにかく、アニメで興味を持った人が「ゲームを遊んでみたい」と思ってもらえるルートが形成されているかどうかが、本当に重要で。そうじゃないと本当にやる意味がないので。