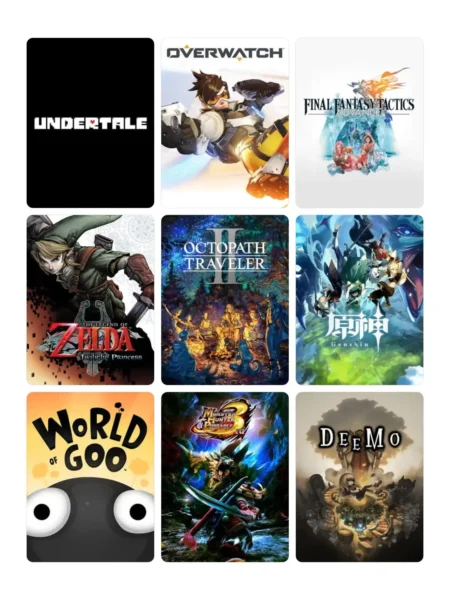新卒でエニックスに入社したときに、まだ黎明期だった携帯アプリ事業を自分で選んだ
──話を締めにもっていく前に、改めて山口さんご自身の話をうかがっておきたいのですが、いったいどんな経緯でゲーム業界にやってきたのか、といったところから教えてもらえますか。
山口氏:
大学を卒業して、当時のエニックスには新卒で入社しました。明確に「ゲーム業界に入りたい」と考えていました。
ほかのゲーム会社も受けていましたが、たまたまエニックスから最初に内定をいただいて。ご存じだと思いますが、スクウェアと合併する前のエニックスは、プロデューサーしかいないというすごく稀有な会社だったんですね。なのでそこからはずっと、プロデューサー人生を歩んでいます。
──世代的にはどういった感じなんですか?
山口氏:
同期入社だと、のちにドロッセルマイヤーズというボードゲームの会社を立ち上げた渡辺範明くんや、さまざまなトライエース作品を手がけてきて、今やトライエースに在籍している小島創くん。1個上には『サガ』シリーズプロデューサーの市川雅統さんがいて。
2個上以上の世代だと安藤武博さんや、あとは『ドラクエ』シリーズチーフプロデューサーの市村龍太郎さん。下の世代だと『ニーア』や『オクトパストラベラー』のスマホ版を担当している横山祐樹くんとか、名前を挙げてくとキリがないぐらいなのですが。本当に3〜4年のあいだにそういった人たちが混在しているような、スゴイ世代でしたね。
──山口さんご自身としては、最初からプロデューサー志向だったのですか? それとも、エニックスに入社したことで結果的に、という感じなんですか?
山口氏:
結果的に、プロデューサーにいちばんうまくハマったという感じですね。理由としては、大学時代の経験が大きかったと思っていまして。大学生のときに、リアルタイムの3Dグラフィックスを使ってゲームを作るという研究室に所属していたんです。
──そう聞くとむしろ、開発現場のほうに向いている印象を受けますが。
山口氏:
当時はCGがすごく流行っていた時代だったので、個人では絶対に手に入らないような高級な機材に触れることができたんですね。CGのほか、JavaやC+のプログラムを実際に書いて、動かして、デバッグして、みたいなことをやっていました。
ただ、そういうことをやっていても、同期の友人とか後輩とかにものすごく頭の良いヤツが多くて、すぐに抜かされるんですよ(笑)。
それでもう「自分はこの領域でちょっと勝負できないな」と思ったんですね。プログラムだけじゃなくてCGのほうでも、やっぱりデッサン力とか空間把握能力みたいなところで、美術系の研鑽を積んできた人にはぜんぜんかなわなくて。最終的に、企画だとかチームを引っ張るリーダーみたいなことを、研究室でもやっていたんです。
当時のゲーム業界はプランナー採用かプログラマー採用かのふたつしかなかったんですが、そんな中でエニックスだけがプロデューサーっていう、得体の知れない職業形式で募集をしていて(笑)。
いろんなことを中途半端にしか知らないという自分の弱点が、ここなら逆に強みに変わるのかな、と思ったんです。もともとエニックスはすごく入りたい会社ではあったんですけど、そんな会社から運命的に内定をいただくことができて、そこから自分のゲーム業界のキャリアが始まった感じですね。
──エニックスでの最初のお仕事は?
山口氏:
入社したときに3つの職種を自分で選べたんです。提示された職種のひとつ目は、オリジナルのコンシューマゲームを作るプロデューサーになるか。ふたつ目は、『ドラゴンクエスト』のシリーズを守るというか、紡いでいくプロデューサーになるか。
そして最後に「いま、携帯事業がおもしろい領域で、これからやろうと思っている」と言われたんです。それで僕は、「携帯アプリをやりたい」と志望を出しました。当時はけっこう珍しい存在だったんですけど。
──そのときになぜ、ほかの人はあまり選ばなかった携帯アプリの事業を選んだのですか?
山口氏:
そのころは若かったのもあって、けっこう「山っ気」がありました(笑)。「ここならいちばん早くヒット作が出せるんじゃないか」と思ったんですよ。
じつはエニックスに入社する際、当時の福嶋会長と「僕は絶対に100万本売ります」という約束を交わして採用されていまして……。
 |
──それはスゴイ(笑)。
山口氏:
アプリなので100万「本」ではないのですが、100万本に匹敵する成果をいちばん早く出せる職種なんじゃないかと思って携帯事業を選びました。
──山口さんとしては、その時点で携帯ゲームの将来性だとか、市場規模みたいなものをご存じだったのですか?
山口氏:
iモードが1000万台、1500万台と普及が進んでいて、「これから絶対におもしろくなるマーケットだ」と言われていました。じつは、当時の自分の上長が齊藤陽介さんだったんですね。齊藤さんはエニックスのモバイル事業のトップもやられていて、モバイル業界の盛り上がりみたいなものは、なんとなく感じていましたね。
スクウェアは貴族でエニックスはヴァイキング? 人たらしでヒットに導く齊藤Pに見る“優秀なゲームプロデューサー”【齊藤陽介×藤澤仁×ヨコオタロウ×安藤武博:座談会】
──とはいえゲーム業界に入って、しかも『ドラクエ』などを作っているエニックスに入って、そこで携帯アプリを作る道を自分から選ぶというのは、ちょっと違和感がある気がして。もともと山口さんの中に「コンソールゲームじゃないものを作りたい」というイメージがあったんですか? それともそこはビジネスライクに「とにかく当てたい」という感覚だったんですか?
山口氏:
当時の携帯アプリは企画や規模感、予算もそんなに高くないものでした。自分にとっていちばん経験と場数を踏めるフィールドかな、と思ったのが大きかったかもしれないです。
──齊藤陽介さんはモバイルだけではなく、『メール de クエスト』とか『クロスゲート』とか、オンラインゲームを黎明期から手がけられていたプロデューサーですよね。いまはその部分についてあまり語られてはいないですけど、かなり稀有な経歴の持ち主だと思うんです。
山口氏:
そういったところで齊藤さんは当時の自分からしてもカリスマというか、憧れみたいな存在でした。その齊藤さんが携帯アプリをやっていたことで、自分もそれをやることに対してあまり違和感とか葛藤とかはなかったですね。
『ドラクエ』チームでゲームの作り方を学び直した後に、アカツキへ
──山口さんが入社されてから、エニックスがスクウェアと合併し、仕事の変遷はどうなっていったのですか?
山口氏:
当時のモバイルゲーム事業部は、合併したときにいちばん早く混ざった部署なんです。なんというか、まったく違う文化の人たちが突然やってきて、転職したような感じでしたね。
それまでのエニックスは、コストやスケジュール、モノ作りのスタイルも全く異なるので、衝突を目の前で見ることもありましたが、勉強になることもありました。
──そのときに感じたことで、いまにつながっていることはありますか?
山口氏:
『ファイナルファンタジーXV』のディレクター、田畑端さんはモバイル事業部の出身なんです。モバイル事業部時代には『ビフォア クライシス ファイナルファンタジーVII』のディレクターを務められていたのですが、ゲームはデジタルなので実際には限界を超えることはできないわけですが、それを「超えた」と感じさせる作品を作ることこそが、自らのアイデンティティだと自分は理解している、とおっしゃられていて。それがすごく印象に残っていますね。
実際に『ビフォア クライシス』は、RPGとしての遊びごたえもあるし、連載型でストーリーが紡がれていったりと、「携帯電話でこんなゲームを作れるんだ」と感じさせてくれた、新しい領域を開いたタイトルでした。
──その後、山口さんはスクウェア・エニックスを退社して、アカツキに移って来られるわけですが、そこまでの経緯は?
山口氏:
ヘンな話、モバイル事業部で自分は大きな失敗をしなかったんですよ。市場が急速に拡大しているマーケットだったので、二番煎じであっても売り上げが出せたわけです。……それを自分の実力と勘違いしてしまって、ちょっと天狗になっていたというか。
そんなときに、それまでの実績を買われてアメリカ支社に転勤になったんですね。日本で成功しているセオリーをそのままアメリカでもやれば勝てるだろう、と思ったのですが、ぜんぜんうまくいかなくて1年ぐらい帰国の途につくことになるんですけれども……。
 |
──なぜうまくいかなかったのですか?
山口氏:
IPを取ってくるところは、上出来なぐらいできていたんです。現地のメディア企業がこぞって「何か携帯アプリを作りたい」と言ってきた時代だったので。でもそれをゲームに落とすところがうまくいかなかったんですね。
現地のデベロッパーと一緒に作ることに慣れていなかったのもありますし、現地の人がほしいと思うものと、こちらの感覚とのズレだとか、いろいろな要因がありました。
帰国してからは、ゲームの作り方をもっとしっかり勉強しなければという考えもあり、『ドラクエ』チームに拾っていただいたんです。最初は『ドラゴンクエストソード 仮面の女王と鏡の塔』に関わり、そのあとに『ドラゴンクエストIX 星空の守り人』でアシスタントプロデューサーを担当し、『ドラゴンクエストIX』の海外版ではプロデューサーをやらせていただきました。
──山口さんが『ドラクエ』の仕事をしているあいだに得たものは、どういうものだったのですか?
山口氏:
『ドラクエ』って本当に国民的RPGなんです。「『ドラクエ』を売るためにはここまで努力しなければいけないのか」というのを実際に肌で感じることができたのは、すごく大きいですね。市村さんが当時プロデューサーだったのですが、仕掛けを何重にも張り巡らせて、それでようやく結果につながるというか。
堀井雄二さんとのお仕事で印象的だったのは、ファーストプレイの感覚。作っている側って、どうしても先の展開を知っているので、ファーストプレイの感覚を持つのは難しいじゃないですか。
──なかなか客観的には見られないですよね。
山口氏:
堀井さんをスゴイなと思ったのは、まさにそこでした。堀井さんはユーザーのファーストプレイの感覚に、瞬時になれるんですよ。「ここがわかりづらいよね」とか「この言い方だとお客さんにはちょっと伝わらないんじゃない」とか、その指摘が本当に的確で。
堀井さんが手を入れると、ユーザー自身が能動的に「これを選択した」って思わせるバランスが、明らかにグッと良くなるんですよね。
──あのクラスの方がまだそこまでされるのか、という感じですね。
山口氏:
その堀井さんが、ご自身の中で「こういうテーマ」、「こういう遊び」を提案しようと作っているのが、ドラゴンクエスト』だと思うんですよね。
スマホゲームにアクション要素を採り入れる「最適解」を見つけ出したい
──では、そろそろ話をまとめたいと思います。『トライブナイン』のゲームに関しては、絶賛開発中とのことですが。

山口氏:
取材の冒頭にもお話ししましたが、今回はだいぶ頭の悪いアプローチをしていて。
オリジナルIPです。ハイエンド3Dは初めてです。アクション要素も入れます。……もう、チャレンジ尽くしで(笑)。しかもそのチームをイチから立ち上げます、と。
──たしかに「頭が悪い」と言いたくなりますね(笑)。
山口氏:
「常識から考えると失敗しかありえないじゃん」みたいな作り方になっているんですよ。でもそこはですね、逆にそういったチャレンジに対して燃える人たちが集まってきてくれていると思っています。ゲームのリリースが近くなってきたら、開発チームのメンバーもぜひ前面に出したいなと思っているんです。本当にスゴイ才能が揃っているので。
本当に僕の認識できる範囲を超えて、おもしろいゲームができそうなチームになりつつあると思っています。まだまだメンバーを集めている状態ではあるんですが、かなりその骨格というか、土台は出来上がりつつあって。ですので、そういったところで働いてみたいという方がいらっしゃいましたら、ぜひご応募いただきたいと(笑)。
 |
──求人の告知も入りましたね(笑)。
山口氏:
いろんな才能が混ざり合っているチームですので、ユーザーさんから見ても、スマートフォンゲームとして「こんなのアリ?」というものを作れているんじゃないかなと。そのあたりは小高さんたちとも一緒に、ストーリー的にもゲーム的にもライバル企業と戦えるものを計画しています。リリースまでちょっとお時間をいただくことになるんですけど、楽しみに待っていただければ。
今回、進捗報告会と題して情報をお伝えしましたので、今後も第2回、第3回という形で、ゲームの進行状況を家庭用ゲームのプロモーションに近い形で公開していければと思っています。
──そうなんですね。
山口氏:
ゲームを作っていく過程みたいなものも含めて、お客さんに楽しんでいただければと思っています。『トライブナイン』の公式Twitterなり、YouTubeなりをぜひ登録していただければと(笑)。
──なんとなく締めのコメントになってきた感じですけど、最後にひとつだけうかがってもいいですか?今回の『トライブナイン』はなぜ、あえてアクション要素を採り入れるのでしょうか?
山口氏:
今回、オリジナルIPの『トライブナイン』でゲームを作るというときに、ターンベースのRPGがいくつも存在している中で、それと同じようなものを作っても、いまの時代では受け入れられないだろうと。
一方でゲームらしいゲームとしては、ある程度リアルタイム性のあるものが評価をされていく流れがあります。コンシューマの世界でも、たとえば『FF』はリアルタイム性やアクション性をどんどん取り入れている。ですからスマートフォンのゲームでも、早晩それがトレンドになっていくだろうと思っています。
ただ実際問題、スマートフォンとアクションゲームは相性がすごく悪いんですよ(笑)。アクションで操作しなきゃいけないっていうのと、長く遊ぶってことは、本当に相性が悪くて。あえて今回そこにトライしているのは、その「解」を見つけるという、大きなチャレンジのひとつなんです。
──ゲームらしいゲームはどんどんリアルタイム性に寄っているというのは、山口さんとしてはどんな理由だと思います?
山口氏:
やっぱり「没入感」が違うっていうのが、いちばん大きいと思うんですよね。自分が操作することで、その世界に入り込んでいる感覚が得られるわけで。コマンドバトルだと、どうしてもキャラクターを俯瞰しているというか、ユニットとして見ている感覚になるので。
あとは、『トライブナイン』がアウトロー物だというのも、アクション性を取り入れた理由ですね。小高さんたちが作る個性的なキャラクターと自分も一緒に戦っているというか、自分の背中を預けて一緒にケンカをしているような没入感がほしかったんです。
そう考えたときに、コマンドバトルでキャラクターを指示する立場になるっていうのが、世界観的にすごく不自然だったんですよね。
──あぁ、なるほど! 『Among Us』ってゲームがあるじゃないですか。あれって要するに人狼ゲームなんですけど、人狼ゲームのキャラクターを自分で動かせるものにすると、こんなにポテンシャルがあったのかと驚いたんです。2Dのコミカルなキャラクターなんだけど、それを自分で動かすことで、人狼ゲームのルールが臨場感があってスリリングなものになる、っていう。
山口氏:
やっぱりアクションゲームのほうが、圧倒的に没入感があるんですよね。キャラクターと自分が一体化している感覚は、ちょっと引いて盤上を見ているコマンドバトルの感覚とはまた違う体験だと思うので。
でもスマートフォンゲームで、実際に操作するのを四六時中やり続けるとなると、さすがに飽きてしまう。そのあたりのバランスをどう取るかっていうのは、それこそ海外製のタイトルでもまだ、ソリューションとして提示できていないところだと思うんです。
なので、そこは今回、自分たちでその「解」を出すのがけっこうなチャレンジになっていて。まぁ、なんとかいけるんじゃないかな……とは思っているんですが(笑)。
──いやでも、それだけチャレンジ尽くしのタイトルはすごく楽しみですよ。
山口氏:
チャレンジばっかり重ねていて。……会社に対してどう説明すればいいのか(笑)。
──そのぐらいの気概でモノを作っているのは、すばらしいことだと思うので。期待しています。(了)
 |
インタビューの中で山口氏も語っていたとおり、スマホゲームの中でもとくにソーシャルゲームと呼ばれるタイプのゲームは、データの集積により成り立っている面がある。ゲーム内でのユーザーの動向を集積し、それに対して最適化された運営を行っていく。そこでは予測可能な範囲での成功が約束されるかもしれないが、一方でエンターテインメントの重要な要素である「驚き」とは無縁になってしまうだろう。
それに対して、近未来の東京で個性的なアウトローたちが破天荒な大暴れを繰り広げる『トライブナイン』の作品世界は、ある意味で真逆のものだ。そのゲーム作りもまた、小高和剛氏をはじめとするTooKyo Gamesのクリエイター集団がシナリオやキャラクターデザインで想像力を自由に羽ばたかせるという、山口氏が言うところの「ごった煮」になっている。何が飛び出してくるかわからない「驚き」こそが、『トライブナイン』のおもしろさだ。
多様なおもしろさを内包した『トライブナイン』の世界観を、いかにしてスマートフォンゲームのメソッドに落とし込んでいくのか。山口氏が語ってくれたように常識外れのチャレンジの連続であるこの試みが成功すれば、それは日本のスマートフォンゲームやIPビジネスが今後向かっていく道筋のひとつを示すことができるのかもしれない。
スマホゲームのリリースはまだしばらく先になるとのことだが、2022年1月放送開始予定のTVアニメ版『トライブナイン』で、まずはその世界観とキャラクターの魅力が見えてくるはずだ。
【あわせて読みたい】
独創的な面白さとはどうやって作られるものなのか?を聞いてみたら、いつもは飄々としてる小高和剛氏が、極めて真面目に答えてくれた。完全新規IP『トライブナイン』は何をしようとしている作品なのか?本作におけるアクの強いキャラクターたちや、エッジの利いたエクストリーム・ベースボールの設定は、じつに小高氏らしいテイストだが、そこにはどのような狙いがあるのだろうか。完全オリジナルの新規IPという「ゼロからイチ」のアイデアを生み出す発想法や、スマートフォンゲームでは異例とも言える膨大な量のシナリオを作成するための体制作りなど、今回の取材では『トライブナイン』を通して、小高氏による創作の根幹に迫ってみた。