スポーツ観戦が持っている「同時性」の盛り上がりを、ストーリーRPGで再現したい
松永氏:
ちょっと話がズレるかもしれないけど、僕が「マインドセットって大事だな」と思ったのは、リアル脱出ゲームなんです。今、オンラインでもリアル脱出ゲームができるんですけど。
藤澤氏:
キットを売ってますよね。
 |
松永氏:
キットでやるとアジトに行かないじゃないですか。だからあの雰囲気による導入が無い。そこでじゃあ、リアル脱出ゲームの「マインドセット」の面白さはどこに生まれるのかというと、ZOOMとかでつないだ時に、向こうの係の人が「よーいドン!」って言ってくれる。そこがすべてだったりするんです。
藤澤氏:
たしかに。
松永氏:
でも「よーいドン!」と口で言ってもらうだけですべてが変わるというのは、スゴイことだなと思って。中身は一緒なんですよ。キットの中の問題を解くだけなんです(笑)。自分のスマホで60分を測れば、それでいいんですけど。でも楽しさは180度違うって、スゴイことだなと。
だから、運営している人がいるところで遊ぶことで、ライブ感が生まれるというか。
藤澤氏:
同時性に近いものがうまれますよね。
松永氏:
一回きりの体験を感じさせる時に、「運営型のゲームって全部、一度きりじゃないの?」というのは、そういうことなのかなと思うんです。
 |
藤澤氏:
たしかに。松永さんは「イマーシブシアター」って体験されました?
松永氏:
いえ、行ってないです。行かれました?
藤澤氏:
行きました。お台場でやっている「Venus of TOKYO」という、体験型の演劇なんですけど。やっぱりすごく新しい表現なんですよ。僕らの時代よりも先輩の時代にオペラがミュージカルに変わったみたいに、お芝居の表現も時代によって新しさを求めて、ちょっとずつ試行錯誤されたり淘汰されたりを繰り返すじゃないですか。その中で今出てきた新しい手法なんだなぁ、というのがイマーシブシアターで。
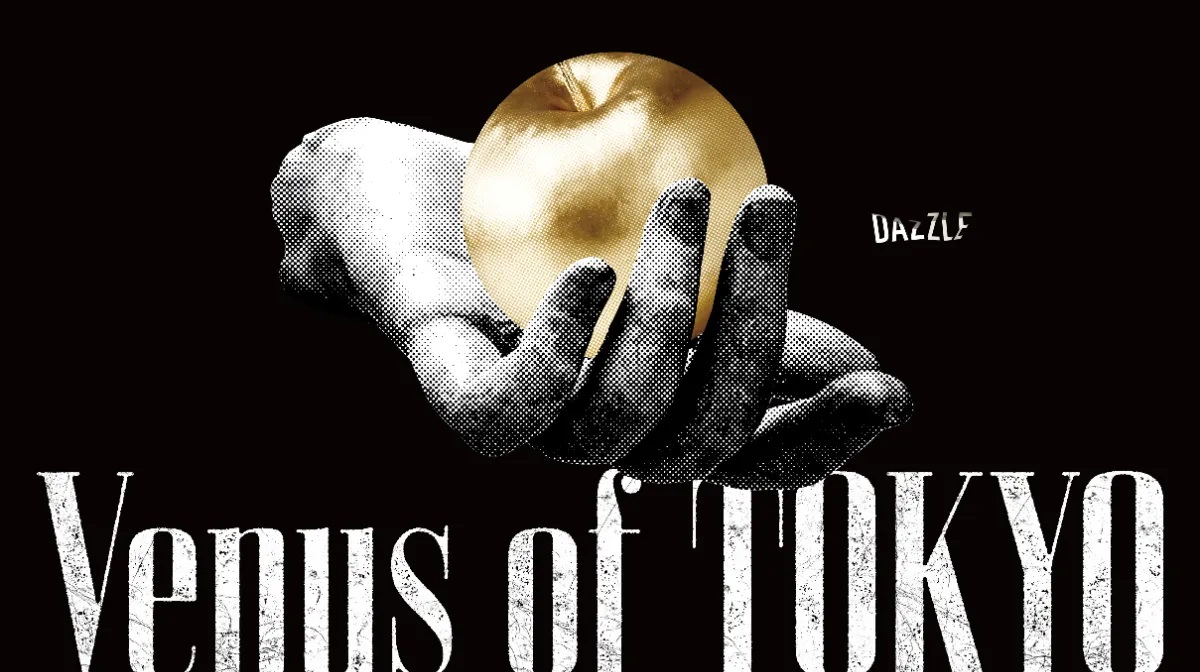
これは同じ芝居を見ていても、人によって見ている場面が違うと捉え方も変わるという試みなんですよ。なので、ぜひ松永さんにも見ていただきたいなと。
特に面白かったのは、さっきのコンサートとか野球の話と同じなんですけど、同じように見ている人が周りにいるというだけで、高揚感が高まるんですよ。だからやっぱり、そこには価値があるのかなと。
松永氏:
それは見たいな。すごくわかります、スポーツ観戦とかライブとかも、楽しみ方って人それぞれ違うじゃないですか。アーティストに何を求めているのか、チームに何を求めているのかというのも違うし、応援する人間としての関わり方も違うし。じつはビールを飲みに来るのが大事な人もいたりとか。でもそんななかで、同じひとつのチームを応援しているのが、すごく素敵だなと思っていて。
藤澤氏:
周りの知らない人とハイタッチしたりしてね(笑)。
松永氏:
あの感覚をストーリーコンテンツやRPGコンテンツで何かできないかなぁって思うんです。
藤澤氏:
それは大きな夢ですよね、本当に。
松永氏:
クライマックスで選択肢を選ぶ理由が人によって違うというのも、それを表現したいと思って。クイズ番組の2択だと、選ぶ理由は「こっちが正解でしょ」って全部一緒じゃないですか。そうじゃなくて、「オレはこう思っているんだけど」という話をしつつも「オレたちはやっぱりこのチームを応援してるよな」という、だからこっちの選択肢を選んだというのが、理想なのかなと。
ビアンカを選んだ人も、その理由はけっこう違っていたと思いますし。
藤澤氏:
ちなみに僕はフローラしか選ばないんですけど(笑)。
一同:
(笑)。
 |
堀井雄二氏の唯一無二のセンスが、『ドラクエ』における選択肢の価値を生んでいる
──ここで話を変えたいなと思うんですけど。ここまでずっとストーリーの話をされてきましたけど、ゲームにおける選択の価値みたいなものを、併せて語れたらいいなと。
先ほどまでのストーリーの話と同じように、昔はゲームにおける選択ってすごくドキドキしたんだけど、今はその価値がかなり薄れてきている。選ぶことの価値、ゲームって本来インタラクティブだよねという価値がなぜ摩耗しているのか、そしてどうやったらそれを取り戻せるんだろうと。
藤澤氏:
僕は今日話したことが、かなりいろんなことの答えになっていると思っていて。物語を読むことの意味づけさえできていれば、どうやら介入感は確保できそうだというのが、今日の大枠の流れじゃないですか。
じゃあ物語における意味づけって、今までは「読むと感動できるよ」みたいなものだったけど、それは人によって感受性が違うから、確実な約束ではない。
抽象的なものに対して人はどんどん興味を失っていくから、物語を読まなくなってしまう。結果的に、介入することに対する興味を失ってしまうから、惰性になっていった。
さっき言ったように物語の意味づけがしっかりしていれば、同じように介入性にも意味が生まれるわけじゃないですか。だから意味づけが、すべての答えではあるんだろうなと。
 |
これは仮にですけど、『シンクロ』も最後の選択でAを選ぶか、Bを選ぶかとなったとして、たとえば中間にある小さな選択肢によっては、Bの選択肢が出なくなるとか。
そうなってくると「途中の選択を間違えたから、オレはもうこっちを選べないんだ!」となって、一個一個の選択肢がものすごい真剣勝負になっていくじゃないですか。それは、そこに意味が付けられているからですよね。だからその意味づけが肝心なのかなと、僕は思ったんです。
松永氏:
さすがです。じつは開発途中の段階で一回、一方の選択肢が消えるというのも試してたんですよ(笑)。
藤澤氏:
なるほど(笑)。
松永氏:
ただ、その場合、途中の緊張感はすごかったんですが、選択肢が消えた状態でラストまで進んでも、ぜんぜん面白くないんですよ。で、これはダメだって。
藤澤氏:
それはたしかに(笑)。
松永氏:
でも藤澤さんがおっしゃるように、途中の選択肢が何かしらの影響を与えているように感じてもらうことがいちばん大事で。だから中だるみせずに読めるように、途中に何を置けるのか、そこから試行錯誤していったんです。
 |
結局、最後に大きなモチベーションがあって、途中の過程もそれに影響しているからこそ、常に油断なく読みたくなるというのが、目指すべき形かなと思っていて。なので、どう進んでも2択はできるけれど、そのコンディションが変わるようになっていったんです。
藤澤氏:
なるほど。意味づけさえしっかりしていさえすれば、プレイヤーは介入に対して積極的に楽しめるものだと思うんですよ。今まではそこを怠っていた部分が大きかったから、どんどん惰性化していったので。
『ドラクエ』も「どうせ“はい“を選んでも“いいえ”を選んでも同じなんでしょ」って思われるし。僕らもたしかに、どっちを選んでも同じ結果にたどり着く分岐をさんざん書いてきたわけなんだけれども。
松永氏:
選択肢は、初期のコンピュータRPGの中でも大きな発明ですよね。ユーザーが自分で選んでいる気持ちになりつつも、進んでいくべき方向にキチンと進ませるという。
──でもゲームにおける主体性って、分岐がなくても担保できると思うんです。選択肢が1個だけでも、場合によってはテキストが表示されるだけでも、没入感が生まれることはあって。
藤澤氏:
パチンコのボタン演出と同じですよね。このボタンを押しても押さなくても大当たりの確率は変わらないし、逆に変わっちゃうと法律違反ですから(笑)。でも押したくなる。
──その意味で言うと、選択肢のあるゲームはいくらでもあるじゃないですか。でもその中で、ビアンカとフローラもそうですけど、『ドラクエ』は選択肢の提示の仕方がオシャレですよね。そのオシャレさって何なんでしょう?
藤澤氏:
それはやっぱり堀井雄二さんのセンスだと思いますよ。
『ドラクエII』でペルポイという、地下にある町が出てくるんですけど。この町の道具屋で商品が売っている中に1行だけ空白があって。その空白を選ぶと「お客さん、誰に聞きました?」って、重要なアイテムを売ってくれるんですよ。
これなんて「カッコイイなぁ、オシャレだなぁ」って、子ども心に思っていたので。こういうのは堀井さんの唯一無二のセンスですよ。
──堀井さんは、小学生が感じるような好奇心を刺激するのが絶妙ですよね。
藤澤氏:
それは堀井さん本人が、会議中にトイレに行って戻ってくると誰もいなくて、ハッと驚くのを見るのを喜ぶとか、そういう今時のYouTuberがやりそうな細かいイタズラを、メチャクチャ仕掛けてくるんですよ。とにかく人をビックリさせるのが好きな人だから。そういう堀井さん自身のサービス精神が、ゲームの中で存分に発揮されているんです。
 |
松永氏:
選択肢の話でいうと、堀井さんが『ドラクエⅠ』のラストに用意された、竜王の選択肢があるじゃないですか。
藤澤氏:
「もしワシの味方になれば、世界の半分をお前にやろう」ですね。
松永氏:
ぼくはあれで「はい」を本当に選んだ人に、じつは会ったことがなくて。
藤澤氏:
僕はたまに会いますよ(笑)。
松永氏:
ホントですか!? というのも、僕は子供の頃、ドラクエはⅡからデビューだったんですけど、「じつはあそこで“はい”を選ぶとゲームオーバーになるんだ」という話が子供のあいだで噂になってて。
だからはじめてドラクエⅡを遊んだ時、ふだんの選択肢にすごい緊張感があったんです(笑)。その後の『ドラクエ』での分岐のない選択肢が、ちゃんとあそこで動機づけがされてるなって。
藤澤氏:
そうですね。
 |
松永氏:
あそこで「はい」を選ぶ人間はほとんどいないというのも把握していて、その上でいちばんインパクトのあることをやっているのがスゴイなと。いちばん最初からちゃんと手を打ってあるというか。
藤澤氏:
だって、コンピュータミステリーアドベンチャーゲームの1作目で、叙述トリックをやる人ですから(笑)。叙述トリックって、いろんなトリックをさんざんやり尽くした最後にやることじゃないですか、普通は。なのに、なんで最初の1個目が叙述トリックなんだろう、という。それが堀井雄二なんですよ。
松永氏:
つねに全振りなんですね。
藤澤氏:
たぶん、当時の小学生や中学生が最初に体験した叙述トリックだと思うんですよね、『ポートピア連続殺人事件』は。
──『ドラクエV』で小学生や中学生に「結婚」について考えさせる人ですからね。
「すぐ手に取れるけど生モノっぽさもある物語」が作れたら、たぶん最強じゃないか
藤澤氏:
スタジオジブリの映画なんて誰もが一度は見たことがあるし、DVDだって多くの人が持っているわけじゃないですか。でもTVでやったら毎回見るし、なんならTwitterで一斉に「バルス!」ってつぶやいたりする。それは結局、「みんなが見ているから」というマジックですよね。みんなと同時に何かをやるのが、みんな好きなんだなって。
──『ラピュタ』の「バルス!」とかは、それがTwitterによって可視化されたことによる効果だと思うんですよ。『ラピュタ』自体はそれまでにもずっとTVで放送されてきたんだけど、それが可視化された瞬間に、こんなに面白くなるんだということが証明された例かなと。
松永氏:
そうですね。可視化されているのは、すごく大事だという気がします。
 |
──藤澤さんは、ご自身の会社名も「ストーリーノート」にするぐらい、物語の力を信じて活動されている方だと思うので。
藤澤氏:
そういう意味ではプロジェクトの起こりって、「こういう体験ができたら面白いよね」という起こり方もあるし、「こういう物語の表現がしたいよね」という起こり方もあるじゃないですか。
そこは半々……もしかしたら若干、物語からの起こりのほうが少ないかもしれないけど。でもけっこうな割合であると思っていて。プロジェクトの起点になりうるものを作れるのが、物語づくりの魅力なんだと思います。なので僕は、物語をやりたいなと。
ディレクターからわざわざシナリオライターに戻る人って、普通はなかなかいないと思うんだけど。でも僕はそこに戻ってでも、もう一回物語を作りたかったという想いが強かったので。そこには特別な想いがありますね。
──逆に、松永さんはなんでそこまで物語に思い入れというか、こだわりがあるんですか?
藤澤氏:
それは聞きたい。
松永氏:
僕の根っこはゲームシステム屋さんなんですけど、だからこそ、ゲームシステムしかないゲームって限界があるなと思っていて。
さっきのスポーツ観戦の話でいうと、野球というスポーツ自体って、ルールであり、要はゲームシステムですよね。でもぜんぜん知らない人たちのプレイを見てても、正直あまり面白くない。選手のバックボーンを知って、その打席にどんなドラマがあるかというのを投影できるかどうかで、楽しさがぜんぜん違うじゃないですか。
どこかの大人と大人がただ球を投げ合っているんじゃなくて、「アイツとアイツにはこんな因縁があって」というのを知ると、ぜんぜん違う。だからどんなゲームも、物語があるから、さらに面白くなれるんだと思ってるんです。
でも逆に難しいと思うのは、その「物語」を実際に体験するのはすごくカロリーがかかるというか。さっきの野球の話でも、選手のバックボーンを詳しく知っていて、それぞれのチームが今年はどんな戦い方をして……みたいなものを全部把握した上で、ひとつの打席がすごく熱いものになるんだけど、それはすごく勉強しないと到達できない。
 |
テーブルトークRPGとかでも、「今回のプレイはものすごかったな!」ってみんなで拍手喝采する瞬間があるんですけど、そこにはものすごいカロリーが必要で。全員にゲームシステムに対する研鑽も必要だし、その上で参加者の相性とかが噛み合って、すごいプレイが生まれるので。
一方で映画とかマンガとか、物語が最初からちゃんと書かれているコンテンツは、そういう大変な苦労をしなくても、誰が見ても2時間ぐらいで感動できる。そう考えた時に、このふたつの間を取れるものはないのかなって考えてしまうんです。
一方的に提供されているコンテンツではなくて、自分なりに読み解いた物語みたいなものが、そんなに苦労しなくても体験できるというのが、理想のゴールなのかなと。「すぐ手に取れるんだけど生モノっぽさもある物語」が作れたら、たぶんそれが最強なんじゃないかと思っていて。
藤澤氏:
そこって本当はグラデーションがあるはずなんだけど、中間を示す言葉がないんですよね。
松永氏:
そうですよね。どちらも「物語」という言葉で指し示しているものなので。自分の場合、そういうものを作ることにすごく興味があるんです。
メールゲームの面白さをいつの日か、もっと手軽な形で復活させたい
松永氏:
藤澤さんと以前話した時に、ユーザーさんが一人称で主人公になる物語、『ドラゴンクエスト』がその王道だと思うんですけど、その一人称体験に今、どれぐらいの価値があるんだろうというのを、以前にした記憶があるんです。自分の中ではそれがすごく大きなテーマになっていて。
映画を見ている時は、自分は主人公ではなくて、用意されている物語をきちんと楽しませてもらいます、という形なんですけど。その一方で『ドラクエ』のように、自分が主人公になってその世界の中に入っていくという体験があって。でもそっちは年々減っているような感じがしていて。
藤澤氏:
減っていますね。
 |
松永氏:
それって本当はものすごく面白いもののはずなのになぁ……というのがずっと、やりたいこととしてあるんですよね。
藤澤氏:
なるほど。それはすごく分かる気がしますね。最初のほうで言った、「観賞」するのか「介入」するのかの真ん中へんですよ。
松永氏:
そうですね。自分は用意された物語の主人公なんだけど、介入もできて、みたいな。
藤澤氏:
実際問題、RPGの歴史を今この時代になって振り返ってみると、ストーリー主体のRPGで自分自身が主人公になれるものって、ほとんどないじゃないですか。それこそ『ドラゴンクエスト』以外にあとは何がある? みたいな話だと思うので。
松永氏:
年々減っていますよね。どうしてもキャラクターも含めて、要素を濃くしていく方向にならざるを得ないんだと思うんです。
藤澤氏:
それが需要と供給の関係でなくなっていったのか、それとも作り手の都合でなくなっていったのかは分からないですけど、ある種の欠落があるのは事実であって。そこを埋めたいという松永さんの気持ちは、僕もすごく共感するというか、分かる気がします。
松永氏:
きっといろんな見方があって、ここは違うんだろうなというのもあるなかで、スマホゲームというものを作って経験を積めたので、この畑の中で何か可能性を提示するとしたら、今回の『シンクロ』のようなものなのかなぁ、と思ってます。だから、いろんな人に遊んでもらって意見をもらいたいんです。
 |
藤澤氏:
ストーリーRPGではなくて、MMORPGとかだと自キャラ=自分じゃないですか。そこらへんの境目がよく分からなくなってきましたね。
僕は『ドラクエ』派か『FF』派かというと、子どもの頃から『ドラクエ』派だったんです。なんでかというと、主人公=自分という視点がほしかったから。
『FF』の主人公は自分じゃなくてキャラクターだ、というところで僕としてはあんまり取っつきが良くなかったんです。でも『FFXI』をやった時に、「めっちゃ『ドラクエ』じゃん」って思ったんですよ(笑)。
松永氏:
自分が主人公になるからですね。
藤澤氏:
そうそう。自分は結局、そこに面白さを感じる人間なんだなって、後から思ったんですよ。
 |
──主人公というよりは、その世界の住人になれるという形ですね。MMORPGだとか、海外のオープンワールドRPGだとかは。
藤澤氏:
急に思い出してきたんですけど、『ドラクエX』のストーリーを企画している時に「主人公が勇者になれない」というのが最初、テーマとしてあったんです。
──それは大勢のプレイヤーが同時に参加する、MMORPGの永遠のテーマですよね。
藤澤氏:
ならそこで、「自分が勇者ではない『ドラゴンクエスト』を勇気を持って作ってみよう」というのが、じつは『ドラクエX』を作り始めた最初の頃の、すごく大事なテーマだったんです。
松永氏:
すごい。きちんとそこをテーマ化して、取り組んでいらっしゃったんですね。
藤澤氏:
それで僕がいた最初のバージョンでは、「勇者の気配を感じるんだけど、姿は出てこない」という。そうやって、匂わせだけをやるというのが『ドラクエX』でしたね。
松永氏:
あくまでプレイヤーはその世界の住人であって。
藤澤氏:
「そういう人がいるらしいぞ」という(笑)。でも『ドラゴンクエスト』で「お前はワン・オブ・ゼムだよ」と言うのは、けっこう勇気が要るというか。
 |
──もともとコンピュータRPGって、自分が勇者になれる世界だったじゃないですか。ところがMMORPGが出てきて、ワン・オブ・ゼムになるんですよ。現実世界でもワン・オブ・ゼムなのに、ゲームの世界でまでワン・オブ・ゼムになるという。
最初は「異世界に行ける」とか「知らない人と出会える」というのが新しかったので、それでも良かったんだけど、ふと気がつくと「なんで現実で仕事をして、家に帰ってきてからもMMORPGで炭鉱を掘ってるんだ!?」という(笑)。
じゃあ何をもってエンタメたり得るのか、という考え方が出てきたのが、2000年代後半ぐらいで。『ドラクエ』がまさにそうですけど、MMORPGにストーリーが乗り始めたり。そのあたりが、MMORPGに対する変化が起きたタイミングなんですよね。
松永氏:
ぼくもだいたい炭鉱夫になるので、MMORPGを勇者になる物語と感じられたことがなくて(笑)。自分は実際にその世界にいるんだけど、自分が大きな物語の主人公でもあって……というのをどう作るか。僕としてはそこに興味があるんですよね。
会社で誰にも受け入れられないんですけど、個人的にはいつか、メールゲーム【※】を大々的に復活させたいんです。
※メールゲーム
郵便を介してプレイするゲーム(PBM: Play By Mail)の一種で、参加者が自分のキャラクターの行動を記した紙を運営元に郵送すると、ゲームマスターからその行動を反映した小説形式の文章が返送されてくるというもの。運営企業によって「ネットゲーム」「ネットワークRPG」など、呼称が異なっている。日本では1990年代に『蓬莱学園の冒険!』『クレギオン』などのタイトルで商業サービスが盛んに行われていた。現在でも電子メールなどに形を変えて運営が行われている。
藤澤氏:
それはあの人(TAITAI)がずっと言ってますよ(笑)。
松永氏:
えっ、そうなんですか!?
──メールゲームではなくて、雑誌の読者参加ゲームの現代版みたいなものをやろうよ、って藤澤さんにはよく話してます(笑)。
藤澤氏:
それが巡り巡って『Project:;COLD』になったんですけど。
松永氏:
そうなんですか! だいぶ巡りましたね(笑)。
僕がメールゲームをやりたいと思うのは、プレイヤーは巨大な世界の一員なんだけど、メールゲームにはゲームマスターがいてくれて、自分が重要な登場人物なんだという形でちゃんとゲームを進行してもらえるからです。本当に理想のゲームだなと思うんですけど。
藤澤氏:
まだやってる人もいますよ、メジャーではないですけど。
松永氏:
もちろん。たださっきの話と同じで、それが手に取りやすい形になっているかとか、そういう理想的な形をもう一回作れないかなと思うんですよね。
 |
藤澤氏:
ウチの会社で求人募集をすると、かなりの確率で、「昔、PBMのマスターをやってました」という人が応募してくるんですよね。そんなに大勢いるのかなと。
松永氏:
『チェンクロ』のメインライターをやってる方も、「昔メールゲームをやってました」と言ってましたね。
藤澤氏:
そうなんですね。ということはやっぱりアレも、何か人間の需要をガッチリと捕まえていた部分があるんですね。
松永氏:
ちゃんと用意された世界とコミュニティで主人公としての体験ができるという意味では、非常に面白い文化だと思うんですけど。
藤澤氏:
あとは、最初のほうで「ゲームのシナリオを読まなくなったのは松永さんのせいだ」と言っておいてアレなんですけど、よく考えたら『ドラクエ』のプレイヤーを勇者でなくしてしまった自分のせいも多少はあるんだろうなと(笑)。なので、僕と松永さんは共犯ということで(笑)。
松永氏:
僕だけが罪を背負わなくて良かったです(笑)。いやでも、そこを改めて引き戻していけばいいんじゃないですか。
藤澤氏:
そういう動きをお互いにしていけるといいですね。(了)
 |
かつて、フィーチャーフォンやスマートフォンといった携帯電話を使ったゲームでは、「長いストーリーを表現できないし、たとえ表現しても読む人間はいない」と思われていた。そこに挑戦したのが、2013年にリリースされた『チェインクロニクル』である。
対談で藤澤氏が指摘しているように、メインストーリーとキャラクター個別のストーリーを分離するという「発明」によって、『チェインクロニクル』はスマホゲームで読み応えのあるストーリーを描き出す新たな時代を切り拓いた。その結果、スマホゲームがどのように変化したのかは、今、多くの人が目にしているとおりだ。
だが一方でこの「発明」は、ゲームにおけるストーリーの位置づけをも変えてしまった。メインストーリーが「当たり前のもの」としてスキップされる一方で、ガチャをはじめとする各種の条件で入手できる個別のストーリーが「ご褒美」として重要視されるという、ある種の格差のようなものすら生まれている。
『シン・クロニクル』は、そんな状況を打破しようとする新たな試みである。対談の中ではコンシューマゲームとの対比で「戻す」という表現が使われているが、実際には「一度きりの物語」や「究極の2択」といった『シンクロ』の特徴と、運営型の形式や他のユーザーとの同時性といったスマホゲームならではの要素が結びつくことで、これまでになかったまた新しい「体験」になるはずだ。
サービスが開始された暁には、今度は『シンクロ』がどのようにRPGを変えるのか、ぜひ自分自身で確かめてもらいたい。


































