『キングダム ハーツ』の敵のバトルシステムを、見よう見まねで組み立てていった若手時代
──専門学校を卒業したあとは、スクウェアに就職されたのですか?
塩川氏:
それが違うんですよ。最初は、小さなゲーム会社に就職したんです。さっき少しお話ししましたけど、専門学校の先輩の手伝いをしていた流れで、そのままそこの会社に入ったのが最初です。1年もいなかったんですけど。
──その会社はなぜ辞めたのですか?
塩川氏:
辞めたというわけではなく、会社がなくなってしまいました(笑)。
──どういう会社だったのですか?
塩川氏:
社員数にしたら10人か、多い時で20人ぐらいだったかな。そんな小さいところでした。そこにはディレクターみたいな人がひとりいて、いわゆる企画職はその人と私だけ、みたいな感じだったんです。
だからいい意味でなんでもやらせてもらいました。仕様書も書きましたし、スクリプトも打ちましたし、イベントシーンも作ればマップの設計もやったり、とにかく手伝いという名目でありとあらゆることをやっていました。その会社自体はすぐなくなってしまいましたけど、「ゲーム作りにはいろんな仕事があるんだな」と知ることができたのは、けっこう良かったなと思いますね。
 |
──小さな会社だからこそ、ゲーム作りの全体を見ることができたということですか?
塩川氏:
そうですね。ゲームがどう作られているのかを、知識じゃなくて自分の作業としてやれたので。「いろんな作業が工程によってぜんぜん違うんだな」というのを、新卒1年目で知れたのはラッキーだったと思います。会社自体がなくなってしまったのはアンラッキーでしたけど(笑)。
──その会社が潰れてから、スクウェアに入社されたのですか?
塩川氏:
そうです。最初が小さい会社だったので、とにかく大きい会社に入ろうと思ったんです。もう会社がなくなるのはイヤだったのもありますし(笑)。
前の会社だとディレクターの人が自分にとっての判断基準のすべてだったので、大きな会社ならいろんな人がいるから、何が業界のスタンダードなのかを学べるんじゃないかと。それで、いろいろと受けさせていただいた中から、当時のスクウェアに入ることになりました。
──スクウェアに入社したのは、何歳ぐらいのことですか?
塩川氏:
21歳のころですね。私が入ったのは、『キングダムハーツ』1作目の開発初期だったんです。企画が立ち上がって初期段階で。そこに私は、バトルプランナーとして参加することになりました。
当時、まだ開発初期の段階でバトルの仕様がほぼない状態から、敵の設計をゼロから担当することになりました。プレイヤー側のことは、バトルプランナーのリーダーの方が作られていました。配属された時には初期に登場する敵のデザインは出来上がっていて、その段階から「あとはよろしく」と、全面的に任せられることとなりました。
さてどうしたものかと。そこから「このゲームにおける、敵とはなんぞや?」というところから考え始めました。
前の会社で多岐にわたる業務を経験していたものの、そこまでバトルに詳しいわけではないので、当時は3Dのアクションゲームだった『ダイナマイト刑事』などを研究して、何コンボで敵は攻撃しているのかとか、モーションがどうなっているとか、他にもいくつかの3Dゲームを見よう見まねで勉強して、「敵とはなんだろう」というのを分析した上で、仕様書に書いていったんです。
 |
こうやって敵が出現して、こうやって移動して攻撃して、こうやってダメージを受けて、こうやって倒されて……と、敵に必要なものを全部洗い出していって。そういう形で徐々に敵のバトルシステムを、イチから組み立てていきました。
──なぜ『ダイナマイト刑事』を参考にしたのですか?
塩川氏:
当時はPS2の初期ですから、3Dゲームと言えばアーケードのほうがまだ、最先端をいっていたんです。360度自由にマップ上を動き回れるアクションRPGを作る上で、参考になる3Dゲームは当時、そんなに数がなくて。だからセガさんの『ダイナマイト刑事』だとか、カプコンさんの『パワーストーン』だとかを特に勉強のためやっていましたね。
──敵のバトルシステムに関しては、当時仕様がない中で、いったい何にフォーカスして考え始めるんですか?
塩川氏:
敵って、言い換えると「やられ役」じゃないですか。なので「いかにいい感じにやられるか」ということをすごく考えました。
敵といっても、ただ適当に歩き回っていて、一方的にバシバシ攻撃されていればいいかというと、そんなことはなくて。「ほら、ここだよ」と、攻撃できそうなタイミングで隙を作ったところをプレイヤーが攻撃することで、達成感を感じられるんです。
あるいは、1、2の3とコンボがつながって、「3」で敵が吹き飛ぶところに達成感を感じるから、1、2のリアクションは抑えめにしなきゃいけないとか。そういうことをいろいろと考えるんです。
「敵がどのように登場するか」というシステムも考えました。プレイヤーが歩いてきた時に、どこで敵がボンと出ればいいのか、今で言うところのレベルデザインみたいな話ですけど。
敵が目の前に出てくると、プレイヤーはビックリするけど、そうするとプレイヤー側の対処する時間が足りなさすぎる。このぐらいの間隔で出てくると、プレイヤーはまず驚いて、それから「じゃあどうする?」みたいな対応が取れる、とか。そんな感じで、どうすればやられ役として美しくなるか、みたいなことを当時はひたすら考えていましたね。
──そういったことを考えるにあたって、誰かから教わったりしたのですか?
塩川氏:
教わるというより、見て学んでいました。当時の私の上長であるプランニングチームのリーダーの方が、本当に優秀な方で、この人の考えや一挙手一投足を盗んで学ぶしかないなと思いました。なので、リーダーの方が書いた仕様書を、一生懸命読み込んで。
そこに書かれている企画の中身についてはもちろんですけど、「こういうことも仕様書で決めなきゃいけないんだ」とか、「これも決めないとプログラマーが困る」みたいなことも勉強になりました。自分の若い頃の上司が優秀な方だったというのは、すごくラッキーでしたね。そこから見よう見まねで、ゲームシステムの組み立て方や、アクションの組み立て方を勉強できたので。
──先輩の言うことって、最初は感心するばかりだと思うんですけど、だんだんと先輩の考えに違和感を覚えたり、自分の考えが出てくるタイミングがあると思うんです。そこはどうでしたか?
塩川氏:
それもありましたね。自分の直接的な上司はひとりでしたけど、大きなプロジェクトでしたから、企画の中でもいくつもセクションが分かれていたりしてチームにはリーダーが何人もいました。当時、自分は20代前半でしたけど、チームには30代中盤とか後半の、それまでに有名タイトルに関わっていた方も大勢いらっしゃいました。
業界内のプランナーの中には、けっこう感覚でやられている方もいます。たとえば「このぐらいにしましょう」と言われても、“このぐらい”とはなんなのかの感覚を理解するのは難しくて。そういう人もいる一方で、「こういうことをすると処理がループして破綻するから、こうしておかないとダメだよ」と、客観的事象を元に本当に理に適った説明をする方もいて。
いろんな方々の仕事のやり方を見てきた中で、その時に思ったのは、「人に説明できるレベルまで自分でちゃんと考え抜かなければいけない」ということですね。「これがなぜ必要なのか?」と聞かれた時に「これとこれがこうなるから必要なんだ」と説明できるようにならないといけない、ということを学びました。
 |
──今現在の若手クリエイターを見ていて、それができている人はいますか?
塩川氏:
最初からできる人は多くはありませんが、できていない人も言ったら気づいてくれる、という感じですかね。「これはなんで必要なの?」と質問して掘り下げていくと、しっかりと考えた上で「じつはこうなんです」と言える人と、まったく答えられない人とに分かれます。
理由が出てくるようなら、「あるならそれをまず書いて」と伝えます。答えられない人は「とりあえず何かやらなきゃいけないから出しました、みたいな明確な考えがない場合が多く、そういった場合は私のほうから「それはただ案が書かれてあるだけで、理由がないから、まず理由を説明できるようにしてきて」と指摘して、必要性と意味を考えてもらいます。
──本人は確信を持ってAというやり方を選んでいるんだけど、その理由を持っていないこともけっこうあるじゃないですか。その場合はどうしているのですか?
塩川氏:
その場合も、聞いていくと何かが出てくるんですよ。「どうしてもAがいいんです」と言うから、「Aの何がいいの?」というのを繰り返しヒアリングしたり、Aがいい理由をとりあえずなんでもいいからホワイトボードに書かせてみたりします。
Aがいい理由を5個出してみて、Bがダメな理由も5個出してみて、というような感じで。ゲームの重要な根幹となる部分に関しては、そのようにクリエイターの考えを引き出して整理したりと、丁寧にやりとりをしていますね。
結局、私を相手に説明するぶんには「Aがいいんです」でもいいかもしれないけど、あと20人にそれを説明する場合には、全員がそれを解ってくれるものでもないですから。大事なことに関しては言語化できるように、しっかり掘り下げさせるようにはしていますね。
 |
──ものづくりの過程で、いわゆる“感覚”で選ぶ時があるじゃないですか。さっきのベテランの方が「このぐらいにしましょう」というのも、それが経験に基づいて出てきたものであれば、かなりの確率で正しかったりすると思うんです。でも、それって言語化されてないですよね、という話であって。
「言語化する」というのは、頭でっかちで作るということではなくて、内にある「なんかいい」と感じているものを、言葉として具体的にアウトプットさせることだと思うんです。でも、それを実体験としてやったことのある人って、じつはそんなに多くないんじゃないか、と思うんです。でも、塩川さんの言葉にはそうしたアウトプットがあるんですよね。
塩川氏:
それは環境から生まれた結果でしかないところも、ちょっとあって。私自身も、最初からそういうコミュニケーションができていたかというと、そんなことはないんですよ。
私は2009年から2014年まで、北米のゲーム開発会社に出向していたんです。この時にある種のカルチャーショックみたいな感じで、自分のゲーム開発者としての視点が塗り替えられました。自分が体験した北米の開発現場では感覚ではなくて、すべてを事象ベースで説明するようになっていたんです。そうじゃないと伝わらなかったので。
たとえば、これは翻訳の問題ではなくて考え方の問題であることを表す一例ですが、ゲームを作っていく中でよく「爽快感」という単語を使うことがあります。これが北米ではまったく通用しなかったんです。
日本だと「こうしたほうが爽快感あるでしょ」みたいなことを普通に言っていたんですけど、私が働いていた北米の開発現場では、まったく通用しなくて。翻訳する人も「なんて言えばいいのか分からない」と。
これは、「曖昧な表現を排除しないと他人には伝わらない」ということを象徴する話なのではないかなと思います。「こうしたほうが爽快感ある」ではなくて、「こういう行動を取ると、敵キャラクターのリアクションが大きくなって、プレイヤーは大きな手応えを感じる」などと言わなくてはいけない。
理由を説明するとか、物事を適切に伝えるということを私が意識するようになったのは、北米の開発現場に5年間いたことが大きいですね。
25歳で『ディシディア ファイナルファンタジー』のディレクターに抜擢
──アメリカへ行く話の前に、『キングダム ハーツ』の開発の話の続きを聞かせてください。『キングダム ハーツ』の開発はどれぐらいの間、携わられたのですか?
塩川氏:
最初期からリリースするまでですね。それが終わって、海外版とかをやった後に『キングダム ハーツII』に携わって。それが終わりかけのころから『ディシディア ファイナルファンタジー』【※】の準備をやっていました。
※『ディシディア ファイナルファンタジー』
スクウェア・エニックスから2008年に発売された、PSP用対戦アクションゲーム。『FF』20周年記念タイトルであり、歴代の『ファイナルファンタジー』に登場するキャラクターたちが光と闇の陣営に分かれて、1対1で対決する。本作を1作目として、PSPの続編やアーケードの対戦ゲームなど、『DISSIDIA』としてのシリーズ展開も行われている。

──『ディシディア ファイナルファンタジー』の中での塩川さんの役割は?
塩川氏:
私は開発の立ち上げからリリースの直前ぐらいまで、ディレクターをしていました。最終的にはディレクターを別の方にバトンタッチすることになったんですけど、企画がゼロの状態から、開発期間全体の9割ぐらいの間ディレクターをしていた感じですね。
──当時25歳ぐらいですよね? それでディレクターに抜擢されたわけですか。
塩川氏:
当時のスクウェア・エニックスで、同年代のディレクターはたぶん一人もいなかったかと思うので、異例のことだったのかなとは思います。
当時の私は、ディレクターはおろかリーダーの経験すらなかったので、自分がディレクターをやるという気持ちはありませんでした。それがある日声をかけられて、ディレクターを任命されて。最初は理解が追い付かなくて「あっ、そうですか……」と(笑)。
──『ディシディア ファイナルファンタジー』の企画のベースとしては、『キングダム ハーツ』で作ったエンジンだとか、そういったものがあったんですか?
塩川氏:
実際にゲームを作るにあたっては、ハードも違いますし、ゼロから作ってはいます。ただ、ノウハウは活きていましたね。特に3Dのリアルタイムアクションの知見がすごく活きたゲームだったと思います。
 |
──塩川さんを含めた若手のスタッフというのは、どんな方が?
塩川氏:
最初期は職種でいうと、私を含めてプランナー、3Dデザイナー、プログラマーがいました。
──そのメンバーは若手スタッフの中でリーダーシップがあった人達だったのですか?
塩川氏:
リーダーシップがあったかはわかりませんが、全員良くも悪くも目立っていたのではないかと思います。
──塩川さんはその中のリーダー格みたいな感じだったのですか?
塩川氏:
ではなかったんです(笑)。基本的には同世代ですけど、年齢的にもたぶん私がいちばん若かったですから。
──今は若い時代にディレクターという立場になることが難しいですけど、当時もそんなに簡単ではなかったはずで。塩川さんのお話を聞いていると、「純粋にポジションを勝ち取ったんだな」と思いました。
他の方だと「会社がヤバそう」とか「先輩が全部辞めちゃった」とか、「会社側の都合で他にやる人がいないから」みたいな形で若い時代にディレクターになった方も多いんですけど、塩川さんの場合は正攻法ですね。
塩川氏:
「やりたいです」と手を挙げて、やらせてもらったという意味ではそうかもしれません。
アメリカに渡って、ロジックを簡潔に説明できないと理解されないことに衝撃を受けた
──『ディシディア ファイナルファンタジー』のあと、アメリカに行かれたのですか?
塩川氏:
その後は日本でしばらく、Flashのゲームだとか、Xbox LIVEアーケードのゲームだとか、そういう小規模のゲームを自分で企画したり手伝ったりしていました。その当時、2008年ぐらいというのは、世界的にはXbox 360やPS3が全盛で、日本はニンテンドーDSのゲームがメインという状況でした。「海外のゲーム開発がスゴイ」といううねりが日本に来ていた、まさにそういう時期だったんです。
業界全体でどうやってこの海外から押し寄せるビッグウェーブに乗るかというのが課題としてあったと思うんです。そんな状況の中で、海外の知見を増やすためのプロジェクトが何個かあって、その中で“海外でゲームを作る”というプロジェクトに挑戦してみないか。と声をかけていただいたんです。
──それは当時、すごく前向きな話として受け取ったのですか? お話だけを聞くとなんとなく「先の見えないプロジェクトに投入されてるな」という感じを受けるんですが……。
塩川氏:
そういう側面もありますね。明日をも知れない取り組みでしたので。ただ当時の自分の心境としては、「人生の中でいつか海外で働く機会があるといいな」ぐらいにはぼんやり思っていたんです。それは普通に若者が抱くただの憧れ的なものでしかなかったけど。
そこにある日「どう?」と声をかけていただいたので、あまり迷うことなく「はい、やります」と返事をしました。
──それで2009年に、北米の開発会社に出向されたわけですけど、行ってみてどうでしたか?
塩川氏:
カルチャーショックの連続でしたね。通用したこともあれば、通用しないこともいっぱいありました。先ほどのコミュニケーションの話もそうですけど、いろんなバックグラウンドを持っている人たちが、あちこちから集まっているので、「あ・うんの呼吸」みたいなものも通用しませんでした。誰にでも分かるように簡潔に、そしてロジックも理解できるようにしゃべらないと、そもそもコミュニケーションが成り立たないんですよ。
一方で、そんな彼らにとっての“共通言語“がいくつかあるんです。それはUnreal Engineをはじめとするゲームエンジンだったり、あとは本だけじゃなくYouTubeのチュートリアル動画のようなものも含めて、とにかく技法や用語が“共通言語”になっていました。欧米は日本と比較すると転職社会ですから、それを“共通言語”にして、いろんなスタジオを渡り歩いていくわけなんです。
 |
それまでに日本で10年ぐらいゲーム開発をやってきましたけど、そういうのを目の当たりにして、こんなことはぜんぜんなかったなと。系統立てて技法を学ぶ機会もなかったし、用語なんてゲームやプロジェクトが変われば、みんなバラバラでしたから。
その時に、「欧米のゲーム開発はこの“共通言語”によって下駄を履いている」ということに気づいて、「これはどうにかしなきゃいけない」と思いました。それで、ゲームデザインの専門書を日本語に翻訳することに興味を持ったんです。
──ちなみに、逆にアメリカでも通用したのは、どういうところですか?
塩川氏:
通用したのは、ゲームの本質的なロジックの部分です。たとえば、プレイヤーがA地点からB地点に行くとして、それをどうやってゲームにするかというのは、アメリカでも同じでしたね。まずプレイヤーにA地点からB地点に行きたいと思わせて、次に行くためのルートを気づかせて、その道中で妨害するための敵を出して、みたいな。
私はよく「人が何を面白いと思うかは万国共通だ」という言い方をしているんですけど。人間が何にモチベーションを感じたり、どういうことに達成感を覚えたりするのかというのは、国籍に関係なく共通なんだなというのは、大きな学びでした。そこは通用するんです。
一方で、程度に関しては差がありますね。たとえば、RPGのシステムの複雑さの程度など、日本のユーザーだとけっこう複雑でも理解できるんですけど、アメリカのユーザーだと理解してもらえるのは少し限られたユーザーだったりとか、そういった比重は国や文化によってそれぞれ違ったりするんです。
けれど、「人間が何を面白いと思うのか」は、脳の仕組み的に決まっていることなので、国とか宗教とか文化にはあんまり影響されないんだなというのが、通用することとして学んだ部分ですね。
 |
──仕事をする上では、いわば「説明コスト」みたいなものがけっこう重要だなと思っているんです。素地とかバックボーンがぜんぜん違っている人が集まっている会社だと、何かをする時に説明コストが膨大になるじゃないですか。そしていわゆる“大会社”って、そういう組織になっていきやすいものだとも思うんです。
たとえばゲームが好きな人間が集まっている編集部だと、「これっていいよね」という説明コストがめちゃくちゃ低いんです。共通のバックボーンがあるので、まさに“あ・うんの呼吸”で伝わる。その説明コストをたとえば10とすると、大会社の他の部署で同じことを説明する際には、説明コストが100ぐらいに跳ね上がるんです。
北米のゲーム会社だと、人種なんかも違うし、さらにバックボーンも違う人たちが集まって作っている。ハリウッド映画とかもそうだと思うんですけど、そういうバックボーンが違う人たちの中で、良いものを作るためのある種のマネジメントのやり方があるんだろうなと。
私はそれが北米の強みでもある一方で、島国である程度固まった人たちで仕事をする日本の説明コストの少なさというのは、たとえば任天堂とかの作り方を見ていると、それをすごく活かしているようにも思えるんです。
塩川氏:
私の場合、10年ぐらい日本でゲームを開発して、日本でもディレクターをやって、海外でもディレクターをやって。それで今に至っているので、日本と欧米の両方を分かった上で、自分としては良いトコ取りをするよう心がけています。
欧米のやり方には良い点も悪い点もあるし、日本のやり方にだって良い点も悪い点もある。どっちの優劣ではなくて、それぞれに良いポイントがあると思うので、帰国してからはその両方を活かそうと思ってやっています。
欧米のゲーム開発における戦い方には大きく分けてふたつの傾向があります。ひとつは「物量戦」です。かけられるコストの高いほうが勝つというのが、けっこう明確なんです。なぜなら正解が決まっているので、正解に対してより早く、より多く向かえる人が勝ちやすい。
もうひとつは、それこそスティーブ・ジョブズ氏のような一部の「天才的なクリエイターの存在が、全体を大きく引き上げる」という傾向です。下駄の履き方がしっかりしているので、そこにスゴイ人が加わると、かけ算になって飛躍的に跳ね上がる。
ただ、そういう人が大勢いるわけではないので、基本的にはそこそこ良くできているけれど、それ以上でも以下でもないゲームが生まれがちですが、それだけだとどうしても物量戦で積み上げてきている側に勝てないので徐々に淘汰されていく構造になっているように思います。
家庭用のゲームだと、そうやって積み上げてられきたノウハウが多いタイトルやスタジオがずっと生き残っているんです。それって要するに、他が1タイトルでかけているコストを、10タイトルぐらいかけて積み上げているわけじゃないですか。そうすると積み上がっていくものがどんどん高くなって、他からは手が届かなくなって、結局はかけられる物量の大きい人が勝つ世界になっている。それを良しとするかどうかは解釈の分かれるところですけど、構造としてはそうなっているので。
じゃあその同じやり方を日本でやるのか? となったら、同じやり方をできるところは勝つかもしれない。だけど、それだけの蓄積とコストをかけられるところは限られているので、そのままのやり方では難しいですよね。
──今からその積み上げをやれと言われても、しんどいですよね。
塩川氏:
欧米のやり方には、見習うべきと思う点はありました。特に、働く時間が短いところとか。
日本のゲーム会社というか日本人は、昨今はいろんなご時世もあるから変わってきましたけど、自分の若い頃とかは単純に働く時間が長くなりがちでした。北米では文字通り9時5時の世界でしたから。「なんで9時5時で働く人たちが、こんなスゴイものを作れるのか、その謎はどこにあるんだろう?」とずっと考えていたんです。
 |
日本人に比べるとアメリカ人の労働時間は明らかに短いにも関わらず、2010年前後の北米からは、ものすごいAAAタイトルがたくさん出てきていた。これはなんでだろうと考えたら、結局は“下駄の履き方”なんですよ。
先ほどお話した“共通の言語”で下駄を履いていているクリエイターがいる上で、かつ物量をかけていて、さらに一部の優れた人間が、かけ算で跳ね上げさせている。その構図で世界は成り立っているんだというのを目の当たりにして、「日本では同じやり方は難しいだろうな」と感じました。
欧米のゲーム開発が「下駄を履いている」ノウハウを、日本に伝えるために監訳や講演を始めた
──「下駄を履いている」というのはどういうことなのか、もう少し詳しく伺いたいのですが。ざっくりいえば、「ノウハウが情報として共有されていて、それが下支えしているから強いんだ」みたいなことでしょうか?
塩川氏:
それも一部だと思います。他の例で言うと、たとえばFPSって、ある程度ゲームのメカニクスが決まっているじゃないですか。もちろん、その中でゲームごとの特性はありますし、クオリティの差とかいろいろあるんですが、基本的なフォーマットは決まっている。
そのフォーマットの上で、どうゲームを作るかを考えるわけですよね。一方で、日本でゲームを作る時には「じゃあゲームシステムはどうするか」と、そこからスタートすることが多いと思うんです。
ゲーム作りでは、べつにゲームシステムをゼロから発明することだけが正義ではないと思うんです。もちろんオリジナリティだったり作家性だったり、そういう部分は当然、評価されるところでもあるんですけど。一方で海外では、「すでに完成しているゲームシステム、ゲームメカニクスを活用して、そこからどういうゲームを作るか」という作り方や考え方を目の当たりにすることが多くて。
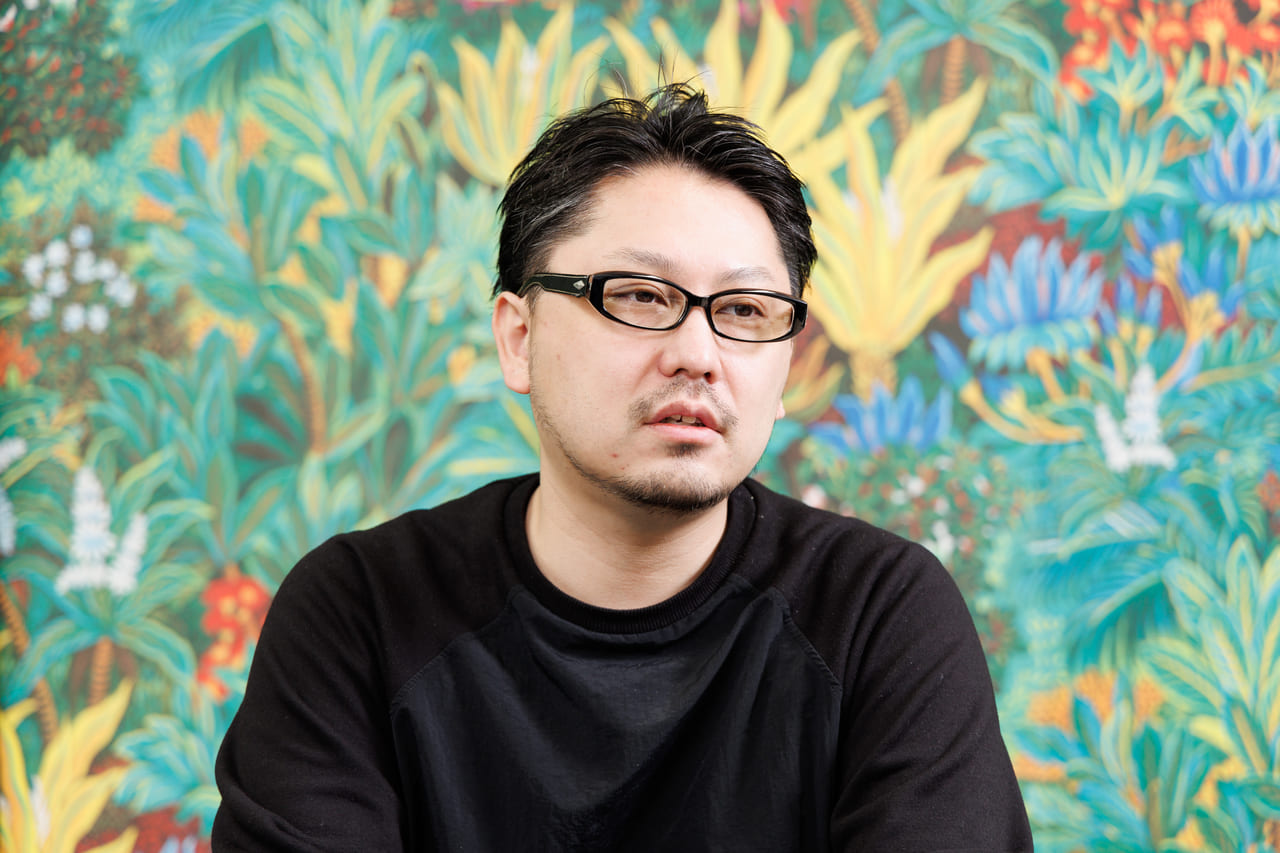 |
それはゲームシステムの話だけではなくて、ゲームエンジンもそうですし、その開発者がこれまでにやってきたことなど、いろんなもので下駄を履いた上で、力を入れるべきところに力を入れていく。それは物量かもしれないし、グラフィックのクオリティかもしれないし、世界観かもしれないですけど、この力の配分をすごく上手くやっているんです。
「FPSはこういうものだから」というので8割のところまでやった上で、残りの2割でどう勝負して、どう跳ねさせるか。そういうやり方が開発のプロセスや、ゲームのメカニクス、アセット、ゲームエンジンなど、いろんなところで当たり前のように浸透していました。
こういう部分について、私は「下駄の履き方が上手いな」と感じていました。それをそのまま転用することが正解かどうかはさておき、やり方のひとつとして上手いやり方だなと、感心した記憶があります。
──なるほど。アメリカに行ってカルチャーショックを受けて、専門書を監訳するところまでいったわけですけど。それは塩川さん自身が向こうに行って、いろんな本を読むようになったということですか?
塩川氏:
もちろん日本にいた時も、ゲームデザインやゲーム企画の本を買ったり見たりはしていたんですけど、当時だとその質や量がぜんぜん違いました。それこそプログラムやグラフィックの本は日本にもいっぱいありましたけど、ゲームデザインの本は日本では少なくて。
ところが北米の本屋に行ったらその類の本がいっぱいあって、「どうなってるんだ、これは!」と思ったんです。本の量だけがすべてではないにしても、これだけ選択肢があって、しかも実際に働いているスタッフの机に置いてあるわけですよ。「こういう環境って日本で見たことないな」と思いました。そこから「この人たちはどんな本を読んでいるんだろう?」と興味を持ち始めたんです。
──とはいえ、そこから「本を訳さなきゃ」と思うのは、また大きな開きがあると思うんですけど(笑)。
塩川氏:
たしかに、めちゃくちゃ飛んでますね(笑)。
 |
──自分自身の仕事だけ見たら、そこまでやることってあんまり関係ないじゃないですか。そこでなぜ、本を訳そうと思ったんだろうなと。
塩川氏:
それにはふたつ理由があって。ひとつ目は単純に、自分自身の英語の勉強だというのがありました。本を読んで分かったふうになるのは簡単ですけど、出力できないと、本当に分かっているかどうか分からないので。あとは仕事にすることで、ちゃんと理解しなきゃいけないという強制力もありますし。
もうひとつの理由としては、自分なんかが偉そうに考えることではなかったんですけど、北米の現地で働いていた中で、当時は日本のゲーム業界に対する危機感みたいなものを、ものすごく感じていたんです。PS2の頃ぐらいまでは、日本のゲームが世界を圧倒していたわけですよね。それが今、この状態で大丈夫なのかという危機感があって。
それに対して自分なりに何かできることがあるのか、というのを当時、すごく考えていました。講演をやり始めたのも2010年からなんですけど、ちょうど同じ時期なんです。
当時、日本と海外の両方で、それなりの規模のタイトルをディレクションした経験のある人間はそんなに存在していなかったはずなので、自分が恵まれてそういう立場を与えていただいたからには、日本のゲーム業界に対して恩返しというか、何か役に立てることはないのかと考えて、まずは講演をやり始めたんです。
専門書の監訳も同じで、当時は日本の業界内の情報交換や交流は非常に限られており勉強できる教材もない中で、これでは勝負に勝てるわけがないと。そんなふうに当時、業界の片隅に身を置く自分なりの危機感を感じていたかもしれないですね。
──「講演を行うようになった」というのは?
塩川氏:
2010年にCEDECで、「はじめての日米共同開発〜日米両国でディレクション経験をして得た、たくさんの気づき〜」という講演を行いました。それが人生で、初めて登壇した機会でした。
──それはどのような講演だったのですか?
塩川氏:
ひとつ例をお話しすると、たとえば北米の開発現場では「アートバイブル」というものを作っています。「アートバイブル」は、このゲームで使う色はコレで、フォントはコレで、線の描き方はこうで、みたいなのを全部、マニュアルとして書くんです。
さっきの“共通言語”と同じ話なんですけど、「これがカッコイイとアートディレクターが決めました」では成り立たないので、どういうものなのか全部マニュアル化するんです。当時私が日本でゲームを開発している時には、そういったものは見たことも聞いたこともなかったんです。今は日本でもやってるところもあるのかもしれないですけど。
でも論理的に考えたら当たり前のことで、大量生産するにはマニュアルがあったほうがいいに決まっていますよね。その当時の日本の開発現場だと、リーダーが全部チェックして、リーダーの職人感覚に任せていることが多かったように思います。でも同じ時代に、欧米の開発現場ではそれが全部、「このゲームで使っていいアートについて」という分厚い書類になっているわけです。そりゃ外部の方に発注するときもすぐに伝わるし、人が流動的に入れ替わってもすぐ仕事ができますよね。
この「アートバイブル」もさっきの下駄の履き方のひとつですけど、北米ではそういうことがそこかしこにありました。「そりゃ9時5時で帰ってもできるよね」と(笑)。
 |
──そういう危機感について、誰かと話し合ったりはしたのですか?
塩川氏:
身近な人とは話しましたけど、なかなか伝わらないことも多かったです。また、当時はちょっとでも欧米の話をしようものなら、「欧米かぶれだ」みたいな感じに揶揄されるような、妙な空気もあったように感じましたし。
──わかります。
塩川氏:
日本は日本で、ニンテンドーDSのゲームがとても盛り上がっていましたから。私の感じていた危機感は共感されにくく、「洋ゲーの話ね、ふうん」みたいな反応が多かったです。 あの頃、他人に説得力を持って伝えるというのは、環境的にも難しかったし、自分もまだ若くて何の実績もなかったですから、耳を傾けるような人もいなかったですし。
──海外と日本の話は、今では決着がついちゃっているところもあって。でも一方では、2017年に『ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド』がその年のゲーム・オブ・ザ・イヤーを取って、2019年に『SEKIRO: SHADOWS DIE TWICE』が取ってと、日本のゲームの再評価があったじゃないですか。それで言うと、2010年ぐらいに危機感を抱いていた塩川さんが、今はどう思っているのかが気になります。


塩川氏:
私自身はもう危機感を前面に持ってはいないですけど、状況自体は悪くなっているなと思っていて。任天堂さんやフロム・ソフトウェアさんなど、いくつかそうやって戦えるところは残っているんですけど、逆にそのいくつかの企業しか残っていないのではないかと感じています。今から10年前ぐらいでは、戦えそうな会社やスタジオがもうちょっとあった気もしますが。
さっきの欧米の話に絡めての話になりますけど、ここまでずっと話をしていたのは、家庭用ゲームの話ですよね。じゃあ今、スマートフォンのゲームはどうかというと、比較対象はおもにアジア圏にあると思っています。
中国がメインに担っていくと思うんですけど、クオリティの高い、大きな規模のタイトルを、そんなに大きな会社じゃないところもたくさん出してきている。今は日本と中国が、スマートフォンのゲーム市場で競合しているような構図になっていて、私の感覚だとこれは前に家庭用ゲームでの日本と欧米の構図で一度経験したなと感じています。
──しかも、ここでもやっぱりスケールの差で負けている。
塩川氏:
そうですね。スピードであったり物量であったりの競争になっているところも、「これ見たことあるぞ」と。だから自分的には、二巡目の感覚ですね。

































