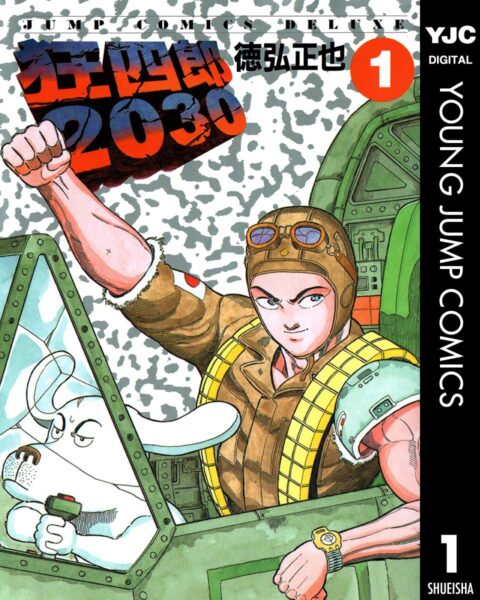『ONE PIECE』考察と陰謀論は似ている?点と点を繋ぐ楽しさと危険性、それを俯瞰しているからこそ、「フィクションと謳った上でそういったものに勝ちたいと思っています」
──考察文化に対する欲求みたいなものが、昨今のブームの原因のひとつにあるというお話でした。一方で、インターネットにある『ONE PIECE』考察や、『HUNTER×HUNTER』考察みたいなものって、根拠がないものを言いたい放題しているフォーマットだという風にも感じます。
大森氏:
わかります。それってすごく陰謀論的ですよね。
──陰謀論、まさにそうです。そういった考察に対するニーズと、陰謀論的なものに対するニーズというのは、非常に近いところにあると思うのですが。
大森氏:
僕もまさにその認識をしています。なんなら僕は「考察」という言葉は本当に無くなってしまった方がいいとさえ思っていて。そういったさまざまなものが「考察」という言葉で一括りにされてしまっているのが非常にややこしいんですよ。
例えば、作品の中で起きている事象の間の部分、説明されない空白のストーリーを想像して、不気味になったり、感情を動かされるというのは、ホラーに限らず、映画などでも妥当な楽しみ方だと思います。
ただそれとは違って、「このシーンだけ登場人物の瞬きの回数が多いから、こういうサインになっているんだ」とか、「背景に一瞬映りこんだ物品にはこういう隠された意味があるんだ」というのは、「バイデン大統領の首のシワが怪しいから、彼はゴム人間に違いない」というのとあまりに近すぎるというか。
──たしかに。ホラーというジャンルだと特に、そういった見方をされてしまいがちかもしれません。
大森氏:
これは考察という言葉が独り歩きした、考察ブームの功罪でもあるとは思うのですが、いま最前線で「考察」って言われているものには、あまりに陰謀論的なものが多すぎると思っているんです。
だから僕は、こういったインタビューを受ける際には「僕の作品は『考察もの』ではありません」と積極的に言うようにしています。
だから『ONE PIECE』の考察も、過去の時系列を整理して、「次はこういうストーリーになるんじゃないか」と想像するのと、「このシーンのこのコマには、こういう隠された意味があるんだ」と考えるのはかなり別物だと思いますね。
後者のような、ロジックを無理やり形成するための、考察自体が目的になっているような考察にはかなり怖さを感じます。
──梨さんはいかがでしょうか。「考察」という言葉に対して、分類のようなものはあると思いますか?
梨氏:
大森さんの話は「考察」という行為自体のなかに種類が分かれている、というものでしたが、考察をする人、受け取る人の層にも違いがあると思っていて。
『ONE PIECE』の例で言うと、「シャンクス複数人説」という、典型的なヨタ考察がありますよね。「シャンクス」というキャラの名前は複数系で、単数形が「シャンク」だというものです。
あれを普通にヨタとして楽しんでいる人というのは、つまるところフェイクドキュメンタリーをフェイクとして楽しんでる層だと思うんです。
一方でそういったものを「そうだったんだ、真実に目覚めさせてくれてありがとう」と言って信じ込んでいる層というのもいるかもしれないじゃないですか。
どちらの層も見ているものは同じなんだけど、見ている人によって文脈が変わってくるというのも、「考察」の難しいところだと思います。
──そういった危険性がありながらも、「ONE PIECE」考察のようなものはかなり人気のコンテンツですよね。陰謀論も、それ自体がハマりやすい構造になっているように思います。見る側が強引にロジックを繋げているコンテンツなので、各々が勝手に妄想した内容が集合体としての強度を持つというか。この仕組み自体は強固なもので、梨さんだったらエンタメ作品で似たようなことができるんじゃないでしょうか(笑)。
梨氏:
やれるとおもいます(笑)。シェアードワールド的な楽しみ方ということですよね。
同じ世界という大きな水槽の中をシェアしていて、そこから取り出すものが場所によって違うから、結果として群像的に見せられるという。
──そういったコンテンツの構造自体は、拡散性や「ハマりやすさ」といった点で強味があると思います。
梨氏:
当時私は中学生くらいでしたが、『艦隊これくしょん -艦これ-』って爆発的に流行りましたよね。スマホ時代になってからは『Fate/Grand Order』や、最近では『ウマ娘 プリティーダービー』がすごく人気です。
こういった作品たちって、「歴史」というとんでもなく大きい文脈があって、そこに乗っかれるという強さがあると思います。
ただのエモいストーリーじゃなくて、元々のエモい文脈がある上でのエモいストーリーというか。それってコンテンツを作る上では非常にありがたい構造ですよね。シェアードワールドというのはそこをイチから作るという試みだと思います。
──そういった意味では、そういった作品は歴史的な事実の二次創作フィクションという考え方になりますよね。そこを現代化したときに、例えば「フェイクニュースを本当にエンタメ化する」といった作品は、非常に危険性の高いものですが、誰も挑んでいない領域なんじゃないでしょうか。
大森氏:
陰謀論の気持ち良さみたいなものって、点と点の繋がりを自分で見つけたと思えちゃうせいなんですよね。実際にはたくさん導線が引かれているんですが、「こことここは繋がっていたんだ!」というものをなぜか自分で見つけたと思えてしまうんです。
だから、現代的なシェアードワールドのコンテンツというのがあるとしたら、全く違う媒体で同時多発的にコンテンツが発表されて、どこかでそれらの繋がりを気づかせる、といったものになると思います。
──そういったギリギリをついた「真実に気づく」ようなコンテンツが、これから先の将来に生まれる可能性があるとして、一方で今のフェイクドキュメンタリーは「フィクションです」と謳った上で流行していますね。
大森氏:
それで言うと、ただバズりを狙うだけなら、「フィクションです」と言わない方がバズると思っています。ただ、今話していた陰謀論のような危険性もあるし、そういった倫理の問題でフィクションだと宣言するようになってきているというのも、今のホラー界隈にはあると思います。
──ここまで話した通り、陰謀論的なものの気持ち良さや構造の強さは明白です。もしその倫理のラインを踏み越えてしまった作品が出てきたときには、それが覇権をとってしまうんじゃないか、という危機感もあります。
大森氏:
だから僕は、フィクションと謳った上で陰謀論に勝ちたいと思っています。
そういう倫理が崩壊してしまったらいくらでも最悪なことができてしまいますし、それこそ今やっているフィクションの作品自体が陰謀論の入口になりかねない、という世界があまりにも近いですから。
一方で、そのような作品は近々出てしまうんだろうな、とも思っています。
ただ、最近はファンの方たちも「フェイクニュースや陰謀論的なものは許さないぞ」という態度の人が増えているので、そういった方々が拒否することで、意外とバズりはしない可能性もありますね。
──ユーザー側のリテラシーも高まってきたということですね。
大森氏:
まあ、実現するかは別として、やりきったらすごいものになるフォーマットだとは思います。
梨氏:
私も5、6個くらいはアイデアを思いつきましたもん。
大森氏:
自分はテレビというメディアの人間でもあるので、できる限りそういった暴力性みたいなものには自覚的でありたいと思っています。
──電ファミもネットニュースのメディアなので、そういった扇情的なニュースには迎合しないようにしたいと考えています。受け手側の皆さんも最近は「フェイクニュースは広めないようにしよう」といった風潮の高まりがある一方で、そもそもインターネットに触れる人の総数が増えていますから、そういったリテラシーのないままにのめり込んでしまう方がいるのも事実です。
大森氏:
だから、そういった矜持やプライドみたいなものも結局はいつか粉砕されるんだと思います。その先に何が待っているのかは分かりませんが……、だからこそ、ささやかなプライドを持ち続けるということでしかないのかなと。
梨氏:
陰謀論とは少し違うかもしれませんが、「どちらにも転びうるな」と思った瞬間があって。
私は『つねにすでに』という、ウェブ上で連載されるマルチメディアプロジェクトをやっていて、既に150万PVくらいあるのですが、その初期のころに公式でDiscordサーバーを作ったんです。
サーバーの存在自体にも物語上の立て付けはあるのですが、メタ的に言うと、最新話が投稿されたときにみんなが考察して楽しめる場があったらいいよね、ということで作ったんです。
これ自体にメリットはすごくあって、どういった層のユーザーさんがどれくらいアクティブなのかというのが可視化できるようになったんですが……。それと同時にX(Twitter)で『つねにすでに』の話をしている人がいなくなったんです。
──X(Twitter)という開けた空間でクラスターを形成していた人たちが全員Discordサーバーの中に集まってしまったんですね。
梨氏:
これっていろいろな意味で危険だなと感じました。一度閉じた空間に集まってしまうと、そこから抜け出せなくなるんです。
コアな層に熱狂を生み出すという点ではものすごくありがたいんですけど、もし私が闇落ちしたときにこれをどう使うかと考えたらだいぶ怖いなと思ったんです。
大森氏:
物語を通じてDiscordサーバーに参加するという行為も非常にロールプレイング的じゃないですか。そしてそのロールプレイと実際の行動の境目って本当に曖昧だと感じます。
そういったロールプレイを繰り返した先に、梨さんのネジがずれた時に起こることっていうのはいくらでも……。
梨氏:
いくらでもできますよ。
大森氏:
そういった主体性みたいなものがコンテンツにあると、フックにもなるし、盛り上がりのきっかけにもなるんですけど、制作側としてはそういった怖さを感じちゃう時もありますね。
梨氏:
そういった点で、あらゆる意味で危険だなという知見を得られたので、ありがたかったです。
──いろいろなことが分かっている梨さんが闇落ちしたらヤバいという怖さもあるかもしれないですね。
梨氏:
(笑)。
大森氏:
梨さんのファンも気づけないと思うんですよね。なんというか、みんなで国会に乗り込んだ後に気づく可能性があるっていう。
梨氏:
私が切腹した後くらいに気づくっていう。
大森氏:
国会の真ん中で。
一同:
(笑)。
大森氏:
でも、Qアノン【※】とかで本当にそうだった人も多いんじゃないでしょうか。
実際に行動を起こして、機動隊に押さえつけられた瞬間に「どこかで道がずれてたかも」って思った人がいるんじゃないかっていう。主体性のあるコンテンツとかロールプレイング的なものって、どうしてもそことは不可分ではいられないと思うので。
作る側としても、楽しむ側としても意識しておいたほうがいいというのはあるかもしれません。
大事にしているのは「知っているものが1個ズレた時に生じる感覚」。誰もが知っているフォーマットが破壊される恐怖
──考察の分類や陰謀論の話もそうですが、ネット発の人気クリエイターの方は、そういった点の解像度が高いと感じます。お二人の創作論みたいなものも伺っていきたいのですが、そもそもお二人が出会ったのはどういう経緯だったのでしょうか?
大森氏:
最初のきっかけは、2022年の10月ごろで、僕が『このテープもってないですか?』という番組と、お笑いコンビのAマッソの『滑稽』というライブの企画を同時進行していたんです。
『このテープもってないですか?』は、家庭にビデオカメラが普及しだした時代の、視聴者から送られてきたテープを見るという昭和の番組のオマージュ企画に、視聴者から送られてきた呪いが時代を超えて伝播する、というフェイクドキュメンタリーだったのですが、そういった作品を作るときに、どういった方と組むのが良いかな、と考えていたんです。
その時に、梨さんが出されていたnoteの『瘤談』を見て「これだ」と思って声をかけました。Twitter(X)のDMを直接送ったのを覚えています。
──ご自分で直接連絡を取られたんですね。もっとこう、界隈の飲み会みたいなもので知り合ったような形を想像していました。
一同:
(笑)。
大森氏:
それから梨さんと『このテープもってないですか?』のお仕事を進めていったのですが、その中でお互いが引用するものだったり、方向性だったりが通じる感覚があったんです。
全部話さなくても「ツーカー」で済むというか。それが新鮮で、『滑稽』の方も是非一緒にやりませんか、となりました。
──コミュニケーションの通りやすさみたいなものがあったんですね。
梨氏:
作品を作るときに、ニュアンスを伝えるのって難しいじゃないですか。
テレビ局でのお仕事だと特に、なにか作品を引き合いに出して例えた時など、普通はその作品自体のことから説明しないといけないので、そこが通じるのがありがたかったです。
──一方で、そういったニュアンスを作品にするときは、視聴者に伝わる形にしていく必要がありますよね。優秀なクリエイターさんは、そういった言語化の能力も高いと思います。
梨氏:
それでいうと、私は「言語化」という言葉の弱火アンチなんです。「小説を書いているのに何を言っているんだ」と思われるかもしれませんが(笑)。
一同:
(笑)。
梨氏:
私の場合、言語のことはあまり信用していないので、「感情のロジックとしてこうなった」というのが分かっていれば、そこに言語を付与する必要はないと考えている派閥なんです。
映画なんかで、「モチーフとしてのシーン」ってありますよね。作中の人物の心象風景とか、そういうもののモチーフをバッと出すようなシーン。
あれっていわゆる「三段論法的なロジック」ではなくて、「その人物にとって大切なものだったから」というような、論理では成り立たないロジックによって成り立っているものだったりします。
大森氏:
「ドツボにはまる」という言い方が正しいかはわかりませんが、コンテンツを数式的に捉えようとすると、なにか違う出口が待っているような気がしますね。
──そういった感情やニュアンスをうまく伝えられる、伝え方の巧拙がクリエイターさんの力に直結するのかな、と思うことがあります。
梨氏:
いま出た数式の話で例えると、「物語の加減乗除をつくる」ということだと思うんですよね。
ミステリー作品で、犯人に殺人を犯した動機を聞くシーンがありますよね。
たとえばそこで「3年前の夏に見た交差点の信号が、紫色に見えたからです」と答えたとする。ここにいわゆる「ロジック」は成り立っていないじゃないですか。
でも、作中で文脈を積み上げることによって、この回答がその作品の世界観においては説得力を持って成り立っているようにみせることってできると思うんです。
これを数式的なロジックだけに当てはめてしまうと、どうしても「恨みがあったからだ」としか言えないですよね。
ですから、作中でしか成り立ち得ないロジックを自分で作って、それを自分が作り出した数式に当てはめるという作業ができている人。作中の論理構造をゼロイチで作り出せる方というのが一流のクリエイターで、そこのアウトプットがうまいからこそ、ニュアンスの論理の飛躍みたいなものも違和感なく受け入れられるんじゃないでしょうか。
──大森さんはいかがでしょうか?ご自身の作品でそういったニュアンスをアウトプットするときに、工夫されていることはありますか。
大森氏:
そこまで意識的にやっているかと言われたら怪しいですが……
自分が「こういったニュアンスを生み出したい」と思った時に一番最初に想像するのは、自分がそれを見た時に、まずどの部分に着目して、どういう風な感情になるだろうかということです。
『イシナガキクエを探しています』で例えると、あれは公開捜索番組という、懐かしいフォーマットのオマージュですが、それってみんなが知っているものですよね。
このように、最初は「知っているもの」から入った方がいいと思っています。その次に、懐かしいものだったり、「こういうのあったな」という感情から大きく1個ずらす、ということをやるんです。
『イシナガキクエ』の場合は、55年も前にいなくなった人をいまだに探しているおじいさんが出てきて、その人のために大きな生放送の番組をしているという設定です。
そういった「知っているものが1個ズレた時に生じる感覚」を、コンテンツの序盤で絶対に持っていきたいと思っています。
文芸的な話になりますが、批評家のマーク・フィッシャーが「奇妙なものは、知っているものの中で1個ずれたもので、ゾッとするものは、そもそもその存在の主体が見えないもの」みたいなことを言っていますけど。
僕はその「奇妙なもの」こそが最初の引きになって、「次はどうなるんだろう」という推進力になるように作っていきたいんです。
──みんなが知っているものから入るというのは、物語のフックとして取っつきやすくするという効果もあるんじゃないでしょうか?そういったマーケティング的な観点も含まれていますか?
大森氏:
そういった観点もめちゃめちゃあると思います。僕はプロデューサーでもあるので、作品を届けるのも仕事ですから。マーケティング的な要素というのはかなりあります。
自分の趣味だけで言うと、もっとマニア向けなものを作りたいと思うこともありますが……。テレビ局における1回のチャンスってかなりシビアですし、その1回でコケて終わってしまう可能性も考えると、マーケティング的な視点でもちゃんと勝ちにいきたいと思っています。
──そう聞くと、大森さんと梨さんがお二人で仕事をされるときの様子が気になります。そういったマーケティング的な観点は大森さんが担当されているんでしょうか。
大森氏:
梨さんのいいところというか、やさしいところなんですが、基本的に僕に最終決定権を持たせてくれますね。
梨氏:
そこはもう、プロに任せた方が絶対にいいので(笑)。
大森氏:
だから、梨さんの中で「いいアイデアだな」と思ったもので、僕個人としてもめちゃめちゃ好きなものでも、フックがなかったり、あまりに人が振り落とされそうなものだったらカットすることはありますね。
梨氏:
個人的には、だからこそ全幅の信頼を置いているというのがあって。「カットしよう」と言ってくれるのが、めちゃめちゃ嬉しいんです。
それこそ、『このテープもってないですか?』の時にギミックのアイデア出しをしていた時の話です。
「NHKの『番組発掘プロジェクト【※】』なんか面白そうですよね。存在しないテレビ番組とかが届いたら面白いんじゃないですか? 」などと、自分がヘラヘラしながら言ったのを、大森さんがものすごくフックのある構成に仕立ててくださったんです。
※「番組発掘プロジェクト」…… 1980年以前に放送された、今はデータが残っていない番組の保存を目的とするNHKのプロジェクト。現存している当時の録画テープを一般から募集している。
大森氏:
『このテープ』の例で言うと、いきなり「こういう番組が発見されました」って映像を流すこともできると思うんですよね。でもそれではやはりフックがないと思ってしまって。
よくある「昭和を振り返る番組」の中にそれが紛れている、その中からパッと出てきてしまうという構造のほうが、「ん?」となる、人が惹きつけられる瞬間を起こしやすいと思ったんです。
梨氏:
そのフォーマットがあるからこそ、フォーマットが破壊された時の怖さもありますしね。
──作品に入り込みやすくしつつ、そういった落差をつくるように心がけていると。ひとつ気になったことがあるのですが、いわゆる「ホラー作家界隈」に、大森さんのようなプロデューサー的な視点を持ったクリエイターさんってどれくらいいらっしゃるものなんでしょうか。
梨氏:
それで言うと答えは簡単で、私が今までテレビの仕事をしてきた中で、一緒に仕事をしたことがあるのが大森さんくらいしかいないんですよ。
この事実でだいたいお分かりいただけると思うのですが、こんな人あんまりいないです。
大森氏:
(笑)。そう言っていただけるとありがたいのですが。
「コンテンツが広がっていくというのは、タコ壺をあふれさせていくという感覚に近い」。マニアで壺がいっぱいになり、新たな人々に波及していく
──物語に入り込むフックを大事にされているというお話で、ホラーブームの「当事者性」と繋がるところもあると思います。そういった、視聴者が前のめりになる瞬間みたいなものが、熱狂のキーになるんじゃないかと。
大森氏:
そうですね、梨さんの作品にしても、他の今のホラー作品に関してもですが、最初に惹きつけられるような導入があって、そこの先にある物語の世界にダイブしていく感覚がありますよね。そういう要素が「当事者性」だったり、「フック」と呼ばれるものだと思います。
──梨さんにも伺いたいのですが、そうして入り込んだ物語の中には、さまざまな仕掛けだったり、点と点が繋がるような仕組みがあると思います。ただ、読者にこれに気づいてもらうのって意外と大変なんじゃないでしょうか。そうした点でなにか工夫されていることってありますか?
梨氏:
そうですね、工夫にもさまざまなレイヤーがあると思いますが、そういった要素で「本当に難しいな」と感じる例があります。
『リンフォン』というネット怪談があって、これは「リンフォン」という立体パズルを解いていくことで、地獄の門が開いていってしまう、という話なんですが……
最後の種明かしが、「主人公の彼女がたまたまアナグラム好きで、『リンフォン』を並び替えると『インフェルノ』、つまり『地獄』という意味になることに気づく」というものなんです。
このオチ、作者はやりたかっただろうな、ここがいちばんやりたかったんだろうな、とは思うんですけど。これの難しいところって、気づいてもらうのも大変なんですが、そのほのめかし方もめんどくさいというのがあって。
大森氏:
そうですね、「ドヤ感」というか、露骨すぎると人は冷めるということですよね。
梨氏:
さらに難しいのが、コンテンツの視聴者の中でも、ちょっとでも解説があると冷めるという方がいらっしゃる一方で、絶対に全部解説されないとダメだというパターンの方もいらっしゃることです。
連作短編のように、点と点がつながるような作品の場合は、「これらの作品は全て無駄なく繋がっているんだ」という視点で鑑賞する方と、普通にひとつひとつの作品のクオリティとして楽しむ方がいて、その中で作者がどこまで旗を振って誘導するかというのはものすごく重要な選択なんです。
そういった前提があって、私が意識する、一番大切だと思うことが、「考察されなくても最低限面白いもの」であるということ。
当事者性の話にもつながりますが、考察ありきの作品になってしまうと、「じゃあ、当事者性がないと楽しめないの」となってしまうと考えているんです。
「意味が分かると怖い話(意味怖)」というネット怪談のジャンルがありますが、あれも裏を返せば「意味がわからないと怖くない」という話になってしまって、これは読者に責任が向かってしまっているような気がしています。
つまり、怖く感じられなかったというのは、物語を読み解けなかった読者のせいだ、となってしまうような気がして、それはすごく危ういなと思っているんです。
だからこそ、単体でも楽しめる「意味が分かるとさらに怖いけど、意味が分からなくても、もちろん怖い」という塩梅が大事なんだと思います。
──受け取る側にもさまざまな態度の人がいるから、誰でも楽しめる作品というのを大切にされているんですね。
大森氏:
人によって違うというのが難しくて、僕が今まで作ってきた作品たちも、それぞれ違う層からのバッシングを受けている感覚があります。
たとえば『このテープもってないですか?』と『イシナガキクエを探しています』で、作品に対して怒っている方の層がそれぞれ違うんです。
梨氏:
たしかに。裏を返せば『SIX HACK【※】』が好きだった層が『このテープ』好きかどうかはわからないみたいな。
※『SIX HACK』…… 2023年に大森氏が制作した「ビジネス番組」。全6回の放送予定だったが3回で打ち切りになり、第4回がネット配信された。
大森氏:
そうですね。だから僕の作った作品でどれが一番好きかというのは、人によってすごく分かれていますね。
──それは、作品ごとに明確にターゲットを分けて考えているということですか。
大森氏:
僕の中で、コンテンツが広がっていくというのは、タコ壺をあふれさせていくという感覚に近いものがあります。ひとつのタコ壺が満杯になって、ほかにあふれて初めてコンテンツが広まっていくんです。
──“タコ壺が溢れる”ですか。面白い表現です。それっていわゆる「視聴者の層」みたいなものでしょうか?
大森氏:
そうですね。『イシナガキクエ』の例で例えると、この作品のターゲットは恐らく2つで、フェイクドキュメンタリーが好きな層と、今まで見たことがない「変なフォーマット」が好きな層です。そこをあふれさせないと、結局他には波及しないと思っていました。
逆に、その層が外から見ても分かるほど盛り上がっていれば、普段はフェイクドキュメンタリーを見ない人なども「なんだか流行っているから見てみよう」となりますよね。そういう風にジャンルを越境していきたいと考えています。
──おふたりの話を聞いていると、インターネットの文脈を持っているけど、他のこともできるクリエイターさんは稀有な存在なのかなとも思います。ちなみに、おふたりが注目している他のクリエイターさんっていらっしゃるんでしょうか。
梨氏:
それで言うと、『ゆる言語学ラジオ』ってご存じですか。
──「springはなぜ春もバネも意味するのか」みたいな、言語学のトピックを紹介しているYouTubeチャンネルですね。
梨氏:
あれの面白いのは、学術的にそういったトピックを分解して再構築するみたいなところなんですが、そこの語り口や視点も面白いんですよね。
ホラーでも民俗学的なモチーフのものって結構人気ですけど、やっぱりガチでやっている人には勝てないなと思わされます。すでに人気のチャンネルですが、もっとバズって良いと思うので名前を挙げました。
──大森さんはいかがですか。
大森氏:
去年の末に見た、『王国(あるいはその家について)』という、草野なつか監督の映画が衝撃的でした。
映画の脱構築みたいな手法を取っている作品で、本番の演技のシーンを流すのではなくて、終始ほとんど台本の「ホン読み」の様子が流されるんです。
実験映画にも近い感じなのですが、「演技ってなんだっけ」とか、「映画ってなんだっけ」という気持ちになって……。
僕は世代ではありませんが、洋服の世界で「マルジェラが現れたときの衝撃」という表現がされるのと近い感覚なのかなと思いました。
ストーリー自体もめちゃめちゃ面白いんですけど、順番がめちゃめちゃで、同じシーンが20回くらい、1度目のホン読み、2度目のホン読み、といったように繰り返されるんです。
見終わった後には自分もそのシーンを暗唱できるようになっていて、物語を人間の体に直接ぶち込まれるような感覚を味わいました。草野なつか監督には、今後も注目しています。