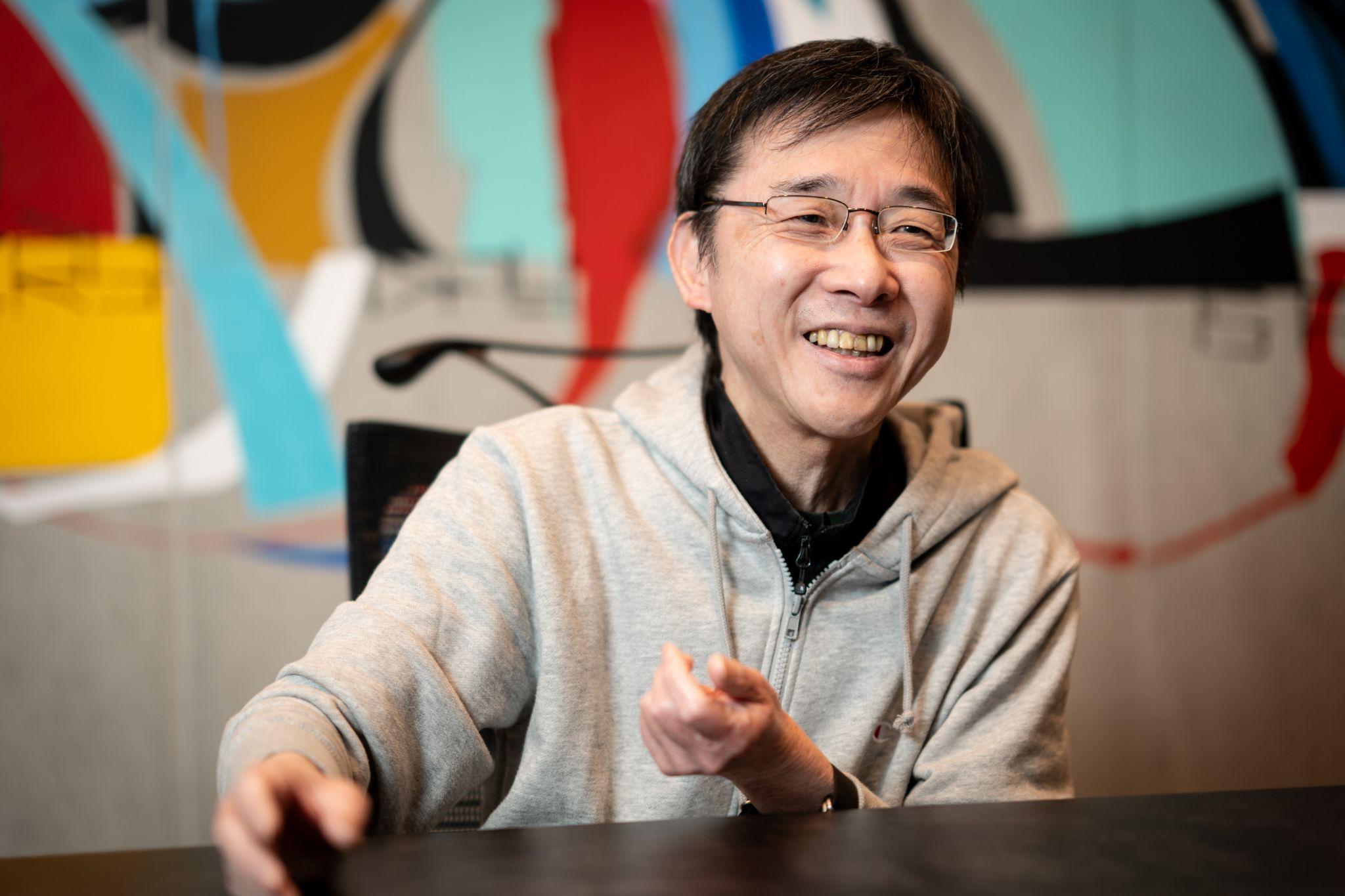ガイナックスからはスタジオぬえと同じ匂いがした
──加藤さんの経歴を拝見したところ、テクモのあとにガイナックスに移られていますよね。
加藤氏:
基本的に僕は飽き性なんです。『忍者龍剣伝』はシリーズで3作作っていて、同じものを作るより新しいことに挑戦したかった。そのタイミングでちょうど『プリンセスメーカー』を遊んで、これにもまた衝撃を受けました。「ゲームってこういうこともできるんだ!」という驚き。
あのころのガイナックスは、普通とは少し違う変なゲームを作っていて、勢いもあったんです。それに、大阪からSFが好きな人達が集まって会社を設立して、アニメやPCゲームを作ったり独自のことをしている動きにスタジオぬえと同じ匂いを感じました。
面接を受けに行ったところ、『忍者龍剣伝』が海外ですごく売れていたことを知ってもらえていて、「すぐに来て!」と言われました。

──当時のガイナックスはどんな雰囲気だったのでしょうか?
加藤氏:
当時のガイナックスは、吉祥寺から練馬寄りの古い木造アパートの一室に会社がありました。一応、アニメ部門とゲーム部門に分かれていたんですけど、何十畳かのワンフロアの中で、ゲーム部門は10畳くらいのスペースだったかな。
僕が入ったころは赤井孝美さんがゲーム部門のトップだったので、僕は赤井さんの下について『プリンセスメーカー2』を一緒に作ることになりました。企画は僕を含めた3人で、グラフィックアーティストが4〜5人、プログラマーが1〜2人の少人数体制でした。
アニメ部門もちょうど『ふしぎの海のナディア』が終わったあとだったからか、とにかくみんな雑然とワイワイガヤガヤやっている雰囲気でしたね。
ただ、みんなノリが関西なんですよ。「なんやねん、加藤そんなんでどないすんねん!」「わははは!」という(笑)。かなり独特なノリがあって、自分の中では「このノリにはついていけないかも……」と思っていました。
そんなとき、テクモ時代の営業を担当していた方がスクウェアに転職して。相談したところ、上層部に話を持っていってくれたんです。ちょうど『クロノ・トリガー』開発に向けて募集を行っていて面接をすることになった、というのがスクウェア入社の経緯ですね。
──『キャプテン翼』や『忍者龍剣伝』のときもそうですが、加藤さんは縁に恵まれているというか、タイミングがすごくいいですよね。
加藤氏:
そうですね。自分の中でつぎの段階に進みたいと思った際に、たまたま求められている場所があって……というのはたしかにあったと思います。
「タイムトラベルもの」をテーマにしたゲームがおもしろくなるはずないと思っていた
──その後、スクウェアに入社し、『クロノ・トリガー』、『クロノ・クロス』に携わることになると……。加藤さんといえば「タイムトラベルもの」という印象がゲームファンとしては強いと思うんです。『クロノ・トリガー』は言わずもがな、現在手がけられている『アナザーエデン』も「タイムトラベル」をテーマとした作品となっています。
加藤氏:
ありがたいことではあるのですが、そもそも僕は「タイムトラベル」をテーマにしたゲームを作ることに対して積極的ではありませんでした。
むしろ「(タイムトラベルもののゲームは)おもしろくなるわけがない」と思っていたくらいなんです。ですから『クロノ・トリガー』のときも、タイムトラベルの案には反対していたんですよ。
──えっ、それはどうしてでしょうか?
加藤氏:
僕自身、子どものころからSF小説が大好きで、とくに「タイムトラベル」を扱った物語は手当たりしだい読んでいました。だからでしょうね、ゲームという媒体でおもしろい作品を作れるイメージがなかったんです。
──タイムトラベルというジャンルについて深く知っていたがゆえに、難しく感じられていたと。
加藤氏:
そうだと思います。『クロノ・トリガー』開発の話がでた当時もタイムトラベルをテーマにしたゲームはたくさんありました。でも、たとえば過去に行ってフラグを立てることで未来が変わる程度、言うならばフラグを確認するだけのゲームでおもしろいとは感じなかった。
いま振り返ってみると『クロノ・トリガー』開発当時は、自分の経験やスキルを見込んでくださったんだと思います。ただ、新入社員だった当時の僕はそのような考えには至らず、仕方なくシナリオ制作を始めたんです。
──加藤さんが『クロノ・トリガー』のシナリオでいちばん描きたかったものはどういったものだったのでしょう?
加藤氏:
『クロノ・トリガー』でやりたかったのはやはり「時空を超えての冒険のおもしろさ」と、中盤でのある「仕掛け」ですね。
ゲームでしか味わえない体験というものをプレイヤーに遊んでもらいたい、という思いが常に自分の中にあります。アニメやドラマではできない、ビデオゲームだからこその新たな驚きというものを実現したい、みたいな。毎回、そうしたところにこだわって作っていますが。
──加藤さんは『クロノ・クロス』でもシナリオを手がけていらっしゃいますが、プレイヤーに解釈を委ねつつ、余韻を残し、謎も残す。26年経った現在でも考察が続いているタイトルです。なぜこれほどまでにプレイヤーの心をつかんだのか、加藤さんご自身はどう分析されていますか?
加藤氏:
「人生の選択肢と向き合うことをプレイヤー自身が体験できるゲーム」だからじゃないかと自分では思っています。
人間はみんな異なる感性や個性、考えかた、生きかたを持っているわけですから、自分の人生がどうあるべきかというのは、誰に言われるわけでもなく、自分の頭で決めていかなければなりませんよね。
それと同じことをゲームの中で体験して、そのことについて考えてほしい。これは「パラレルワールド」をテーマにしたときに考えていたことでした。
──あらかじめ決められた道筋をたどるのではなく、どんな選択肢を選ぶか考えてほしいという想いがあったと。
加藤氏:
人生って正義や愛が勝って地球を救うみたいなものではなくて、みんながそれぞれの人生を送って、うまいこと生きた人もいれば、そうではなかった人もいる。
そういう選択に対して、はたから見たら「なんでそんなバカな選択をしたんだ?」って思うかもしれないけど、それこそが当人の中では大事な選択だったかもしれない。
そういういろいろな見方ができることを意識してほしいし、ゲームプレイを通じて「人生ってなんだ?」というのを考えてほしいと思って作ったんです。だから、ちょっと意地悪なんですよね。
──選択肢が多くなれば、そのぶん制作は大変だったのではないかと思います。どのようにストーリーを組み立てていったのでしょう?
加藤氏:
パラレルワールドをテーマにする以上、プレイヤーを迷わせたり考えさせるものにしようとは考えていました。
だから、まずはメインのお話をしっかりと完成させて、そこからは「あのときこうしていたら……」という話の別筋を細かく分けていき、その内容が矛盾していないかをひたすらにチェックしていくような形で作っていました。
──簡単にお話されていますが、それって相当大変な作業なのでは……。
加藤氏:
大学で言語学を履修していたスタッフにお願いして、パーティーメンバーを自由に選択しても、イベントとして成立するものを作ってもらいました。そのおかげで、どれだけ話が分岐したり、パーティーが入れ替わってもゲームとして破綻しないものが作れたのでありがたかったですね。
『MMOでも物語を大事にしたい想いから『FF11』は生まれた
──『ファイナルファンタジー XI』(以下『FF11』)では『ジラートの幻影』までのストーリーを手がけていらっしゃいますが、当時MMOに濃密な物語を用意するというのはとても珍しかったですよね。どのようなアプローチを心がけたのでしょうか?
加藤氏:
当時流行っているオンラインゲームを遊んでみたのですが、僕としてはまったくおもしろいとは思わなかったんです。なぜなら、物語もなく、フィールドに出向いてモンスターを殴りに行くだけだったから。
ただ、オンラインゲームには、大きな箱庭の中でほかのプレイヤーと交流したり、協力したり、好きなように遊べるという新鮮な体験がありました。
でも僕は知らない人に話しかけるのが嫌だったから、ひとりで黙々とプレイしていた。当然、なにもおもしろくないんですよ。
同じものを作っても仕方がないし、僕がシナリオを書くからには、しっかりとストーリー性を持たせてドラマを魅せて、みんながひとつの物語を体験して、感動を共有するものにしたいと考えたわけです。
──オンラインプレイだからこその物語を描くことを意識されていたと。
加藤氏:
「どうすればMMOでそういう体験に繋がる物語ができるだろう?」といろいろ考えてみるわけですが、これが難しい。
たとえば「お城にゴブリンが襲ってきて町が焼かれて崩壊する」という話は書けません。そのイベントを見ている人はいいけど、新規プレイヤーはいきなり町がなくなっていたらゲームにならないですから。
そして、世界の状況を大きく変えるような出来事には、プレイヤー全員に参加してもらわないといけないので、大イベントとして実施する必要がある。……といったように「できること、できないこと」を考えながら物語を組み立てていきました。

──進捗状況が異なるプレイヤーが一緒に遊ぶからこその制約があったんですね。
加藤氏:
あと、当時は通信環境の問題でプレイヤー全員が同じ場所からスタートするとサーバーに負荷がかかって重くなってしまうこともあったから、その回答としてプレイヤーのスタート地点を3つの国から選ぶ形式にしました。通信環境という制約を逆手に取って、バラバラだったプレイヤーが一箇所に集まるような喜びを演出できたのかなと思います。
オンラインゲームだからこその制約は多かったですが、これまでと同じように「どうすれば実現できるか」を考えて、作っていきました。
去年、『FF11』が22周年を迎えたというメールをもらったのですが、まだサービスが続いてるのはすごいことだと思います。
※FF11は2025年5月16日に23周年を迎え、現在もサービス継続中。
理想的な物語を作ることができた『バテン・カイトス』。とはいえ、モヤモヤすることも多かったフリーランス時代
──『FF11』に携わったあとはフリーランスの期間を経て、グリーに入社されています。フリーランスとして活動を続ける考えはなかったのでしょうか?
加藤氏:
フリーランスは気楽なんですが、モヤモヤすることも多かったんですよ。
──モヤモヤ、といいますと?
加藤氏:
書いてお渡ししたものがそのままゲームにならないんです。僕が「10」の内容を渡して書いたら「入らないから8にして」と言われて、8にしたら今度は「やっぱり5にして」みたいに言われたりね。そこまでくるとさすがに……。
──そうなるともはや加藤さんのシナリオとはいえないものになってしまいますよね。
加藤氏:
そのときは「僕は原案か監修ってことにして、あとは好きにしてください」と言って。そのあと実際にどうなったのかは見ていないので知りませんけれども……。
もちろん理想的な物語を作れたこともありました。『バテン・カイトス』はその筆頭ですね。

──『バテン・カイトス』をプレイしたときは、展開に衝撃を受けました。プレイヤーと主人公の立ち位置を活かしたシナリオが本当にすごくて……。
加藤氏:
『バテン・カイトス』は名前を入力する段階からプレイヤーを物語に取り込んでいるんです。そのプレイヤーが精霊として物語の主人公と相棒のように語り合うところから、じつはもう仕掛けが動き出しているというね。
映画やドラマのようなほかのコンテンツでは実現できない、ゲームだからこそ描けるという意味で僕の理想的なシナリオです。自分としてもよくできたというか、自慢している作品です(笑)。
ですから『バテン・カイトス』が好きというプレイヤーに接すると、僕もうれしくなりますね。
──『バテン・カイトス』を遊んだことのない人に勧めまくっています(笑)。
加藤氏:
あとは、テクモ時代に一緒に仕事をした冨江さんとの繋がりで担当した『風来のシレン』(『3』、『4』、『5』を担当)も僕が書いたシナリオがベースになっています。
あのときは、ちょうど和風の伝奇ものを書きたいと思っていたんです。そこに『シレン』の話がきたので、「待ってました!」と言わんばかりに、ある程度自由にやらせてもらいました。
『風来のシレン3』は、ファンからの反応は賛否両論あったと聞いています。4作目、5作目は従来の『シレン』らしいお話にしたら評判が良かったようです。僕は『風来のシレン3』の話は結構好きなんですけどね。

──うまくいったケースもありつつ、フリーランスならではの大変さがあったわけですね。
加藤氏:
自分の思うようにゲームが作れないことが増えてきたことに加えて、その時期ってちょうど家庭用ゲームが苦戦し始めるころなんですよ。だから「これからシナリオの仕事はどうなるんだろう?」といった危機感のようなものもありました。
当時はスマートフォン向けゲームの勢いがあって、そこなら新しくておもしろい仕事ができるんじゃないかと思い、いわゆる転職サイトのようなところに登録したんですね。そうしたらその日のうちにグリーから連絡があり、面接をすることになったというわけです。