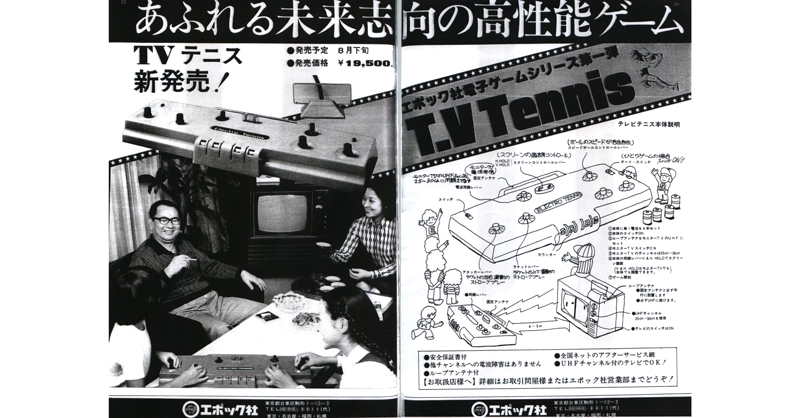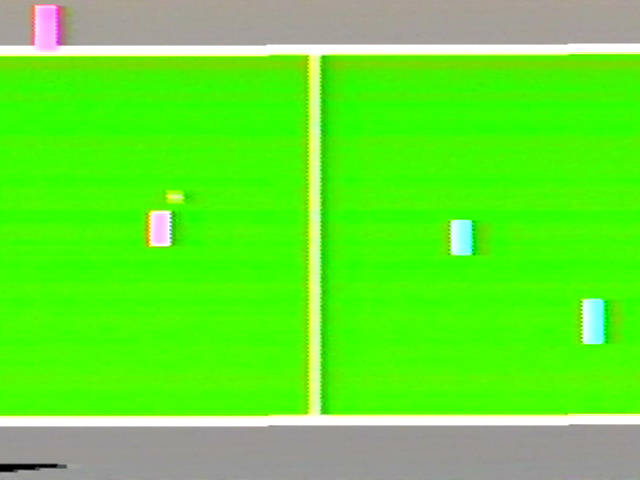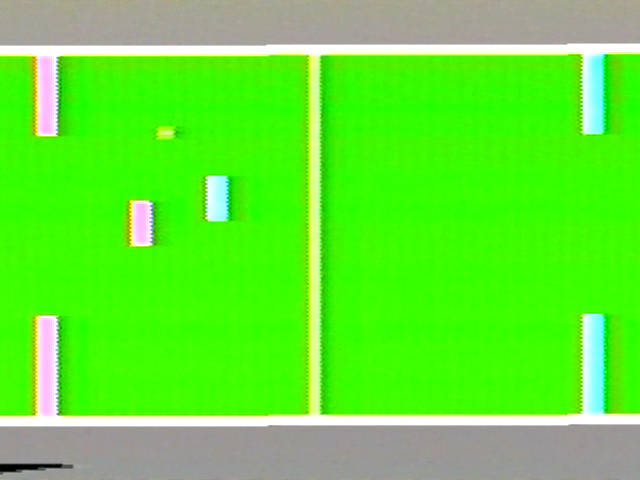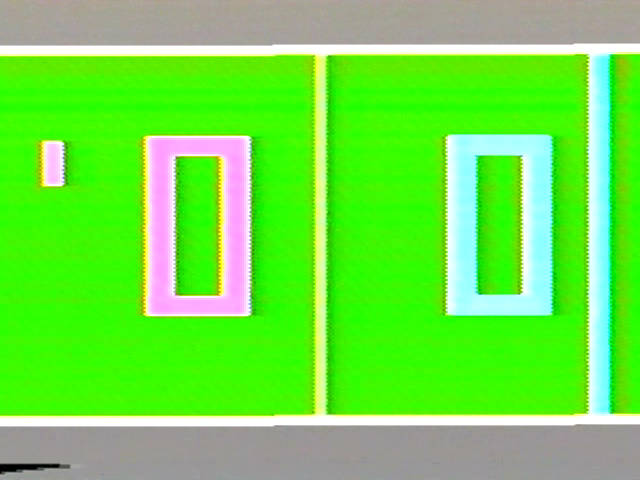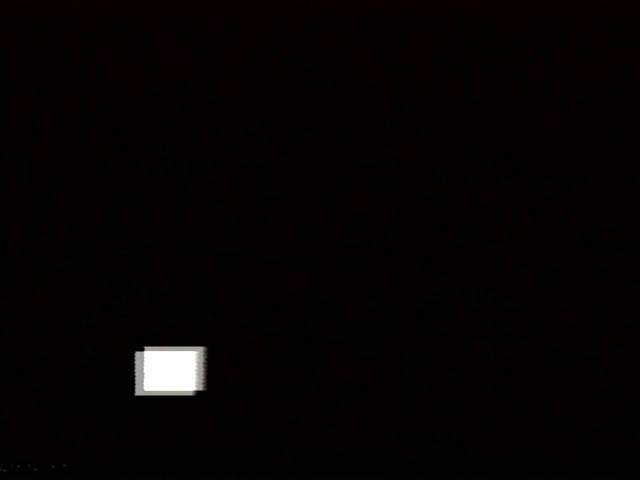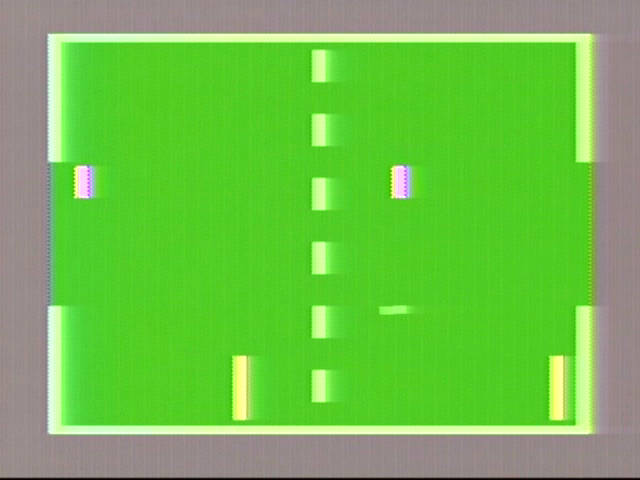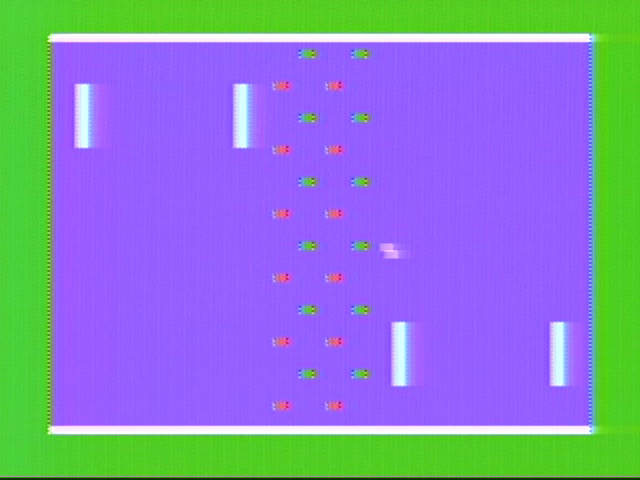野球盤の開発者がアイデアを出したシステム10


1977年8月、エポック社は開発に2年数ヵ月をかけて新機種のシステム10を投入。本体セットは10000円を切る9800円。
鮮やかなフルカラー画面と全方向に動くラケットが、まず人目を惹く。しかしそのウリはもちろんゲーム内容だ。
システム10のボールゲームは、ラケットの上端にボールを当てると速球が、下段に当てるとジグザグ魔球が打てるのが最大の特徴で、そのタイミングは難しいが、練習すればするほど快感が味わえるようになっていた。また4人で遊ぶことにより、速球と魔球を組み合わせたフォーメーションの攻防が楽しむこともできた。
左)『テニス』は4人プレイ必須。フォーメーション攻撃が熱い。
右)『サッカー』は全方向移動ラケットで、球を押し込む感じが楽しい。
システム10の仕様は野球盤の開発者でもある前田竹虎社長(当時)がみずからアイデアを出したという。同氏はその昔、青山にただひとつあったボーリング場に通いながら、1961年にはボーリングゲームを開発。
しかし、このときもあっという間に類似品が蔓延してしまったという。
「ゲームが儲かりそうだというので、最近おもちゃメーカーの参入も多いが、遊びの幅と深みのないゲームを乱発していると、子どもたちからも親たちからも不信を買ってしまう。野球盤のように繰り返して飽きの来ない商品を開発しなければ。テレビゲームに乗り出せるのも言ってみれば野球盤のおかげなのです」
(日経流通新聞 1977年8月18日号)
左)ひとり用の練習ゲーム『ワンマンゲーム』。ミス回数を画面に表示。
右)『フリーピストル』では、画面内の辺で反射する標的を撃つ。光線銃を使用。
任天堂テレビゲームの原点──テレビゲーム15、テレビゲーム6
そして任天堂も、すぐれたボールゲーム機を1977年6月に発売していた。鮮やかなフルカラー画面と6種類の多彩なゲームが楽しめるテレビゲーム6は9800円という超低価格だった(このわずか2ヵ月まえに出た松下電器のGIチップ製白黒テレビゲームが24800円である)。
この時期の乱売合戦に終止符を打ったといわれるハードである。

そして15種類のゲームが遊べるテレビゲーム15。両者は同一のゲームLSIを搭載しており、10000円以下という玩具として妥当な価格を打ち出すため、スイッチを加工してセレクトできるゲームの数を削った低価格のテレビゲーム6と、正常な利益の出るテレビゲーム15に分けられ発売されたのは有名なエピソードだ。
意外にも消費者の多くは、15000円と高価だがゲーム数の多い後者を選び、結果的に、2種類合わせてこの時期最大の70万台以上のヒットを飛ばすことになる。

テレビゲーム6と15に搭載された三菱製のLSIチップは、そもそもある電卓メーカーが三菱電機に開発を依頼していたものの、在庫調整の失敗から倒産し、宙に浮いた状態のものを任天堂が引き受けたものだ。
テレビゲーム6や15にも、ボールゲームを熱くプレイする技のバリエーションがふんだんに盛り込まれていた。パドル操作でくり出すカットボールやスマッシュ、そしてパドルを消してしまう裏技など、多彩なテクニックが可能だった。
ハンデ機能や、ご近所迷惑にならないテレビ側のサウンド出力など、家族や友人と長く楽しめる工夫がなされていた。
ちなみに、筆者の母親は電子機器といえば電子レンジしか触らないほど、大のIT機器嫌いだ。往時の『脳トレ』や『Wii Fit』のブームにも、まるで興味なし。
そんな母と子どものころ唯一いっしょに遊んだのがテレビゲーム15だった。片手でできる手軽さに、美しい画面、そして爽快なゲーム内容が、嫌われなかった理由だろう。
左)『ホッケー』ではセンターラインが定期的に閉じ、集中攻撃が可能。
右)『テニス』は中央の障害物ゾーンでボールが複雑な反射をする。
左)『ピンポン』には見えない壁があるので予想外の打ち合いが展開する。
右)光線銃不要の射撃ゲーム。パーフェクトは15点。
そんなテレビゲーム15の心臓部であるLSIを開発した三菱電機北伊丹製作所の半導体チームは、財閥系の三菱グループにありながら、新しいことはどんどんやろうというベンチャー気質に溢れる人々だった。
そこには、さらにおもしろいボールゲームを開発しようと、嬉々として開発に取り組む若手技術者たちと、そんな彼らを背後から見守るベテラン技術者たちの姿があった。彼らの何人かはその後にリコーに移り、数年後、任天堂と運命の再会を果たすことになる。彼らこそ、のちにファミコンを作る男たちだ。

技術は好奇心の手段である
テレビゲーム産業の父と呼ばれ、ブームの渦中にいたATARI社のノーラン・ブッシュネル会長(当時)は、1976年のボールゲーム狂想曲をこう分析している。
「将来、半導体メーカーはビデオゲーム市場から引っ込むだろう。
理由は価格変動の激しさにある。5ドル値下すればお客は飛びつくだろうが、半導体メーカーの根本の間違いは、あくまで半導体を売っていると考え、玩具を売っていると考えられないところにある」
(電子技術1976年12月号)
少々回りくどい言い回しだが、つまり消費者はゲームを買っているのであって、エレクトロニクス技術や製品を買っているのではない、という主張である。もちろん、テレビゲームとは半導体技術があってこそ初めて成り立つものであるが、技術はあくまで遊びを作るための手段だ。
娯楽業とは、いかに相手を楽しませるかというサービス業というわけだ。テレビゲームという娯楽は、カスタムLSIという数億円規模の投資リスクがあり、競争相手も多く薄利商品だ。
それでも“自分たちが遊びを作る”という意識にブレがなかった任天堂とエポック社は、娯楽を作る企業としての気骨があった。いや、好奇心に溢れていたというべきか。そしてこの2社こそが、ファミコンが登場するまでの日本のテレビゲーム市場を牽引していくことになるのである。
【次回ダイジェスト】現実世界を超えて~野球ゲームからブレイクアウト
ボールゲームの人気が去ったあと、ゲームデザイナーたちは新しいゲーム作りに苦心する。機能の弱いハードでどうやって娯楽を生み出すのか? 現実の遊びやスポーツを電子化したシミュレータゲーム、そして現実世界にはないブレイクアウト系のマシンが登場する。
しかし“侵略者”の影は、すぐそこまで迫っていた……。

参考文献:
日経産業新聞1976年3月17日号 ポストカラーのつなぎ? テレビゲーム
日経流通新聞1977年8月18日号 顔:ポスト電卓にぴったり・10面相テレビゲーム
トイズマガジン1977年5月号 特別企画 今年のエース!テレビゲーム
電子材料1977年7月号 家庭用ビデオゲーム
週刊新潮1978年1月13日号 新聞カクザイに転落した・・・
毎日新聞1977年12月29日号 景品人気no.1 テレビゲーム業界ニッコリ
【あわせて読みたい】
世界初の家庭用ゲーム機は、プレイヤーが画面にフィルムを貼り付けて遊ぶもの──ファミコン以前のテレビゲーム機の系譜を語ろう【新連載:ロード・トゥ・ファミコン】昨今のレトロゲームブームにあって、ファミリーコンピュータ登場以降のムーブメントや作品群については、さまざまな場所で語られることも多い。だが、それ以前に家庭に滑り込んだゲーム機について語られることは数少ない。その知られざるファミコン以前の歴史を辿ろうとするのがこの連載だ。名付けてRoad To Famicom(ロード・トゥ・ファミコン)。ファミコンへの道だ。