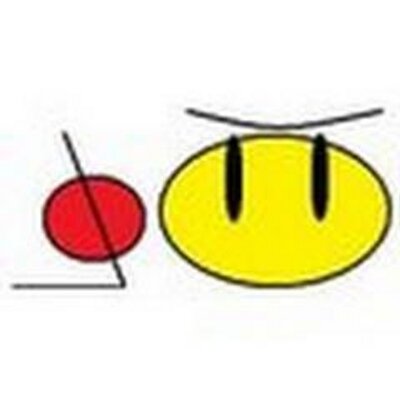VRはクリエイションの新しい場所になるか
――少し『Rez』からVR全体に話題を広げさせてください。以前、水口さんがAR三兄弟の川田さん【※】との対談で「ゲームのクリエイションは冬の季節に入った」と発言していました。その際、むしろソーシャルゲームのような「興味のない人間にお金をいかに使わせるか」という手法はアーケードの時代には当たり前で、自分たちはそうでないゲーム開発の場所を作ってきた、と。でも、それも厳しくなっていて、新しい場所が必要になっている、と話されていたんです。その場所を水口さんは、いまVRに見いだしてるのではないかと思うんです。
※AR三兄弟の川田さん
AR三兄弟とは、株式会社トルク所属の3人組開発ユニットのこと。様々なメディアを通じて、既存の枠にとらわれない新作の発明と発表を続けている。川田さんというのは、メンバーの1人の川田十夢氏のこと。1976年生まれ、熊本県出身。AR三兄弟において、企画・発明・執筆を担当。テレビ番組にも出演することがあり、幅広い領域で活躍中。
水口氏:
ずっと待っていたからね。
でも、過去130年間、ずーっと四角いフレームの中で、映像表現が行われてきたわけじゃない。だから、いきなりフレームが存在しない環境で、三次元空間に人間を招き入れられると言われても、最初はどうしていいのか戸惑うよね。
――だって、水口さんの新人時代の話を聞いていると、2DのゲームがCGで3Dになっただけで、あれだけ混乱したわけですもんね。
水口氏:
でもね、まだこんなもんじゃないですよ。このVRから始まる革命は。
ソーシャルゲームの文法から入った人なんかは、最初は大変だろうなあと思うけど、なるべく若いうちにVRに触れた方がいいよね。若い人には期待しています。
――ただ、ほとんどの人は「VRとは何か?」が全く見えていない気がしますね。その中で『Rez』だけが凄まじく先を行っているというのが所感だったのですが、今日の話を聞いていると、そもそも水口さんはVRが来るのを、セガの門を叩いた頃からずっと待っていたという感じで、そりゃ一人だけ別世界にいるわけだな、と思いました(笑)。
水口氏:
そりゃあ、いろいろ経験したからね。ようやく、思うままに、存分に表現できる時代が始まった。もうしばらくは、この感慨に浸らせてください(笑)。
 |
――ただ、多くのクリエイターはやっぱり制約から入るので、この「四角いフレーム」が消滅した世界で、何を描くべきかは凄く戸惑う気がするんです。
水口氏:
もう、既存のジャンルや文法を気にしない方がいいんだよ。固執しない方がいい。よく「今までのやり方だと、VRでは上手く表現できない」とか言うけど、それは当たり前のこと。だって、これまでは、すべてを無理矢理二次元に置き換えてきたんだから。
あと、僕がVRを制作して感じるのは、やっぱりこれまでのクリエイティブは「感覚の分断」による進化だったんだなあ、ということね。
――感覚の分断ですか?
水口氏:
僕たちは何かを表現するときに、視覚は視覚、聴覚は聴覚、言葉は言葉として表現することが多いじゃない。でもね、本当はさ、人間が最初に何かをイメージするときは、最初から分かれてないでしょ?
――ああ……それはなんとなく分かります。実際、自分がライターとして文章を書いているときだって、本当は脳内では取材したときの風景や音声、ときには匂いや触り心地、さらにはそのときの感情まで思い出しながら文字にしているわけですよ。
水口氏:
でしょ?
結局、これは人間がずっと抱えてきた問題で、本当の発想やイマジネーションはそもそも統合的で、印象に境目なんかないはずなんです。ところが、それを表現するときには、「映像ではこんな感じ」「言葉ではこんな感じ」と、部分的に抽出する方法をとってきた。
――よくわかります。そもそも紙なら文字と絵、AV機器でもせいぜい四角い画面に動画と音楽を乗せられるだけですからね。逆に言えば、画家や歌手や物書きのような存在というのは、そういう貧弱なメディアしかなかった時代に、それでも何とかイマジネーションの統合体験を表現すべく、特定の感覚器官をいびつに酷使してきた職業に過ぎないのかもしれないのかな、と。
水口氏:
長い目で見ると、VR以後の進化の先に見えるのは、そういう分断がなくなっていく未来だと思う。人は、より自然な形で自分の心の奥底にあるイマジネーションを、共感覚的なままに伝えたり、体験できるようになるんです。
――物書きの世界だと「文章一本で全て表現しきれる技術があるやつは偉い」みたいな価値観はあるんですよ。でも、本当に大事なのは本人が心の奥底にどれほど魅力的な表現内容を持ち合わせているかであって、そこはマルチメディア表現の「解像度」と利便性が上がる中で、今後厳しく問われていきそうですね。
水口氏:
まだまだしばらくは20世紀的なメディアの呪縛から解けるのには、時間がかかるでしょう。でも、徐々にみんなの感覚が開いていくんじゃないかな。
――いまお話を聞いていて、水口さんが以前にTED×Tokyoで「ゲームの未来は“感覚のドラマ”になっていく」と話されていたのを思い出したんです。そのときは「何言ってるんだ、この人?」としか思えなかったんですが(笑)、「Area X」と今のVRの未来の話を踏まえると、驚くほどクリアに分かる気がしました。
※TED×Tokyoでの水口氏のスピーチ。まさに「四角いディスプレイ」の前でKinectを使った『Child Of Eden』での演奏をしたあとに、未来のゲームは「感覚のドラマ」になっていくと語っている。
水口氏:
……これで2011年か。これもまだVR前夜だね。
少人数で開発された『Rez infinite』
――ちょっと話を現実に引き戻しますが、『Rez Infinite』って何人くらいのプロジェクトなんですか?
水口氏:
えっと……プログラマーが4人、アートが3人、ゲームデザイン、プロダクションマネジメント、プロデューサー、サウンドが1~2人ずつ。だから、全部で12〜13人かな。20年近く一緒に仕事をしてきた小寺功くんのスタジオMonstarsと僕のスタジオResonairとの合同チームです。
ちなみに、全体の開発期間は15ヶ月で、「Area X」そのものの制作期間は……半年くらいかな。開発がスタートする前に、アートディレクターの石原孝士と、1年半くらい細々とプリプロダクションを続けてたんだけどね。
――現代のゲーム開発として見ると凄まじい体制ですね。今ってもう、数百人規模で何年もかけて開発するのが当然の世界じゃないですか。
水口氏:
それは、もはや過去のイメージになりつつあると思うよ?
最近は多くの人たちが独立するようになったし。そうすると自ずと、効率を考えるようになるし、無駄がなくなっていく。いい開発エンジンも普及したし。だから、本当はみんなもっと、どんどんインディペンデントになって新しい潮流を生み出した方がいいんだけどね、アメリカみたいに。
――水口さんがセガを飛び出されたのは、やはりそういう想いからですか?
水口氏:
いや、僕の場合は、「これ以上、セガにいても会社に迷惑をかけるだけだな」と思ったから(笑)。やっぱり自分の好きなことを自由に続けるためには、自分でリスクを負うしかないもん。
 |
その後は、自分に合った物作りの体制を試行錯誤してきた感じだね。
――今の開発のチームって、内製というか全員社員なんですか?
水口氏:
いや、社員とかじゃなく、アライアンス制なの。
Enhance Games【※】はハリウッド映画におけるパブリッシャーや配給会社みたいなもの……と言えばいいかな。新しい企画やIPを生み出して、資金を集めて、プロダクション設計して、マーケティングやパブリッシングを行うのね。MonstarsやResonairのようなスタジオや、個人のクリエイター達と契約してアライアンスを組んで、制作に入る。アメリカの映画業界と同じ構造です。
※Enhance Games
水口氏が発足、CEOを務めている開発会社。カリフォルニアはに籍を置く米国法人。
――とはいえ、ここまで話してきたような水口さんのビジョンを理解できるスタッフなんて、そうそういないと思うんですが。
水口氏:
まあたしかに過去作品を一緒に経験した人が多いけど……でも、これからは、いろんな可能性があるからね。基本的な考え方は、自分の仕事に責任を持てて、自分でマネジメントできるクリエイターやスタジオとアライアンスを組むこと。だから、マネージャーも置かないし、人事もナシ。
――そんなやり方が成立するんですか?
水口氏:
クリエイター集めて会社を大きくしようとかやり出すと、質の低下を招くでしょ? これは僕がずっと試行錯誤しての、一つの結論です。実際、ハリウッドでは監督も、俳優も、多くの専門スタッフも、基本一人一人がインディペンデントでいて、ユナイトする形でスタジオがある。社員クリエイターとかはいない。
――となると、シリコンバレーのサービス開発のように、プロジェクト単位で離散集合していくイメージですか。
水口氏:
将来考えられるプロダクトの計画を、なるべくメンバーにシェアして、そこからコミット度の部分を交渉する感じです。例えば、「20%は別の仕事をやりたい」と言われたら、僕は「自分にとって必要なものはやって。ただ、この80%のコミットはしっかりね」、みたいな感じでね。
 |
人間、自分がやりたいものに対するコミットメントのパワーは凄まじいわけで、妨害するとブレーキになっちゃう。それに結局、そういう仕事をやってもらった方が、才能の伸び方も全然違う。自分の100%の時間を、寝る間も惜しんで150%使う人もいるでしょう?
ところが、社員になると、「会社が給料払ってるんだから、この人に何か仕事を与えておかないと」みたいな変なパワーが働いて、だんだんおかしくなっていくんです。
――いや、なぜこんな話を聞いたのかというと、「Area X」なんてどう見てもカッチリとしたスタジオの制作体制から産まれてくるようには思えなかったんです。
水口氏:
それは……どちらかというと、チーム間での意思疎通とか、意思共有の話かもしれない。例えば、『Child of Eden』のときもそうだったんだけど、アートディレクターの石原くんには、綿密なシナリオじゃなくて、最初に「詩」のような文章を書いて渡したりとかしたんだよね。
――あ、それは昔、業界の水口哲也伝説として聞いたことがあります! 企画書としてポエムを渡された、と……(笑)。
水口氏:
(笑)。
でも、相手の発想に火をつけるときには、綿密に書かれた文章を渡すよりも、あえて行間をたくさん作る方がいい時もあるんだよね。それを埋めるために、自分から能動的に作品のことを考えていくようになるから。これがない状態で最後まで行くと、多くのスタッフが、口をぱくぱく開けて仕事を待っている状態になってしまう。
――それは、やっぱりセガが町工場みたいな規模から大企業になっていく中で、体験されたことなんですか。
水口氏:
そこは単純に……気持ちのいい雰囲気で仕事をしたいからね。クリエイターが強くなって、プロジェクト単位で結束して、ライフタイムで利益分配されていくような仕組みが一般化できれば、もっと作品やクリエイターが中心の業界になると思うんだよね。
だってさ、クリエイティブを理解できないマネージャーがクリエイターを評価する会社なんて、ひどいと思わない? お互いにとってとんでもないストレスだよ。
――ははは、まさに(笑)。でも、水口さんがセガで無茶なことを言って、みんなを困らせているという話を清水さんが聞かされていた頃からすると、本当に水口さんの製作を取り巻く環境は大きく変わっているんですね。
水口氏:
テクノロジーが大きく進化したからね。僕はこの状況を支えているのは大きく2つあって、UnityやUnreal Engineのような開発エンジンを自由に使えるようになったこと、それと流通がデジタルに変わって、パブリッシング自体が大きなリスクじゃなくなった、ということだと思う。
――ちなみに、今回、『Rez』のVR化を持ちかけたのはソニーですか?
水口氏:
いや、最初は自分で借金してスタートしてます。
 |
Kickstarter【※】も考えて、アメリカに法人を立ち上げたんだけど、当時は他のプロジェクトが大炎上して大荒れになっていた時期で、クラウドファンディングは泣く泣くあきらめたのね。そこで、まずは自分でEnhanceを立ち上げて、セガに『Rez』のライセンスアウトをお願いしに行った。
※Kickstarter(キックスターター)
世界でもっとも大きなクラウドファンディングのプラットフォームの一つ。2009年にアメリカで設立。クリエイティブなプロジェクトやユニークなアイディアを持つクリエイターたちのに向けてクラウドファンディングによる資金調達を行う手段を提供している。
――凄い執念ですね。
水口氏:
で、セガからOKをもらって、アメリカのSIEと話をしてプロトタイピング【※】して、「Area X」を作り始める頃にEnhanceとして最初の資金調達をして……という流れですね。
※プロトタイピング
試作品(プロトタイプ)の制作する行為、及びその過程。
――確かに、実はクレジットのスペシャルサンクスを見ると、元ガンホー会長の孫泰蔵さん【※1】だとか、『ITビジネスの原理』著者の尾原和啓さん【※2】のような、日本のIT業界の知る人ぞ知るプレイヤーたちがいますよね。
※1 孫泰蔵
1972年生まれ。佐賀県出身の連続起業家、実業家、投資家。元ガンホー・オンライン・エンターテイメント会長。兄はソフトバンクグループの創業者である孫正義。2009年にスタートアップ支援をするためにMOVIDA JAPAN株式会社を設立したことでも話題となった。その後2013年には、さらに広範囲なスタートアップ支援を行うべくMistletoe株式会社を設立。IoTスタートアップの育成を行う株式会社ABBALabや、インダストリアル・デザイナーの起業教育を行うGEUDA一般社団法人など、数多くの起業家・スタートアップ育成活動のサポートをしてきた。「Slush Asia」の仕掛け人のうちの1人としても有名。
※2 尾原和啓
1970年生まれ。日本の執筆家・IT批評家。マッキンゼー・アンド・カンパニーにてキャリアをスタートし、NTTドコモのiモード事業立ち上げ支援、リクルート、ケイ・ラボラトリー(現:KLab)、コーポレートディレクション、サイバード、電子金券開発、リクルート(2回目)、オプト、Googleなどの事業企画、投資、新規事業に従事。ボランティアで「TED」カンファレンスの日本オーディションに関わるなど、米国シリコンバレーのIT事情にも詳しい。
水口氏:
尾原さんがいろんな人に声をかけてくれてね、すごく嬉しかったな。
尾原さんはGoogle時代にTEDxTokyoの運営チームにいて、2011年に登壇を依頼されたときから友人なんですよ。そして孫泰蔵さんは『スペチャン』が好きでいてくれて、最初に背中を押してくれた。「Area X」や「シナスタジア・スーツ」の構想も、迷わず「やった方がいい」って言ってくれたんです。モブキャスト代表取締役の藪考樹さんやB Dash Venturesの渡辺洋行さんも出資を名乗り出てくれた。みなさんが最初の支援者です。いつもいろいろアドバイスをもらってる。本当にありがたいです。

――しかし、ここで名前が挙がってるのがIT業界の人間たちで、ゲーム業界の人間たちじゃないことに僕はある種の悔しさとダメさを感じてしまいますね……。一方でこのクレジットを見ると、いかに水口さんがゲーム云々以前に、正しくコンピュータ文化の流れを汲んだ出自の人なのかが分かるわけですが。
水口氏:
確かに、そう言われてみるとそうだね。
だけど、もうゲームもITもVRも境目はないからね。ITの方がVRに近いという感じもあるし。むしろこの方が自然な流れなんじゃない?
Rezの今後は
――それでは、さすがにそろそろ取材は終わりなのですが、今後水口さんは『Rez』をどう展開していく予定なのでしょうか。
水口氏:
今回の『Rez Infinite』の「Area X」は、実験でもあり予告編でもあるという位置づけです。なので、何年後かには必ず、このプロローグの本編に取り掛かります。
一同:
……え。
――何年後かなんですか……。もう出来た端からDLできるようにしていただけたりしないのでしょうか……。
水口氏:
……(笑)。まあ、そういう考え方もあるよね。
ただ、じっくり時間をかけて準備したいんだよね。まあここまで時間が経っても消えなかったから、きっと大丈夫でしょ。
――ううむ。ちなみに、僕は『Rez Infinite』の「Area X」って、出てからずっと眠る前に必ずやってから寝ていて、就寝前の音楽のように使っているんです。なので次のステージがそろそろ欲しくて……。
水口氏:
いやあ、その話はすごく嬉しい……。寝る前や週末とか、ちょっとした時間に、そんな風に遊んでもらえたらなあと思っていたから。
――そうしたら、やっぱりDL販売というモデルは一つアリなんじゃないでしょうか。いま娯楽ってソーシャルゲームのような隙間時間に次々に体験を提供してくるモデルか、フェスや映画のような大規模な祝祭的な娯楽でドンと年に一度稼いでいくモデルが強いですけど、そこにVRや海外ドラマはその中間の辺りで継続的に濃密な体験を与えるコンテンツとして台頭していますよね。いや、要は、新作が欲しいわけですけど(笑)。
水口氏:
そっか……一度スタッフと検討してみます。
でも、そんなにプレイしてくれてるのは、本当に嬉しいな。ちなみに、やり続けていると、どういう「Wants」が出てきます?
 |
――新作がやりたいですね。
水口氏:
ははは……(笑)。
――ジャンキーみたいですみません(笑)。ただ、とりあえずある程度プレイした頃から、あえてビュンビュン飛び回りながら撃っていくようになりましたね。もちろん、「気楽に」モードですが。15分くらいで終わる気持ちよさを最大限に引き出すには、それがいいのかなと。バイクでちょっと外を走ってくるような感じかもしれないです。
水口氏:
音楽に対して何か「Wants」は?
自分で音をカスタマイズしてみたい欲求とか……演奏する楽器も変えられるようにして、自分の好みにBGMをチューニングしていくとか?
――不思議とあまりカスタマイズの欲求は生まれないゲームので、ちょっと分からないですね。ただ、昔『ウイングコマンダーIII』【※】という宇宙戦争のゲームが、ロックオンしたりミサイルを撃つたびに曲が変わっていって、音楽でゲームにのめり込ませてきたのが印象的なんです。個人的には、そのゲームに比較すると、むしろ『Rez Infinite』の音楽の変化は控えめな気がしていますね。もっと座禅を組むモードになったら曲がテンポアップしたり、スピードを上げたときには音と光がもっと強烈にスパークするような感じで、気持ちにより「シナスタジア」があると、嬉しい気がしますね。

(画像はソフトウェアカタログより)
水口氏:
なるほどね……。
VRの空間を他の人と共有したいとかはどう? たとえば殺伐としていない形での、もっとみんなが幸せになれる一期一会のようなソーシャル要素が、VRの中に作れないか、とか。
―― 『Rez Infinite』ってあらゆる体験がソーシャル性の快楽を前提に設計され始めた時代に、全くの個人的な体験でありながら凄まじく面白いというのが、逆に鮮烈だとも思うんです。でも、僕らがもっとVRに慣れたときに、またソーシャルの快楽を求めていく気もしてしまうのも事実ですね。
水口氏:
孤独感とか寂しさの中にソーシャル感が入ってくると、感情がまた刺激される気がするんだけどね。
例えば『バーニングマン』【※】みたいに、広大なネバダの砂漠で凄い孤独感の中にいても、砂漠の真ん中で誰かと出会うと、人間的な感情が鋭敏に伝わってくる。あの感じっていいなあ、とも思うんだよ。
※バーニングマン
アメリカ合衆国で開催される大規模なイベント。会場は、ネバダ州リノ市の約150km 北北東に位置するブラックロック砂漠。参加者はそこで、あらゆるインフラを断たれた状態で一週間過ごすが、食料含め必要なものは自力で調達しなければならない。会場内での貨幣の使用や商行為は明確に禁止されており、見返りを求めない「贈り物経済」と「親切なこころ」でコミュニティを成立させることが求められる。
――あ、バーニングマンに行かれているんですね。
水口氏:
1998年頃から行ってたんですよ。
今は7万人とか集まっちゃう場になったけど、僕が行き始めた当時はまだ3千~5千人くらいだったので、場が本当にピースフルなんだよね。ああいう過酷な自然の中で、人に寄り添いあっていると、自然に翻弄されながら一生懸命に奉仕しようとする人間という存在が、本当にチャーミングに見えてくる。しかも、それが何千人といるわけで、実に独特の雰囲気の場所だったなあ。
――確かに、VRの中にそういう空間が生まれたら、本当に面白いかもしれませんね。
VRは次の時代への“踏み台”に過ぎない!?
――さて……大体聞いてしまったあげくに、こっちまで質問されてしまった状況なのですが(笑)、最後に一つだけいいでしょうか。よく編集部でもプレイした人間たち同士で、「なんで『Rez』はこんなに酔わないんだろう?」と話し合うんです。水口さんは、その秘密って分かりますか?
水口氏:
みんなで気分悪くなりながら、スタッフ総出で細かいところまで徹底してチューニングやったからね(笑)。中盤からファイナルにかけては、スタッフ総出でその調整をひたすらやってた。何をどうすれば酔うのかも、だいたい体でわかってきたと思う。
――そうなんですね。いや、実は取材前に読んだインタビューで、『Rez Infinite』が酔いにくい理由として、水口さんが「みんな、本当は空を飛びたい願望があるからじゃないの?」と言ってて凄く面白かったんです。
水口氏:
「Area X」を考える過程で、ほんとうはVRで何を体験したいんだろうって思ったら、素直に、飛ぶように、泳ぐように、その空間を移動したいって思った。空を思うがままに飛び回りたいって思ったんだよね、単純に。
でも周囲のスタッフの反応は……「そりゃ酔いそうだね」と(笑)。
 |
――なるほど(笑)。
水口氏:
でも、もしそんな気持ちの良さそうな体験も実現できないのなら、VRっていうメディアの未来にはコミットできないなあ、とも思った。で、試してみたら、意外にも酔わなかった。やっぱり、『Rez Infinite』は現実模倣の作品じゃないのが大きいと思う。
――VRって、リアルなゲームほど酔うんですよね。
水口氏:
僕らが経験的に思い込んでいるディメンション(次元)が、自分の意思とは無関係に動いたときに、「酔い」は生まれやすいのかな、と思う。プレイヤーにちゃんと主導権があれば、脳が混乱を起こしにくいとも言える。そういう意味では『Rez Infinite』の世界って、ディメンションも感じにくいし、酔いにくくなってると思う。
――ちなみに、ちょっと言うと、先ほど水口さんに挨拶に来たドワンゴVR部のエンジニアの一人が、VR酔いに慣れるために、毎晩Oculus Riftをつけて寝ていたらしいんですよ。そしたら、VRで酔わなくなった代わりに現実空間で酔うようになったと言うんです(笑)。
水口氏:
……へー、なるほどね(笑)。
――ただ、僕も一度『Rez Infinite』をぶっ続けで何時間もプレイしたあとに、ヘッドギアを外してふと周囲に視線を合わせたときに、視線を合わせた箇所が何も反応しないことに、ちょっと「くらっ」と来てしまったんですよ。でも、これって「酔い」の構造からすると、自然な気もするんです。つまりはVRで現実で可能な行動よりも理想的な行動ができるようになって、それが脳の経験として蓄積されたときに、実は現実の側に私たちは「酔い」を覚えるという「反転」も起きうるのではないかと……。
水口氏:
実はさ、人間の経験のほとんどはイリュージョンだって思わない?
ディズニーランドの体験だってイリュージョンだし、都市だっていろんな人のイメージの外在化だし。腕を失った人が幻肢に苦しむのも、その証拠だよね。VRの経験を、脳がリアルの体験として認識していくのは、フツーの話だと思う。
ただ、それすらも過渡期の話でしかない気もするなあ……。本当は僕はVRの時代なんて早く終わればいいと、いつも思ってるの。
 |
――ええー、そうなんですか(笑)。
水口氏:
VRは次のステップへの過程だと思うよ。
これからVRで共感覚的な統合体験がたくさん生み出されるだろうけど、その体験は今度は現実の世界にインストールされてくるはず。ARやMRの技術とともに。そこにIoTやAIような技術も結びつく。
インターネットの接続が当たり前になると、もうあらゆるものが融合していくだろうなあ。その世界では、これまでで言うところの「映像」メディアなんかは、あらゆる角度からセンサーでスキャンされている世界の、「たまたま視覚の側面を切り取ったもの」でしかなくなると思う。
――水口さんが、そういう時代に作りたいと思うのは、どんなエンターテイメントですか?
水口氏:
例えばだけど、新しい時代のミュージカルとかね。人間の演じるミュージカルに、さらに大きなイマジネーションが合成されて、リアルの演劇表現などでバラバラに進化してきた数々の手法が、どんどん統合されていく――そんな新しいストーリーテリングは面白そう。またジャンルとかカテゴリーとか難しいと思うけど(笑)。
――『Rez』もゲームショップでどの棚に置いていいか分かりにくかったですが(笑)、もはやこれは地上のどんな場所にあるべきかも分からないですね。
水口氏:
時折、カテゴリーとかジャンルとか、肩書きとか、正直どうでもよくなっちゃう(笑)。もちろん、ゲームデザイナーとしての自分も確実に存在しているんだけど、もうそれだけでは無理ですね。
――まだまだ孤独は続くかもしれない(笑)
水口氏:
いやいや、以前に比べれば、ずいぶん仲間がたくさんいます。
シナスタジアを理解してくれる人は増えたし、若い才能のあるスタッフも増えたし、テクノロジーも進化した。ついにVR技術が成熟して、そのうちARやMRもやってくる。開発エンジンのクオリティも上がったし、アイデアやイメージさえあれば、もはや表現できないクリエイティブはなくなってくる。ここから先、時代の進化のスピードは、皆が思っているより早いと思う。クリエイティブ的には、どんどん理想の環境に近づいてる。
だからね、ここからは楽しく行きたいです。新しい体験を生むためには、大きなエネルギーが必要だから。マグマ溜りみたいに、溜め込んで一気に噴出させるの。やっぱり、それがないと大きなジャンプは生まれないから。
――今日は本当に長い時間、ありがとうございます。まあ、そこは溜め込まずに「Area X」の続きを早く出して欲しかったりもするファン心理もあるのですが……(笑)。(了)
 |
インタビューの開始前、水口氏に『Rez Infinite』をプレイする様子を見せていただく機会を得た。
その際、水口氏は「僕のプレイは別に上手くない」と言いつつ、「でも一番気持ちよくなるようにプレイしようとしている」と照れていた。上の写真はプレイ時の氏の姿であるが、しみじみと味わうように自分のゲームを操作する様子が、とても印象的だ。ゲームの表現力が上がったとき――ゲームデザインが生み出す「達成感」とも、映画のようなストーリーの「面白さ」とも違う――ほとんど言葉に尽くせぬ感覚の生み出す「感動」が可能になる。
その後のインタビューで語られた話を聞きながら、筆者は目の前に、取材前に『Rez』をプレイしたときの、この氏の姿を思い浮かべていた。
そもそも当日、我々は水口氏のパブリックイメージから、理知的で落ち着いた雰囲気の取材になることを想定していた。
だが、知己の清水亮氏に盛り上げていただいた面も多分にありつつも、とにかく現場は氏の溢れかえるようなエネルギーに巻き込まれ、7時間、最後まで笑いが絶えない熱気溢れる場所となった。歯医者の予約をその場でキャンセルして、にっこりと「今日はどこまでも付き合いますよ」と言い放つ氏の姿には、「水口哲也という人間を、我々は理解できていなかったのだな」と圧倒されたものである。
そんなエネルギーの塊のようなハチャメチャ人生の果てに、氏が辿り着いた『Rez Infinite』。しかし、それも今や水口氏が30年近いクリエイター人生の中でやっと踏み出せた「第一歩」でしかない。長く縛り付けられてきた「制約」を振り払ったその場所で、水口氏は次に何を描き出すのか。その光景を全身で味わえる日を楽しみに待ちたい。