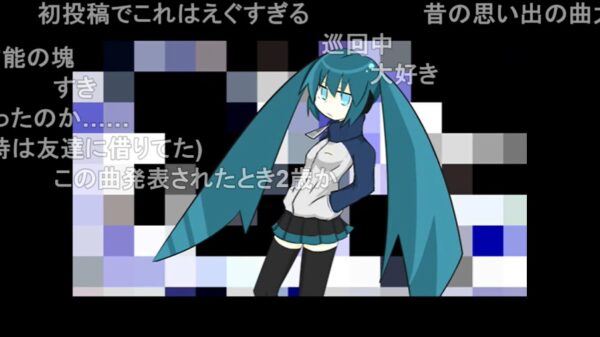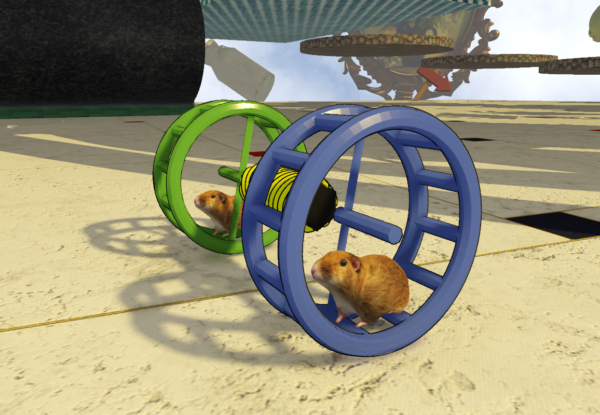『サイレントヒル』や『SIREN』といった名作ホラーゲームを手がけた外山圭一郎氏の新作『野狗子: Slitterhead』(以下、『野狗子』)が2024年11月8日に発売された。
不気味な怪物の姿、そして飛び散る人間の体と血……。タイトル発表時に公開されたトレーラーに映し出された光景を見て、「どんなホラーゲームになるんだ?」という期待の声が国内外から寄せられていた。
しかし、実際に触ってみると、いい意味で想像していたものとは異なる体験が待っていた。
人間の体に憑依して怪物と戦うアクション要素もあれば、しっかりとホラー的エッセンスも感じられる。1990年代香港を感じさせる独特の世界観はケレン味があり、精神生命体である主人公と「稀少体」と呼ばれる人間とのドラマにも引き込まれる。なかでも、憑依による移動のスピード感は、ほかのゲームでは味わえないゲーム性を有している。
しかしながら、本作をひと言で説明するのは難しい。なぜなら、ホラーの定義はプレイヤーそれぞれで異なるし、『野狗子』が提示するゲーム体験が新しいものだからである。
かつて『サイレントヒル』でサイコホラーを生み出し、『サイレン』でホラーアドベンチャーというジャンルを確立してきた、外山氏らしいタイトルと言えるだろう。

このたび電ファミニコゲーマーでは、『野狗子』の魅力に迫るべく、開発を担当した「Bokeh Game Studio」(ボーカゲームスタジオ)の中心メンバーにインタビューを実施。
『野狗子』というゲームがどのような発想から生まれ、どのように作られたのか。本作のクリエイティブディレクターを務める外山圭一郎氏、プロデューサーを務める佐藤一信氏、ゲームディレクターを務める大倉純也氏のお三方に話をうかがった。
また、『野狗子』は外山氏らがSIE(ソニー・インタラクティブエンタテインメント)から独立後に手がける初タイトルでもある。開発体制や苦労話、1作目を作り終えての手応えはどうだったのか。取材では開発の裏側についても話が波及した。

『野狗子』は「もしいまの自分が「SIREN3」を作るとしたら」の発想から生まれた作品だった
──外山さんが手がける新作ということで、発表当初から「どんなホラーゲームになるのか」と、国内外問わず注目を集めていた『野狗子』ですが、まずは本作が「どのような着想から生まれたのか」について教えていただけないでしょうか。
外山氏:
『野狗子』は「もしいまの自分が「SIREN3」を作るとしたら」 という発想から考えた作品になっています。
きっかけは、SIEに在籍していた時期に遡ります。当時、『SIREN』がリバイバル的に人気が復活していたため、関連作品を作ってもいいのではないかという話があがったんです。しかし、会社的に求めているのはAAA級タイトルでした。
そこで、『SIREN』的なコンセプトかつ、AAA級なゲームの構想を考えたわけです。その案の中のひとつが、『野狗子』の原型に繋がっているんですね。
──「SIREN3」の構想がベースにあるんですね。
外山氏:
最近は「ホラー」の看板を掲げる作品が増えていますが、個人的にホラーとAAA級作品というのは相性が悪いと思っています。
では、どういう切り口ならばホラーとAAA級作品の組み合わせが成立するのか。もし「SIREN3」を作るとしたらどういう作品になるのか。そう考える中で「地方都市」という舞台のイメージが浮かびました。
寒村や孤島という舞台設定をチョイスした『SIREN』シリーズともテーマは一貫していますし、ホラーの在り方としてより難しいチャレンジをしたい気持ちもあったわけです。ただ、実現が難しいと感じていました。そんなとき、香港を訪れる機会があったんですね。
──香港を訪れたとき、どんなインスピレーションを受けたんでしょう?
外山氏:
それ以前にも出張で香港に行く機会は多かったのですが、ネオンの彩りや雑多な街並みなど「昔の良さ」みたいなものが年々減っていたんですね。もちろん現在の香港も魅力的ですが、自分の中で香港と言えば、頭に浮かぶのは「80年代、90年代の香港」。じつは実際にその時代の香港を見られてはいないのですが、「行ってみたかったなあ……」と寂しさが湧いてきたんです。
同時に、これだけ自分が「見たかった」、「行きたかった」と思う場所なのであれば、同じような気持ちの人はきっといるはずだとも考えたんです。そして、香港という舞台であるならAAA級のゲームだったとしてもオープンワールドのような形で成立させることができるのではないかと。
そんなことを考えているあいだに諸事情あって独立することになりました。そうなるとAAAというわけにはいかないので再考が必要になりましたが、どうも原案として捨てられなかったみたいです。
──会社独立の際、本作の企画を進めることは、ある程度決められていたのでしょうか。
外山氏:
ほかにも何種類かの原案を用意して、佐藤と大倉に提案しています。その中で『野狗子』の原案が採用され、開発することになりました。
──『野狗子』は「CERO:Z」(18才以上のみ対象)指定ですが、その前提で作られたのでしょうか? それとも結果的にCERO:Zになったのですか?
外山氏:
じつは最初からCERO:Zの想定で考えていました。SIE在籍時代にはなかなか実現できなかったので、今回は思い切って挑戦してみようと。
佐藤氏:
そうですね。実際にどうなるのか試してみたいという興味がありました。
──CERO:Zもそうですが、プラットフォームもプレイステーションのほか、Steam、Xboxと、幅広いハードで発売されたことも外山さんにとっては初めてのチャレンジですよね。
佐藤氏:
やめておけばよかったと思う瞬間もありました(笑)。
外山氏:
CERO:Zなら大丈夫だと思っていた表現でも、許されないことも意外と多いんですよね。その点は予想外でした。
佐藤氏:
CEROの担当者から「これはダメです」、「この表現のままでは発売できません」、「CERO:Zを越えた表現なのでやめてください」といった指摘を受けることも多く、「どうしよう……」と焦ってしまうこともありました。
ただ、血まみれな姿や部位欠損については、とくに触れられなかったのが印象に残っています。開発中は、現状よりもセクシャルな表現を攻めていて、そこが調整の多いポイントでした。もしかしたらそちらが目立ちすぎてしまったのかもしれません(笑)。
一同:
(笑)。
「脳を吸いとる」描写であれば、ゲームとしても表現しやすい
──本作のタイトル名は『野狗子: Slitterhead』(やくし スリッターヘッド)と、独特なネーミングですが、これも企画初期から決められていたのですか?
外山氏:
最初から「野狗子」という名前は決まっていました。ただ、欧米圏での展開を考えた際に、英語のタイトル名もあったほうがいいだろうということで「Slitterhead」を追加した形になります。
佐藤氏:
いま振り返ると、「Slitterhead」というタイトルも良いものになったと思います。
外山氏:
エゴサ(エゴサーチ)しやすい名前というのは重要ですからね。
──PCやスマホで「やくし」と打ち込んでも「野狗子」とは変換できないですよね。
佐藤氏:
それはわかってたことなんですけど、本当に困りました。
難しいですよね。わかりやすい言葉なら浸透するかといえば必ずしもそうではないですし、少し謎めいているくらいのほうが興味を持ってもらえるかもしれない。
海外では、漢字自体が視覚的なインパクトを持っていますし、それをエフェクトの一部として楽しんでもらえればいいかなと。結果的に『SIREN』や『サイレントヒル』みたいに「S」の文字も入りましたし。
──『野狗子』が発表されたのち、死人の脳を吸う妖怪として中国の短編小説集『聊斎志異』に「野狗子」が描かれていることを知りました。外山さんはもともとこの存在をご存じだったんでしょうか。
外山氏:
いえ、まったく知りませんでした。作中における敵の設定を考えていた際、「人を食べる怪物」ではありきたりなので、着想のヒントを探していました。
そこで「脳を食う怪物」というのを見つけて面白いなと思ったのが、「野狗子」を知ったきっかけです。
──なるほど。企画を考える中で見つけられたと。
外山氏:
その流れについては、自分が好きなコミック的な手法が影響している部分があるような気がします。
というのも、諸星大二郎先生や山岸凉子先生の作品のように「冒頭で伝承が語られて、それをモチーフにした現代劇が描かれる」というアプローチがすごく好きなんですよ。
加えて、ちょうどその時期には、ゲームとしての表現について苦心していました。「人を食い散らかす」ような描写はレーティング的に考えてもゲームで表現するのは大変です。「脳を吸いとる」描写であれば、差別化も図れてゲームとしても扱いやすいと考えていたんです。
佐藤氏:
それを聞いて思い出しました。初期のころは「どこまで残虐的な表現をしていいのか」という議論を何度もしましたよね。
「肉片が転がる」、「断面図をリアルに描く」など、最初はもっと生々しい表現も検討していました。ただ、我々としてもユーザーさんに「気持ち悪い」と感じてほしいわけではないので、かなり慎重に調整しました。
でも、少しでも気を抜くとすぐにそっちの方向性になってしまって……。数えきれないほど調整をお願いした記憶があります。
大倉氏:
何度も止めましたね。腕が切れてしまう描写は必要だけど、それを気持ち悪く感じさせるように描く必要はない、と。
佐藤氏:
ですので、脳を吸いとる野狗子という存在は我々としてもちょうどよかったというのはあります。体を食い散らかされたらたまったもんじゃありませんから(笑)。恐らく、気持ち悪くて遊んでられない作品になってしまいます。
『SIREN』の「視界ジャック」を発展させた「憑依」
──『野狗子』の特徴のひとつである「他人に憑依する」という要素は初期から考えられていたのですか?
外山氏:
はい。『SIREN』に存在した他人や屍人の視覚を乗っ取る「視界ジャック」を発展させたのが、本作の「憑依」というシステムです。
──本作では、上階にいる人間に憑依することで階段を上らなくてすみますし、落下中に地上の人間に憑依して損傷を免れるなど、独特の移動が可能となっています。横軸だけではなく、縦軸の動きがシステム的に可能となっているわけですが、移動に自由度と爽快感を持たせるとするアイデアは、どのような経緯で生まれたのでしょうか?
外山氏:
縦軸の移動に対するイメージとしては、香港をモデルに舞台を作ろうと考えた最初期の段階からありました。ネオンサインの上に立ち、看板から看板へとジャンプしながら敵を追いかけるといった立体的なアクションは、体験させたいことの根幹として頭の中にありました。
『GRAVITY DAZE』(『グラビティデイズ』)【※】を経験しているからでしょうか。そのイメージと重なり、当たり前のように、そこは考えていました。
※『グラビティデイズ』……2012年2月9日に発売されたプレイステーション Vita用ソフト。壁に張り付いて歩く、物を浮かせて投げる、地面を高速移動するなど、重力を自由に操ることできるアクションゲームで、正式タイトルは『GRAVITY DAZE/重力的眩暈:上層への帰還において彼女の内宇宙に生じた摂動』。2017年には続編『GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択』が発売されている。
──その辺を歩いているおじさんやおばさん、いわゆる「モブキャラ」に憑依して操作できるというアイデアも、企画段階から存在していたのでしょうか。
外山氏:
そうですね、わりと初期の段階から存在していました。
──外山さんからの「憑依」というアイデアを、大倉さんはディレクターとしてどのようにゲームに落とし込んでいったのでしょうか。
大倉氏:
憑依、とくに「人(モブキャラ)を使い捨てる」という要素については、自然とそうなったと感じています。
外山の初期案の中に、「誰にでも憑依できて、自分自身の体がない」、「その状態で天敵である野狗子と数で戦う」とあったので、それをゲームに落とし込もうとするとこうなるのかなあと。
──実際にプレイしてみると、想像していた以上にスピード感があるのが印象的でした。
大倉氏:
じつは、初期段階では現在よりさらにテンポの速いアクションだったんです。ただ、視点の動きやカメラの振動も大きく、チーム内で酔ってしまう人もいました。
アクションプログラムを担当するチームの若手エースと何度も話し合い、ユーザーにとって「使いやすく、気持ちよく」操作できる速度を模索し、現在の速さに落ち着いています。カメラの挙動や速度の調整に数ヵ月はかかっていますね。
──「憑依」が移動だけではなく、バトルで活用できることに独自性とおもしろさを感じました。モブキャラを囮に使えたり、命を使い捨てにしたり、さらには爆発させるスキルまであったりと、すごくインパクトがありました。
佐藤氏:
爆発させるスキルは確かにインパクトは大きいですね。ゲーム的にも効果的にダメージが与えられる手段ですし。
──モブキャラを使ったアクションというアイデアは、どのように考えられていったのでしょうか。
大倉氏:
基本的には「憑依」を軸に連想していく形で固めていきました。たとえば、自分が他人に憑依するだけの力しか持たず、周囲の人間を駒のように扱えたらどのように戦うだろうか……という発想ですね。
倫理観を捨てて「まわりの人間は駒だ」と割り切ったとき、血を爆発させるといった荒々しい戦術も思い浮かびました。こうしたアイデアをどんどん組み合わせていったものになります。
たとえば、最初は「ショットガンで自分の腕ごと吹っ飛ばして、その血を使って攻撃する」という、もっと過激なアイデアもありました。
──(笑)。街全体で、乗り移ることのできるモブキャラは何人くらいいるのですか?
大倉氏:
街全体で何人いるという設定ではなく、エリアごとに設定しています。このエリアに100人、あのエリアに100人、といったような配置です。
処理負荷に応じて自動的に表示数を調整しているので、具体的な総数は言いづらいですね。多いエリアで80人から100人だと思います。
──それだけ多くのモブキャラが登場するわけですが、ひとりひとりが本当にその街に住んでいるような生活感あふれるキャラクターデザインで興味を惹かれました。
外山氏:
コンセプトとして『SIREN』からの継承という視点もあって、あえて「普通の人」を描くことを大事にしています。
佐藤氏:
もちろん、フォーカスされるキャラクターには多少凝ったデザインをしていますが、モブキャラたちは自然な姿で、その場にいる雰囲気を大切にしています。
大倉氏:
むしろ、上半身裸のおじさんが戦闘で活躍してかっこいい姿を見せてくれるのが面白いんですよね。主人公ではないのですが、独特の存在感があり、そのギャップが楽しいといいますか。
──開発中、愛着が湧いて自然と名前がついてしまったモブキャラはいるのでしょうか?
佐藤氏:
正式な名前はないですが、チーム内で「長靴の親父」とか「パンイチのおっちゃん」などのあだ名が自然とついているキャラクターはいましたね。
開発中は一般人の配置も頻繁に調整が入るので、「あのおっちゃん、どこに行ったの?」なんて言いながら探すこともありました。
外山氏:
ストーリーに影響しない部分では、わりと自由に配置していましたよね。
佐藤氏:
ユーザーの皆さんにもプレイを進める中で、こうしたキャラクターたちに自分なりのあだ名をつけて楽しんでもらいたいですね。
外山氏:
ユーザーの皆さんの方が僕らより面白いあだ名をつけてくれるはずですし、どんな呼びかたが生まれるか楽しみです。