1回目のクレジットを見ても「やめないで!」
──「憑依」システムによる移動や戦闘というアクションがフォーカスされた分、『野狗子』はホラーゲームとして捉えられていない側面があるかと思うのですが、その部分をどう捉えていらっしゃいますか?
外山氏:
その点については、そもそも「ホラーとは何か」という点について、改めて考える必要があると思います。何をもってホラーと定義するのかという問題ですね。
大倉氏:
そもそもみなさんの中に、さまざまなホラーの形がありますからね。
外山氏:
「怖いか怖くないか」だけで判断するなら、僕たちの作品はあまり怖くはありません。『サイレントヒル』や『SIREN』を作っていたときも、個人的には「そんなに怖くないんだけどなぁ」と感じていました。
ただ、怖くないとしても「ホラー的なエッセンス」はあって、僕にとって『野狗子』はホラーだと思っています。
佐藤氏:
ホラーのテイストはあると確信しています。実際、過去に実施したユーザーテストでも、怖さや驚きを感じてくれていた方はいました。
でも、本作では対峙したクリーチャーは倒せてしまうわけです。倒すという爽快感を内包したゲームですので、倒せはするけども倒しに行くのかいかないのか考えさせる作品だった『SIREN』や『サイレントヒル』と比べるとちょっと違う印象になってしまいます。
──世界観そのものがホラーということですよね。
外山氏:
作中では脳みそを吸いとる存在が街の中に潜んでいるわけです。そんなことが起きている時点で、相当おかしい状況になっていますから(笑)。
たとえば、伊藤潤二先生の作品は間違いなくホラーですよね。ほとんどの人がそう答えると思います。でも、似たような要素があったとしても、マンガ『東京喰種トーキョーグール』【※】をホラーと呼ぶかというと人によるところがあるじゃないですか。
陰惨であるとか、 人が死ぬとか、そこでホラーかどうかを定義するわけではないと……。僕としては「怪物に抵抗できるからホラーではない」というのはちょっと腑に落ちない。だから、なおのこと「ホラーってなんなんだろう」となるわけですね。
※『東京喰種』……石田スイが原作を手がけるマンガ。人間社会に紛れた人を喰らう怪人、喰種(グール)が蔓延する東京。主人公の金木研はある事件をきっかけに半喰種となってしまい、苦悩と恐怖に満ちた日々を送ることになる。
佐藤氏:
ホラーファンの方々はジャンルへの愛が高いので、それぞれに「理想のホラー像」をお持ちだと思います。
逆に、本作のように「こういうホラーもあるんだ」という新しい提案として受け止めていただけるとうれしいですね。
──『SIREN』では群像劇かつボーイミーツ的な要素があり、『グラビティデイズ』では少女を中心に、街や彼女自身の物語が描かれていました。『野狗子』では稀少体というキャラクターたちが物語の中心を担っていますが、ストーリーの見せ方をどのように設定されたのでしょうか?
外山氏:
本作の物語で中心となるのは、主人公である憑鬼、そして稀少体であるジュリーとアレックスの3人だと考えています。憑鬼が稀少体であるふたりのあいだで揺れ動いていく……というコンセプトは最初から決めていました。
具体的な展開については、ストーリーを書き進める中で自然に形作られた部分が多いです。シナリオを書く中で、自分でも予期しない展開になり、驚きながら書き進めたこともありました。
作家の方がおっしゃる「キャラクターがひとり歩きする」という感覚です。書き手として、自分の想定を超える展開が生まれる瞬間は、非常に面白く感じましたね。


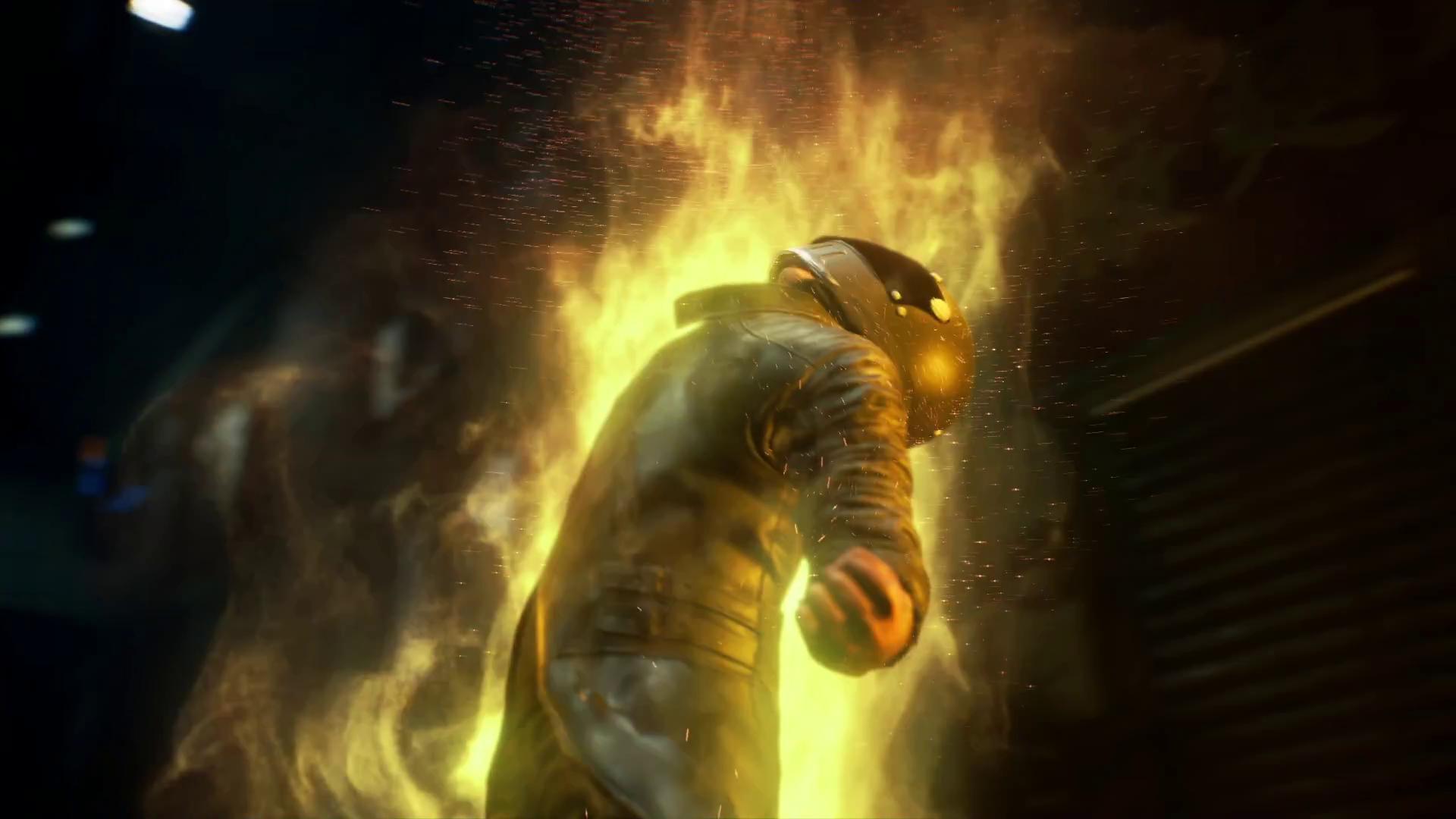
──キャラクターデザインを吉川達哉さんにお願いしようと決めたのはいつごろだったんでしょう。
外山氏:
かなり早い段階でお願いすることを決めていました。ジュリーとアレックスには「一般人の一面を持ちながら、ヒーローである」という特別な存在感を持たせる必要がありました。
それを単に衣装でごまかすのではなく、キャラクターそのものの顔や立ち振舞い、存在感で表現することが求められたんです。
吉川さんのデザインは、その点で非常に優れています。キャラクターを構築する際、外面的な特徴ではなく、その存在自体が持つ独特の雰囲気や説得力を作り上げることができるんです。吉川さんだからこそ表現していただけたキャラクターデザインになっていると思います。
──外山さんの手がける作品には、クリア後に余韻が残るというか、読後感のようなものがある印象があります。『野狗子』でもどんな結末が訪れるのか期待しているユーザーも多いと思います。
外山氏:
う~ん、あるといいなぁ。
佐藤氏:
本作では、含みを持たせつつも、しっかり完結している結末になっていると思います。
外山氏:
余韻や含みが残っているのは、いまの自分たちのスタンスがそのまま反映されているからでしょうね。
──2週目にも仕掛けを入れていらっしゃいますよね?
佐藤氏:
完全な2週目とは少し違いますが、そういった要素も……。
外山氏:
そこは『SIREN』を踏襲しています(笑)。
佐藤氏:
実際、1回目のクレジットを見て「クリアした!」と思ってプレイを終えてしまった方もいると思います。我々からすると「まだやめないで!」と伝えたくなるといいますか(笑)。
特撮作品や『呪術廻戦』など、本作の着想に影響を与えたインスピレーションの源
──ジュリーとアレックスが「ヒーロー」であるという設定は、外山さんの特撮ヒーロー愛がかなり反映されているのでしょうか?
外山氏:
それは間違いありません。『野狗子』はマンガ的エッセンスが大きいのですが、同等に特撮の影響も現れています。
とくに『牙狼』や『仮面ライダーアマゾンズ』など、いわゆる大人向けの特撮作品から多くのインスピレーションを受けていますね。とくにキャラクター性を形成する部分は影響されていると思います。
──少し話がそれてしまうのですが、外山さんがそこまで魅了される特撮の魅力について教えていただけないでしょうか。
外山氏:
自分の考える特撮の魅力として、「写実的な表現」でありながらリアリティさを曖昧にする「あやふや」さがあると考えています。
たとえば、特撮ヒーローが「それ、どこから出したの?」とツッコミたくなるようなアイテムの出しかたをするシーンがありますよね。でも、特撮ではそれが自然と受け入れられている。
僕自身、『サイレントヒル』のときから「主人公はカバンも持っていないのにどうやってアイテムを持ち運んでいるんだろう?」と疑問に感じることがありました。
そこで「誰かの見ている夢の世界だから」という解釈を編み出したんですが、リアル思考な方からはツッコまれてしまう。かといって、理論武装するのも自分の中ではちょっと違う。
でも特撮だと普通にそれが許される(笑)。近年、リアリティ重視な作品が多いと思うのですが、こういう特撮のあやふやさが自分はすごく好きなんです。唯一無二の良さがあると思っています。
──外山さんが特撮をそう捉えているという話は、初めてうかがったかもしれません。
外山氏:
これまでほとんどお話したことはありません。特撮の話は、開発チーム内でも海外メディアに対してでも伝わりにくい部分があったんです。
ただ、「自分もそういうの好きなんです!」という人がいれば、その人とは延々と話していました(笑)。
──そのほかに、本作の着想に影響を与えたり、アイデアの源になった作品はありますか?
外山氏:
マンガが好きで、できる範囲で新しい作品をチェックしています。マンガは自分のタイミングで読めますし、個人のアイデアが強烈に表現されているところが魅力的ですね。
ひとりの作家による「強烈なアイデアや鮮烈な表現」があるからこそ、マンガは日本だけでなく世界中でも評価されているんだと思います。「マンガが持つ独特のエッセンス」を吸収することが僕にとっては大きなインスピレーションになっています。
──たとえばどのような作品でしょう?
外山氏:
あまりにも有名な作品ですが、現代的なケレン味という部分で『呪術廻戦』でしょうか。能力バトル自体が、いまのエンタメ界で非常に大きな流れのひとつですよね。とくに海外ではアニメの影響が強いですから、「これ、あのアニメみたいじゃん」と思ってもらえるのは大きな強みになると思います。
また、主人公の憑鬼のキャラクター設定や中盤以降の展開は、ヤマシタトモコ先生の『WHITE NOTE PAD』(ホワイトノートパッド)という作品からの着想が大きいです。本当にいい作品です。


Bokeh Game Studioとしての強みや魅力
──本作はBokeh Game Studio設立後、初のタイトルになります。1作目を作り終えたいま、このスタジオの強みや魅力についてはどう考えていますか?
外山氏:
Bokeh Game Studioの強みは、チーム全体の柔軟性と創造力だと思います。とくに大倉のように、個人のフィーリングやアイデアをチームの中で組み合わせ、それをどう着地させるかを考えられる人材がいることは大きいです。
佐藤氏:
『野狗子』の制作過程でも感じたのは、チームが「新しいこと」への対応に慣れている点ですね。
『SIREN』や『グラビティデイズ』での経験から、変わった仕様が来ることに対して、「とりあえずやってみよう」というマインドが根付いています。仕様書を細かく書くより、実際に作りながら調整するほうが効率的なんです。
大倉氏:
そのため、業務委託や派遣の方がきた際に戸惑われることはあります。でも、仕様書に時間をかけるより、実装しながら感触を確かめつつ作っていくほうが早いんですよ。
たとえば「この必殺技、こんな感じでやってみよう」と、まずはコンセプトだけ固めてスタートし、試行錯誤しながら完成に近づけていく。この進め方ができることが「Bokehらしい部分」だと思います。
佐藤氏:
SIE時代から「 アジャイル」や「スクラム」と呼ばれる「小さな目標を作って2週間やってみる。ダメだったら切り替える」という方式をとることがありました。
もちろん、フレキシブルである反面、スケジュールをガッツリ使ってしまうので自分たちがしっかりしていないと完成しないんですけどね。
外山氏:
自分たちにはこのスタイルがあっているんでしょうね。だからこそ、『SIREN』、『グラビティデイズ』、『野狗子』と、異なるタイプのゲームを作ることができたのだと思います。
佐藤氏:
ありがたいことに「Bokehで働きたい」という声をいただくこともあるのですが、さきほど大倉が述べたように、このスタイルに戸惑う方も多いですね。とくに「考えた人が実装することもある」という部分に驚かれることが多いです。
外山氏:
でも、ゲーム業界に入るきっかけが「自分のアイデアを活かしたい」という思いだった方にとっては、うちのアプローチは非常に魅力的だと思います。しんどい部分もありますけど、自由度の高さはチームの大きな財産です。
佐藤氏:
じつは『SIREN』のころから「やれる人がやる」という姿勢で進めてきました。正直、きついと感じる人は多いでしょうし、自分自身も感じたことはあります。でも、そこが外山の色なんです。
もちろん、このスタイルが合わない方もいらっしゃいます。でも、合う方にとってはやりがいがある環境だと思いますね。
外山氏:
確かにきついと感じる人はいるかもしれません。でも、『サイレントヒル』の山岡晃さんや伊藤暢達さん、『グラビティデイズ』の斎藤俊介さんや緒賀岳志さんなど、関わってくれたスタッフが評価を得て活躍の場を広げている例が多いのは、自分のスタイルを貫いてよかったと胸を張れることですね。





































