みんなも騙されてゲームを作ってほしい!
斉藤氏:
今はインターネットでみんなが感じたことを、そのままゲームにするとけっこういいゲームができるんじゃないかと思います。『NEEDY GIRL OVERDOSE』はそれを証明したゲームかなと。ほんとみんな、じゃんじゃんゲームを作ったほうがいい。
とりい氏:
みんなゲームを作った方がいい。
斉藤氏:
この苦しみをみんなに味わってほしい。
とりい氏:
みんなも騙されて半年って言われてほしい(笑)。
一同:
(笑)。
 |
とりい氏:
発売延期したのを覚えてるからな、みんな……。 周りの人間に話を聞くと「まさかあれ完成するとは」と言っていましたよね。
斉藤氏:
完成すると思ってなかった、本当にね。
とりい氏:
思ってなかった。にゃるらさんは疑ってたかもしれない、斉藤さんも疑ってるかもしれない、斉藤さんの嫁さんも多分疑ってた。でも、私とねんないさんは「いやこれはできる!」と。
斉藤氏:
疑ってなかったね。本当にいいチームだった。にゃるらくんも素晴らしいし、僕もがんばりましたけど、ほんとにとりいさんとねんないさんがすごくいいチームだった。
デザイナーふたりがUnityを使えるチームは本当に最高のチーム。ゲームとして形になったのは、とりいとねんないさんのおかげ。
コミケの原稿で一番最初に「プロデューサーの仕事は祈ることです」と書いていましたからね。「完成すると祈り、完成して売れたら感謝の祈りを捧げる。これがプロデューサーの主な仕事です」と書きました。
とりい氏:
ねんないさんが一番かっこよかったエピソードなんですけど、みんなが本当に完成するのか一番疑いが深くなった時期があったんです。構成はできたけど、実際に形になってるのが出てきてなくて、みんな心配してた時期。そして斉藤さんも一番病んでいた。
そんなとき、ねんないさんから電話がかかってきて「ゲームはなにでできてると思います?」と聞いてきたんですよ。「性癖ですよね」と言ったら「はい、そうです」と。
「このゲームは誰の性癖ですかね」「にゃるらさんですよね」「わかってますね。これ、ちゃんとにゃるらさんの性癖になってますかね?」と言われて「これからします」と返して。「じゃあやりましょう」と電話を切ったという(笑)。
斉藤氏:
「もっともっと、性癖を引き出してください」とかさ。「にゃるらさんはもっとパンツを脱ぐべきです」とか言ってたよね。それで僕たちも気合入って、完成直前だったけどにゃるらくんにも「なんでこんなに薬が出てくるの?お前にとって意味があるはずだ!」とめっちゃ迫りましたよね。
ずーっと出てこなかったんですけど「いやでも、承認欲求はめちゃめちゃキマるんで。薬よりキマるんですよね」みたいなことをポロっと言って。「それじゃん!」と。
「このゲームに薬が出てくる意味じゃん、じゃあフォロワー100万突破したら、おくすり効かなくなっていいよね」と詰めだして。
 |
とりい氏:
積み上げてきたすべてを破壊するグランドエンドがあるんですけど。
「このときの超てんちゃんは何を考えているんですか?」とにゃるらさんに迫ったら、「一瞬でも伝説になれて、超気持ちよかったと思いますよ」と言ったんです。
斉藤氏:
素晴らしい回答だった! 「じゃあ、なんかもうバカみたいに明るくていいね」って。
とりい氏:
「バズったら気持ちいい!」「それってインターネットだね」って(笑)。
──いいですね、バズったら気持ちいい。
斉藤氏:
あんなに屈託がありそうなエンディングなのに「何も考えてねえんだこの女!」と。あれは最高だった。
とりい氏:
にゃるらさんは「いや、薬より気持ちよかったと思いますよ」と言ってて本当にサイコーだった。
斉藤氏:
彼はマジで薬キメてるやつの顔で言っていました。彼はインターネットで気持ちいい瞬間をとても体験してきて、「本当に気持ちいいときは気持ちいいんだ」ということが僕らにも理解できた。
「彼にとってのインターネットというものは、薬に近いんだ」ということが本当にわかった。「おくすりより気持ちいいから、フォロワー100万超えたらおくすりは効果なくそう」とか、はいしんのストーリーもハマって。
とりい氏:
そうそう。あれでゲームの筋の最後のひとつがきれいにハマりました。
斉藤氏:
「インターネットは超気持ちいい!」以上。
文学的な屈託を持って呼び込むんだけど、「御託はいいんだ、フォロワーが増えるって気持ちいいんだよ」。それを追い求めるとあのエンディングになる。その後は誰も知らない、それが彼女の絶頂だったからって。「それで人生は終わるべきだと思います」と。
電ファミにいた経験が、ゲームづくりの役に立った
──さて、ここまで素知らぬ顔でインタビューしてきましたが、実は斉藤さんもとりいさんも電ファミ編集部にいたことがあり、私(実存)も部下であり、同僚でした。僕はまだ電ファミでメディアを続けていますが、ぜひお聞きしたいことがあります。
メディアにいた経験はゲームづくりに役に立ちましたか?
斉藤氏:
取材とか記事から学んだものはとても大きいです。基本的にメディアに一回入ることは作り手にとってはすごくいいことだと思います。
とりい氏:
めちゃくちゃ学びました。メディアって、全ての情報が集まってくるじゃないですか。それがすごく良かったです。特に電ファミのインタビューを全部読むのは、すごく勉強になったし、「筋肉がついたな」と感じがします。
斉藤氏:
「ゲームの企画書」をはじめとしたインタビューに聞き手として行くたびに、「これは使える」とアンチョコに書き加えてましたからね。インディーゲームに使えると思うことは、全部メモしてあります。
 |
──とりいさんはそもそもどういう経緯で電ファミに入ることになったんでしょうか?
とりい氏:
新卒で入った会社が朝起きないといけない会社だったんです。
──朝、起きれないということですね。それってなにげに会社に所属することを妨げる大きな性質ですよね。
とりい氏:
朝起きれないだけで、人権がどんどん剥奪されていく状況が本当につらくて。
「うう、辛い」と言いながら、夜中の3時ぐらいにインターネットを見てて、たまたま電ファミの記事を読んだんです。
そのときに「このメディアは“パンクス”がやってる」と確信しました。インターネットに5万字のインタビュー載せるのはパンクスしかいない!って。なので、記事が出るたびに「いいな~」と思ってたらある日タイムラインに流れてきた求人を見たんですよね。
斉藤氏:
たぶん、僕のツイートだよね。編集長(TAITAI)から「地頭が良くて、行き場のないやつ」みたいなオーダーを受けて探していました。
とりい氏:
ピッタリだった。行き場はなかったです!
あと「ちゃんとゲームは好きか」と聞かれました。
──実際、電ファミに入ってみてどうでしたか?
とりい氏:
カットされる前のインタビューが読めたのが一番サイコーでした。いろんな理由で消える前の本当のことを読めて、その中にはけっこう赤裸々なテクニックとかもあって。めちゃくちゃ勉強になりました。
あと、単に楽しかったです。電ファミに入ってから、朝起きるのが辛くなくなったんですよ。なぜかというと、いろんな面白い年上に会えたから。
斉藤さんからは「いいか、職場というのはなんと人の金で面白いことをしていいんだ」と聞いて、「人の金で、面白いことをしていい!そんな発想はなかったぞ!」となりました。
気合いの入った大人を見ると、やっぱりいいなと思いました。仕事に気合を入れても、怒られないんだって思いました。
──まさに斉藤さんが誘う理由のひとつになった、「ヴェイパーウェイヴ」の記事も書いてましたよね。
とりい氏:
「なんで誰も『スプラトゥーン2』のヴェイパーウェイヴの話してないんだよ!」と思いを込めながら書きましたね。
──そこから電ファミを辞めて会社を作ったわけですけれども、それはどういう動機とどういう流れだったんですか?
とりい氏:
辞めるちょっと前にこう解散の雰囲気が出てたじゃないですか。1月くらいですかね。
「電ファミ、ドワンゴから独立する?」みたいな話が始まるちょっと前に、別のところから「プログラム書いてくれ」という案件が降ってきて、その仕事をくれた人に「お前は会社を作った方がいい」みたいなことを吹き込まれました。
そうしてお金が溜まってきて、起業! Xemono(くせもの)というデザイン会社を作りました。
そのあともやれることをすべてやって会社が沈まないようにしていました。
電ファミはいい場所でしたよ、本当に。ちゃんと人生をギュギュっと曲げてくれたので、めちゃくちゃ感謝しています。
 |
「ゲームで表現すること」がネイティブな世代の作家を育てた経験
──続いて斉藤さんの経歴についても、改めてお聞きできればと思います。
斉藤氏:
ドワンゴに2011年に入社したんですけど、その前後って、まさにTwitterが面白くなった時期だったんです。電ファミで一時期デスクをやっていた稲葉ほたてというスーパーライターと一緒に「ネットの文化人類学」をやろうみたいな感じで同人誌を作っていて、2年間ぐらい真面目に働かない不良社員だったんですよ。
その不良社員時代は、ひたすら同人誌を作ってたわけです。インターネットのいろんな女の子に取材をしました。『ハリーポッター』のネット上にある夢小説を全部読んだり、Pixivの『テニスの王子様』の二次創作ランキング100位まで全部読んだり、『カゲロウプロジェクト』のファンのヒアリングとかをひたすらしていた。
そういうことをやりながら、にゃるらくんよりちょっと上の世代のインターネットを過ごしていました。
 |
──今のゲーム実況だとか、ネットの流行り物を仕事として最初期にやった人ですよね。「ネットを使ったコンテンツとはどうあるべきか」みたいな視点が斉藤さんのテーマというか。
斉藤氏:
そうですね。そしてその過程で『殺戮の天使』というタイトルを立ち上げたんです。経緯としては、ゲーム実況が流行りそうで、ツクールっぽいゲーム、かつストーリーのあるものがすごくウケてると。『Ib』とか、『霧雨が降る森』とかですね。
「ボーカロイド」がまさにフィクション化していく様子や、『カゲプロ』であったり、その小説化であったりとか、「そういったことがゲーム実況でも起こるかもしれないな」と思って、「ゲームマガジン」というゲームの連載プロジェクトで『殺戮の天使』を始めたんです。
「ゲームマガジン」はもともとインディーゲームの担当をしていたんですけど、「自作ゲームフェス」というイベントをやったときの受賞作家がすごく優秀で。ちょうどKADOKAWAとの統合もあった時期だったので、この作家たちとゲームを連載すればメディア化できるかな、という経緯ではじまりましたね。
──ゲームで表現することがネイティブな世代の作家ですよね。漫画で育った人が漫画を真似して描くように、自分を表現するときにゲームにたどり着く。それが斉藤さんが「ゲームマガジン」でやっていたことだと思います。
斉藤氏:
そして大変運良く『殺戮の天使』が当たり、10代女子に大人気になり、コミカライズが結果200万部ぐらい、アニメ化までいきました。
というのがまず、僕のインターネットとドワンゴにおけるキャリアです。ちょうどその頃、その隣の部署で平さんが『電ファミニコゲーマー』を立てていて。
『殺戮の天使』は売れていたんですけれども、ドワンゴには直接売上を出していなくて、行き場のないプロジェクトだったんです。
──ドワンゴの視点で見るとただの赤字プロジェクトですね。
斉藤氏:
僕はなにか困るたびに、ロンダリングできるから部署を変えていたんですよ。2回か3回ぐらい部署を変えたところで限界が来て、もういよいよ立場がなくなってきたとき、最後に平さんに頭下げて「申し訳ないですけど引き取ってください。これがたぶん最後の場所になるんで、拾ってください」と言いました。
「電ファミ、もっとやりましょうよ」と言って、僕は最大限予算をモリモリにした企画書を作りました。ヤバい企画書を作って、その上司・平さんと僕の間にいた部長に託して「これ通してきてください」と。
そうしたらその企画書が通って、すごい額の予算が降りてきて(笑)。その莫大な予算を使って「1日1本でいい!1日1本に死ぬほど予算を注ぎ込め!使い切れないから大丈夫!」とじゃぶじゃぶお金を使って記事を作るという副編をやっていました。すごく楽しかった。
そんな感じで、電ファミにいた日々は青春でしたね。
『NEEDY GIRL OVERDOSE』を作る運命だった
──その青春の結晶が『NEEDY GIRL OVERDOSE』であると。
斉藤氏:
そうですね。我々はインターネット自体はネイティブではないですけど、青春期にともに過ごしたものです。ゲームもちょっと前の世代の青春だったので、その意味では『NEEDY GIRL OVERDOSE』はそのふたつの青春を合わせたみたいなものだと思います。
僕らより下の世代、20代前半になってくるとこれは『マインクラフト』とかになってくるだろうしね。
とりい氏:
プラットフォームになっちゃいますからね。
斉藤氏:
インターネットの思い出が、コンテンツによるものじゃないかもしれないなって感じもするし。
 |
とりい氏:
『RPGツクール4』で初めて作ったゲームのことを思い出しました。超大作を作ろうと思って、最初と最後だけ作って終わったんですけど(笑)。
斉藤氏:
わかる。僕も『RPGツクール』だった。
たしかに何かを作ろうとしたとき、それがインタラクティブであることについて、我々には何の抵抗感もないと思います。
──お話を聞いていると『NEEDY GIRL OVERDOSE』は考えて考えて、理屈で積み上げていったというよりは、ネイティブな感性で勝負した作品。そこが勝因というか、強さなのかなという印象です。
斉藤氏:
僕はなにかが混じり合うのって、運命だと思っているんです。にゃるらくんと会ったとき、今このときに、にゃるらくんが「ゲームを作りたい」と言ったことは運命だと思ったんですけど、ほんとにそうでしたね。
こんなプロデュースワーク、一生にもう1回あるかどうか分からない。
とりい氏:
また『NEEDY GIRL OVERDOSE』をやるって言われたら、やります?
斉藤氏:
いやまあ、2年前に戻ったらやるでしょうね。今はもう当たってるから、間違いなくやるよ(笑)。だからどんな時にもやるんじゃない。
──たとえ世界が永劫回帰だったとしても、『NEEDY GIRL OVERDOSE』はやると。
斉藤氏:
『NEEDY GIRL OVERDOSE』はやる。どうやってやったらうまく行くかわかるから、記憶が残ってたらなおのことやる。でもこのレベルはもう一回できるのかな?とは思いますね。
このレベルでみんな運命を背負うような状況ってそうそうないので、もうちょっとそういうタイミングを待つことになるかなと思います。あと10年ぐらいはかかるかもしれないですけど。
 |
本作のテーマのダークさとは裏腹に、爽やかな話題の多かった『NEEDY GIRL OVERDOSE』インタビュー。
何度も語られたように、本来予定していた半年を大幅にオーバーした2年間で、本作の魅力のひとつである狂気的なまでの解像度は形作られた。インターネットを描くことに関してこの上ないキャスティングであるにゃるら氏を迎え、デザイナーふたりがUnityに精通しているというこの上なく「SSR」なチームによる、濃密な2年間で形作られた青春の結晶とも言える作品が『NEEDY GIRL OVERDOSE』だ。
本作をプレイし、「超てんちゃん」という偶像、インターネットエンジェルに熱狂することは、もう一度インターネットで青春を過ごすことではないだろうか。「ジェルばんは!」、「†昇天†」。同じ言葉でつながる符号的なコミュニケーションで感じるぼんやりとした連帯感は心地が良いし、それこそが我々の愛したインターネットではなかっただろうか。
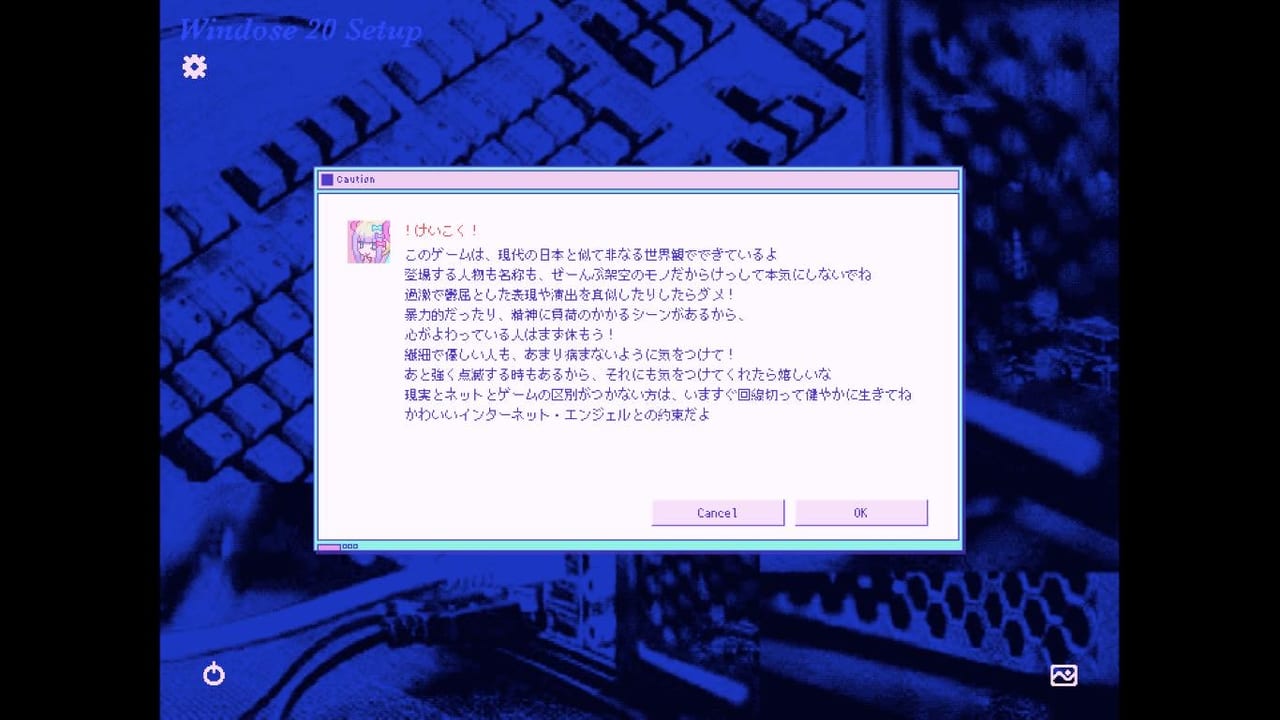 |
在りし日のインターネットを懐かしむ我々を刺し、今のインターネットを生きるZ世代にも共感される本作の影響力は計り知れず、今や国境を超えてワールドワイドに波及する。ついに発売されたNintendo Switch版を通して、『NEEDY GIRL OVERDOSE』にギュッと詰まった「インターネット」がより多くのニキやネキに伝わることが、オタクくんのひとりである漏れとしても、非常に喜ばしく、そして愛おしく感じる。インターネットやめろ!


































