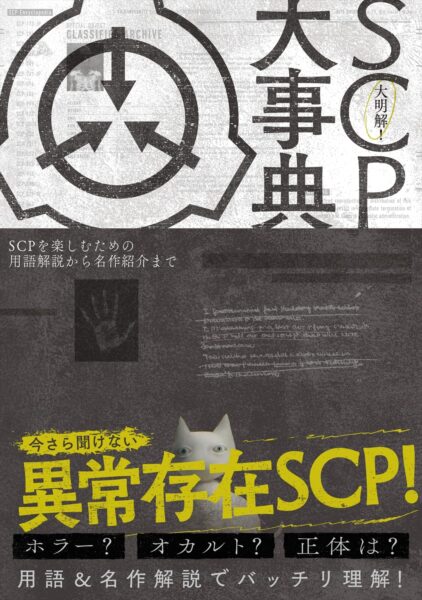『SEKIRO: Shadow Die Twice』(以下、『SEKIRO』)で最後の敵と相まみえたとき、道中で培ってきたシステムの理解や、苦労しながらも倒してきた敵の数を根拠にした自信は、確かにあった。しかし、刃を交えた瞬間に「ひるみ」を感じた。何もわからぬまま屠られ、二戦目には「絶望」した。自信が慢心だったことに気づき、精神が疲弊の波に飲まれそうなって、それでも狂ったようにプレイし続けた。
その中で筆者は、『SEKIRO』にぼんやりと感じていた、“研ぎ澄まされて残ったもの”を見つめなおしていた。
 |
文/Nobuhiko Nakanishi
編集/ishigenn
削り磨かれ残った「戦闘」という結晶
『デモンズソウル』と『ダークソウル』三部作、『ブラッドボーン』はいわゆる「ソウルボーン」シリーズとファンから呼称されている。どれも高い難度で知られる作品ではあるが、それでもそれぞれの作品には「オンライン」という最強の救済措置が搭載されていた。
腕に覚えのあるプレイヤーは白サインを書き、自信がないプレイヤーは助けを求める。もちろん、ソロでプレイし、ひとりでゲームをクリアすることも可能だ。難度はある程度コントロール可能であり、「死にゲー」と呼ばれる難しさを維持しながら遊び方に大きな幅をもたせるこのシステムは、同シリーズが多くのプレイヤーから支持を得た要因のひとつでもある。

しかし『SEKIRO』において、オンライン要素は全て排除された。それだけではなく、これまで遊びの幅であり救済措置でもあったレベリングおよびアイテム収集、キャラクターメイキングといったRPG要素もない。メイン武器は「楔丸」という日本刀が一振りのみ。防具の概念もない。成長要素は特定のベクトルのみに限られている。
このように、ソウルボーンシリーズから協力要素もキャラクター設計の自由度も削られて生まれた『SEKIRO』。そこに残ったのは、あらゆるものを削った上で磨き切られた、純度の高い「戦闘」という名前の結晶だ。
過去のソウルボーンシリーズ作品における戦闘が完成されていなかったわけではない。何もわからぬまま初見で倒され、その後も死にながらパターンを構築。それでも「あと一撃」が届かない。その「あと一撃をどう届かせるのかという戦闘」の醍醐味は、シリーズを通じて高度に完成されてきたものだ。しかし、『SEKIRO』の戦闘の完成度は明らかに群を抜いている。
戦いは「鍔迫り合い」が如く
 |
『SEKIRO』には「弾き」というジャストガードシステムが搭載されている。ソウルボーンシリーズの「パリィ」のように成功させれば即座に致命攻撃が可能になるものではなく、敵の攻撃を刀で弾くことで増えていく敵の「体幹ゲージ」を満たせば、相手の体幹を崩し一撃を放つことができるという代物だ。
しかし、それは「自身の攻撃を当てるか相手に防御させつつ、敵の攻撃は弾く」という理想の流れを完遂すればの話である。『SEKIRO』における敵の攻撃パターンはかつてないほど種類が多く、その隙も圧倒的に少ない。通常攻撃に加えガード不能技である「投げ」や「突き」、「下段」をどういったタイミングで繰り出してくるのか。あるいは、その攻撃を弾くのか回避するのか、あるいはジャンプするのかなど、プレイヤーの頭を悩ませることになる。
いずれの行動にも最適解が用意されており、もしそれを外して攻撃を一撃でも食らってしまえば体力は大きく削られ、追撃を受ければ”死の圏内”に入る。自身の体力を回復し、リカバリーに集中したり、敵の攻撃にひるんで距離を置き続けていれば、敵の体幹ゲージは時間経過で回復していってしまう。そして体感ゲージは主人公である隻狼にもあり、攻撃を防御しゲージが満たされると致命の一撃を受けてしまう。
 |
好機はこちら側に傾いているのか、あちら側に傾いているのか。シーソーゲームの中で戦いは進んでいく。得られるものと失うもののバランスが、「弾き」と「体幹ゲージ」を中心としたリアルタイムの戦闘で絶妙に拮抗していく。それは言わば「鍔迫り合い」と呼ぶに相応しい一瞬であり、「ソウルボーン」シリーズでは到達しえなかった鋭い緊張感を生み出している。
『SEKIRO』の結晶内で光る「あと一撃の戦闘」
このように解説すると、『SEKIRO』の戦闘はソウルボーンシリーズと微妙に異なる程度にしか見えないかもしれない。しかし、オンライン要素や成長要素を取り除き、プレイヤーと敵をシングルプレイでほぼ振れ幅のない世界に閉じ込めたとき、そこで発生する緻密な戦いへの”感情移入”はより大きく増幅することになる。
負ければそれは自分の実力、勝てばそれは自分の実力。そこに「オンラインで協力する」や「レベリングで体力を高めてから戦う」、あるいは「特定の武器を収集してそれを使う」といった幅はない。幅がないゆえに、戦闘の楽しさも苦しさも、不安も疲れも恐れも、絶望も快感も寂しさも欲望も、すべてプレイヤーへとダイレクトに伝わっていく。
 |
その『SEKIRO』の完成度に到達していることを踏まえた上で、ソウルボーンシリーズで構築されてきた「あと一撃の戦闘」を振り返るとどうだろうか。確かに敵の攻撃手段は多いが無限ではない。その中のひとつのパターンの攻撃モーション、予備動作、派生パターンを見切ることができれば、そこにほんの少し心の余裕が生まれる。そこから徐々に敵の動きを自分の体に染み込ませる。敵の攻撃に対する自分の動きは徐々に頭ではなく、脊髄反射に変わっていく。それは戦うための脳神経が徐々に太くなっていくようなものだ。
最初はまったく動きが見えなかった敵と何度も何度も殺し合い、失敗して、そして立ち上がることを繰り返していくと、どこかあるポイントでその膠着の均衡が破れる瞬間が訪れる。立ち合いの中にあるどこかの刹那、今まであれほど早かった敵の動きがスローモーションに見えるときがくる。何度も繰り返し食らっていた攻撃を避けられる瞬間、弾ききれなかった攻撃が弾ける瞬間が来る。
趨勢の天秤が一気に傾き、反転攻勢に舵を切ったそのとき、愛しい鍔迫り合いの時間は終わる。敵との非言語対話を繰り返すようなその戦闘シーケンスは、「忍殺」というシステム上用意されたカットインにより明確な終わりを告げ、戦闘の各所で緊張感によって蓋をされていたアドレナリンが噴出を許される。ずっと届かなかったはるか遠い「一撃」がようやく届く。
 |
突如乗れるようになる「自転車」
死んで覚えることだけではなく、指先に覚え込ませるというさらに”その先”を求めるゲーム性は、プレイヤーにかなりの労力を求めてくる。そして成長が実感できる瞬間が他のシリーズに比べて遅いということが、必要以上に本作の難度を高く見せる要因になっている。
しかし本作は道程こそ険しいが、理不尽に難度が高いわけではない。感覚的に言うならそれは、それは「自転車」に乗るためのプロセスによく似ている。自転車に乗るために必要な体の動きやバランス感覚について、頭で理解することはさして重要ではなく、繰り返し失敗して小脳に失敗パターンを覚えこませることが必要だ。そうして体全体の動きが連動したときに、突如として自転車に乗れるようになる。“一般的な成長のイメージ”が「徐々に結果が生まれてくる」ものだとすれば、成果が一気に現れるように見えるという意味で、自転車に初めて乗れるようになった体験は「できないものが突如できるようになる」の典型だ。
 |
『SEKIRO』の戦闘においても、敵に勝利した瞬間はやはり「できないものが突如できるようになる」瞬間だ。自転車に乗れるようになったとき、もう乗れなかったときのことなど覚えていないだろう。『SEKIRO』の戦闘も一回の勝利で難度は劇的に下がる。それはパターン構築と正確な対応、全体の連動性が確保されない限りほとんど勝利できない、という独特の構造が生むものだ。一見、突然勝利できるようになったかのように見えるが、それは単に内部的な成長が表に出てくる瞬間がほかのゲームに比べて遅いことに起因する現象だ。
そしてだからこそ、今まで鍔迫り合いをしていた相手が、ある瞬間に自分と圧倒的な力量の差を付けられていることに気づく。戦い、負け続けた好敵手が、ある瞬間にすでに敵ではなくなっている。それに気づいた瞬間に湧き上がる制覇した愉悦とも好敵手を喪失したとも取れる複雑な感情は『SEKIRO』固有のものである。それが本作のゲームシステムと物語性の幸せな融合を生み出していることも、疑えない事実だ。
 |
『SEKIRO』のこのエッジの効いたバトルシステムと苦難に満ちたシングルプレイだからこそ、物語は心に突き刺さり、NPCに対する愛情も、対戦相手への愛着も生まれる。そしてシングルプレイだからこそ、それら全ての感情はプレイヤーひとりに帰属する、オリジナルなものになる。「ビデオゲーム」が「ビデオゲーム」という仕組みを使ってどんな感情をプレイヤーに感じさせたいのか、言葉や演出で表現する作家性ではなく、「ビデオゲーム」という言語が生み出せる感情や情動の答えは間違いなくここにある。
『SEKIRO』は殺傷の為に作られた武器が、はてしない鋳造の果てに図らずも芸術の域に達してしまった「日本刀」のようなものだ。狂気と正気の狭間に浮き出てくるその威容には、余計な部分がなく、削ぎすぎの部分もない。『SEKIRO』の、初めからその形があったかのように完璧であまりにも美しいそのシェイプは、「ビデオゲーム」というジャンルに正統に向き合った結果意図せずして結実してしまった果実だ。知らず知らずの内にビデオゲームというジャンルに摩耗し、いつの間にかどこか冷めた目で見ていた自分に鮮烈な熱量を注ぎ込むほどに。これをマスターピースと呼ばないなら、いったいなにをそう呼ぶのか。
最後の敵との戦いに入ってから数時間が経っていた。もしかしたら永劫に届かないのではないかと思っていたラスボスに、遠い「一撃」が届いたとき、かつて感じたことのないほど強い達成感を感じながら、同時に自分のなかにある感情がただの嬉しさだけではないことも理解した。
詰んでしまうかもしれないという恐怖からの解放。蓄積された疲労の自覚。しつこく挑戦し続ける自分と延々と死合ってくれたラスボスへの惜別。この美しく完成されたゲームが終わってしまうことへの寂寥。何度も折れかけた心の中、最後まで立ち上がり続けるモチベーションを与えてくれたのは、「左手の人差し指」だったことへの驚き。そしてその中で最も意外だったのは、一呼吸置いた後に湧き出した「再戦」への渇望だった。
 |
その欲望は消えない。周回しても周回しても、高難易度を攻略し終えてもまだ何もかにも足りない。戦いの欲望はさらなる戦いへの欲望を増幅していくだけだ。「弾く」ために使う指が、白刃が交わされる「キンキン」という音を聴きたがる。勝っても倒しても屠っても、それは完璧ではない。納得できずまた敵を見つけて切り結ぶ。まるで戦闘中毒だ。なるほど「身体は闘争を求める」とはよく言ったものだ。冒頭「狂ったようにプレイした」と書いたが、もともとゲーマーという生き物はもともとどこか狂っていて、それを思い出すきっかけを常に伺っているものなのだろう。
六道の内の修羅道は永遠に戦い争い続ける場所だと聞く。『SEKIRO』というタイトルは存外にそこに近い場所なのかもしれない。多くを削ぎ落した『SEKIRO』にはなにが残っているのか。そう、そこには倒すべき「敵」がいて「死闘」があるのだ。
【あわせて読みたい】
なぜ『レッド・デッド・リデンプション2』は時代遅れで、それゆえに美しいのか。Rockstarが目指す狂気と理想の“世界”『レッド・デッド・リデンプション2』(以下、RDR2)は、Rockstar Gamesにしか作れない、かつてビデオゲームが持っていたひとつの狂気、あるいは夢と理想の最果てだ。たとえそれがもう時代遅れのものだとしても、彼らはそんな事実にすら興味がないのかもしれない。