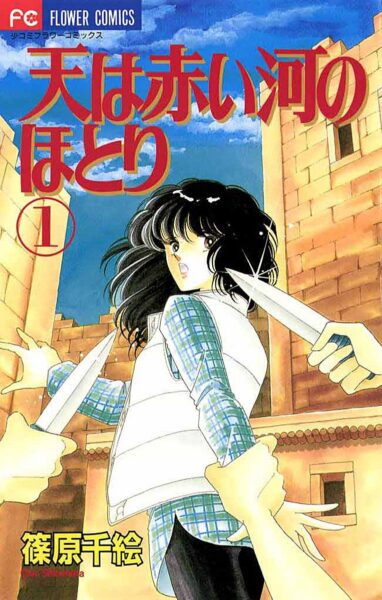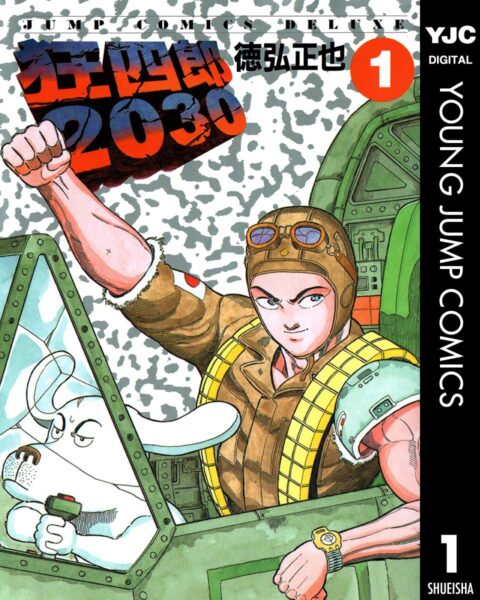子孫の積み上げた成果を回収した新作『ゼルダ』

(画像はゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 1st トレーラーより)
本作はまず、広大なマップ、開始直後からどこにでも行ける自由度の高さ、豊富なサブクエスト、ファストトラベルーーと、最新のオープンワールドに必須と思われる要素が“ほぼ”網羅された、世界標準に忠実な作りになっている。
だが、それでも一つ変わらないものがある。それが、「経験値」である。初代以来の「ゼルダ」のアイデンティティ(『リンクの冒険』を除く)であり、ミッション達成して「ハートのかけら(本作では「克服の証」)」を一定数集めたときにだけ「パラメータの上昇=成長を認める」というルールは、今作でもブレていないのだ。

(画像は【日刊】愛に生きるゼルダの伝説ブレスオブザワイルド part5より)
ただし本作では、ユーザーに対する厳しさは大きく緩和されている。
一つは、ミッションに相当する「試練の祠」が120箇所もあり、ゲームクリアに必要とされる数を見つける難度がそう高くないということ。祠を探す労力が無駄になりにくいから、プレイ時間と主人公の強さは比例しやすく、実質的に「経験値」システムに近づいている。祠の半分、60も取ると残りの祠を探すのは急激に難しくなるが、その頃にはアクションが不得手でもラスボスを倒すのは容易くなっているはずだ。
もう一つは、「行ったり来たり」の体験そのものが「ごほうび」になっていることだ。
オープンワールドは増えているが、「探索」が好評を得ている作品は実はさほど多くない。プレイの動機となる「どこかに行けば何かが見つかり、何かが起こる」ためには、あらかじめ凝ったギミックや高度なAIを仕込んでおく必要がある。その手間を掛ける、あるいは自動化できる技術を持つメーカーは限られている。
『ゼルダBotW』はそこにコストを掛けるとともに、「オープンワールドの基本」にとことん忠実であろうとした。それは、「目に見える場所は必ず行けるし、山でも崖でも登れる」ということだ。3Dゆえに登山ルートも一通りではないから、ユーザーの数だけ「専用の景色」が存在する。本作がユーザー同士の「共通体験」がほとんどなく、話が噛み合いにくいといわれるゆえんだ。

(画像はゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド 3rd トレーラーより)
だが、何の手がかりもないままに行き当たりばったりであれば、「だだっ広いだけ」とそう変わりはない。そこで祠センサーがあるわけだが、もう一つのヒントを出しているのが本作の凄みになっている。それは、「等高線のある地図」だ。

(画像:編集部撮影)
等高線があるから、現地に行く前に地形を読み、登山ルートの計画が立てられる。そこでの読み間違えや失敗は地図の読み方にフィードバックされ、読み解きをより賢くする。つまりゲームの外にいるプレイヤーを育て、「探索」に経験値を導入したのと等しい効果を実現しているのだ。
初代『ゼルダ』が開拓した、世界を「行ったり来たり」するコンセプト――それは、その志を発展させた「メトロイドヴァニア」や最新のオープンワールドでも、なおもシステムの主軸であり続けている。そうして数多く創られてきた子孫たちの積み上げた成果を回収した『ゼルダBotW』の大ヒットが、任天堂の新ハードNintendo Switchの快進撃を力強く牽引している様は痛快だ。
本作はBlu-rayの採用などにより限りなく拡張されて「オープンワールド疲れ」を起こしかねない世界の広がりに一石を投じ、比較的コンパクトな(マップは京都市を参考にしたという話もあった)世界を等高線により“折りたたむ”ことに成功した。そしてそれによって、探索する満足感と「プレイヤー自身の成長」を実装したことは、ゲームの歴史に革新をもたらした。
それは、石を巧みに配置して巨山や大海に見立てて、狭い空間に「広がり」を感じさせる日本庭園をどこか思わせる。かつて韓国の文芸評論家・李御寧が提唱した「縮み志向」【※】は、オープンワールドを進化させる上で、実は鍵になる概念なのかもしれない。
※縮み志向
『「縮み」志向の日本人』(学生社・1982)で述べられている日本文化論の概念。扇子、トランジスタなどを例に、小さいものに美を認め、あらゆるものを「縮める」ところに日本文化の特徴があるとした。
コマンド選択式とアクションRPGを融合させた『聖剣伝説2』
最後に、アクションRPGの歴史における、もう一つの掛け算の話もしておきたい。
これは「アクションRPG×コマンド選択式」という、一度は別々の道をたどった2つのスタイルが合流したものだ。
「アクションRPG」の強みはビジュアルや操作の分かりやすさにあるが、「コマンド選択式」は源流となったTRPGの「自由度の高さゆえの複雑さ」を保つ形式だった。その2つの緊張関係の中で、シンプルな操作系の中に複雑さを取り込み、時間に追われるリアルタイム進行とキャラや戦術の凝ったカスタマイズを織り合わせる「アクションとコマンド選択式の融合」が進んでいった歴史がある。
そんな「ゼルダ」から派生したもう一つの系譜――それこそが「聖剣伝説」シリーズ【※】だ。

(画像は『聖剣伝説コレクション』公式プロモーションムービーより)
実は、このシリーズの生みの親である石井浩一氏【※】も初代『ゼルダ』が好きだという。その理由は「ゲームでも世界を表現できると気づけたから」とのことだ。ただ、「ゼルダ」は難度が高めで、女性や子供が最後まで遊べていないという状況はあり、そこで「誰もが最後までストーリーを堪能できるシステムにする」ことに決めたと語っている。
※石井浩一
1964年生まれ。日本のゲームクリエイター。坂口博信氏のもとでプランナーとして「ファイナルファンタジー」シリーズに携わる。「聖剣伝説」シリーズの生みの親でもある。
その結果、『聖剣伝説』は「経験値」によるレベルアップ制を導入して、難度の点で「クリア保証」をする一方で、仲間と出会っては別れる“切ない話”によって、最後まで見届けたくなる動機づけをした。総じて言えば、「甘口にしてFF的なストーリー性を加味したゼルダ」といった仕上がりだったと言えるだろう。
そんなこのシリーズが、RPGのあり方を揺さぶる「問いかけ」をしたのは、『聖剣伝説2』【※】のときだった。
1986年に初代『ドラクエ』と『ゼルダ』が登場して以降、国内RPGは「時間に追われないコマンド選択式RPG」と「リアルタイム進行するアクション型」に分かれていったが、『聖剣伝説2』は、この2つを融合する試みを行ったのだ。

(画像はSQUARE ENIX公式サイトより)
アクションRPGの悩みーーアクション性と自由な行動の矛盾
その試みの意義を知るには、アクションRPGにおける、“誕生以来の悩み”を知る必要がある。
アクションRPGは誕生以来、RPGの楽しみである「幅広い行動の自由に頭を悩ませられること」に対して、常にジレンマを抱えてきた。敵との攻防に忙しく追われる中で「戦い」以外の行動をやるにしても、「あらかじめボタンにセットしたアイテムを使う」などの単純なことしかできない。だが、かといって凝ったことを行うためにステータス/装備画面に切り替えると、テンポが悪くなってしまう。

※2 ウルティマ(画像右)……1981年にオリジン社から発売されたコンピューターRPG。『ウィザードリィ』と並び、コンピューターRPGゲームの草分け的作品であり、2Dフィールド型RPGの始祖と言われる。
(画像はそれぞれWikipediaより)
本連載の第一回目で、国産RPGの源流となった『ウィザードリィ』や『ウルティマ』が、ともに『ダンジョンズ&ドラゴンズ』(以下、『D&D』)【※1】の「剣と魔法」の世界観を受け継いでいる事情を述べた。それを受け継いだアクションRPGでも、やはり「剣=物理攻撃」と「魔法=それ以外の何か」を行えるようにする試みは、積み重ねられてきた。
例えば、アクションRPGの礎となった『ドルアーガの塔』の続編だった、アーケードゲーム『イシターの復活』【※2】もその一つだ。操作キャラをカイとギルの二人として、前者に直接攻撃、後者に呪文パートを割り当てた。だが、それぞれの役割に集中できる……ということはなく、基本的には一人のプレイヤーが同時に二人を操るのは、なかなか大変だ。例えば、「コールギル」という、カイだけでフロアを回り、出口を見つけたらギルを呼び寄せるための呪文が存在している。きっと制作スタッフも、操作が複雑すぎる自覚はあったのだろう。

(画像はソフトウェアカタログより)
※1 ダンジョンズ&ドラゴンズ ……オリジナルの開発者は、Gary Gygax氏とDavid Arneson氏で、Tactical Studies Rules社が1974年に制作・販売した。世界で最初のTRPGであり、後世のRPGに大きな影響を与えた。
その後、カプコンによる『D&D』シリーズが、同名のTRPGを原作として、殴る蹴るのベルトスクロールアクション(横に長いベルト状のステージを横スクロールさせながら戦うことから)をベースに、RPGらしい行動の幅の広さを加味してみせた。
やり方は『イシターの復活』よりシンプルで、「アイテムを選択するボタン」および「使用ボタン」を一つずつ用意。そこで選べるアイテムの中に「魔法」があるという仕組みだ。クレリックなら回復・補助魔法、エルフは攻撃魔法を「アイテムとして」持たせ、TRPG風にキャラを特徴づけているわけだ。
では話を戻して、『聖剣伝説2』は、この問題にどういう回答をしたのか――それが、リングコマンド【※】の導入だった。

(画像はSQUARE ENIX公式サイトより)
ボタンを押すと、「アイテム」や「魔法」などの円メニュー(リング)が現れ、様々なことができるようになる。もちろん、一度出してしまうとゲーム進行が止まるので、厳密にはリアルタイムではない。だが、同じ画面内で装備の変更やステータス確認、ボタン配置のエディットもできるため、「アクション性と自由な行動の矛盾」は小さくなっている。
さらに、カプコンの『D&D』とも共通する点として、プレイヤーの攻撃結果が常に一定ではないという要素が入っているのも見逃せない。『D&D』では、攻撃ダメージは乱数(サイコロを振る)により決定される。それに対して、『聖剣伝説2』では、物理攻撃の命中率と回避率のパラメータが設定され、攻撃しても避けられ、逆に自動的に防御することもある。
いずれも、リアルタイム性のないRPG(TRPGとコマンド選択式の違いはあるが)の「確率でクリティカルヒット(会心の一撃)やミスもありうる」世界を再現するシステムだ。両者がともに「アクションと非リアルタイムRPGの融合」を図っていた結果だろう。
現代RPGでも続くシンプルさ×複雑さの掛け算
そして、こうした「アクションと非リアルタイムRPGの融合」は、単なる過去の話ではない。
「アクションRPG」の強みはビジュアルや操作の分かりやすさにあるが、「コマンド選択式」は源流のTRPGに備わっていたリソース(体力や装備)管理や「ゲームマスターとプレイヤーとのやり取り」といった複雑さを、深みがあるままに扱いやすくしたシステムだという話は上に書いたとおりだ。
その意図は、いずれも遊ぶ人の間口を広げることを狙っていたことにある。そして「明快なシンプルさ」と「深みある複雑さ」は、要するに人によって違う「好き嫌い」に行き着く。ただ一つの正解はないのだ。
だから、両者は今でも綱引きを続けている。例えば、多人数が同時にプレイするリアルタイム性の強いオンラインRPGでは、画面を切り替えずにあらかじめアサインされたキーで操作を完結させる傾向が強い。逆に一人用のオフラインRPGでは、メイン画面からインベントリ(所持品管理)画面に切り替え、目の前に敵が迫る中で落ち着いて装備を整えたり、体力を回復できる。
では、これら2つは断絶しているのだろうか?――いや、違う。
リアルタイム性が強くても、スキルツリー選びやアイテム合成にじっくり時間を掛けられたり、オフラインRPGでも次々と武器を取り替えるなどスピーディな操作が用意されていることはざらにあるのだ。

ここまでの連載で見てきたように、コンピュータRPGというジャンルが豊かに花開いたのは、様々な異質さが出会い、反発し、溶け合った「掛け算」が繰り広げられてきたからだ。
初めは人間同士が集まって遊ぶTRPGとコンピュータが出会った。やがて2Dマップの『ウルティマ』と3Dダンジョンの『ウィザードリィ』が生まれ、2つが掛け合わされた初代『ドラゴンクエスト』が実を結んだ。この「掛け算」には、ファミコンに代表される家庭用ゲーム機の普及に伴ったプレイヤー層の拡がりから導かれた、「やさしさの時代」が乗数に加わるだろう。
その一方でRPGとアクションの「掛け算」はアクションRPGを誕生させ、技術革新によるデータ空間の拡大は「ゼルダ」の箱庭、ひいてはオープンワールドの定着にも繋がった。
アクションとコマンド選択式の分離は、それぞれの分野でシステムを進化させ、両者は互いに垣根を超えて成果を取り入れた。そして、その先には人の数だけ違った「掛け算」があるオンラインがあり、さらに「初代ゼルダの子孫たち」のノウハウを回収して、とてつもない存在になった『ゼルダBotW』がある。
そう、この国にRPGという概念が渡ってきてから約40年――RPGの本当の戦いはこれからだ!
(打ち切りエンドのようですが、まだ連載は続きます。次回からは、SLG編が開始します)
※裏ゼルダに関する注釈の記述を修正いたしました(6月28日)